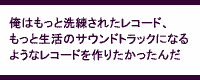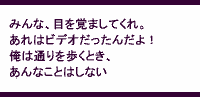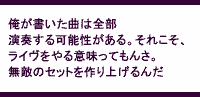| 誇り高きフロントマン、Richard Ashcroftが、初めて堂々と存在を認められるようになったのはVerveの頃、とりわけシングル“Bitter Sweet Symphony”の大ヒットの時だった。Andrew Loog Oldham OrchestraによるRolling Stones“The Last Time”のカヴァーをループサンプルに使ったこの楽曲は、即座にブリットポップのクラシックとなった。話題を集めたこの曲のビデオで、Ashcroftは道行く人々にわざとぶつかりながら歩道を歩く。このクリップは、Verve自体が衝突を起こしていることを預言していたのである。訴訟、ドラッグ、メンバー間の衝突など、すべてが原因となり、Verveは'99年に終焉を迎えた。3rdアルバムにして最も成功したアルバム『Urban Hymns』をリリースしてから、わずか2年後のことであった。
2000年になってごたごたが収まると、Ashcroftは1stソロアルバム『Alone With Everybody』をリリースし、評論家から絶賛された。その頃、AshcroftはLAUNCH本社に立ち寄り、編集部のDave DiMartinoに、ソロ活動やロックンロールにおける商業主義、そして私生活について語ってくれた。
――最も基本的なことを訊きますが、なぜ、ニューアルバムは単純にVerveの作品ではないのですか?
RICHARD:バンドが解散したからだよ(笑)。それに俺のソロアルバムだから。ただ、Verveはストーリー的にもタイミング的にも、ちょうど最期を迎えていたんだと思う。俺がこうやって座ってインタヴューに答えて、バンドにいた過去8年間のごたごたを話すのは難しいんだ。だから、これが俺のソロアルバムで気が楽だよ。自分で宣伝するっていうのは苦手なんだけどね。名前やタイトルを宣伝するほうがずっと簡単だ。突然、俺の名前になったんだ。俺名義のアルバムになった要因は、ほとんど他の人たちの決断から導かれたことさ。バンド解散の責任の一部はもちろん俺にもあるけど、他の人たちが決めたことによって、俺が難しい決断をしなければならない場面が多々あった。究極の決断はいつも俺に任されていたからね。
――“Richard Ashcroft”のアルバムには何が期待されていると思いますか?
RICHARD:俺はもっと洗練されたレコード、もっと生活のサウンドトラックになるようなレコードを作りたかったんだ。そのためには、聴く人にさまざまな情景を届けられるようなものでないとね。“Bitter Sweet Symphony”だけじゃなくて、アルバム全部を聴いたらわかるだろうけど、最後のアルバムではいろんな感情を取り上げた。俺ならソロアルバムにはエモーショナルな音楽、ソウルフルな音楽を期待するね。楽器やミュージシャンを全体の流れから取り出して、それが他と溶け合うようなものを聴きたい。深みのある、飽きの来ない作品。時がたつに連れて良くなっていくようなアルバムだ。
――ソロアルバムの制作中、自由であるという感覚を楽しみましたか?
RICHARD:自由だという感覚はものすごくあったよ。でも、スタジオでの自由というのは、ソングライターやアーティストやプロデューサーを殺してしまうことも多々ある。ほぼ完全な自由というのは恐ろしいものさ。選択肢が多すぎるんだから。ただ俺の場合、よかったのは、ミュージシャンとして限界があるってことだな。でも、想像力はとてつもないんだ。限界があって、そこに想像力が加わって、新しいものが生まれる。そこからもうひとつのアングルが生まれる。そのアングルは、誰かが20年余り前にものすごく上手くやってしまったから、もうやりようがないと思う奴もいるだろうけどね。
俺は確かに解放感や自由を感じたよ。バンドにはアーティストとしての自由はすごくあったけど、当然、ヴォーカルのレコードは作れないからね。ソロアルバムならアカペラ4重唱だって、ヒップホップだって、レコードを作ろうと思えば作れたんだ。このアルバムは俺の次のアルバムへの扉だと思う。これからどんな方向へ行くのも自由だ。ニューヨークっぽいものでも、ビートっぽいものでもね。選択の余地がまだ十分あると思う。次のレコードがどんなものになるか、期待させるだろ。それでも俺が(Verveの)『Urban Hymns』や『A Northern Soul』のために書いた曲と上手くなじむんだ。例えば全部を順番にテープに録音したとしても、アルバムからアルバムへと、すごくスムースにつながると思うよ。
――あなたはスタジオで何日も、何週間も、何カ月も過ごすタイプですか? それともスタジオでのありのままを記録して、翌日にはリリースするタイプですか?
RICHARD:ちょうど真ん中だな。実際に音楽を録音すること自体はすぐにできる。ある種のインスピレーションが沸いてくるんだ。ただ、じっと座って何かを学ぶってことができないんだよ。俺はそんなふうにはできない。他のミュージシャンやソングライターはやってるけどね。連中は音楽への取り組み方がえらく几帳面なんだ。俺はそんなふうにやったことはない。俺は骨組みのできてる曲、つまりピアノやキーボードやギターで歌える曲を持ち込んで、その段階から始める。曲の核さえあれば、周りをどうするかはほとんど2の次で、あとは勘に頼ってるんだ。あまり考えたりしない。で、その核みたいなものにカオスを足して、一方で歌詞に背景を加えて実際に歌えるようにする。すごくオープンなのさ。何をやろうが自由だった。楽しかったよ。
――洗練された自然発生的な音楽のようなものでしょうか……
RICHARD:うーん、何て言うか……、俺にとって音楽は瞬間なんだ。瞬間、瞬間をテープに記録することなのさ。ジャムセッションの最中に、凝縮された15分間っていうのがあるだろう。ところが、それが12分にまとめられ、あれこれ手を加えられ、15回もプレイされたら、2度と同じことは起こらないんだ。そこにはカオスが内包されている。そのカオスの中にアートがある。ただし、分析できるようなアートじゃない。行き当たりばったりの演奏によって新しい方向性が導かれ、失敗こそが素晴らしいサウンドを生む。つまり、それは自分の想像力を超えたものなんだ。
――Verveの成功であなたは名声を手に入れました。私生活に影響がありましたか?
RICHARD:イギリスでの生活は、明らかに大変になったよ。小さい国だからね。あのビデオはMTVで飽きるほど放映された。おかげで、みんなが俺自身や俺の音楽や、俺の表現するものについて、偏った考え方をするようになった。ビデオを作った時点で、そうなることはわかってたんだ。だからこそ、俺はビデオの中の通りを歩いているシーンで、ああいうふうに見えたんだと思う。あの時、俺は歩きながら、自分が大切にしていたたくさんの事から歩き去っていったんだから。
俺はプライバシーが大事だし、人から見られるより、自分が覗き見しながら歩くほうがいい。でも、俺はあえて身を売ったんだ。だから、甘んじて非難を浴びないといけないし、生活が変わったことを受け入れて適応しないといけない。「ああ、こんなビデオを作ったのはちょっと馬鹿だったかな」って。
でも、感じとしては……、一番最近作った自分のビデオと比べてみると、見方によってはイギリス映画みたいだと思うけどね。ところが、俺が主役ってことになると、現実との境界線があやふやになってしまうんだ。普通はアーティスト自身とビデオの登場人物を区別できるはずなんだけどね。俺がビデオをやると、境界線がすべてぼやけるみたいだ。で、通りで人にぶつかったのは俺自身ってことになる。みんな、目を覚ましてくれ。あれはビデオだったんだよ! 撮影だったんだ。わかるだろ? あれは現実じゃない。俺は通りを歩くとき、あんなことはしない。
いい面もあったよ。みんながアルバムのことを知ったんだから。でも、今思えば、みんなが知ったのはアルバムの1曲だけだったんだ。そして俺は、Rolling Stonesのレコードを拝借して通りを歩いた、ただそれだけの男のままだ。本当はそれだけじゃなくて、もっともっと中味がある。でも、現実としては、表に見えていることだけを鵜呑みにする人が多い。そういうものなんだ。彼らがこのレコードを買うかどうか、理解するかどうか、理解したいと思うかどうか、俺にはどうしようもないよ。
――新しいアルバムからは今までと違うサウンドが聴こえますが、どんなところが成長したのでしょう? ソングライターとしてどういう方向に向かっているのですか?
RICHARD:とてもシンプルなツールで、感情や感覚や精神をなんとか伝えられるようになった。想像力は広がったし、恐怖心もない。何人かにこのアルバムを聴いてもらったんだ。人によっては部屋に入ってきて、ペダルスチールの音を聴くとカントリーだと思ってドアを閉めてしまう。ペダルスチールを使うとそういう反応だ。でも、俺はそんなことは怖くない。レコーディング中、音に関してははそういう部分で成長してるんじゃないかな。ただ、歌詞に関しては、この数年で次第に核心をえぐるようになってきた。言うべきことがあれば、ちゃんと言う。それも、できるだけ少ない言葉で言うようにしてるんだ。
――どうしてペダルスチールを使うことにしたのですか?
RICHARD:単純にサウンドのことを考えてるだけさ。ソングライターとして、プロデューサーとして、今までとは違う新しい使い方をしたい。今までどんなふうに使われてたかなんて気にしない。俺がどう使うかが大事なんだ。俺の音楽にどうフィットするかの問題さ。ペダルスチールはすごくソウルフルな楽器で、ギターにできないことができる。ベーシックなギターミュージックには辟易してるんだ。だからギターによるハーモニクスが必要なら、かわりにペダルスチールを使うのは自然な選択だった。いろんなことができるからね。
アルバムには(スタジオミュージシャンの)BJがたぶん知らない音がいっぱい入ってる。BJがやると、エフェクトやペダルやいろいろ使って、すごくワイルドでブッとんだ音になるからね。さらに、その上にブッとんだギターを加えてあるんだ。例えば“Slow Is My Heart”なんかでは、中間の8セクションでBJのギターがうなってる。あいつのギターはほんとにスゴイよ。
――“Bitter Sweet Symphony”のサンプリングに関する苦い経験から学んだ教訓をひとつだけ挙げるとしたら、それは何でしょう?
RICHARD:学んだことなんて何もないよ。俺がいつも思っていたことがはっきりしただけ……だと思う。あのサンプルで重要だったのは、Staple Singersのあの曲を聴いたことのある人は、あんまりいないんじゃないかと思ったってこと。Stonesの曲は、タイトルはよく覚えてないけどStaple Singersの完全なパクリなんだ。でも、そっちのほうが本流になりつつあったから、俺は大もとの曲をピックアップして、今まで聴いたこともないような音に作り上げた。だから、ちょっとしたアート作品だったんだ。
もしサンプルを使わなかったら、同じサウンドにはならなかっただろう。ほんのちょっとした違いでも、まったく別物になってしまうという考えに取りつかれていたからね。あれを使わなければ違っていたかもしれない。そんなことは到底できなかった。遅すぎたんだ。もう完成してしまった。面白い音楽だったからリリースしたのさ。ワイルドな曲だったし、みんなに聴かせる必要があった。だから結果は後で受け入れることにしたんだ。発売されて、手に入れられるようになったとたんに、アメリカもイギリスもヨーロッパも飛びついたのは面白かったよ。そっくりなコマーシャルソングがいっぱい流れてる。すごく不思議だ。
本質的にあの曲は'90年代後半のポップアートだと思ってるんだ。君は“Bitter Sweet Symphony”、君は金の奴隷、そして君は死ぬ。突然、Nikeが出てきたり、Foxhill Cars……だっけ? が出てきたり。だから、俺は家でリモコンを持って待ち構えてる。そういうコマーシャルを見たり聞いたりしなくてすむようにね。すごく嫌なもんだよ。俺自身がすごく偏ったキャラクターに見られるから嫌なんだ。
――あなたの音楽がコマーシャルで流れることによって、もっとレコードが売れるのでは?
RICHARD:自分が信じていないもののおかげでレコードがもっと売れても、俺には関係ない。アーティストが商品を宣伝するのはどうも嫌だな。あいつらが、自分の宣伝してる商品を信じきっているとは思えない。お金のためだってみんなわかってるからね。
例えば(John Lennonの)“Instant Karma”のような曲とか、Stoogesっぽい曲のイメージを作り上げたとして、それが自分にとっては何か意味あるものなのに、コマーシャルに使われる。想像してこれほどがっかりすることはないよ。しかも、宣伝している商品がその曲に見合うほどの価値を持たないとすればね。曲のほうがよほど重要だったり、時間を超越していたり、価値があったりするんだ。俺にしてみればがっかりさ。他の人たちにとってはいいことかもしれないけど。意見が分かれるところさ。もう誰も俺たちの音楽をかけないから、コマーシャルが世界のジュークボックスなんだって言う人もいる。でも、それは言いわけだよ。
――ニューヨークに関しては、あなたが書いた曲のとおりですか?
RICHARD:そうだね。最後のヴァースではこう歌ってる。「ジュリアーニが君たちを一掃したって聞いた/でも、俺はいくらでも方法を見つけられる……」本当は「ろくでなしになる方法を」だったと思う。でも、編集してうまく変えたんだ。
俺が初めて来たのは、たかだか8、9年前だけど、その頃とは違う街になってる。どことなく違う街みたいに感じるんだ。ホームレスがみんなどこに行かされたのかもよくわからない。ベトナム戦争の退役軍人だって、'80年代の後半から'90年代初めまではまだいたんだ。軍服を着た人たちを見かけたものさ。あの歌はニューヨークにやってくるわがままなイギリス人のことを歌ってるんだ。奴らのために作られた舞台で、奴らは吸いつくし、飲みつくす。ホームレスさえ旅の一部だったんだ。「俺の映画の一部をどこへやったんだ? あれを見るために金を払ったのに。俺のホームレスを返せよ、ジュリアーニ!」あんたはめちゃくちゃにしちまった。観光客が来なくなるぞ。
――シングルの“A Song For The Lovers”はどんな曲ですか?
RICHARD:“A Song For The Lovers”……、メインはMarvin Gaye、それにAl GreenやBeach Boysの“God Only Knows”の影響が混じってる。あの手の曲はみんな恋人たちの歌なんだ。Al Greenの曲もほとんどそうさ。実際にインスピレーションを得たのは、たぶん(Joy Divisionの)“Love Will Tear Us Apart”だ。ちょうど情事を楽しもうとしてたときに、ホテルの部屋のラジオで聴いたんだけど、まさにぴったりというか、俺の人生のその瞬間の最高のサウンドトラックのように思えたんだ。当時としては、ちょっと古くさく聴こえたけど、俺にとっては最高のサウンドだった。おかげで“Play Misty For Me”のように男が聴きたがるラヴソングのアイディアが湧いてきたんだ。実際に俺が歌っているような曲を聴きたいんだなって。一筋縄ではいかない奇妙なコンセプトの曲さ。『Forever Changes』少々とScott Walker少々を溶かして、大きなシチュー鍋に全部放り込んで、何が出来るかなって感じ。
――普通、人は賢明なこともするし、馬鹿なこともするものです。あなたの場合、これまでのキャリアの中で、どんなことをしてきたかを話してくれますか?
RICHARD:俺がやったことで一番賢明だったのは、たぶん、ずっと人々を説得したり、だましたりしながら、俺たちはまず第一にバンドなんだってことをわかってもらえるようにしたことだな。一番馬鹿なことは……、俺たちはすごく馬鹿だって思われるようなことをたくさんした。1stアルバム(『A Storm In Heaven』)ではシングルを入れるのを拒否したんだ。俺たちはやたら熱血漢気どりで、「アルバムにシングルは入れねえよ、ファンはもう買ってるんだから!」って。コンセプトとしては素晴らしいけど、スタジオに入っても曲がないとなると事態は深刻だ。あとはそうだなぁ……、ばかなことばかりやってたよ。多すぎて、全部は言えないくらいだ。
――おそらくあなたがした最も賢明なことのひとつは、子供を持ったことでしょう。そのことで生活はどんなふうに変わりましたか?
RICHARD:息子が産まれてまだ7週間なんだ。けど、俺の中ではすでに大きな変化が起こってる。数カ月前、息子が産まれる前に、その先6カ月の計画を立てたんだけど、その計画をいま見ながら考えているんだ。おーい! 俺はヘルメットをかぶって、コットンウールにくるまれて、あいつが5才になるまで待ってるほうがいいっていうのか。それとも、かわいい息子を連れて世界中を回りたいんだろうかってね。そういうことを考えずにいられないんだ。
音楽について言えば、何か途方もないもの、時間を超越したものしか見えていないし、素晴らしい体験、圧倒されるような……、今まで知らなかった世界が開かれるだろう。これまでもそうだったからね。まだ楽器も決めていないし、どんな感じかもわからないし、どう表現したらいいのかもわからない。だってそうするにも言葉も単語も方法も見つからないんだから。
実際に感じるまで、どんな感じがするか全然わからないっていう状況だよ。ツアーをどうするかとか、その他のことをどう処理していくかとか、いろんなことが絶対に変わると思う。いい方向に変わるんだけどね。優先順位を決めるんだ。くだらないことは間違いなくカットされる。みんながストレスに感じてるようなことから、俺はもう開放された。優先順位と責任によって何もかもが大きく変わったってことだ。俺の意見も変わったよ。
――あなたについてはいろいろ書かれてきましたが、評論家たちはあなたを正しくとらえていると思いますか?
RICHARD:時どき、自分でも自分がわからないんだ。人は何でも作り上げすぎるんじゃないかな。興奮しすぎるんだよ。みんなが期待することはばかげてる、時おりね。いかれたこと、ヒッピーなこと……。わかってほしいんだけど、'90年代にイギリスで俺たちは「ニュー・グラム」だったり、「マンチェスター・シューゲイザー」だったり、「ニュー・シリアスネス」だったりした。そういうとんでもない代名詞が、音楽を始めたばかりの俺たちの行く手を待ち受けていたんだ。自分たちが何なのか、なんてわかってやしない。ただ大騒ぎしてるだけさ。ベストを尽くして、思いどおりの騒ぎの中から好きなものが生まれるのにまかせてる。
音楽を作ってると、必ず疑問を感じる時が来ると確信してるんだ。“尊大”なのは俺の趣味じゃない。俺もみんなと同じように不安なんだから。“尊大で決して壊れない”ような感覚に陥ると、いつか完全に無一文になる日が来ると思うし、それは最悪だ。だって自分が作り出したこの獣のようなもの、このフランケンシュタインのような怪物は、自分に似合わないんだから。わかるだろう?
――ツアーバンドを組む楽しみを手にしたわけですが、もう決めましたか?
RICHARD:レコードと同じように、できるだけビッグなサウンドを出せるようにしたいんだけど、それには12人は必要だ。6人か7人でもできるかもしれない。ドラムにはVerveのPeteを考えた。サックスプレイヤーとホーンプレイヤーと、キーボードが2、3人。ベースと、BJのギター。ビッグバンドを考えてるんだ。俺がギターを置いて、バンドにやらせるまでには時間がかかるだろうな。ちょっとJames Brownぽくするかもしれない。
――Verveの曲を演奏するつもりは?
RICHARD:俺が書いた曲を演奏するのになんら抵抗はないよ。最後のアルバムの7曲と、その前のアルバムの2曲、それにB面用にも何曲か書いた。全部演奏する可能性がある。それこそ、ライヴをやる意味ってもんさ。無敵のセットを作り上げるんだ。世界で他には誰もやれないセットリストをね。
――あなたが音楽的に高く評価している人は誰ですか?
RICHARD:俺はLou Reedの、みんなにクレイジーだって言われるようなところがすごいと思うんだ。ちょうど本で読んだんだけど、レコード会社の人が初めて『Metal Machine Music』を聴きに来た時の話があった。彼はそれを大音量の4チャンネルサウンドで台無しにしたそうだ。フィードバックやホワイトノイズでね。俺はおふくろがNeil Youngのことを話していたのを思い出したよ。おふくろは、『Harvest』や定番の曲を期待してマンチェスターに見に行ったのに、彼は出てきてヴォコーダーの曲ばかりやったんだって。なぜ、こういう人たちがそんなことをするのか、俺には理解できる。自分が“Lou Reed”であることや、“Neil Young”であることから逃げ出したくなる時があるんだ。でも、逃げ出せない。本当にすごい人たちだよね。Bob Dylanもすごいと思う。Van Morrisonも。
自分にとって成功とは何か、優先順位をつけなきゃいけないんだ。もしも成功が、自分のベストの曲を書いてレコーディングすること、自分の音楽に最大限の愛と魂を注ぐこと、レコードを完成させて世に出すことであるならば、それで達成される。それが成功だ。そういうふうに成功を理解すべきなんだ。それ以上を求めてそのことを忘れてしまったり、100万枚売ることが成功だとか何とか、そういう妄想に取りつかれ始めると、人はあまりの失望感にスタート地点からさらに急降下してしまう。Neil YoungやBob Dylanのような人たちは、いい時もあれば悪い時もあり、失敗作もリリースしてきた。あらゆることを経験しながらも、彼らは音楽を作り続けてきたんだ。それは難しいことさ。 |