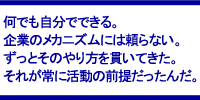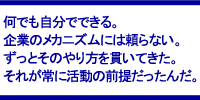 |
Duran Duranが同名タイトルのデビューアルバムで第2次ブリティッシュインヴェージョンを開始したとき、このグループが20年近く経っても健在であることを予想した者は極めて少なかった。彼らは批評家、懐疑主義者、その他多くのスノッブな音楽関係者によって、使い捨てのピンナップ向けビジュアル系美形バンドがまた1つ登場しただけとすぐに片付けられてしまったのである。だがDuran Duranは何回ものメンバーチェンジ、MTVとラジオのフォーマットの急激な変化、音楽プレスによる批判や攻撃、かつては思春期前だったファン層の高齢化、そして商業的に大失敗に終わった数枚のアルバム、といった数々の試練を乗り越えて生き残ってきた。そして彼らはいつものように自分たちのスタイルでそれをやってのけ、私たちに汗を流す姿を見せることなど決してなかったのである。
彼らは『Pop Trash』という図々しいタイトルの10枚目のスタジオアルバムを引っ提げて帰ってきた。オープニングを飾るのはゴージャスで甘美なバラード「Someone Else Not Me」で、「Save A Prayer」や「Ordinary World」といったDuran Duranのスローテンポの名曲を思わせる作品である。また「Lava Lamp」「Mars Meets Venus」「LadyXanax」「The Sun Dosen't Shine Forever」などの素晴らしい作品群は、Duran Duranがポップなソングライティングにかけては高度なドラマとスタイルを作りだすコツを忘れてはいないことを証明している。すべての“trash(ゴミくず)”が使い捨てとは限らないことは明白だ。
Duran DuranのSimon LeBon, Nick Rhodes, Warren Cuccurulloとの以下のインタヴューの抜粋ビデオは、LAUNCH on CD-ROMのIssue 42で見ることができる。また同ディスクには「Someone Else Not Me」をライヴ演奏する独占映像も収録されており、世界的に有名なプレイボーイマンションで「Girls On Film」さながらの光景が繰り広げられている。
――『Pop Trash』というのは素晴らしいアルバムタイトルですが、その背景にある意味とこれを選んだ理由は何なのでしょうか? 自己批判のようにもとれるのですが。
SIMON:そうだね、確かに『Pop Trash』と呼ぶのには、自分たちに対する自己批判が少し含まれてると思う。僕たちは20年間かなりの攻撃を受けてきたんだ。だから“言われる前に自分から言ってしまおう”みたいな気分になったのさ。まるで「Wild Boys」のビデオを作ったときに、“The Mad Max Factor”というフレーズを思い付いたようにね。だけど、『Pop Trash』には皮肉も含まれているんだ。'80年代に僕たちが駆けだしだったころ、NMEという音楽紙のインタヴューを受けたことがある。記事の最後に“せいぜい今のうちに楽しんでおくことだ。Duran Duranは使い捨ての中身のないポップスという意味では最高だが、来年には姿を消しているだろう”と書かれていたことは忘れない。その僕たちが20年経ってもこうして生き残っていて、今やNMEは部数を伸ばそうとBritney Spearsや'N Syncを表紙に使っているんだから面白いよね。まったくのお笑いぐさだけど、素晴らしいことでもあるよ。
それから『Pop Trash』には別の側面もあって、“ポップなゴミくず”というのは一種のカルチャーなのさ。つまりね、僕たちの暮らしている世界ではアートとコマーシャリズムが密接に融合しているんだ。今やレコードは映画と連係しないかぎりヒットしないし、こうした類の商業主義化されたアートが氾濫している。それは使い捨てのガラクタだから捨て去ることができるし、ずっと持っている必要はないんだ。それにとりたてて趣味の良い作品でもないという点も、僕たちが意味しているところなんだ。テイスト(趣味)というのは、誰もがこだわるべきものだと考えている。宗旨変えをしたら近所の人に何を言われるかわからないだろう。『Pop Trash』はエンジョイできる作品で、聞き込むこともできるけど、捨ててもかまわないものなのさ。
WARREN:『Pop Trash』というのはTシャツに描いたときに見映えが良くて、心の奥に引っかかる言葉だというのが、僕の基本的な考え方さ。つまり、優れたマーチャンダイズ商品を作ろうってことだよ。でも実際のタイトルは「Pop Trash Movie」という、Nickと僕が'96年に再結成したBlondieのために書いた曲から来ているんだ。この業界ではよくあることだけど、法律的な問題がいろいろと起こってリリースには至らなかった。Blondieはレコーディングしてくれて、当時Simonはそれを聞いてすごく気に入っていたのさ。それでニューアルバムを作るときに真っ先に選ばれた曲の1つになったわけだよ。
アルバムには1年半くらい前から『Hallucinating Elvis』という仮タイトルが付けられていたんだけれど、みんなが『Hallucinating Elvis』はいつ発売されるのかって聞くようになってきたから、それじゃ変えようかということになってね。そこで曲のタイトルから最後の言葉を切り落として、『Pop Trash』になったというわけさ。まったく適切なタイトルだと思うよ。だって最近の業界で起きていることを見てごらん、ガラクタでいっぱいじゃないか。Duran Duranはまさしく使い捨てのバンドだって、ずっと思われてきたからね。最初の頃は特にさんざんそんなふうに書かれたものだよ。だけど20年後に僕らは、自分たちの最も強力な作品の1つを作り上げたんだ。
NICK:Duran Duranにはずっと皮肉な側面があって、このタイトルには抵抗できないと思うよ。ある日「Pop Trash Movie」という曲にOKを出したんだけど、“Pop Trash”という言葉に目がとまってしまって、“うん、これはいいフレーズだよな。ポピュラーカルチャーの一部になるような何かを感じさせる響きがある”って考えたのさ。だから、多くのものごとを表す言葉だと僕たちは考えているんだ。実際に僕にとって“PopTrash”とは良い素材というか、僕たちが取り囲まれているあらゆるものごとという意味さ。例えばウィンドウディスプレイとか、安い食品のパッケージとか、生活の中にあるちょっと安っぽいものを表わすんだ。
――どうして「Pop Trash Movie」はBlondieのヴァージョンで陽の目を見なかったのですか?
NICK:「Pop Trash Movie」は確かにBlondieのために書かれたのさ。Warrenと僕が少し昔、そう3年ほど前に作ったんだ。ちょうどBlondieが再結成しようとしている時期だった。僕はずっと彼らのファンで、'80年代の初めに共演してからDebbie Harryとは連絡を取り続けていたんだよ。僕にとって彼らは消えてしまってほしくないバンドの1つだった。くだらない音楽ビジネスの食い物にされるなんて、悲しすぎる話だよ。だから、何曲か手伝えれば嬉しいと思って、ニューヨークへ行って彼らと一緒に「Pop TrashMovie」ともう1曲「Studio 54」というのを録音したのさ。素晴らしい出来で、彼らも満足してくれたと思う。だけどBlondieは、今では閉鎖されたEMI Americaとのつまらない訴訟騒ぎに巻き込まれてしまった。確か、彼らがEMIを訴えたんだと思うけど、例の曲は法律的なごたごたの中でどこかに棚上げされてしまって、使われることはなかったんだ。だけどSimonが「Pop Trash Movie」をとっても気に入って、“あれをやりたい”って言いだしたのさ。それで彼に合うようにキーを変えたんだけど、うまく歌ってくれたと思うよ。Blondieのヴァージョンとはかなり違った感じになったけどね。
――その2曲のBlondieヴァージョンが公開される予定はないのでしょうか?
NICK:BlondieのヴァージョンがNapsterにまだ乗っかってないのは驚きだよ。アップされてなくてよかったけどね。
――現在のボーイズグループの爆発的人気にともなって、VH-1では過去のティーンアイドルやボーイズグループを振り返るプログラムを数多くやっています。もちろんそこではDuran Duranが、常に'80年代におけるビッグなティーンアイドルのバンドの1つとして紹介されているわけです。だけど私としてはDuran Duranがそのカテゴリーに属するとは考えていません。皆さんはどうですか? それと現在のボーイズグループについてどう思いますか?
NICK:そうだね、大切なのは広い視野でものごとをとらえることさ。つまり、Duran DuranはBeatlesやDoorsと同じ場所から登場して、同じような反響を得ていたということなんだ。彼らにもティーンエイジャーのファンは大勢いたけど、オーディエンスはあらゆる層に広がっていた。オーディエンスの中身を理解せずに歴史を語るのは誤解を招きかねない。'84年頃の古い映像を見れば、オーディエンスが完全に多様化していることがわかるよ。もちろん、女の子はたくさんいたけどね。
彼女たちの強烈な反応に驚いたのは僕たちのほうだった。だって搾取や核戦争といったとっても暗いテーマの曲を歌っていたからさ。ステージで「The Chauffeur」みたいな曲を歌っても、ファンは黄色い歓声を上げているというのは、理解できなかったよ。僕たちが影響を受けたのはVelvet Underground、David Bowie、Roxy Musicとパンクロック、それにChicなんかのディスコものの一部。そんな背景から出てきたんだから、ファンの反応は理解できなかったし、あまり意味があるとも思えなかったね。だけど一方で、あれほど巨大なオーディエンスがいて、本当に音楽を聞きたいという人がいたのは素晴らしいことだった。どんな種類のオーディエンスであれ、そのことは常に感謝しなくちゃいけないよね。
WARREN:うーん“80年代のボーイズバンド”を取り上げるときに、Duran Duranやその他のグループがいましたと言うのはおかしいよ。実際は全然違ったんだから。BeatlesとかStonesとか、'60年代に10代のファンを多く集めたバンドを語るときにそんな言い方はしないだろう。これには流行りの曲やバンドを取り上げる雑誌とも大いに関係があって、今では飽和状態に達していると思うんだ。知ったことじゃないけど、音楽にはまったく関係のない話だよね。
最近の連中をグループと呼ぶにせよ、ましなやつらはTemptationsやFour Topsといった'60年代のヴォーカルグループに影響を受けているようだ。素晴らしい声を持っていて、振り付けは最小限に抑えている。だけど曲作りのクォリティということに関しては、Motownの曲を書いていた人々は素晴らしかったけど、今それに匹敵するソングライターはいないよ。
SIMON:現在の少年グループについての見解ねえ? 1つでもはまってなくて良かったよ。連中がコントロールを握るのは難しいだろうな。Backstreet Boysには独自のスタッフを開拓している兆しが見えるけどね。レコード会社やマネージメント事務所が、ショウビズに憧れるキッズに対してグループに参加しないか、みたいな宣伝をやって集めた場合には、非常に困難な状況になるだろう。連中はグループを結成させて、ダンスを教え込む。それが今では唯一の資格だからさ。つまりルックスが良くて、踊れればOKというわけだよ。メンバーは自分で曲を作らず、誰かが代わりにやってくれる。9カ月ごとにアルバムを出せるし、アルバム用の曲を半年から1年もかけて作る必要もないから、いいことかもね。
それに半分くらいのケースでは、自分たちのパートを歌っていなかったりする。だってライヴの時にテープに合わせて口パクしてるんだから、自分で歌っているわけないよな。生で演奏しているのはバンドだけだよ。悲しいことだと思うし、自分だったら、きっとエンジョイできない状況だろうね。僕にとってバンドの一員であるということは、ビッグビジネスに汚染されたり、制度でパターン化されていないアイデアを得るため、ということに尽きるよ。このアイデアは破壊的なもので、個人として存在するということなのさ。つまり、若さを保って“何でも自分でできる。企業のメカニズムには頼らない。自分がすべてなんだ”と宣言するようなものだよ。僕たちはずっとそのようなやり方を貫いてきた。それが常にバンド活動の前提条件だったんだ。
――みなさんは音楽業界の激変を目のあたりにされてきたと思うのですが?
SIMON:まったく近頃の音楽業界には驚かされるよ。とっても企業化が進んでいる。ハーバード大でビジネスを勉強した連中を迎え入れて、感覚と魂の世界に分析的なビジネスの見方をあてはめようとして、そこから多くの儲けを導きだそうとしているのさ。だけど自然のサイクルというやつがあって、必ず反動が起きると思う。'70年代の終わりに、恐竜のようなロックバンドに対して大きな反動が起きたようにね。僕たちみたいな連中が集まってパンクロックが誕生したんだ。それはまるで(2本の指を突き上げる)ようなものだった。そうだろ? それがまた起きる、そんな方向にあると思うよ。つまり、インディペンデント系といっても、今じゃみんなメジャーの傘下にある。だから、オフオフブロードウェイみたいにインディペンデント=インディペンデントになっていくだろう。わかるかい?
――現在の音楽状況においてDuran Duranをどのように位置づけられますか?ボーイズグループや極めてマッチョなラウドロックの隆盛は、あなた方の存在に対するアンチテーゼとも思えるのですが。
SIMON:ラウドロックの連中がどうしたって言うんだい? 連中みたいなのをイギリスじゃラガーラウトって呼ぶのさ。つまりビール飲み(の無骨者)と同じ意味だよ。僕たちのポジションがどこにあるかって? その2つのカテゴリーに入らないのは確かだけど、そういうのにうんざりしている人も大勢いるし、その時どきのチャートで何が入っているかに惑わされない人だってたくさんいるんだ。そんな人たちが気に入るようなことを僕たちがやっていればいいんだけどね。
イギリスではTravisみたいなバンドが成功を収めていて、こうした傾向は明白なんだ。彼らは非常にトラディショナルな曲作りをする連中で、カントリーのサウンドを施したフォーキーって感じなんだよ。イギリスではこの2年で最大のヒット作になっている。アメリカではどうなるかわからないけどね。彼らがイギリスで上手くいくのなら僕らも大丈夫だし、彼らがアメリカでも上手くやれるのなら、僕らやれるだろう。それに加えて僕らには熱心な信奉者がいてくれて、いったん火がつけば彼らも動きだして、大きな流れになるだろうし、そうすれば僕たちも新しいリスナー層を引きつけることができるかもしれない。
NICK:そうそう、面白いことにね、Limp BizkitとKornの両方がDuran Duranについて本当にいいことを言ってくれてるんだ。連中が成長した時期に僕らが活躍してたってことだろうね。僕たちが彼らに与えた直接的な影響は僕にはわからないだろうけど、僕らがやっていたことに関して彼らが大きな評価を与えてくれていることは確かなようだ。もちろん彼らがやっていることについて僕も同じ気持ちでいるよ。必ずしも店に買いに出かけて家で聞くような種類の音楽じゃないけど、Limp Bizkitの最初のやつはとってもクールだったし、Kornも素晴らしい。ジャンルは違うけど、少なくとも僕には面白い音楽だね。
WARREN:Limp BizkitとKorn、それにKid Rockとか、最近出てきた音楽はけっこう好きだよ。ロックンロールの歴史を通じてブラックミュージックがどれほど白人のミュージシャンに影響を与えてきたか、それを確認できるのは素晴らしいことだ。同じようにファンクも白人の音楽に取り入れられていったし、ラップが入ってきているのもいいことだと思うよ。だってBlondieが「Rapture」をやったとき、僕は“ワォ、時流に乗ってるな”と思ったのを覚えているよ。もちろん曲は好きだったし、いいメロディだったけど、こんなトレンドがいつまで続くのかって考えたのも確かだ。それが今では、僕もインスピレーションの多くをヒップホップから得るようになってしまった。そのすべてがDuran Duranの音楽に反映されているわけじゃないけど、近頃の一番面白いことはヒップホップの世界で起きているというのが僕の認識なんだ。
――「Notorious」のサンプルがPuff Daddy/Notorious B.I.Gの曲に使われたのをどう思いましたか?
WARREN:Puffyは裕福で趣味のいい男だ。ヤツがピックアップしたサンプルの中じゃましなほうの1つだと思うよ。まるでNotorious B.I.Gのためにあつらえたようなもので、彼もLil' Kimもいい仕事をしたと思う。実際のラップの技術は難しいということを一般の人は理解していないから、“ウーン、音楽はいいんだけど、ラップは好きじゃないんだ”なんて言うのさ。だけど、連中がやっていることにちゃんと耳を傾ければ、タイミングが命で声の質が極めて重要なのもわかるはずだ。古い曲をサンプリングして、そこから何か新しいものを作りだすというアイデアは好きだし、自分を表現する素晴らしい手段だと思うね。多くのリスナーにとっての親しみやすさが出るし、同時に何か新しいものを加えることもできるんだ。それに他のアーティストが10年、20年前に作った音楽を、まったく違ったオーディエンスに紹介することにもなるのが素晴らしいよ。
――Duran Duranに影響を受けたという若手で、人気上昇中のアーティストは他にご存じでしょうか?
WARREN:そうだね、これは僕がいたMissing Personsなんかの80年代初期の多くのグループにもあてはまることだと思うよ。No Doubtがそんなバンドに大きな影響を受けたと言ってたね。Kornは数年前にある雑誌のインタヴューで、ツアーの時にDuran DuranとMissingPersonsのアルバムを聞いていると語っていた。僕にとっては、1つの短い文章の中に2つのグループが存在しているのは信じられないことだったよ。なんだかおかしくてね。つまり20年前に音楽を作っていれば、そのころ5歳か7歳か、もうちょっと年上の子供たちがその音楽を聞いて気に入って、それで楽器を手にしたなんてことが起こりえるのさ。まるで僕がElvisやBeatlesを聞いて、ギターを弾きたくなったようにね。必ずしも大きくなってからラジオで聞いて育ったのと同じような音楽を作るようになるってわけじゃないけど。だけど、そうしたアーティストとの出会いには何か意味があって、自分も音楽をやりたいと思うようになり、世に出て音楽を作り、人々を楽しませることを一生の仕事にするくらいに、エネルギーを注ぎ込むよう無意識のうちにさせられているんだ。
SIMON:確かに僕たちは多くのバンドに影響を与えたけど、長い間ずっと人気があったから、そうなるのも当然だったと言えるね。HoleはDuran Duranの曲をカヴァーしているし、NirvanaもDuran Duranの曲をカヴァーしてくれた。だけど今では僕たちはFred Durstのような人に注目している。彼は影響の1つとして僕たちを挙げているし、KornのJonathanも僕たちの影響を受けたと表明しているんだ。彼が今やっていることからすれば、まったく信じられないよね。彼の音楽に影響は聞き取れないけど、僕たちの音楽がどのように作用したのかは理解できるよ。僕はJoni Mitchellに大きな影響を受けているけど、そんなことは僕の音楽からは聞き取れないだろう。
――他にファンが驚くような意外な人から影響を受けていますか?
SIMON:James Brown、それにJim MorrisonとDoorsだね。Doorsをバックバンドみたいに言うつもりはないけど、僕はJim Morrisonを、特に歌詞作りの面でDoorsとは少し切り離して捉えているんだ。David Bowieは言うまでもないよね。面白いものもいっぱいあるよ、聖歌隊で歌っていた教会音楽とか。
――最近、Duran Duranのトリビュートアルバムが出ました。GoldfingerやReelBigFishなど、あなた方の影響を受けたと言うスカやパンクのバンドが大勢参加しています。どう思われますか?
NICK:そうだね、最初にそのトリビュートアルバムを聞いたときは、かなり驚いたよ。Eve's Plumがやった「Save A Prayer」が気に入ったね。とってもいいよ。でも、僕たちが影響を与えたとか、僕たちの曲が好きだったとは思えないようなアーティストたちだからさ。いくつかのトラックは気に入ったけどね。それでDuran Duranについて言えるのは、僕たちが多様性をずっと維持しようと努力してきたということだよ。自分たちでバリアを築いたことは一度もなかった。つまりね“あれをやってみよう、ちょっとヒップホップみたいなのをやろう、今度はアンビエントな作品だ、オーケストラを使う曲はどうだろう、それにバラードやグルーヴものも”といった具合なのさ。僕らはたくさんの違っタイプの音楽が好きだから、こういうのが僕たちのやり方なんだ。
――実際のところ『Pop Trash』は前作の『Medazzaland』よりもバラード志向のようですが、これは意図的な選択だったのでしょうか? 『Wedding Album』は2曲のシングルヒットしたバラードのおかげで大成功を収めましたからね。バラード作戦に戻るというのは意識した戦略だったんですか?
NICK:アルバム全体のテンポは、おそらく前のやつよりも少しスローだけど、別に意図的なものじゃないよ。そんなふうに曲が集まったというだけなんだ。面白いと思える曲を集めていったら、結果的にスローなテンポの曲がそろったということさ。例えば「PopTrash Movie」はストーリー性のある伝統的な意味でのバラードで、“Pop TrashMovie”とは正しくそういうものなんだ。言っておくけど「Last Day On Earth」は、たぶん僕たちがアルバムでやった曲では、かなりの長い期間の中でも最もテンポの速い曲だよ。だからアルバムには光と影のようなコントラストがあるのさ。でも、それも特別な理由があってのことじゃないんだ。
WARREN:『Pop Trash』に関しては、腰を落ち着けてたくさんの曲を作った。“バラードをもっと作らなくちゃ”みたいな、事前にコンセプトを立てたことは全然なかったよ。バラードの1つ「Pop Trash Movie」は、アルバムが完成してから追加された曲だしね。一番最初のころに書かれた「Sun Doesn't Shine Forever」と「Someone Else Not Me」の2曲は、両方が同じアルバムに収録されるかどうかもわかっていなかったんだ。このアルバムには「Lava Lamp」とか「Hallucinating Elvis」みたいにとってもアップテンポの曲も入っているけど、おそらく僕たちがやった曲の中で最も速くて最もアグレッシヴな曲の1つが「Last Day On Earth」だろう。曲のバランスがとってもうまくとれていると思うよ。確かにこれまでは、1つのアルバムにシングルになりそうな本当に優れたバラードが3曲も入っていたことはなかったけどね。そこが従来との違いなんだろうな。どの曲もすごく強力なのさ。
SIMON:僕にとって『Pop Trash』はバラード集ではなくて、前のアルバムでやったような機械仕掛けの音楽に対する反動という意味が大きいんだ。曲を書くというよりも製造するといった感じのエレクトロニック音楽で、筋肉質の音楽じゃないのさ。それで特にWarrenと僕が筋肉質の音楽に回帰する必要があると考えたんだ。それは僕たちのある種のルーツであり、聞いて育った音楽であり、僕らが得意とする分野でもあるよね。バラードというのもその流れから出てきたようなもので、自分にとってよりナチュラルに響く音楽を追求した結果なんだ。でも「Pop Trash Movie」はバラードじゃなくて、エピック(叙事詩)だよ。
――Warrenはバラードと言ってましたけど。
SIMON:Warrenは頭がイカレちゃってるからね、まったく大馬鹿野郎だよ。「Pop Trash Movie」はエピックであって、バラードではない。バラードとはストーリーを語るちょっと短い歌で、「Someone Else Not Me」ならバラードと呼んでもいいと思うよ。つまりジューシーな感じでテンポが遅めの曲って意味だよね。確かにそういう曲なら今度のアルバムにいっぱい入っているけど、それが今の気分に合っているということさ。だけどアルバムに入っているのはそんな曲だけじゃないよ。たぶん僕たちが歳をとるにつれて、気分がスローダウンしていっているんだろうね。
【後編に続く】
|