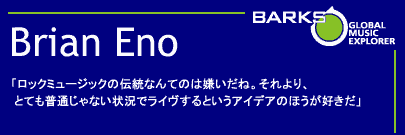『Drawn From Life』
BRYAN ENO & J. PETER SCHWALM
Virgin Internatinal VJCP-68327
2001年7月25日発売 2,548(tax in)
1 FROM THAT MOMENT
2 PERSIS
3 LIKE PICTURES PART#1
4 LIKE PICTURES PART#2
5 NIGHT TRAFFIC
6 RISING DUST
7 INTENSER
8 MORE DUST
9 BLOOM
10 TWO VOICES
11 BLOOM(INSTRUMENTAL)
| | | 「私はほとんどの時間をここで過ごしているんだ」。Brian Enoはロンドンのノッティングヒルにある、スタジオと作業場に改装された19世紀の小さな家を案内しながらそう言った。玄関の横には快適なレコーディングルームがあり、彼は少し前までそこに座ってベースギターで何か即興演奏を録音していた。今はEnoの4年ぶりとなる新作『Drawn From Life』でコラボレートしたドイツの若いDJ、J. Peter Schwalmがコントロールデスクに陣取り、その即興演奏を何か新しいものに変えようと操作している。
次に向かったパーティションで仕切られた一角には2台のコンピュータがあり(「昼も夜も、ここでかなりの時間を過ごしているよ」)、1台は次々と形と色が変化するEnoのプログラムを、もう1台は次々とサウンドが変化するプログラムを走らせていた。この部屋は白い壁のギャラリースペースへとつながっており、そこには同じ機種のチープな大型ラジカセが掛けられている。それぞれに異なったEno作品のCDがセットされてエンドレスかつアトランダムに再生され、サウンドが1台から1台へと漂うように行き来して、その瞬間ごとにユニークで予想のつかない組み合わせを次々と生み出している。これは「自己生成音楽、つまり自らの命を持つように設計された音楽」を作るための実験の一部だという。ポストイットのノートにダイアグラムを走り書きしながら説明するEnoはエキセントリックなコンピュータの魔術師そのもので、今も私たちが期待する通りの人物だ。
こんなに静かな白い空間――天窓の上ではブラックバードが音楽に合わせて歌っていそうだ――にはどこか不釣り合いな、迷彩色の服を彼が着ていることを除けば。
'97年に前のアルバム『The Drop』をリリースして以来、Enoは音と光のインスタレーション(サンフランシスコの現代アート美術館に最新作がある)の創作、本の執筆やU2やJamesといったバンドのプロデュースといった書ききれないほど多くのプロジェクトを手がけるかたわら、ある種の戦争を闘っていた。それは、音楽におけるコンピュータの支配に対する闘いという、彼にとってはむしろ予想外のものだった。
最初は“人さし指の戦い”だったという。「優れたプレイヤーを見れば、肉体のさまざまな部分のすべてを使って、体の動きに反応する楽器に対応していることがわかる。各パーツは同時に多次元で動いていて、そうした次元の多くは論理を超越したものなんだ」とEnoは語り始めた。
「コンピュータ作業の基本は、頭脳だけが判断して人さし指だけが実行するというアイデアに規定されている。人間の小さな一部だけで音楽を作るのと、肉体、知性、感情、美意識、精神といった全体像を反映させるのとでは、どちらが望ましいのだろう? 私はその問題を解決しようとずっと努力してきた。いつでも自分にできるかぎりのものを最大限取り入れたいと思ってきたし、自分の存在の中の小さな部分だけを使ってコンピュータを操作するのにも退屈していたのさ。コンピュータのデザインは最悪なものばかりだからね!」
友人からSchwalmのファーストアルバム『Slop Shop』を渡されたとき、Enoは仲間の戦士にであったと認識して、ミーティングを持つことになった。「彼もその問題を感じていて、同じように考えていたんだ。彼は別の方向からやってきて問題にぶつかったのさ。私はオーガニックな音楽からコンピュータの方向にトライして問題を見つけたのに対して、彼はコンピュータから始めてライヴ演奏やインプロヴィゼーションをするようになって、両者の有機的な結びつきを何とか実現したいと考えたんだよ」
「私たちは一緒に音楽を作る以外にたくさんの研究を進めてきたけど、新たな作業の方法へと発展しつつあるんだ。つまり、一般の人たちがいつも演奏しているのと同じように、実際に演奏されるそのままの形を正確に捉えたうえで、その時点でしばらくコンピュータの世界で進んでいくのか、それとも生演奏の世界に戻っていくのかを選択できるのさ。双方の可能性を締め出すことなしに、両方の間を自由に行き来できるというのが望ましい形なんだ」
何でも同じ長さのセクションに分割しようとする、コンピュータの飽くなき欲望に関する複雑な説明(残念ながら長すぎてここには掲載できないが)は問題の難しさを物語っているが、それこそがコンピュータのやりたいことであり、実際に行なっていることなのだという。「バンドと一緒に仕事をして部屋にコンピュータがあったら、結局、その作品のコンポーザーは色あせたRolling Stonesの1982ワールドツアーのTシャツを着てディスプレイの前に座り、12年間ピザ以外のものを食べていない男で、バンドはそいつにすべてを委ねて座っているだけだということが確実にわかるだろう。その男は天才かもしれないけど(そうだったらいいけど)、バンドの連中ほど面白いわけではないということが往々にしてあるのさ」
EnoとSchwalmは一緒に仕事をしてジャムセッションをする以外にも、個々に録音した音楽作品をやり取りして(アヴァンギャルドなヒップホップDJであるSchwalmは、フランクフルトに自身のスタジオを構えている)ダビングや編集を加えている。「数カ月ごとに2、3日ずつと、かなり頻繁に会ってはひたすら一緒に演奏するんだ。彼はドイツにコピーを持ち帰って、私はここに残って別のコピーで作業を進める。一部分を取り出してコンピュータで編集して何らかのストラクチャーに仕上げたり、ちょっとしたループ作成マシンに取り込んでそれをベースに作業をしたりするのさ。だから次に彼がやって来るときには、前にやったものをベースにした新しい提案が用意されていて、それに編集やダビングなんかを次々に加えていくんだよ」。『Drawn From Life』に収録された作品の一部は「こうした再編集と蒸留のプロセスを少なくとも6回は経て制作されている」という。
最初のミーティング直後の'98年に、EnoとSchwalmはドイツでのステージで共演している。これはEnoにとって'90年代で最初のコンサートだったが、さらに何度かライヴショウを行なう計画もあったという。つまり、今年予定されているRoxy Musicの再結成ツアーへの参加をEnoが拒否した理由として、最近Bryan Ferryが挙げていた“彼はステージで演奏するのが大の苦手なのさ”という話はこれで信憑性がなくなったようだ。
「ロックミュージックの伝統なんてのは嫌いだね。私には耐えられないよ!」とEnoは認める。「それよりも、とても変わった状況でライヴするというアイデアのほうが好きなんだ。富士山の麓でショウをやるとか、それからアクロポリスやスロヴァキアの洞窟なんかもいいね。でも一般的にライヴ演奏なんてのはくだらないアイデアだよ。ステージでの作業の多くはパーソナリティのプレゼンテーションなのさ。“おお、あれこそが彼だ!”なんてね。私はそんなのに関心を持ったこともないよ。それに音楽の面では絶望的だしね。自分たちの演奏をちゃんと聴くことさえできないんだから。初期のRoxy Musicのコンサートだって単なるノイズの塊みたいなもので、自分たちがどんな演奏をしていたかなんてまったくわからなかったよ」
それは別にしても、常に変化を求めて実験する姿勢からも明らかなように、Enoは同じことの繰り返しを好まない。「過去に生きるなんてごめんだね。私はいつでも何か新しいことをやっていたいんだ。常に忘れることを心掛け、物事を頭から追い出すことに懸命なんだよ」、彼は笑いながらスタジオを見回して言った。「だったら、少しとっ散らかっているけど、ここにいて“これだ”というものを探していたほうがいいからね」 By Sylvie Simmons/LAUNCH.com | |