選ばれし者

選ばれし者 |
シンガー、ソングライター、プロデューサー、そしてアレンジャーでもあるBrian McKnight は、いわゆるマルチな才能を持つ人間のひとりで、引き受ける仕事という仕事に卓越した腕を見せてくれる。 彼のインスピレーションのルーツは、ゴスペルやジャズに深く根差したものだが、最初のパフォーマンスはティーンエイジャー時代のフュージョン・アンサンブルとの共演だった。 やがて彼は、ひと夏に集中して書いた65曲から選曲したデモを制作。そのテープをあちこちに配った結果、2週間後にはMercuryとの契約を獲得し、'92年にはデビューアルバム『Brian McKnight』でトップ20入りを果たした。 また、自らのレコーディングのかたわら、Vanessa WilliamsからBoyz II Menにいたるまで、数多くのアーティストに曲を提供し、プロデュースも手掛けた。 かつてはプロのバスケットボール選手の道に進むことを真剣に考えたこともあるMcKnightは、カリフォルニア州ヴェニスビーチの海岸近くのコートでも、たびたびその姿を目撃されている。彼はコート上で自分の持つ競争心を発揮したり、“どこにでもいるような”男に戻るのである。 「どんな子供もプロになりたいと熱望するものだよ」と長身の彼はかつて自らも抱いたNBA入りへの憧れを語る。 「でも、自分の夢のすべてが叶えられるわけではないことに俺はすぐに気がついた。今現在はミュージシャンになるという夢を生きているんだ」 |
LAUNCH:あなたのヴォーカルパフォーマンスには実に様々な感情が込められていますが、あれほど自由に熱意を込めて感情表現するためのインスピレーションを、どのように手に入れているのですか? BRIAN: 楽曲にはそれぞれ異なるインスピレーションがある。とても個人的な想いのこもった曲。純粋に想像力から生まれた曲。インスピレーションの源は何かというと、少なくとも俺に関して言えば、小さい時から教会で歌いながら育ったことで、歌のテーマからあらゆる感情を引き出す術を身につけた、ということになる。それからオーディエンスにいかに共感してもらえるかということも学んだ。なぜなら歌うというのは人々を感動させることだからさ。俺はその頃から変っていない。マイクの前に立つといつでも、俺の歌を聴いてくれている人、つまり、慰めの必要な誰かがいることを思い出す。個人的な想いを込めるのは、そうすることでリスナーも個人的な共感を覚えてくれるからだ。それは役者をやることからも学べることだね。自分のやっていることを人に納得してもらわなければならない。ライヴを聴いているお客さんが望むのは、そういった類のプロフェショナリズムだよ。 LAUNCH:そんな風に自分のすべてを注ぎ込むために自分を奮い立たせるのは、難しいと感じる時もありますか? BRIAN: それはライヴでよりもスタジオでの方がさらに難しいね。ライヴでは、オーディエンスのフィードバックを得られる。でも、スタジオで自分しかいなければ、自分の感情や想いに自分で共感しなければならない。反応を返してくれる人はいないからね。それが大前提になる。もし同じ空間にいる他の人間が感じてくれれば、俺も感じることができるんだけど。 LAUNCH:ヴォーカル録りのためにスタジオ入りする時の様子を教えて下さい。 BRIAN: 今はコツというものが身についていると思うし、それを出したりしまったりもできる。難なくそうなったと思っている人も多いけど、俺はこういうことを12年も13年もやってきているんだ。それからもうひとつ重要なことは、俺自身が楽曲も手掛けているということで、それは他人が書いた歌詞を読むのとはわけがちがってくる。マイクの前に立つまで、俺は自分の曲を頭の中にしまっておく。ヴォーカル録りに30分も40分もかけることは決してない。それ以上かけたら機械的なサウンドになってしまうから。ミスはいつだってある。でも、大事なのはいかに感情が込められるかってこと。完璧であることよりもね。 LAUNCH:ヴォーカルに対してはどんなアプローチをしているのですか? BRIAN: 楽曲のための道具になるということ。俺にとっては曲が最も重要な要素だ。時々、20年前の曲を耳にすることがあるけど、シンガーは思い出せなくても、歌詞は覚えている。俺も自分の歌にはそういったアプローチをとっているんだ。職業欄を埋める時は、いつも「ソングライター」と書き、決して「シンガー」とか「アーティスト」とは書かない。シンガーというものは、現われては消えていくものだから。 LAUNCH:あなたにとってアイドル的存在のシンガーというのはいますか? BRIAN: そいつはすばらしい質問だ。ハードなシンガーもソフトなシンガーも好きだよ。Luther(Vandross)が歌っているのを聴くと、美しい声だと思うし、心地良く、耳元にささやかれるような感じだよね。でも、Stevie(Wonder)の場合はパワフルだ。James Ingramもそうだけど、やっぱりパワーなんだよね。Jamesは高音も出せるし、低音も問題ない。俺が惹かれるのはそういったシンガーさ。両方が出来ることが大切だよ。俺はJamesやMichael McDonaldをお手本にしている。こういったシンガーたちが俺に向上心を与えてくれるんだ。 LAUNCH: Stevie Wonderには会ったことがあるそうですね。 BRIAN: おかしな話さ。ニューヨークに日曜日は誰もがマイクを使える場所がある。ある晩そこにSteiveが来ていた。彼は俺と一緒にステージに上がり、こう言ったんだ。「「Anytime」を私のために歌ってくれないか。一番お気に入りの曲だからね」。…あれ以上の誉め言葉があるだろうか。彼は俺が毎日、彼の真似をしているのを知っているんだ。彼こそが俺にとってのゴッドファーザーだよ。Steive Wonderの業績に影響を受けていないなんて言える人間はいないさ。 LAUNCH: StevieやLutherのような人が築いたソウルの黄金時代は過ぎ去ってしまったと思いますか? BRIAN: その質問が四六時中持ち出されるのは、非常に興味深いね。「我々はあそこへ戻れるか? 音楽はあの時代に戻れるか?」…云々。俺には分からない。音楽は日々変化しているし、次にビッグになるものを予測するのは難しい。俺は自分のやることをやって、それが大勢の人々に受け入れられることを望むだけだ。Marvin(Gaye)やStevieが大変革を起こした25年前の音楽状況とは今は違うから。今や誰にでも手に入るテクノロジーが揃っている。誰かの先を行くというのは一筋縄ではいかない。Stevieは曲を生み出すためにテクノロジーを用いたわけではなかった。曲の魅力をより高めるために使ったんだ。俺も自分の作品を引き立たせるために色々な道具を使うが、道具を引き立てるために自分の作品を使うことはないよ。 LAUNCH: テクノロジーを使いこなすことが得意なミュージシャンは、もっと本質的なアコースティックな楽器にも熟練した腕前を見せられるものでしょうか? BRIAN: テクノロジーに慣れている人にアコースティック楽器をやらせるのは簡単じゃない。そんなことしなくても成功している人がたくさんいるのを彼らは知っているから。俺はピアノやギターの弾き方を学ばなければならなかった。パッチではなくてね。ドラマーがドラムをプレイしたり、ドラムをプログラミングするのと、キーボーディストがドラムをプログラミングするのとはわけが違う。お手軽にテクノロジーを身につけることは出来るだろうが、10年、15年とこの世界でやっていくつもりなら、たとえ曲が書けても、楽器を演奏することを覚え、基礎を身につけるべきだ。いつも同じように同じサウンドが出せるわけではないけれど、基礎さえしっかりしていれば、何かを創り出すことができるんだ。 LAUNCH: 最初に自分の音楽をレコーディングした時はどんな気分でしたか? 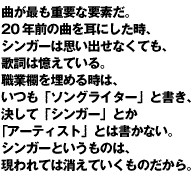 BRIAN: BRIAN:お菓子屋にいる子供みたいだった。俺はずっと、自分の頭の中にある音楽が、実際に録音されるとどんなふうに聴こえるのか聞いてみたかったんだ。舞い上がってしまったよ。山ほどの曲を書いても、レコードで聴きたいと思ったり、商業的に成立するようなのは20曲に1曲だからね。今後も曲をたくさん書いていくつもりだけど、俺には公式のようなやり方があるんだ。時折、万能札のような曲が出来ることもあるよ。でも、俺の書く曲の多くは自分のためだけに存在している。至極単純なことだよ。今日はR&Bの曲を書こう、というようには考えない。カテゴリーで考えることはない。俺のオーディエンスは実に幅広いんだ。ニューヨークでは孫を連れたお年寄りの姿も見かける。俺に出来るのは、すばらしい曲を書く努力をすることであり、それを他人がどのカテゴリーに分類しようが、かまわないさ。 LAUNCH: あなたはジャズ狂で、ティーンエイジャーの時にフュージョンをやりだしたのがスタートですよね。そういったバックグラウンドは、あなたの今の音楽にどのような影響を与えていますか? BRIAN: ミュージシャンには、一番難しいものをこなせるようになりたいという欲求がある。それはクラシックだと考えるのが一般的だろうが、クラシックはすべて楽譜があり、難しいのは楽譜上の音楽を間違えることなく演奏することだ。ジャズの本質はインプロヴィゼーションであり、瞬間を捉えることが大事で、今こういう風にやっていることは、二度と同じようにはできない。俺は巨匠たちを研究したよ。今はベンチに座っているベテランの人たちのように俺もバスケットボールをやりたいのか? 俺はマイケル・ジョーダンのようにプレイしたい。Thelonius Monkのような本当に深みのあるピアノプレイヤーたちに感じる気持ちもそれと同じだ。映画『Shine』に出てくる子供にRachmaninoffが与えた脳をも溶かしてしまうような感動を、Monkは与えてくれるよ。音楽は最大の感動を与えてくれる芸術形式だ。なぜならそれは視覚的なものではないからだよ。あんな風に心を動かせるものはこの世にふたつとない。俺は成長期にジャズからそんな感動を受けた。ジャズが出来る人間にはシンプルなことも出来る、というわけだよ。 LAUNCH:若い頃にそのような意欲的で複雑な音楽をやり始めた時、違和感を感じませんでしたか? つまり、他のキッズのようにシンプルなポップミュージックにもっと興味を持つべきだという気持ちにはなりませんでした? BRIAN: 同じ音楽の趣味を持っている友達を見つけるのは難しかった。でも、それで孤立したわけじゃないよ。俺はあらゆることに興味があったからね。俺の父は子供たちに、いかなる環境にも適応することを教えてくれた。アウトサイダーでいることよりも、色々なことに積極的に関わり、上達したいという心をね。俺は学業は苦手だった。だが運動選手であり、ミュージシャンだった。どんな状況からも締め出されるのはいやだった。それが何よりも大切なことだったと思う。 LAUNCH:ジャズとポップミュージックを比較するとどうですか? 大きな違いは何でしょう? BRIAN: ジャズはとにかく商業的ではない種類の音楽だ。ポップミュージックを扱うということは、音楽的な造詣が深くない人たちを対象にしているということになる。見くびっているわけではないよ。だが、分かり易いものを聴いてきている人たちなんだ。俺にはジャズができるし、そこに心の拠り所を持っているから、自分の本来の姿を満足させるためにシンプルなものに戻ってくる必要がある。普通の人間には理解できないかもしれないがね。音楽的なフラストレーションをすべて吐き出すことができてこそ、またシンプルなものに戻ってこられるのさ。ヒット作品にならないとしても、自分の中の音楽人間を満足させてくれるんだ。 LAUNCH:現在作っている音楽にジャズの要素を取り入れるつもりはありますか? 商業的に成功させるには、どのように取り入れればいいのでしょうか? BRIAN: 世間にはそういった音楽を聴きたいという人もいると思う。俺もずっと若い頃、自分の出来ることは何でもかんでも世の中の人に披露したいと思っていた。だからこそ俺の音楽もそういうサウンドだったわけだよ。ジャズを採り入れ、ジャズに対する愛のすべてをレコードに表現した。それで19歳という年齢を超えた自分を示すことも出来た。ただし、あのサウンドは理解を超えていると思った人もいたかもしれないがね。年を重ねた今、俺はレコードの売上げを意識するようになった。『Anytime』はジャズの要素を取り入れることが可能なことを証明してくれたが、やはりヒットを出し続けることも大切だ。Lionel Richieに言われたよ、批評家の言うことなど忘れろってね。だが次々にヒットを出し続ければ、何も心配しなくてすむんだ。 LAUNCH:批評家にどう思われているかが気になりますか? BRIAN: 音楽を解さない人たちの言うことに耳など傾けていられないよ。『Anytime』がリリースされた時、評判は悪く、最初は俺も傷ついた。曲というのは自分の子供と同じだからね。「おまえの子供はみにくい」なんて聞きたくない言葉だ。でも、俺にはあれが良い作品で、売れると分かっていた。少し時間をくれよってね。そしてその通りだった。批評家の言うことに気を取られてはいられない。彼らに自分の気持ちをくじかれるなんてまっぴらだ。自分の信念を守ることが大切だよ。 LAUNCH:ジャズへのアプローチ、そしてR&Bへのアプローチは、今演っているような音楽に対するものと異なりますか? BRIAN: 楽器が違うね。俺がプレイできるようになった楽器は、ほとんどがハイスクール時代に習い覚えたものだ。ハイスクールの時はジャズ=フュージョンのバンドを持っていて、俺はキーボードプレイヤーだった。楽器がどのような作用をするか、楽器をプレイする上での理論に俺は興味があったんだ。家に持ってかえって、じっくりプレイしてみたものさ。それがプロデューサー業につながるとは思ってもみなかったけれど。こんなことを言われることがあるんだ。「自分で何もかもやってしまうのは自己中心的ではないか」って。自己中心的になる、ならないの問題ではなく、自分でやってしまった方が早いってことなんだ。アルバムでは他のミュージシャンにもプレイしてもらっているよ。でも、俺は自分でやってしまえると言いたいね。それが音楽をやる動機ではないけれど。ライヴでもそういう要素は取り入れたい。それが俺の現在の正直な気持ちだ。 LAUNCH:自分を仕事中毒だと思いますか? BRIAN: 同時代の人たちを観察していて思うのは、彼らはスタジオに住んでいるけど、俺はそうじゃないということ。俺には生活というものがある。俺は音楽作りを9時から5時までの仕事のようなものと見なしているんだ。毎日何か新しいものを作り出そうと努力し、それが終われば自分の時間を持つ。 LAUNCH:プライヴェートと仕事とのバランスをどのようにとっていますか? BRIAN: 仕事に当てる時間というのを決めている。火曜日から金曜日にかけては、夜の8時から朝の2時まで音楽というマジック作りに励む。他の日は家族のためにある。子供の宿題を手伝ってあげるためにもなるべく家にいるようにしているし、子供たちが寝ている間に仕事をするように努めているよ。自分に問いかけてみたんだ。「本当に重要なことは何か?」って。それは家にいること、日常に起きる重要な物事のために家族のそばにいることだ。レコーディングという生活は、スケジュールのひとつにすぎない。 LAUNCH:そのスケジュールは、とりわけニューアルバムを作るというプレッシャーがある時、どのように守っていくのですか? BRIAN: 自分へのチャレンジに等しいね。今夜は仕事をするということを承知していれば、その場に持っていく曲がなくては話にならないってことが分かっている。手ぶらでスタジオへ行くことは絶対ない。「曲作りの壁にぶつかることはないのか?」とよく訊かれるが、「ないよ。曲が何も出来てないのならスタジオには行かない。曲が浮かぶまでギターを抱えて坐っているよ」と俺は答える。何かを完成させるために1日中働きづめることはしないがね。「これを表現するには別の方法があるはずだ」と考えながら、知識を総動員させる必要に迫られることもない。会話のような曲を書くように努めているんだ。決まったやり方があって、そこから逸れることは滅多にないね。 LAUNCH:それにしてもミュージシャンでスポーツ好きというのは面白いですよね。運動選手としての経験が音楽キャリアに何か役立っていることがありますか? BRIAN: 俺にとっては何もかもがスポーツ的意味合いを持っている。ピンポンをしたら、とにかく勝ちたいと思う。それがささいなゲームだろうが構わない、何しろ勝ちたいんだ。本塁に立てば、満塁ホームランを打てるチャンスはいつだってあるし、そうすれば見逃した時のことはすべて忘れてもらえる。本塁に立つということがチャンスであり、場外まで打てば、皆がそれまでのことは忘れるんだ。 LAUNCH:真剣にプロ・バスケットボール選手になろうと思っていたというのは本当なんですか? BRIAN: コートやフィールドに足を踏み入れた子供なら、誰もがプロになりたいと熱望するものだよ。プロ・バスケットボール選手は最高の仕事だと思う。ただ俺が気がついたのは、抱いている夢のすべてを叶えるわけにはいかない、ということなんだ。俺はミュージシャンになるという夢を叶え、さらに仲間たちとバスケットボールを楽しむチャンスもある。今やっていることがこの世での自分の使命だと思うよ。 LAUNCH:ヴェニスビーチでまだバスケットの試合を楽しんでいるそうですね? BRIAN: 驚いている人たちがいるようだけど、俺には大切なことなんだ。それで普通の人間でいられる。地に足をつけていられる。ヴェニスの住民たちと仲良くなれたしね。あそこに出かけて行くようになってもう何年もたつよ。人が大勢集まって、楽しい日曜日の午後のひとときだね。俺は競争するのがとても好きなんだ。有名人的振る舞いだなんだは忘れてしまう。ただバスケットをやりたいだけなのさ。 LAUNCH:一般の人たちにはほとんど知られていないプライベートな面があなたにはあるということですね。 BRIAN: 一般の人には内面まで見るという機会はないからね。彼らから見る俺は、曲であり、ビデオであり、ショウの一部といった限られた部分でしかないわけだ。庶民的な人物としては見なされていないから、俺のそういった姿を見た人は驚いてしまう。それは困ったことでもある。俺のそういう面が理解されないというのは残念なことさ。俺の機嫌の悪い時をたまたま見かけた人は、人生で最悪の気分のBrianを見たことになるだろうし、他の気分の時の俺には二度と会わないわけだから。誰にでも気分の悪い日があり、調子の良くない時があり、イライラしている時もある。誰でも同じだよ。そういう時に誰かを失望させてしまうのがとてもつらいね。それがジレンマだよ、多分。 LAUNCH:アーティストとしてのBrian McKnightは、大胆なこともやってきましたよね。例えばステージ上で衣装替えするとか! あれはなかなかスキャンダラスでした。 BRIAN: 少なくともあれに関しては、特にあからさまにセクシャルなことを狙ったわけではなかった。ステージ上で自分の股を握ったり、観客席から選んだ女性とセックスの真似事をすることに比べればね。どういった反応が出るかやってみようと決めていたんだ。問題はどうやって上手くやるかということ。あれはショウの進行上のつなぎとしてやったことに過ぎない。女性客にはファンタジーを与える状況作りができたし、上手くいったよ。裏目に出て大不評を買う可能性もあったけれど、俺たちはチャンスに賭けてみたのさ。 LAUNCH:今後のコンサートでも、さらなる驚きが期待できますか? BRIAN: 次のニューオーリンズのショウに関しては、特に何も目新しいことはないね。新作が出て、売れ始めたら、ちょっと時間をかけて考えてみるつもりだ。大抵の場合、アルバムが出たら、そのサポートのために即座にツアーに出る。今回はじっくりと寝かせて、世間が盛り上がるのを待って、それから求めに応じる、という風にするつもりでいる。完成したばかりの新作では、俺はキーボードからは距離を置いているんだ。今回はかなりギターをプレイしていて、ライヴにもそういった要素が取り入れられるだろうね。前回はステージでベースを弾いた。それが一番好きな楽器なんだが、問題はプレイしながら歌うのが無理だということ。俺のオーディエンスは80%が女性でね。俺が立ち上がって歌う姿を見なくては気が済まない。楽器の演奏がステージ上の単なる演出でないことを証明できるのはいいことだよ。実際俺には出来るんだから。でもその部分を無理矢理オーディエンスに押し付けたくはないんだ。 LAUNCH:最初にプロのミュージシャンとして始めた頃のことを教えて下さい。 BRIAN: バーでピアノを弾いていたんだ。ホテルのバーで。そういうのがあるだろう? ブランデーグラスやなんか置いてピアノを弾いてるのが。俺もそういうピアノ弾きだった。付け髭なんかしてね。15歳ぐらいだったかな。17歳の頃にはバンドを持って演奏していたからね。バンド名はSpontaneous Inventions。Bobby McFerrinのアルバム名『Spontaneous Inventions』から取ったんだ。 LAUNCH:それからレコード契約を結んだのですね? BRIAN: 俺は滅多に他人のために曲を書かない。俺が曲を書くのは、それが自分のやりたいことだからだ。カレッジ時代のことだが、退学処分になってしまって、その時ちょうど書きあげた曲がレコード契約につながった。だから、学校から追い出されてなかったら、今の俺はなかっただろうね。退学になって3ヶ月後、レコード契約を結んで、あとは知ってのとおりさ。 LAUNCH:ついに「成功したんだ」と最初に確信した瞬間はありましたか? BRIAN: いつそう感じたかって? '91年に1stアルバムを出した頃じゃないだろうか。ラジオ局の人たちにある曲を聴かせて、彼らの反応を見ていた。それでこう思ったんだ。「よし、俺の書いた曲を彼らは気に入っているぞ。この様子からすれば今後も曲作りをしてやっていけるだろう」。今だに不安感はあるよ。自分の声だけで勝負しているようなものなんだから。自分の作品は何だって大いに気に入るけれど、他の人たちがどう感じるかは分からないものだからね。 LAUNCH:先ほど、役者をやっていれば、という話をされていましたね。演技の方にも手を広げている感触はどうですか? BRIAN: 全く新しいことを始めたんだからエキサイティングさ。つまり、何かを学ぶということ。音楽に関しては自分ですべて分かっていると思うから、他人の意見についてそれほどオープンにはなれない。ところが演技の方は学ばねばならない新境地だ。監督たちは当然のように彼らの思い通りのことを役者に求めてくる。それが演じることのとても面白いところだよ。ポップミュージックを聴いていても、それほど際立ったものは多くないだろ。でもアメリカの心を感動させるすばらしい音楽や映画は存在する。新しいことに参加できるのはとにかくエキサイティングだ。 LAUNCH:音楽業と俳優業のバランスを上手くとっていけると思いますか? BRIAN: そのふたつは共存できると思うよ。一方のためにもう一方を抑える必要もない。俺は演技の虫に冒されているけれど、だからといって音楽から遠ざかることはない。今はあせらずにゆっくりとやっていくよ。いずれ時機がきたら適役がまわってくるだろうから。 Billy Johnson Jr |