無定型流動サウンド

米国での話で恐縮だが、このところ、それと知らずにGomezの音楽を耳にしている人も多いはずだ。Philips ElectronicsのTVコマーシャルで使用されている、The Beatlesの「Getting Better」の焼き直しヴァージョンが、実は彼らなのである。 英国からやってきたこのクレイジーな若手バンドの物語は、デビューを夢みる無名ミュージシャンにとっては羨望の的だろう。 彼らは初めてのギグを行なう何ヵ月も前に、早々と契約に漕ぎつけた。Virgin Recordsとの契約から2年後、ノンストップでツアーに励んだGomezはイギリスで批評家連の寵児となり、デビュー盤『Bring It On』('98年)が、年間最優秀アルバムに贈られるMercury Prizeを獲得。2ndアルバム『Liquid Skin』でも、Jimi HendrixやThe Beatlesへの傾倒ぶりは相変わらずだが、Gomezが断じて“レトロ”でないことは明白だ。 先日、メンバーのTom GrayとIan Ball、Ben Ottewellが、LAUNCHのエグゼクティヴエディターDave DiMartinoのインタヴューにこたえ、批評家達に認められてからの生活や、ステージでの奇妙なハプニング、アメリカとイギリスの音楽の違いなどについて話をしてくれた。 |
LAUNCH: バンドについての記事を読むと、ライターがあなたたちの音楽を言い表すのに悪戦苦闘していて面白いですね。この表現は当たっているぞと思った呼び方はありますか? TOM: 何ともいえないな。ずいぶんいろんな呼び方をされた。あらん限りの形容詞を駆使してね。“スワンプロック”とか“ポストモダンブルース”とか“'90年代のジャグ”とか。よくもまあこれだけ思いつくもんだよ。そういう言葉で説明をつけたりカテゴリー化することができない音楽をやろう、というのが僕らの目的なんだ。Gomezは定型にはまるようなバンドじゃない。 IAN: 音楽を言葉で表そうとするなんて、おかしなことだ。音楽は言葉じゃないんだから。ブルースバンドだとかポップバンドだとかいわれて、確かに僕らはブルースナンバーもやればポップナンバーもやるけれど、“サイケデリックブルースポップ”とかいう長ったらしい名称を作り出したって、僕らの音楽の半分も説明していない。そんな言葉では伝わらないんだ。これはいいと思った呼び方なんか1つもない。変な習慣だよ。僕は自分の聴く音楽をカテゴライズできない。どんな音楽が好きかと訊かれても、音楽が好きなんだとしか言いようがない。こういうジャンルでないと聴かない、みたいな偏見がないんだ。だから、このバンドがやっているのは“音楽”だ、とだけ説明するのがいいと思う。“サウンドと声”さ。 BEN: どんなふうに呼ばれたか、あまり覚えてないけど、“エレクトリック・ジャグバンド”っていうのがあった。あれは悪くなかったな。 LAUNCH: あなたたちはレコードを作ってから初ライヴをやりましたよね。普通とは順序が逆ですが、何か理由があったのですか? TOM: もともとガレージでジャムってるだけだったんだ。自分たちのサウンドを見つけようとあれこれやっていた。契約は僕らにものすごい衝撃を与えたし、契約したからにはライヴをやらなきゃいけないって気がついた。当初のパニック…なにしろ一度もライヴをやったことがなかったから…が収まった後は、いろんなことをどんどん覚えていったけどね。かなり早い時期からギグをやりはじめて、契約後18ヵ月のうち14ヵ月はギグに費やした。短期間で覚えなくちゃいけないことがいっぱいあって、たいへんだったよ。最初のうちは、レコードと比較されることがないから、まだよかった。いくら失敗しても安心だった。オーディエンスは僕らの演奏をありのままに受け止めて、「この興奮は何だ?」って思ってくれたんだ。レコードが出るころには、もうライヴのコツをつかんでいたしね。それから、いつのまにかイギリス各地のフェスティヴァルに出演するようになったんだけど、あれは厳しい試練だった。 IAN: アルバムを録音した時点では、ギグをまったくやってなかった。それで満足だったとか不満だったとかいうんじゃなく、単に状況がそうだったんだ。大抵のバンドは、レコード契約する何年も前からクラブやパブで演奏していたんだろうけど、僕らにはそういう経験がない。別にライヴをやらないぞと思っていたわけじゃないんだ。金がなかったし、移動用の車も機材もなかった。僕らにあったのは録音装置と、オンボロのギターだけ。これがまたヴォリュームの調節が効かないギターで、レコーディングするとすごいサウンドになるけど、ライヴでは最悪だったよ。そんなこんなで、ライヴなんかできっこなかった。クラブでプレイしたくても、マイクやアンプや必要なものを買う金がどこにもなかったんだ。 BEN: 不思議な感覚だったね。レコードを作った後、イギリスのある新進バンドとツアーに出たら、いきなり世間にさらされて、すごいプレッシャーを感じた。そうやって揉まれたのがよかったんだろうけど。最初はひどいもんだった。目も当てられなかったよ。 LAUNCH: アメリカの音楽とイギリスの音楽はよく比較されますが、あなたたちが聴いて大きな違いがありますか? TOM: 実際の音より歴史が比較されるんじゃないかな。アメリカでもイギリスでもポップはポップだし、ブラックR&Bといえばアメリカでもイギリスでも同じものを指す。ただ歴史が違うんだ。ポピュラーミュージックでいうと、アメリカ人がGeorge Gershwinを聞いていたときに、イギリス人はミュージックホールの音楽を聞いていた。ロックンロールは8年の歳月をかけて大西洋の両側で誕生した。国籍なんて考えたこともないよ。'60年代にメロディックなポップを書こうとしたソングライターといえば、英国ではLennon & McCartney、米国にはPaul Simonがいる。で、Paul SimonはポップミュージックにGershwinやBerlinを採り入れ、Lennon & McCartneyはロックンロールにミュージックホール風の味つけをした。最近はブリットポップが話題になってるけれど、悪い冗談だ。ブリットポップの唯一の問題点は、ちっともポップじゃないことさ。いい曲がないし、誰もがRay Daviesになろうとしたって意味がない。イギリスの郊外の町を舞台にしたキッチンの流し台の歌ばかりじゃ、みんな飽きちゃうよ。 IAN: 60~70年前なら、アメリカとイギリスの音楽は違ったかもしれない。でも僕はそんなふうに考えないな。今は世界共通だよ。音楽にはそれぞれ複雑な背景があって、正確な由来は誰にもわからない。僕らが熱中しているリズミックな音楽は、たぶんアフリカから生まれたんだろうね。ただ、このごろのアメリカのバンドは、イギリスでは絶対に受けない。たとえば、僕がすばらしいと思うDave Matthews Bandにしたって、アメリカで街を歩いていたら人が押し寄せるだろうけど、イギリスでは誰も気づかないよ。どういうわけか、ああいう音楽はイギリス受けしないんだ。いくら僕がすばらしいと思ってもね。 BEN: アメリカのバンドがしないようなことを、僕らはするんだと思う。「Tijuana Lady」みたいな曲をやるバンドは、アメリカにはめったにいない。あの曲のユーモアを解さない人が多いんだ。ステージであれを歌うときは、真面目な顔をしてるのに苦労するよ。僕らがイギリス的なのは、何よりもああいうユーモアのセンスがあるからだ。ブリットポップ・シーンは自意識過剰なくらいにイギリス的だね。それはそれでいいけれど、ちょっと意識しすぎだよ。 LAUNCH: バンド内では意見も好みもさまざまなようですが、自分は好きなのに他のメンバーが嫌いなものはありますか? 音楽論を闘わせることは? TOM: あんまりないな。僕が好きでみんなが嫌いなものは思い浮かばない。みんなが好きでも僕が毛嫌いするものはあるけど。 BEN: 音楽に関してはあまり好き嫌いがないんだ。メンバーの中にはDave Matthews Bandの崇拝者もいるけど。僕は何とも思わないな。Queenもそう。みんながQueenをかけようとすると、CDを隠しちゃう。 IAN: やっぱDave Matthews Bandだよ。僕とOllieはDave Matthews Bandの大ファンなのに、他のみんなはよくないっていう。妙なことにね。好きじゃないものは僕にもたくさんあるよ。Joni Mitchellみたいな神経に障るダンスミュージックとか。結局みんなが好きなのはJimi Hendrixだ。ギグの前やギグの後に必ずかけるし、朝起きて一番に聴くのもJimi Hendrix。 LAUNCH: Gomezはアメリカ人の好みにぴったりなようです。“アメリカ的なサウンド”のバンドであることが幸いしていると思いますか? TOM: アメリカ的かどうかわからないな。ジャーナリストが気紛れでそう言ってるだけじゃない? 音楽を聴くのにアメリカもイギリスもないよ。黒人がElvisを聴いたって何の問題もないだろう。でも、Elvisの音楽は黒人っぽいからラジオでかけるべきじゃない、って言った人たちもいたよね。実際には、そういう専門的なことはどうでもいいんだ。音楽を聞くときにそんなこと考えない。裏に何か計略があるんだろうなんて勘ぐったりしない。「アイスランドっぽいから、これは聞かない」みたいなのは、僕には理解できないよ。音楽に限ったことではないけど、単純に“好き”か“嫌い”かしかない。ショウを見にくる人のほとんどが、好きで来てくれるんだと思うと、本当にすごいことだ。 BEN: オーディエンスが親しんできたサウンドだっていうことはあるかもしれないけど、それだけじゃないと思いたい。僕らなりのサウンドを気に入ってくれてる、とね。 LAUNCH: 今までにやったいちばん奇妙なギグは? TOM: イタリアのフェスティヴァルに出演したときだ。僕らは最後のバンドで、一日中呑んでた。最後といってもヘッドライナーってわけじゃなく、みんなが帰るときに演奏で送り出す役さ。すごく人気があるイタリアのバンドの後だったけど、それでもまだ1万人くらい観客が残ってた。昼間からさんざん呑んで、ステージに上がったのが夜中の1時。とっても暑い日で、しかも一日呑んでたもんだから、もうヘロヘロだったんだ。僕がHammondを弾きまくり、Moogでノイズを出さなきゃいけない「Ree's Wagon」って曲があるんだけど、あのときはMoogを持っていくのを忘れて、しかたないからステージで踊り狂った。酔っ払って朦朧とした状態で、ステージに腹ばいになり、床をバンバン叩いて這いまわったよ。イタリアのオーディエンスにどこまで通じたか知らないけど。 IAN: 1ヵ月続いたヨーロッパツアーの終わり近くに、パリ郊外の小さな町へ行った。そこで僕とBenとドラマーのOllieは、ギグの前にジンをしこたま飲んだ。そしたらOllieは完全にイッちゃって、リズムが全然定まらない。プレイできる状態じゃなかったんだ。それで僕らもつられて歌詞を変えてみたり、曲の途中で演奏をやめちゃったりしてね。おかげで、ツアー中にたまったフラストレーションを気持ちよく発散できたよ。ギグとしては大混乱でも、最高に楽しかった。お客さんも僕らと同じくらい酔っ払っていたから、けっこう楽しんでくれたと思う。まあ厄払いみたいなもんだ。 BEN: コペンハーゲンにコミューン風の町があるんだ。法律も何も存在しない愉快な場所さ。僕らは古いバーの2階でプレイした。そこではマリファナも合法だし、素敵なギグだったよ。店のコックがサックスを吹く奴で、ステージに飛び入りしてサックスやベースを一緒にプレイしたんだ。あれは楽しかったな。とてもリラックスしたいい雰囲気だった。 LAUNCH: 音楽に関して特に好きな時代がありますか? TOM: 僕らがイギリスで活動を始めたころは、いろんなバンドがレトロ趣味に走った後だったので、ちょっと軽く見られた。Kula ShakerやOcean Colour Sceneは、まさに'69年のサウンドを再現しようとしていたんだ。初めは僕らもそういうバンドだと思われて、レトロだと言われ、「レトロじゃない、古いものをやるつもりはない」って反論した。進歩的であろうとしたんだ…文字通りの意味で。'60年代の終わりに存在した自由がとだえてしまったのは、マスコミがすべてをコントロールし、何でもカテゴライズするようになったからだ。僕らがバンドとしてどんな時代をめざすかっていうと、アルバムが歌と音楽的な熱意と細々したアイデアの寄せ集めにすぎないような時代。余計なことを考えないで、曲やアイデアを気ままにいじくりまわして楽しみたい。スタイルやジャンルや筋の通った計画なんかに頭を悩ませるほど憂鬱なことはないよ。そういう意味では'60年代が好きかな。あの時代のレコードを聴くと、たとえば『Revolver』はいきなり「Taxman」で始まって、次にまったく感じの違う「Eleanor Rigby」が来る。残念ながら、今じゃそんなレコードはまずないよね。 IAN: いちばん興味があるのは、静かな静かなアンビエントミュージック。Talk Talkみたいなバンド。彼らのここ2枚のアルバムが気に入ってる。とても希薄なサウンドで、そこに興味を引かれるんだ。でもライヴでは無理だね。サウンドスケープの世界への旅につきあってくれるオーディエンスでないと。ギグに足を運ぶ人たちは、僕もそうだけど、跳びはねたり一緒に歌ったりしたいものだろ。だからこれは、僕個人の二次的な興味ってところだ。 LAUNCH: 初めてアメリカへ来たときのことを話してください。まずどこでプレイしたいと思っていましたか? BEN: サンフランシスコ。実際に行ったよ。クールだった。Eagle-Eye Cherryとツアーして、彼の前座で30分のショウをやっていたんだけど、僕らは彼があまり好きじゃなくて気が重かった。それがサンフランシスコでは単独のショウで、2時間半くらいプレイしたんだ。ティファナに程近いサンディエゴでも「Tijuana Lady」をやったし。 IAN: 子供のころ、両親に連れられてアメリカに来たことがある。それから4年ほど前、ガールフレンドと一緒にサンフランシスコとL.A.に行った。真っ先に行きたかったのがサンフランシスコ。いろんな人からいろんな話を聞いてたから。僕はRed House Paintersが大好きだったんだけど、彼らはサンフランシスコのことばかり歌ってたので、きっとこんな場所なんだろうなっていうイメージが焼きついていたんだ。あいにくまだ20歳だったもんだから、飲酒年齢の制限にひっかかって、悔しい思いをしたよ。今はもう堂々とバーに入れる年になったから、オフのときにゆっくりアメリカ旅行をしたいね。 TOM: 僕はニューヨークシティに行きたくてたまらなかった。それにニューオーリンズ。こっちはいまだに行ってない。そのうち絶対行くよ。ティファナにも行ったことがないんだ。Ianはティファナに行ったんだよね。 LAUNCH: これはIanに話してもらうしかないですね! IAN: サンフランシスコとL.A.へ行ったとき、宿泊先のホステルが企画したティファナへのバス旅行に参加したんだ。真夏で、気温は110度くらいあった。マルガリータやCoronaのビールを飲んで、ティファナのスピリットに浸ったのはいいとしても、僕のガールフレンドが正気をなくしちゃってね。国境を越えて戻ってくるときは、自分もフラフラなのに彼女を背負って歩くはめになって、まいったよ。ティファナのことはほとんど覚えてないんだ。アメリカに再入国するときのことはよく覚えてるけど。メキシコに入るのは簡単で、誰に咎められることもなくそのまま歩いて入ればいい。ところがアメリカに戻るとなると、銃を持った奴らが立ってる長い通路を上っていかなきゃならないんだ。そのうえ僕がおぶったガールフレンドは、すっかりイカレちゃってわけのわからないことを言ってるし。誰かを背負って国境を越えるなんて普通じゃないから、変な目で見られてもしょうがないよね。 LAUNCH: Gomezの特徴の1つに、タイプの違うシンガーがそろっていることが挙げられますが、それぞれのヴォーカルのいいところは? BEN: 僕はやたらシャウトする騒々しいタイプ。Thomasはいい感じのミッドレンジの声をしてる。Ianの声はちょっと女の子みたいに聴こえる。一緒に歌うにはちょうどいいんだ。 TOM: 僕のヴォーカルにはいいところなんかないよ。僕の書いた曲をBenにもIanにも歌ってもらえないことがあるからさ(笑)。2人のほうが僕より断然いいシンガーだ。 IAN: Tomの場合はいろんなスタイルで歌えるんだ。ただ歌うだけじゃなくて、曲の主人公になりきって歌う。Benは狼みたいに吠えるし、僕が歌うとまるで女の子だけど。 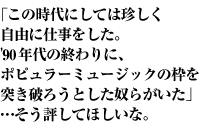 LAUNCH: LAUNCH:ところでGomezというのは誰のことですか? BEN: どうしてこんなバンド名になったかってこと? 大学時代の友達の名前だよ。契約前に大学でプレイしたことがあって、そのころ僕らには名前がなかった。浮かぶのはジョークみたいな名前ばかりで、ちっともいい名前を思いつかなかったから。それで、その友達は僕らがどこで演奏するか知らなかったので、彼に場所を知らせるためにドアにGomezと書いた紙を貼っておいた。それがそのままバンド名になったんだ。 LAUNCH: ポップ史上もっとも重要なミュージシャンは誰だと思いますか? BEN: たくさんいる。Jimi Hendrixかな。でも彼は他の誰とも違う立場にあると思う。The BeatlesやStonesが重要なのはもちろんだし、J.J.CaleやRy Cooderも尊敬してる。あんまり大勢いて、誰か1人を選ぶことはできないよ。 IAN: もっとも重要なミュージシャンはJimi Hendrix。断トツだよ。わかりきったことさ。後にも先にも彼みたいな人はいない。 TOM: 答えは簡単。The Beatlesには誰もかなわない。話し合ってそうしたのかどうか知らないけど、複数の人たちのコンビネーションが、ポップのアイデアをもとに、もっとずっと偉大なものを生み出したんだと思う。Lennon & McCartneyはもちろんのこと、Brian Wilsonも、Princeなんかも、ポップをまったく新しいレベルへと導いた。グレイトなポップは、文句のつけようがないほどグレイトなんだ。そういうのは稀にしか出てこない。 LAUNCH: PhilipsのCFで流れている「Getting Better」をやっているのがGomezだということを知らない人もたくさんいるでしょう。あの仕事をすることになった経緯は? コマーシャルで使われるようになって状況は変わりましたか? BEN: みんなが関心を持ってくれた。それはいいことだ。だけど、シングルとしてリリースするかどうかをしょっちゅう聞かれるのは煩わしいね。1日だけThe Beatlesになれて楽しかった。Abbey Roadでレコーディングしたんだ。その後、新曲の録音もあそこでやったよ。まあ、いいことばかりじゃないけど、楽しいことは楽しかった。 TOM: 稼ぐためなら何でもするさ。次の計画を実行に移すには金が必要だ。これほど不安定な職業はないってことを忘れちゃいけない。「1日だけThe Beatlesになれば大金を稼げる」って言われたら、断われやしないよ。だって一石二鳥じゃないか。それが紛れもない事実だ。音楽を作って生活していくためには、プロとして決断しなくちゃ。 IAN: そんなにカッコいい話じゃないんだけどね。あの仕事を頼まれたとき、僕らはすごく金に困っていて、「OK、やってみよう」と答えた。でも、あの曲をどう演奏したらいいんだろうと思ったよ。指定された日にスタジオへ行って、曲を覚えて、あれこれ試して、その晩に仕上げた。何も準備してなかったんだ。よかったのは、あれでみんなに僕らの声を知ってもらえたこと。そうすればアルバムを聴こうって気にもなるだろう。知らせるということが大切なんだ。それにしても妙な出来事だった。僕らがやったものを本当に使ってくれるとは思わなかったよ。いいところを選んで使ってる。最後の部分はすごくいい出来だった。「Getting Better」というより、僕らが勝手にジャムってる感じで。 LAUNCH: 多くのアメリカ人は、あなたたちがイギリスでMercury Prizeを獲ったという記事を読んで、初めてGomezの名を知ったわけですが、急に有名になることに不安はありましたか? BEN: うん、少しね。あれ以来、雪だるま式にふくれあがってきたから。僕らは地道にやってただけだ。シングルを出したってチャートインもしなかったけど、プレイできるだけでハッピーだった。ところがあの受賞騒ぎで、タブロイド紙の連中に突然マイクを突きつけられた。最初はとまどったよ。あの賞をもらってすぐ、こっち(アメリカ)に来たんだ。イギリスでは僕らを取り巻く状況がものすごくクレイジーなことになってた。でもアメリカでは、誰も僕らを知らなかった。それで天狗にならずにすんだよ。 LAUNCH: 1stアルバムではできなかったことで、2ndでやりたいと思っていたことがありますか? 2ndで大きく変わった点は? 私たちは『Liquid Skin』にどんなことを期待すればいいでしょう? TOM: 僕がチンパンジーみたいに歌ってる! このアルバムのハイライトだよ。Ianが“7枚のベールのダンス”を踊る音がバックに入ってるんだ。僕らは何度もきれいな空気の音をとらえることに成功した。Benは再生不可能なくらいの高音で歌っているしね。だからレコードの隅から隅までを聴こうとしないほうがいい。何を期待するべきか? 何にも期待しないことさ。そうすればハッピーでいられる。期待しすぎるとバカをみる(笑)。とにかく、僕らの側にこれといった指針があるわけじゃなし、特定のことを期待しないに限る。 BEN: 大きな変化はいくつかある。1stを作ってるときは、これがリリースされるとか、誰かが聴いてくれるといった実感がなくて、作業のしかたもデタラメだった。今回はもっと自覚ができて、いいものを作らなきゃというプレッシャーがあった。それにライヴの経験を積んだことが、プレイスタイルに少なからぬ影響を及ぼしていると思う。 IAN: 今回は自由と時間とあったかいスタジオがあった。それに、あらかじめ曲を作ってあったから、どんなスタイルで録音するかということのほうが課題になった。いろんな可能性があったし、プロデュース面に力を入れたよ。スタジオ機器を自在に使えるようになると、4トラックで録音するよりずっと楽なんだ。楽というか、思い通りのサウンドがつくれる。1stアルバムはもっとレイドバックしてて、ひとりよがりな感じだったね。 LAUNCH: 20年後、ロック史の本にどう書かれていたいですか? TOM: Gomezの墓碑銘になんて書いてほしいか? 飛行機が墜落してメンバー全員死んじゃったら、僕らを一緒に埋めて、墓石に刻んでほしいのはね…、この時代にしては珍しく自由に仕事をしたってことかな。“'90年代の終わりに、ポピュラーミュージックの枠を突き破ろうとした奴らがいた”と評してほしいね。 IAN: ずっとやりたいと思っていたことを、誰にもとやかく言わせずに実行したバンド。音楽的自由のために闘った十字軍。 BEN: 「革新的」、あるいは「こいつらにはなんでこんなことができたんだ?」って。 by Dave DiMartino |