| 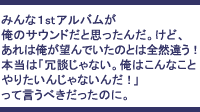
| ライヴアルバムというのは普通、ファンのお気に入りの曲を集めたお祭りのようなものだ。だからこそコンサートにも人が集まる。しかし、Bruce Hornsbyにとって初のライヴ作となる2枚組CD『Here Come The Noisemakers』は、まったく趣を異にしている。過去を封印して次へ進むための作品なのだ。
単にスタジオヴァージョンより長めに演奏するというようなことではない。それならHornsbyは、'86年に「The Way It Is」で脚光を浴びる以前から、ずっとライヴでやってきたことだ。この最初のヒット曲にさえ彼の美意識はどことなくにじみ出ていて、自由奔放なピアノプレイは当時の代表的なポップとは一線を画していた。たとえば誰かが長めの即興演奏の最中に、Samuel Barberの「Nocturne」やGeorge Garshwinの「I Loves You Porgy」を弾き始めたら……。実際、Hornsbyが『Noisemakers』の中で「The Way It Is」の導入部にやっていることだが、ファンは多くの場合、ショウの後にスーパーで何を買えばいいかを考え始めるに違いない。そんなファンに向かってこのアーティストは、これ以上はないというくらい穏やかな口調で、黙って座って聴け、と言っているのである。
いや、実はインプロヴィゼーション以上に『Noisemakers』全体を貫いているものがある。それは昔のアルバムや数え切れないほどのコンサートで、Hornsby自身が築き上げ、磨き上げてきたスタイルに対する“拒絶”である。彼がいちばん望んでいるのは、ここ数年より以前に自分がしてきたことすべてを、人々に忘れてもらうことなのだ。もし彼を喜ばせたければ、あなたが買った『The Way It Is』と『Scenes From The Southside』を、スキート射撃の標的として差し出せばいい。彼の考えでは、それらのアルバムのBruce Hornsbyはもはや永遠に存在しないのだ。
客観的に言って、ヴィンテージのHornsbyとポストモダンのHornsbyは確かに違うとはいえ、我々の耳にはその差はごくわずかである。しかし、LAUNCHとの最新インタヴューで彼自身は、作品の質が根本的に変わったのだと明言した。それだけにとどまらず、昔の作品はお払い箱にしても全然かまわないと認めている。何が彼をそこまでさせたのだろうか?
――そもそもライヴアルバムをやろうと思ったのはなぜですか?
HORNSBY:理由は2つあるんだ。もう何年も前から、コアなファンにしつこくせがまれていたことがひとつ。それからもうひとつは、俺が誰かは知っていても、実際にどんなことをやっているかは知らないという人達の存在だ。もうそろそろ俺達がやっていることを記録として残すべきタイミングじゃないかと思った。これまでの作品もそういう役割を果たしていなくはないけど、このライヴアルバムほど自分達のやっていることを余すところなく伝えるものはない。正直言うと、俺はこのバンドこそRangeと呼ぶべきだったかもしれない。とても広範なスタイルを持っているからね。今までのバンドの中でもベストと言っていいくらいだよ。すべての面について満足しているし、そう言えるのは今のバンドが初めてだ。
俺達がショウの最中にリクエストを受けるのは知ってるよね。ある晩、Paul Simonの「Kodachrome」という曲をリクエストした人がいた。ところが、俺はKodacolorの「Kodachrome」というのを知らなかった。それで、「えーと、Paul Simonの他の曲なら知ってるんだけど」と言って、“The Boxer”を弾き始めたんだ。すかさずバンドの連中も同調してくれた。俺が求めているのはそういうことさ。いい耳を持っていて、臨機応変にできるメンバーが望ましい。彼らはもう1000回以上もギグをこなしているから、膨大なレパートリーと知識を身に付けているんだ。
――あなたのショウには即興の部分が多々ありますが、特にソロに関して、ライヴ収録の時には、いつもと異なるアプローチでプレイするというようなことは? たとえば普段はもっと2階席にもアピールするのに、そうしないとか。
HORNSBY:それは上手い言い訳だな。俺は2階席なんて特に気にしてないから。基本的にそのほうがいいプレイができると思うんだ。どっちにしろ、サウンドエンジニアが役割をちゃんと果たしていれば、いいプレイさえすれば2階席にも届くはずだからね。最初の数年は俺もみんなを喜ばせようと頑張ってたこともあるけど、いざ収録テープを聴くと、オーディエンスに必死でいい顔を見せようが、演奏は酷いもんだった。だから、いい顔を見せるのはほどほどにして、本業に集中したほうがいいってことになったのさ。
――アレンジを変えたものもありますよね。例えば「Valley Road」とか…。
HORNSBY:そう来ると思ったよ!(笑)
――あれは基本的には4/4の曲ですが。
HORNSBY:今は違うよ!
――なぜ6/8に変えたんです?
HORNSBY:あの夜、自然にそうなったんだ。曲を新たに生まれ変わらせるという意味において、あれほどパーフェクトな例はない。まさに思い描いていたとおりさ。
――もともと、あそこで「Valley Road」をやるつもりだったんですか?
HORNSBY:いいや。Greatful Deadの“Wharf Rat”の演奏が終わりにさしかかったところだったんだ。で、俺はメンバーに「こっちを見ろ!」って言った。手の合図がいろいろあって、その中に「そのまま続けろ」という意味のもあってね。俺が思いきり力をこめて床を指差すんだ。それでメンバーはそのまま演奏を続け、俺は“Sometimes I lead, sometimes I follow...”と歌いだしたんだけど、彼らは「あのバカ野郎! このノリのまま“Valley Road”をやるつもりかよ」って感じだった。
――このライヴアルバムの中で、オリジナルのレコーディングとキーを変えた曲はありますか?
HORNSBY:もちろん! “Rainbow's Cadillac”は3音高くなった。でも、他はだいたい下がってる。なぜかというと、あんまり高い声で歌うのに嫌気がさしてるからさ。声をふりしぼるのが嫌なんだ。それに、正直言ってあまりいい響きだとも思えないし。確かに2作目か3作目のアルバムまでは、できるだけ高い声で歌おうとしていたんだ。高ければ高いほど強力だという馬鹿げた考え方をしていたからね。そのことは後悔してる。今はこれまでよりずっと自分の歌い方に自信を持っているんだ。
――なぜ昔よりも歌が上手くなったと感じているのですか?
HORNSBY:何というか、微妙な問題だから誤解されたくはないんだけど、俺はJohn Molo(ドラマー)と21年間も一緒にプレイしていた。彼は素晴らしいドラマーだ。今はPhil Lesh(Greatful Dead、Other Onesの元ベーシスト)と一緒にやっていて、凄まじいサウンドを叩き出してる。俺にとって、彼はOther OnesバンドのMVPだったし、兄弟のように感じてもいた。でも、自分の音楽に、違う感性のグルーヴを聴いてみたいと思うようになったんだ。
基本的にはブラックっぽくなってしまったから、もう以前のようには戻れないかもしれないね。リズムセクションのフィーリングが今までとは違ったことで、俺のヴォーカルもよりディープでソウルフルなものに変わったから。ただ、それだけじゃない。俺の作品を聴けば、徐々に進歩して肩の力が抜けているのがわかるはずだ。例えば『The Way It Is』の後に『Here Come The Noisemakers』を聴くと、俺にはまったく別人のように聴こえる。申し訳ないけど俺としては、オリジナルヴァージョンの“Mandolin Rain”はもう聴きたくないんだよ。
――スタジオでのレコーディングの手法を、ライヴパフォーマンスのレコーディング方法に切り替えるのは簡単なことですか?
HORNSBY:2つがもっと近づけばといつも願っているんだけどね。スタジオでももっとライヴ感が出せればといつも思ってる。例外はあるよ。『Hot House』は、俺達がスタジオで作ったアルバムの中ではかなり威勢のいい作品だ。だから自分の作品の中でもお気に入りのひとつといえる。何となく躍動感があるんだ。でも、取り組み方はまったく違う。たぶん俺のレコーディングのやり方がサイテーなんだろうけど。
――出来上がった作品はそうは聴こえませんよ。
HORNSBY:優しいことを言ってくれるね。でも、俺としてはすごく後悔してるんだ。決して右から左へと簡単にできることじゃないからね。自分でもとてもよく出来てると思うところはあるよ。でも、「畜生!」って言いたくなることのほうがはるかに多い。このアルバムには副題をつけたほうがいいんじゃないかな。『Here Come The Noisemakers: Bruce Hornsby Live―The Way We Wish The Records Had Been』(ノイズメーカー登場:Bruce Hornsbyライヴ―今までのアルバムもこんなふうだったらよかったのに)ってね。
――本気ですか?
HORNSBY:もちろん。ちょうどいい見本が1曲目の“Great Divide”さ。悪いけどオリジナルヴァージョンより数段かっこいい。ウソみたいだよ。
――もしそれが本当なら、なぜ自分が満足しないアルバムをリリースしてきたのですか?
HORNSBY:そう、たぶん理由は2つある。ひとつは自分の音楽を見失っていて、実際よりもいいものだと思い込んでたってこと。それに自分の頭を壁に叩きつけるような事態にまで陥っていたんだ。あれ以上は出来なかった。だから、そのまま出すことにした。上々の出来だと言ってくれる人もいたしね。
――つまり、考え方に変化があったのはこれ以前のことですよね。その時点でさえ、自分の作品に完璧に満足してはいなかったと?
HORNSBY:そう、そう、そうだよ。1stアルバムはまさにそんな感じだった。後悔してる部分がものすごくたくさんある。まったく何てこった! 当時、俺のカミさんはパサデナにあるグラフィックデザインの会社に勤めていてね。2人でVan Nuysに住んでいた頃の話さ。俺は1stアルバムのマスターを受け取った――アナログの試作盤だ。で、部屋の暗がりに座りこんでいたんだ。アルバム全編を聴き終えたところだった。ちょうどその時、彼女が帰ってきて、うなだれている俺を見つけて訊いた。「どうかしたの?」「俺のアルバムは最低だ」
――うわぁ。
HORNSBY:酷いなんてもんじゃないさ! そんふうに感じることはよくあるけど、あれはまさしく最悪のケースだった。
――あなたが自らに高い基準を課している証拠だと思いますが……。
HORNSBY:そうかな。俺自身は高い基準とは全然思わないけど。ただ大失敗ばかりしてるだけだと思うよ。(笑)
――これを読んでる読者はそこから何を学ぶべきだと?
HORNSBY:えーと、まず1stアルバムでは俺はプロセスを把握していなかった。決定権もあまりなかった。自分よりもまわりの人間のほうがよくわかっていたんだと思う。俺はまだほんの駆け出しだったからね。例えば、スタジオにKeith Jarrettのソロアルバムを数枚持って行って、プロデューサーのElliot Scheinerに「ピアノはこういうサウンドにしたい」と言ったんだ。彼はそのアルバムを聴いてからこう言った。「いや、これはいいサウンドとは言えない。いいサウンドとはどんなものか君に教えてあげよう」。で、結局ピアノはこんな明るいサウンドになったってわけ。
――いい音だったじゃないですか。
HORNSBY:みんなそう言う! みんなあれが俺のサウンドだと思ったんだ。けど、あれは俺が望んでいたのとは全然違う! 俺がやりたかったことは、ここ数枚のアルバムに反映されているよ。もう少しナチュラルなサウンドさ。Elliotのヴァージョンだったからこそ、あのアルバムがヒットしたという可能性は大いにあるよ。俺のほうが大間違いだったのかも知れない。でも、俺には好きになれなかった。繊細すぎて温かみのない音に聴こえるんだ。俺が不本意ながらも従ったのは、「何だって言うんだ、この人は最高のアルバムをいくつも手掛けたプロデューサーなんだぞ」と考えたからさ。自分自身のために立ち上がる勇気はなかったんだ。本当は「冗談じゃない。俺はこんなことやりたいんじゃないんだ!」って言うべきだったのに。
――たとえ新人でも、アーティストは自分が発表する作品に責任を持たなければなりません。
HORNSBY:とても難しいことさ。先々後悔するかもしれない妥協点が出てくる可能性は毎日いくらでもあるからね。それはヴォーカルの歪ませ具合かもしれないし、他の人にとっては最高で、自分にとっては曲をぶち壊しにしているとしか思えないパートかもしれない。でも、スタジオにいるみんなは気に入っていて、その後押しに自分自身も徐々に揺らぎ始める。後で振り返った時には、「みんなのほうが間違ってたんだ!」って言えるかもしれないけどね。自分で聴いてみて好きになれなかったら、それは間違ってるんだ。バンドの場合は別だよ。妥協せざるを得ないんだから。でも、もしソロアーティストで、確固たるヴィジョンを持っているなら、そういうのは間違ってる。
――曲作りのプロセスは昔とどう変わりましたか?
HORNSBY:そんなには変わってないよ。というか、プロセスと呼べるようなものは特に決まっていなかったから。決まりきったやり方があるわけじゃないし。歌詞を先に書くことが多いけど、曲を先に書く場合もある。そのほうが似たり寄ったりの作品になりにくいと思うんだ。変わったのはひとつだけ。初めの数年はこんなふうに考えていた。もし自分が思いついたアイディアを覚えていられないようだったら、それはその程度のアイディアにすぎない、ってね。でも、8年前くらいに、「そんなのは馬鹿げてる。俺は今や先週やったことさえ覚えてないじゃないか。これはちゃんと録っておこう」って。それで今はピアノの上にカセットプレイヤーを置いて、何かアイディアを思いつくと録音しているんだ。
――最近は曲を書く際、昔とは違ってもっとジャジーな感じのメロディが聴こえているんですか?
HORNSBY:そう、このあいだ3コードの曲をレコーディングしたばかりだよ。最近の俺のアルバムには、とてもシンプルなハーモニーの曲が多い。いちばん自慢できるのは、いちばんシンプルな曲さ。素晴らしく複雑なものを目指してるわけじゃないんだ。バルトークを目標にしてるんじゃないんだから。そういうものを手掛けることもあるだろうけど、その次はきっとGeorge Jonesのアルバムにもぴったり合いそうなものをやるだろうね。
ものすごくいろんなタイプの音楽が好きなんだ。だから自分の中でその時に何が流行っているかによる。曲作りのプロセスも、それに……、同等とは言わないがかなりの比重で……演奏者としてのプロセスも、すべて自分を駆り立てるためのものなのさ。俺は常に自分が最高だと思うことをやろうとしている。なかなか期待通りにはいかないけれど、たまには上出来と思えることもあるだろう。簡単なことではないけど、それが俺の目標なんだ。 |



