意図的な憂鬱

意図的な憂鬱 Our Lady Peace(OLP)の作る曲には、生死にかかわる事柄がよく取り上げられている。少なくとも、フロントマンのRaine Maidaの場合はそうだ。これは彼の犯罪に関わりがあった過去に起因している。 何年か前、彼はトロント大学の学生だったが、ロックンロールの虜になってしまって学業がおろそかになりそうなとき、犯罪学講座のおかげで学位取得の道を踏み外さずにすんだ。Maidaは、自分の歌に登場する複雑なキャラクターをプロファイリングしよう、という衝動に駆られたことはないと言う。しかし、彼が受けた教育は彼の音楽に対する見かたに大きな影響を与えることになった。 「そこでは、自分が生きていく状況に対して、型にはまった見かたをしないようにと教えられた。僕は、曲を書くときに、憂うつそのものという状況から、ある種の信条やある種の積極性を見出そうと一生懸命なんだ。ひとりの若者が部屋で、ショットガンを持って座って考えている。銃口を口に突っ込むか、テレビに向けるか。銃口を振り回すのをやめて、ある種思いやりのあるシナリオになればいいなと思う。この若者を、敗者としてではなく、ただ誰かに抱擁してほしいと思っている人間として見るということ、少し時間が必要なだけの人間として見るということなんだ」
「陳腐な決まり文句だけど、年をとればとるほど、そのことに向かい合わなくちゃいけない。ある日突然宗教に走ってしまう人もいる。これは偶然じゃない。僕にとってそれは、宗教に逃避しなくてはならなくなる前に、居心地のいい場所を見つけるということなんだ。今の僕は死ぬことを恐がっているからね。でも、自分が不滅の存在ではないことを最終的に悟ったのなら、願わくば60年の人生を見つめていられる場所を見つけようとしたい。そのことを考えようとしないで、人生の最後の年月を、魂がまったく入っていないありきたりのものにしたくないんだ」 Our Lady Peaceは'94年のデビュー以来、心地よいサウンドに落ち着こうなどという気はなかった。『Naveed』は、はっきりわかるグランジのアピールでいっぱいだったが、'97年の『Clumsy』では、Maidaとその仲間たち、すなわちMike Turner(ギター)、Jeremy Taggart(ドラム)、Duncan Coutts(ベース)は、バンドのサウンドに磨きをかけようと余念がなかった。 Maidaは言う。 「この5年間に、曲作りの技術を身に付けた。2分でできてしまう曲というのもあるんだ。演奏や作曲をしていて、あっという間に完成してしまうんだ。そんな時こそ、自動的な曲作りみたいだって気付く時で、自分ではコントロールできない。だから何の心配もない。創造性だけが手に入れなきゃならないことなんだよ」 by Sandy_Masuo |
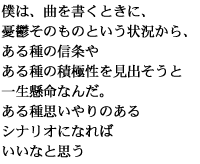 彼は言う。
彼は言う。