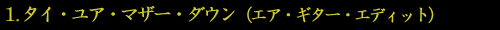 |
| '70年代ロックのエッセンスを凝縮したロックンロール・ナンバー。ロックの真骨頂といえばシャッフルだが、クイーンのシャッフル曲はそう多くはない。ロジャーのタメにタメたドラムスが繰り出すシャッフルはロックらしい後ろノリで、ブライアンのハード・ディストーション・ギターとの絡みが、なんともかっこいいグルーヴを作ってくれている。キメのシンバルのバシャバシャした音、スライド・ギターのうねり、フレディとロジャーのサビのハモリ、どれをとってもクイーンらしい音が満載で、ロック・バンドとしてのクイーンは、この曲で完成したと言ってもいい。ところで、クイーンというバンドは“何をやっても過剰”という言葉が相応しい。この曲が収録されたアルバム『華麗なるレース』には、「ボヘミアン・ラプソディ」の路線に続く「サムバディ・トゥ・ラヴ(愛にすべてを)」という過剰なコーラスワークの曲があり、ファンを萌えさせると同時に腹をいっぱいにさせた。 |
|
 |
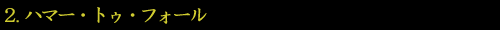 | ライヴでは欠かせない曲としてお馴染みの曲だ。ブライアンらしいストレートなロックでありながら、随所に気を利かせた作りがクイーンらしくて嬉しい。オルガンの刻み、ギター・ソロ終わり部分のギター・オーケストレーション、コーラスのエフェクトなど、聴くたびに新しい発見があって、通常のロックバンドとは一線を画すアレンジの丁寧さがある。この曲が収録されたアルバム『ザ・ワークス』は、クイーンとしての11作目の作品。 |
|
 |
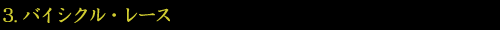  | | 【試聴】 |
| クイーンというバンドのファン層が決定的に変わった記念碑的なアルバム『ジャズ』収録の奇妙な曲。このアルバムでファンをやめた人、そして新しくファンになった人が真っ二つに分かれた。クイーンにある意味での偏差値の高い音楽を求めすぎた人は、この曲のハジケっぷりが我慢できなかったのだろう。しかし聴き直してみると、ものすごいアイデアに溢れた曲である。積み重なる転調、ギターのハモリ、コーラス、そしてある意味メッセージ性の高い歌詞。フレディの狂気と言ってしまえばそれまでだが、これほどまでに溢れ出るアイデアを1曲の中に詰め込む情熱とテクニックを持つバンドは、他には多分見当たらない。なおかつ、PVにはハダカで自転車に乗るオネーちゃん…。フレディにはアカデミックな面とお下劣な面が混在していた。どちらも、反対側をあざ笑うかのような極端さがありながらも、音楽的に緻密に計算されている。優れたロジックによる下品さ、これがフレディの魅力であった。 |
|
 |
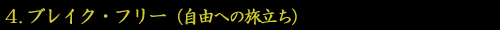 | もはやハードロック・バンドとは呼ばれなくなったクイーン中期の作品。その原動力となったのがベーシストのジョン・ディーコンで、これも彼の作品である。他の3人が個性豊かで、それぞれベスト・プレイがある中で、ジョンがプレイヤーとして称えられたのは「ボヘミアン・ラプソディ」でのベース・プレイくらいか。だが、彼の作る曲はポップでわかりやすく、ブライアンとフレディが作る摩訶不思議な世界、またロジャーが作る純粋なロックンロールとも違い、ヒット・チューンに上がったものが少なくない。この曲は、まるで打ち込みで作ったようなリズム・トラック、ゆるやかだがセンスの良いコード進行と、女性シンガーが歌ってもよいポップさ、そしてなによりもシンセサイザー! しかし、そこはクイーン。フレディが曲の素直さを破壊しようとするかのようにメロディを崩していき、「ワシが歌ったらクイーンなんじゃい!」という気合が感じられる。 |
|
 |
 | ピアノ弾き語りの小品かと思いきや、次第に音が積み重ねられていき、やがてクイーン独自のオーケストレーションが加わる。初期クイーンの王道の音作りが楽しめる曲である。『ア・ナイト・アット・ジ・オペラ(オペラ座の夜)』に収録された「シーサイド・ランデヴー」の傍流とでも言える楽曲。ブライアンのねちっこいギター・ソロや、サビ後に出てくるヴォーカル、メロディを追いかけるコーラスの豪華さなど、もうファンならニヤニヤの雰囲気がいっぱい。この曲、『グレイテスト・ヒッツ』にも収録されていたこともあって、ファンの間では人気が高い。 |
|
 |
 | ブライアンのロマンチックなラヴソング。クイーンの世界的な人気を決定的なものにしたとともに、クイーンをハードロック・バンドと認知していた古いファンが雪崩のように離れていったといわれるアルバム『ザ・ゲーム』に収録。シンセサイザーを導入し、全体的にヒット・チャートを狙ったようなポップな曲が多い中で、この「セイヴ・ミー」は初期クイーンを彷彿とさせるようなクラシックな音作り。メロディラインを美しくなぞるフレディのヴォーカルも素晴らしいが、ブライアンのギターはその中でも秀逸。オーケストラのような重厚な音からハーモニックスを多く含んだヒステリックなギター・ソロに続くあたりは鳥肌モノのプレイだ。この曲がアルバムの最後に入っていたということの意味を深読みして“次のクイーンのアルバムは初期のように正統派に戻る”と予想するファンもいたが、『フラッシュ・ゴードン』、そして『ホット・スペース』で、見事にその予想を裏切られることになった。 |
|
 |
 | この曲がセレクトされたことに驚きを感じると共に、クイーン・ファンの懐の深さを感じる。ボトムは今までのクイーンにはないほど太く、ヘヴィさを前面に押し出した音作り。コスモポリタンな強烈なメッセージなど、何者か巨大なものと戦う姿勢が感じられる強烈な曲だ。ここまでのアルバムにあった過剰さは息を潜め(といっても程度もんだが)、ロック・バンドとしてのコアな衝動がストレートに伝わってくる。12作目のアルバム『カインド・オブ・マジック』に収録。 |
|
 |
 | “フレディのヴォーカルが怖い”と女子ファンに言わしめた後期の代表曲。ここで聴くことができるヴォーカルの力強さ、演奏のアヴァンギャルドさ、バンドとしてのバランスのよさは特筆モノで、クイーンが元気になって戻ってきたという印象を与えた。フレディだけでなくブライアンもが、シャウトでアジテートする内容は、人生をいかに充実して生きられるのかということ。フレディの症状が進んできたことと呼応しているのか、自分への叫びとも受け取れる。クイーンが現実に直面した悲しみを克服するために、この強いサウンドと歌詞が必要だったのだ。フレディ追悼コンサートで、ザ・フーのロジャー・ダルトリーが涙を目にためながらマイクを振り回し絶叫したシーンを思い出す。話は変わるが、途中でテンポ・チェンジしてギター・ソロが始まるところなど、ロックってカッコイイなぁ、とつくづく思ってしまう。 |
|
 |
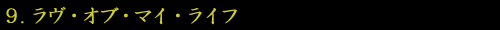 | 驚いたのは、この曲が数々のベスト・アルバムに収録されたことがなく、今回が初めてだということだ。初期クイーンの代表曲であるだけでなく、ロック史に残る名曲とも言われる曲だけに不思議。アルバム『オペラ座の夜』に収録されていた時は、前の曲のアウトロとこの曲のイントロがかぶっていたが、今回のヴァージョンはそれを抜いてある。そういう意味でも貴重なヴァージョンだ。シンプルなバック・トラックに重厚なコーラス、その上で歌われる切ない愛。ブライアンの弾く甘いトーンのソロやオーケストレーションが曲を盛り上げる。一分の隙もないアレンジは、この時期のクイーンの特徴で、それを実現しているのがピアノとギター、そして声という必要最低限のものだけ。“過剰さ”があってもクイーン、省いてもクイーン。それが揺るぎないクイーンの強さの秘訣なのである。ちなみにライヴではキーが一音低く、ブライアンのアコギだけで演奏される。スタジオ盤とは違う魅力があって美しい。また、一番最後に「イェェェ~♪」と歌うのはライヴ・ヴァージョン。 |
|
 |
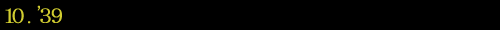 | この曲は人気がある。海外ではどうなのか分からないが、日本ではこの曲をフェイヴァリットの第一に挙げるファンが多い。必然的にカラオケ・ボックスで聴く機会も多い。基本的にアコギ一本で歌えるので、難解な曲の多いクイーンの曲の中にあっても、気軽に歌える名曲として人気があるのだろう。ライヴでは4人がステージ中央に集まり、ブライアンがアコギ、ジョンはベース、ロジャーが立ったままバスドラを蹴りタンバリンを打ち鳴らすというスタイルで演奏された。オーソドックスなフォーク・ソングでありながら、アメリカのカントリー・ソングのエッセンスを取り入れてもあり、途中の部分ではロジャーの超高音域を活かした重厚なコーラスも聴ける。曲作りの巧みさは見事だ。「一番好きなクイーンの曲は?」と訊かれた時に「'39」と答えるのが通でカッコイイとされている。 |
|
 |
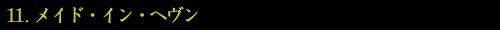 | イントロのフロアタムは天国の扉をノックする音、そしてブライアンのギターはファンファーレといったら感傷的すぎるだろうか。フレディの死後、録音されていたヴォーカル音源を元に演奏を付け加えてリリースされたアルバム『メイド・イン・ヘヴン』収録のタイトル曲である。伸びやかで艶のあるフレディの声は、こちらの胸に迫る力強さを内包し“すべて天が造りたまう”と歌う。自分の力では変えられない現状を天に委ねるのは弱さではなく、人生を全身全霊で生きた者の特権なのであると。この歌を聴いて、初めてフレディが本当に死んでしまったことを実感できた。そういうファンも多いはず。海の向こうの著名なミュージシャンが死んだというのではなく、同じ空の下で精一杯生きる独りの男が死んだのだと。そしてその男は、有り余るほどの才能を抱え、それを全世界の人に残してくれた。この曲は、デビューからクイーンを見てきたファンに衝撃だった。でも、やっとフレディと別れを告げられたのだ。ちょっとセンチすぎたかな。 |
|
 |
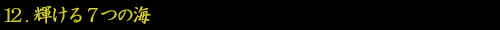 | 1stアルバムではインストゥルメンタルの練習曲風に入っていた曲だが、2ndアルバムで歌が入りシングルとしてもリリースされた。この頃のクイーンは、白か黒の衣装とグラマラスな化粧をまとった様式美を重んじるロック・バンドとしてミーハーな存在で、それでいて緻密な音の構築で音楽的にも認められるという両面を持つバンドだった。この曲が収録されているアルバム『クイーンII』は、片面がホワイト・サイドとしてブライアン中心の楽曲、そしてもう片面がブラック・サイドとしてフレディ中心の楽曲という風に色分けされており、特に曲構成の難解さとフレディの狂気が前面に出たブラック・サイドの出来は特筆もの。組曲風にアレンジされており、「オウガ・バトル」「フェリーフェラーの神技」「ネヴァーモア」「マーチ・オブ・ザ・ブラック・クイーン」と休みなくつながる構成は壮絶。今でもクイーンの一番好きなアルバムに挙げるファンが多い。 |
|
 |
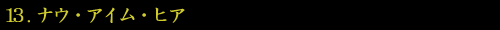 | クイーンの初来日コンサートのオープニング曲だったはず。真っ暗なステージにブライアンのギターの刻みが聞こえてきて、シンバル・クラッシュとともに、スポットライトがフレディの姿を照らし出す。そんな演出でファンは狂喜したのだった。まだフレディが長髪の頃の姿であります。重い8ビートのリズムとブライアンのリフ、ケレン味出しまくりでキメのポーズを繰り返すフレディ、ハイトーン・ヴォイスでコーラスに厚みを加えるロジャー、地味にボトムを支えるジョン。4人のロック・ミュージシャンを世界へ送り出したのは、この曲から始まった日本でのコンサートだったと断言してしまいたい。ロックのカッコよさが詰まった佳曲だ。 |
|
 |
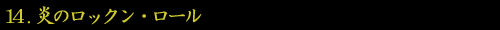 | クイーンの記念すべきデビュー曲。イントロのギター・サウンドを聴いただけで、これはタダモノじゃないなと感じたロック・ファンに乾杯! そう、この曲は、単純なロックンロール曲と思われがちだが、そんな簡単な作りにはなっていないのだ。転調を重ねていくのにポップで分かりやすいメロディ・ライン、ブレイクでの重たーいドラムソロ、多重録音を重ねたギター・オーケストレーション、過剰なまでのエフェクト処理など、クイーンの本質が凝縮されている。フレディのヴォーカルも若々しく、こういうハードな曲での自分の表現の仕方を模索しているようにも聞こえる。しかし、歌詞の内容からは、己が道を信じるということについては、もうこの頃から確立されていたようだ。クイーンが、他のバンドとは全く違う音と感性で世界的なバンドになる予兆を感じられる、荒々しいが繊細な曲である。フレディ追悼コンサートでは、この曲をエクストリームが演奏した。ゲイリー・シャロンが泣きそうになりながらクイーン・メドレーを歌うのが印象的だった。 |
|
 |
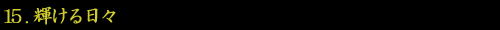 | クイーンの事実上のラスト・アルバム、フレディの絶唱が集められた壮絶なアルバム『イニュエンドゥ』に収録された楽曲。このアルバム制作中には、フレディの寿命が目前に迫っていることが分かっており、4人それぞれが覚悟のもとで制作されたアルバムだ。上方に向かって飛翔していくようなメロディと、今までを懐かしみながらも悔いを残さない歌詞。フレディの声に衰えなど全く感じない。クイーンの歴史には紆余曲折があり、世間の評価に一喜一憂したり、行くべき道が分からなくなって衝突したり、他のバンドがそうであるように、順風満帆で来たバンドではない。しかし、悩んだだけの価値のある実験的なことや、常人が考えもつかない発想で発表した楽曲は世界的な成功を呼び込み、今やクラシックとも言える存在になっている。そんな悩んだ日々をフレディは懐かしむ。自分の人生は本当に幸せだったと。 |
|
 |
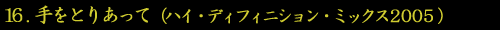  | | 【PV】 | |  | | 【試聴】 |
| この曲を聴くと涙が止まらない。そんなファンの声を良く聞く。この曲こそが、クイーンが日本のファンにとって特別な存在、いや、クイーンにとって日本のファンが特別な存在という証なのだ。「ボヘミアン・ラプソディ」以前に「キラークイーン」がヒットしたとはいえ、この当時のクイーンはまだ世界的に認められた存在ではなかった。しかし、その魅力を真っ先に嗅ぎつけ、クイーンを大スターのごとく遇したのが日本のファンなのだった。クイーン側も“日本は第二の故郷”と言ってはばからず、日本ファンとクイーンの結びつきは確固たるものとして、それから先も続いていく。そういう日本のファンに対するクイーンからの返答がこの曲「手をとりあって」だ。これが5thアルバム『ア・デイ・アット・ザ・レイセス(華麗なるレース)』に収録された時のファンの喜びようといったら。アジア風な旋律とアレンジを持ったこの曲は、日本人が聴いてもエキゾチックな雰囲気があり、クイーンの数多くの楽曲の中でもひときわ目立つ存在だ。この曲が収録されることに、今回のベスト・アルバム『ジュエルズII』の意義があったと言っては言い過ぎかな? 今回の収録にあたってリミックスがほどこされ、音の一粒一粒が聴きやすくなっている。 |
|
 |
