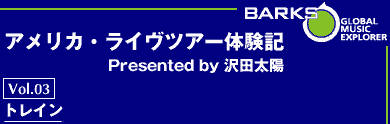ここ10年ほど、オルタナティヴ・ロックは「メインストリームに対しての反抗音楽」として機能してきた。そしてそれは、'80年代後半にバブル状に膨れ上がった手ぬるいロックを一掃するのに大いに貢献した。
しかし、いつしかそんなオルタナティヴ自体が主流となってしまった今、払拭すべき敵となるべき存在はなくなってしまい、オルタナ自体が自然と「保守王道」となるしかなくなってしまった。
そんな状態であるならば、オルタナがポップに洗練されて行くのはごく自然の成りゆきなのではないだろうか。それに、いつまでも眉間に皺を寄せたシリアスな歌ばかりを聴衆も聴いていたくはないはずだ。
そろそろ理屈抜きによくできた「ポップス」というものをちゃんと聴きたい。トレインとは、そういう時代のニーズに見事に応えた存在なのだ。
そんな、現在のアメリカのロックシーンの象徴とも言えるトレインのライヴを彼らの地元サンフランシスコの名物ライヴハウス、ウォーフィールドで目撃してきた。
会場に詰め掛けた観客で目立つのは30代前後の比較的高い年齢層の人たち。これはやはり『ドロップス・オブ・ジュピター』がアメリカのアダルト・ラジオ局でウケていることを反映してのことだろう。
そしてそんな観客を迎え撃つトレインの5人のメンバーも、そんな観客とほぼ近い世代と思しき実にシンプルな風貌。
2ndアルバムの中の「リスペクト」で幕を開けた今回のライヴだが、やはり'90年代のバンドとは違い、コードやコーラスに凝った職人気質のポップスを聴かせてくれる。 | . | ヴォーカルのパットも実に伸びやかなハイトーン・ヴォイスを披露。この辺は予想通りに'80年代バンドっぽいニュアンスだが、パットがトランペット、サックス、パーカッションをプレイし、ギタリストが頻繁にマンドリンに持ち換えるなど、ジャジーかつ土臭い演奏ができる器用さを見せるところが現在のジャム・バンドっぽくもある。
いずれにしても、演奏のうまさ、ミュージシャンシップの高さに関しては保証つきであると言ってよい。勢いと若さにまかせたライヴも良いが、こういう安定した実力をもった連中によるライヴというのも決して見逃せない。
また、極めてシンギングしやすいアンセム的な楽曲が目白押しのため、会場はどの曲でも合唱につぐ合唱。そして、オリジナル曲のみならず、レッド・ツェッペリンやチープ・トリックのカヴァーまで披露。この辺のハードロックを元曲に忠実な高いキーで歌えるところにこのバンドの音楽的ルーツ(おそらくメタルだろう)が垣間見えもした。
MCも女性をステージにあげて口説いてみたりなど、エンターテインメント性も高い。やはり地元でのライヴということで終始大盛り上がりではあったが、こうしたライヴのノリに対してときに「手ぬるいぞ!」「売れ線に走りやがって」とばかりにブーイングを飛ばす向きもあったが、これに対してもヴォーカルのパットが「僕達のことをジャム・バンドって思ってる人たちには軟弱に聴こえるかもしれないけど、僕達はチープ・トリックの曲だってやるんだぜ!」とやり返すなど、肝っ玉の座り具合もまた見事だった。
派手なルックスもカリスマ性もない。しかし、“若者の代弁者”的キャラクター性が必要以上に求められ過ぎた'90年代の反動として、こうした地味ながらもちゃんとした実力を持ったバンドがそろそろ評価されるべきではないか。
僕はそう思いながら、ライヴ会場を後にした。 |