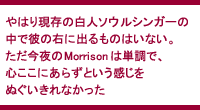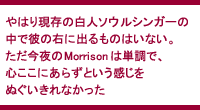 | そのバンドは真っ赤なスーツを着込んでいた。Van Morrisonのバンドである。このいでたちを見れば、北アイルランドはベルファスト出身のカウボーイの目指すところは明らかである。'50年代から'60年代の古き良きR&Bへの郷愁だ。このところMorrisonは、昔は良かったと堂々と称える動きを見せ、昨年はスキッフルのアルバムに加え、Linda Gail Lewis(Jerry Lee Lewisの妹)とのデュエットでロカビリーや古いブルースのカヴァーアルバムをリリース。情熱を傾けたプロジェクトなのかもしれないが、今回のライヴを見る限り、それは伝わってこない。エキサイティングなステージというよりは、ベテランのサポートを得てやっと、ストイックなパフォーマンスに陥るのを免れているありさまなのだ。
サポートの腕の良さは最初から見てとれた。まずはウォームアップにバンドだけでJohnny Guitar Watsonの“Hot Little Mama”を聴かせたあと、Lewis嬢がピアノを弾きながら、鼻にかかった甘い独特のヴォーカルで2曲ほど見事に歌う。それから、ようやくMorrisonの登場。キラキラ光るブラックスーツに粋な帽子、サングラスという洒落た格好で、Lewisと“Let's Talk About Us”をデュエット。3者が順番に登場するこのステージングは、何組ものアーティストが共演するいわゆるR&Bレヴューを彷彿とさせる。続いてMorrisonは、クラシックブルースと自分の音楽との接点を強調するように、自作の“Back On Top”や“These Dreams Of You”を熱唱した。
こうした趣向ならコンサートも盛り上がるはずなのだが、バンドのインストゥルメンタルパートの間中、まるでバス停で待つ通勤サラリーマンのようにステージに突っ立っているMorrisonのスタイルは、せっかくのショウの楽しみを半減させた。今夜はヴォーカリストに徹し、楽器を手にしておらず、バンドや観客との掛け合いにも興味がないらしい。一方、バンドのほうは盛り上げようと懸命だ。ことにホーンセクションのLee Goodall、Martin Winnings、Matt Holland、それにギタリストでリーダーのNed Edwardsは素晴らしい。Morrisonが続けざまにセットをこなしていくのに、よくついていっている。なにしろ曲が終わりきらないうちに、次の曲のタイトルを紹介するといった具合なのだ。だが、観客に過去を呼び起こさせようとするあまり、彼自身が過去の彼方に行ってしまったかのようにも思われた。
とはいえ、Morrisonの歌はやはりうまい(ただし観客受けを狙った“Moondance”や“Brown Eyed Girl”をおざなりに歌ったのを除いて)。今夜のハイライトは、感情のこもった“Philosopher's Stone”と“Old Black Joe”、ジャジーな“Brand New Cadillac”だった。やはり現存の白人ソウルシンガーの中で彼の右に出るものはいない。ただ今夜のMorrisonは単調で、心ここにあらずという感じを拭いきれなかった。アンコールでは“Shake, Rattle & Roll”や“Whole Lotta Shakin' Going On”(この曲でLewisは兄同様にピアノスツールをひっくり返し、観客は喝采)などのロックンロール・スタンダードをメドレーで歌ったあと、そのままステージを降りてしまったのである。あれは本当にMorrisonだったんだろうか。 |