“血の花”の予言

不死身の陰鬱な神々The Cureが放つ12枚目のスタジオ録音盤『Bloodflowers』は、'82年の画期的な『Pornography』(いまだにCureの作品中もっとも閉所恐怖症的で放逸で気の滅入る1枚といわれる)に始まり、憂いに沈んだ傑作と呼ぶほかない'89年の『Disintegration』と続いた、暗く陰気な3部作のドラマティックな最終章というもっぱらの評判だ。 Cureの最新作には、『Pornography』に描かれた恐怖と絶望の底なし沼も、『Disintegration』の壮大なオーケストレーションも見られないが、それでも“3部作説”が単なるマーケティング戦略にとどまらないと納得させるサウンドの類似がある。これは「Love Cats」「Inbetween Days」「Why Can't I Be You?」「Friday I'm In Love」といったオルタナポップ・ラジオ向きの(彼らとしては)元気のいい曲で知られるCureとは別のCureである。 そのことは『Bloodflowers』の代表曲「Watching Me Fall」…激しく泣き叫ぶような声が延々11分も続き、「One Hundred Years」(『Pornography』収録)の凶暴な咆哮や、『Disintegration』の苦しげなタイトル曲を彷佛させる…を聴いただけで明らかだ。これら3枚のアルバムを立て続けに聴けるくらいマゾヒスティックな人がいたら、カミソリや睡眠薬は遠ざけておいたほうがいい、とだけ言っておこう。 しかし、CureのリーダーRobert Smith(ゴシックロックの偶像にして、Cureの最重要人物。今にも絞め殺されそうな、やるせなくすすり泣くような、あの独特なヴォーカルはもちろんのこと、ボサボサ頭と深紅の口紅がトレードマーク)の考えによれば、『Bloodflowers』は大きな全体の中の一部というより、1枚の独立したアルバムだ。 「『Bloodflowers』が『Pornography』に始まり『Disintegration』と続いてきた3部作の第3部かって? それは違うな」 「3部作だとしたら、最初の2部のことを知っていないと、第3部が意味をなさない。でもこの場合、『Pornography』や『Disintegration』を聴いたことがなくても『Bloodflowers』を楽しむことはできる」 「Cureが絶好調のときにどれだけのことができるかみんなに見せつけるために、僕がスタジオで利用したのが『Pornography』と『Disintegration』だった。『Bloodflowers』もそこまでレベルの高いアルバムになったらいいなと思ってはいたよ。そういう点では、3枚のアルバムは密接に結びついているといえる。過去の僕と現在の僕をつなぐという点で。自分がどう変わったかを見ると興味深いものがあるね」 22年におよぶCureのキャリアを通じて、Robert Smithはさまざまなキャラクターに変身してきた。 たとえば、'78年のすっきりとしたデビュー作『Three Imaginary Boys』(「Cureのアルバムの中でいちばん嫌いだ。作りたいサウンドをちっとも作れなかった」とぼやくRobert)ではポストパンクのミニマリスト。 軽いユーロディスコをフィーチャーした'83年の『Japanese Whispers』(「人がCureに対して持っているイメージを壊したかった。冗談みたいなレコードだったね。いい思い出はない。思い出すと気分が悪くなる…」)ではいたずら好きなわんぱく小僧。 『The Top』(「ちょっと混乱したレコードだった」とは、Robertの控えめなコメント)では、指をくねらせながら“イモムシ娘”や“バナナフィッシュの骨”や“グルーヴィーな紫のシャツを着たブタ”について取り留めもなく喋りまくる、イカレたヤク中。 しかし、ここ3作のミッドテンポのメランコリックな音こそが、『Seventeen Seconds』(「このアルバムで Cureが本当に始まるんだと思えた」)と『Faith』の不吉なペアと並んで、この先ずっと“真性のCureサウンド”とされていくことだろう。 「今回のニューアルバムに関して最初に受けたインタヴューというのが、イギリスでのことだけど、いきなり『いかにもCureらしいサウンドだ、過去10年間のいつ作られてもおかしくなかった』と言われてね」 「相手は侮辱のつもりで言ったんだろうが、僕は『それはうれしいよ。ありがとう!』っていう感じだった」 けれども彼は 「'80年代の初め、トリオに戻って作った3枚のアルバムのサウンドは、すごく特徴的で、ちょっと聴けばすぐに僕たちだとわかる音だった。'80年代末、『Disintegration』のころには、それとはまた別のはっきりしたCureサウンドができあがった。キーボードを中心に、幾重にも重ね、あれこれと手を加えた、大がかりで劇的なサウンドだ。そして現在のラインナップが、両方の要素を採り入れて、さらに新しいCureサウンドを発展させた」 種々のスタイルで実験や探究を繰り返してきたからこそ、Cureはアンダーグラウンドとメインストリームを隔てる細い不安定な境界線の上を、20年以上も歩き続けてこられたのだ。 「一般の人たちは、ビデオやポップな曲を通してCureを知っている。でも、それはCureの本質ではない」 「僕にとって、感情のレベルでもっとも意味を持つのは、シングルになったり商業的に成功するような曲じゃない。僕たちはアルバム志向のバンドだと思うよ。シングル志向のバンドじゃなくて」 紛れもないメインストリームの仲間入りを果たし、Cureの影響を受けたSmashing Pumpkinsなどオルタナロックの寵児たちと張り合うくらいビックになることを、Robertはわざと避けているのだろうか。 なぜヒットを狙って、「Love Song」や「Friday I'm In Love」「Let's Go To Bed」のような曲を次々に出さないのだろう。 Robertは肩をすくめて言う。 「僕の大部分は、そういうたぐいの成功を求めていないんだ」 「『Wish』のツアーには、僕にすごい悪影響を及ぼす側面があった。成功者のライフスタイルに誘惑されたんだ。それでも自分に何が起こっているかを見極めるだけの知性はまだあったから、こんなふうに暮らしていたらあっというまに人間性を失うと判断した。Cureのキャリアにおいては、成功することよりも成功しないことに時間をかけてきたよ。成功というものを味わってみて、人が思うほどいいものじゃないとわかったんだ」 皮肉なことだが、この商業的野心の欠如こそ、Cureが驚くほど長続きしている要因かもしれない。 「Cureがファッショナブルなバンドだと思ったことはない」 「ファッションよりもスタイルのセンスがある人たちに惹かれるんだ。はやりのバンドであるより、スタイリッシュなバンドでありたい。いろんな面で思いきり流行遅れのバンドでいたい。ヒップで新しいといわれた時期もあるけど。そこがこのグループの不思議なところさ。僕たちには大勢の幅広い一般のオーディエンスと、小人数の熱狂的でハードコアなオーディエンスがいる。両方が一致するなんて、めったにないことだ。不思議だよ。精神分裂気味のグループだってことかな」 CureをBillboardのチャートに送り込み、アリーナ会場を満員にしたのが、大勢の幅広い一般のオーディエンスである一方、今日までバンドを存続させてきたのは、小人数の熱狂的でハードコアなオーディエンスだ。 こうした熱烈で忠実なファンの存在は、Robertの荒涼として不安に満ちた歌詞(同じく荒涼として不安に満ちた声で歌われる)と大いに関係がある。 Robertに負けず劣らずペシミスティックなMorrisseyの場合がそうだったように、暗い絶望に沈んだ無数のファンは、この歌詞に共鳴し、Robertの悲痛な歌声に慰めとカタルシスを見い出した。 しかしRobertの書く詞は、必ずしも自らの体験に基づくものではないようだ。 彼はまた、自分は世間が言うような自殺願望の情けない奴ではないと主張する。 「みんな歌詞を読んで、僕という人間を知ってるつもりでいるけど、曲にあらわれるのは僕の中のほんの小さな一部分だ。それ以外の部分は、たいていのときは不満もなく、自分の生活に満足している僕で、歌を書こうとは思わない。創作したいという欲求を感じないんだ」 創作の欲求を感じないといえば…『Bloodflowers』のリリース以来、これがCureのラストアルバムになるという噂が、まことしやかにささやかれている。言うまでもなく、この手の噂が流れるのは初めてのことではないし、 Robert本人が事実と認めたものもあった。 古くは『Pornography』のころ、Cureの消滅は時間の問題と思われた。彼は 「通過儀礼みたいなアルバムだ。あらゆる面で自分に多大な影響を及ぼす作品…感情的にも、物理的にも、精神的にも…を作ったのは、あれが最初だった。おかげで死にそうになったよ」 RobertがCureの解散を初めて真剣に考えたのは、10年前、『Disintegration』の時期だ。彼が言うには、このアルバムは 『Wish』をリリースした'92年にもCureは解散したはずだったが、 Robertは再び“オオカミ少年”になる。 「『Wish』を出した後、僕は完全に音楽の世界を離れ、バンドも必然的に解散した」のは事実だ。が、Cureには執念深い“恋猫”よりも多くの命があるらしく、'96年には『Wild Mood Swings』でまたも復活。 「あのときは心機一転という気持ちだった。理屈じゃなく、もう一度やりたいと思った。生まれかわったみたいだったよ」 つまり、Cureは基本的にはずっと続いていたということだ。ただし、ここ10年はリリースのペースがぐっと落ちている。 「ここ10年間にはアルバム4枚、その前の10年間には8枚作った。曲を書くペースを落としたのには僕なりの理由があるけれど、それがグループの息の長さに関係するとは思わない。僕自身は以前より欲がなくなったけど」 で、今回の真偽のほどは? Cureはもうすぐ終わってしまうのか。 『Bloodflowers』は Cureにとって最後のアルバムになるのか。Robertの答えはいつもどおり曖昧だ。 「40になったらやめて他のことをするって、いつも言ってたんだ。最高作を発表すると同時に幕を引くグループなんて、めったにいないよね。それをやってみたいんだ。最後までいい仕事をするグループだったと言われたい。『Bloodflowers』は最後の作品として作ったし、有終の美を飾るにふさわしいものができたと思う。『Wish』に取って代わってCureのベスト3に入るアルバムだ」 しかし、ニューアルバムに収録された“39”というほろ苦いタイトルの曲で、Robertが Cureの“最後のアルバム”をレコーディングしたことが、アーティストとしての情熱に新たに火をつけたとは、なんとも皮肉である。 「要するに、アルバム作り…実際の制作過程と、最終的にできあがったもの。それはバンドの信念そのものだ…が僕をまたやる気にさせたってことさ」 「逆説的だね。このレコードを作る前は、バンドとその中に占める自分の役割に、そうとう嫌気がさしていたのに。きっとバンドの寿命が尽きたんだろうから、ここらで景気よく退場しようと思ってた。でも、このアルバムを作って、僕たちはまだ質のいい音楽をやれるとわかったら、次のアルバムも作りたいっていう気持ちになったんだ」 『Bloodflowers』のタイトル曲にある「この花は決して枯れない」という一節が、 Cureの将来をもっとも的確に予言しているのかもしれない。 by Lyndsey Parker |
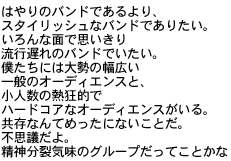 堂々3位になった「Love Cats」をはじめとするトップ40ヒットを飛ばし、1枚ならず2枚のグレイテストヒッツ集をリリースし、ドジャースタジアムのように巨大なアリーナを満杯にし、しかも頑固で挑戦的なまでの難解さを保つCureは、特異なバンドである。
堂々3位になった「Love Cats」をはじめとするトップ40ヒットを飛ばし、1枚ならず2枚のグレイテストヒッツ集をリリースし、ドジャースタジアムのように巨大なアリーナを満杯にし、しかも頑固で挑戦的なまでの難解さを保つCureは、特異なバンドである。