Green Strohmeyer-Gartsideはインタヴューの冒頭にこう宣言した。「僕は過去からものを見ることはしないし、過去から音を聴くこともしない」。 長らく活動を休止していたScritti Polittiのリードシンガーが、おなじみの甘い声で「過去」というのは、彼のグループがニューウェイヴ後に大量発生したダンスミュージックの主力プレイヤーだった'80年代中期のことだ。あれから長い時が流れた。 現在42歳のGartsideは、'90年代のほとんどを、人目を避けて過ごしてきた。Scritti Polittiの3rdアルバム『Provision』を'88年にリリースしてまもなく、音楽業界に愛想を尽かした彼は、生まれ故郷であるウェールズの田舎家に引きこもった。
彼の声は、大ヒットした「Wood Beez」でAretha Franklinのように祈ることを歌った当時とちっとも変わっていないが、目の前にすわっているGreenはまるで別人だ。彼が冗談めかして「ダイアナ妃時代」と呼ぶ、あのウェイヴのかかったブロンドヘアは跡形もない。今はライトブラウンの髪をツンツンに立て、唇の下にピアスをつけ、あごひげを生やし、大きな青い瞳をサングラスで隠している。まだ自分のすべてをさらす心の準備ができていないのかもしれないが、1つだけ確かなのは、Scritti Polittiの音楽が完全復活したことだ。 自ら好んで10年近い隠遁生活を送ったGreenは、11年ぶりのニューアルバム『Anomie & Bonhomie』で、西暦2000年を祝おうとしている。 『Anomie & Bonhomie』は、好評を博したScrittiのクラシックポップサウンドを再現する一方、昨今大人気のヒップホップの領域にも踏み込んでいる。Gartsideはこの新作のセッションに、ヒップホップアーティストとロックミュージシャンのオールスターラインナップを招集した。ヴォーカリストのMos DefやLee Majors。Grace Jones風の激しいヴォーカルばかりか、ファンキーなベースも聞かせるMe'shell Ndegeocello。ギターの腕を遺憾なく発揮するWendy Melvin(Prince、Wendy & Lisa)とAllen Cato(Sly Stoneのオリジナルギタリストの息子)。そしてプロデューサーは、元Scritti Polittiのキーボード奏者David Gamson。 昔からのファンならすぐにわかるだろうが、Gartsideは単にめまぐるしく移り変わる流行に便乗しようとして、このような創作上のアプローチをとったわけではない。Scrittiのブレイクとなった'85年のアルバム『Cupid & Psyche 85』を聞いてみるといい。キーボード主体のミックスに、幅広いビートやジャマイカのダンスサウンドを採り入れ、クラブでヒットした“Flesh & Blood”ではロンドンのDJ、Ranking Annをゲストシンガーに迎えたほどだ。 今思えばGartsideは、ヒップホップという名称がまだないころからヒップホップの実験をしていたことになる。それでも本人は、ポップ的異種交配の先駆者と呼ばれるのを嫌う。
「そういう考え方は傲慢だし間違っている」という彼は、おそらく質問を深読みしすぎているのだろう。
「あまりにも目的論的で、初めからそう計画していたみたいじゃないか。全然そんなのじゃないんだ。新しいことをやって自分で楽しみたかっただけだよ。そうでなくちゃつまらない。自分の好みを表現する手段であって、改革運動でもなんでもない。僕はポップミュージックが好きで、ヒップホップをポップミュージックだと思っている。このレコードは2年前に作ったものだから、今は何を期待していいのかわからないな。出すタイミングとしては、2年前より今のほうがいいということはあるかもしれない」
タイミングのよさは、一聴すれば明らかだ。『Anomie & Bonhomie』は、長いこと行方をくらましていたアーティストの華々しい復帰記念盤である。
まったくいい質問だ
“基盤”ってのが気に入った
LAUNCH:
Scritti Polittiの最後のアルバムからもう10年以上たちます。あなたの声は今もあのころのままですし、Scritti Polittiという名前はよく知られていますが、今回のレコーディングでは別の名前を使うことも考えたのでは?
GARTSIDE:
一時は考えた。だけど名前を変えても、得することは何もないと思ったんだ。ブランクがすごく長かっただけに、そんなことで悩んでいられなかった。存在してもいないバンドに新しい名前をつけるなんてバカバカしいよ。とにかくまたDavid Gamsonと組むことになったし、誰だろうとこの船に乗り込んだのがScrittiってこと。いい隠れみのだよね。
LAUNCH:
どうしてこういうアルバムタイトルになったのですか?
GARTSIDE:
“anomie”(フランス語で“無規範状態”の概念を意味する)というのは、たとえば批評論とか、ポストモダン系のどうしようもない論文によく出てくる言葉でね。現代では個人も集団も、明確な価値規範を失っている。僕が気に入ったのは、“anomie”に対する英語の訳語がないという事実だ。“bonhomie”(同じくフランス語で“人のよさ、親切”の意)もそう。翻訳が不可能だったり、同一の基準で比較できなかったりする言語に興味がある。それに、この2つの単語がかもす緊張感がいい。“anomie”は何らかの喪失を表す言葉で、悲しみや衰退を連想させ、“bonhomie”は社交的に満たされた状態を思わせる。こっち(ニューヨークシティ)でホテルに泊まっているとき、理論と言語に関するなんだかわけのわからない本を読んだら、“anomie”って言葉が出てきたんだ。それから数分後、今度はレストランを紹介するNew York Timesの記事で“bonhomie”に出くわした。これは神のお告げだと思ったよ(笑)。
LAUNCH:
ニューアルバムでは『Cupid & Psyche』期のScrittiに顕著なホワイトソウル/ダンスポップ・サウンドを、ヒップホップと融合させていますね。まったく異なる2つの世界を、どのようにして衝突させた…あるいは衝突しないようにしたのでしょう?
GARTSIDE:
そう、言ってみれば衝突だね。列車事故みたいなもんだ。「これほど矛盾なくまとめあげるとは見事」だとか、時には「組織的統一」なんてことまで言われるけれど、そんなことしてるつもりはない。あるアイディアを別のアイディアにぶつけてみるんだ。単純な人材調達システムとしては、みんなに電話して「聴かせたいものがあるからスタジオに遊びに来ない? もし気に入ったら一緒に演ろうよ」って言うことさ。Meshellとは食事に行って、好きな音のことを話して、デモを聴いてもらった。いずれにせよ声をかけてみて、相手の反応を見る。断わられたことはないと思うな。
LAUNCH:
参加アーティストはあなたの以前の作品を知っているのですか?
GARTSIDE:
僕は何も聞かない。知ってる人もいれば知らない人もいるだろうし、向こうから言い出す場合もある。仕事が終わってから「ところで、君の曲はよく知ってるよ」なんてね。でも、そんなのどっちだっていいんだ。まず曲を聴いてもらう。OKしてくれるといいなと思いながらね。そして、それがどういう歌かを説明する。「近年の資本主義のイデオロギーに対するヘナチョコ攻撃とでもいうかな。ねえMos Def、どうだい、このテーマでラップしてくれないか?」 すると彼は「いいとも」って答える。…ほんとだって。
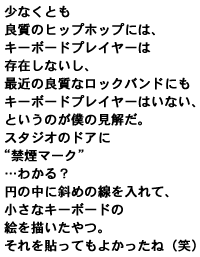 LAUNCH: LAUNCH:
「Tinseltown To The Boogiedown」といった曲は、あなた自身とアーバン系アーティストの共通基盤を見つけようという試みですか?
GARTSIDE:
どうなんだろう。それ、すごくいい質問だね。パッと思い浮かぶのは、君が言ってるのは空間的隠喩だってことだ。僕は空間的隠喩が好きじゃないんだけど(笑)。基盤なんかなくて、僕らはみなこの(両腕を大きく広げて)3次元にいる、といえばいいかな。同様に、僕らを分かつような基盤もない。それより量子物理学の観点から分析しようか(笑)。“共通基盤”という考え方がどうも気になって…それはさておき、あれがどういう歌か知りたい?
LAUNCH:
ぜひ。
GARTSIDE:
仕事と余暇と…あの曲で死という言葉を使ったっけ? 使うべきだったかな…この世紀末アメリカにおける、仕事と余暇とセックスと死についての歌。正直言って、歌詞を覚えてない。僕の意見では出来損ないの歌詞だ。それにしても、さっきのはまったくいい質問だ。“基盤”ってのが気に入った。
LAUNCH:
アルバムの1曲目「Um」は、久しぶりに音楽活動を再開した今、新規巻き直しで一から出直すぞという告白なのでしょうか?
GARTSIDE:
えーと…歌詞を思い出せないな。ちょっと待って、何か面白いこと言ってるはずだから。
LAUNCH:
どうぞゆっくり考えてください。
GARTSIDE:
(30秒ほど考え込んで)うん、思い出してきた。たとえば“ガレンの谷にナイフを入れた”という一節がある。“ガレンの谷”というのは脳の一部だ。僕の親友の幼い息子は、実際にガレンの谷にナイフを入れた…僕がこの曲を書いているとき、脳腫瘍の手術でね。さらに面白いのは…、それで、僕はどうしたんだっけ?
LAUNCH:
「僕は切り取る、ベイビー、僕は閉じる」です。
GARTSIDE:
そうだ、僕がした確認作業のことを歌ってるんだ。そうそう、君の言う通り。そういう歌だよ。ほかの関心事にもふれていて、妙に自伝的だ。
キーボードの入り込む余地はない
お呼びじゃないのはわかってたよ
LAUNCH:
「The First Goodbye」は、アルバム中もっともストレートなポップソングですね。
GARTSIDE:
そうだね、バラード形式で詩を書いてみた。物語風になっていて、これも僕としては珍しい。自伝的だったり告白的だったりする歌はあまり好きじゃないけれど、ここでは実在する特定の場所や人間を取りあげている。“ガレンの谷”みたいな、何のことか誰にもわからないような事柄を扱うのに対して、明確な存在についての歌を書こうと、直感的に思ったんだ。それとバラード形式の実践を組み合わせた。バラードが好きなんだ。でも書くのは難しい。私的ではっきりしたもののことを書くのもね。
LAUNCH:
Miles Davisがあなたの「Perfect Way」をカヴァーしたときは、どんな気持ちでした?
GARTSIDE:
それはびっくりして舞い上がったよ。最初は彼からロンドンの自宅に電話が入って、一緒にやってくれないかと言われた。僕はそのときに「こういうバラードを書いてるんだけど、こっちへ来て一緒にやらない?」と言ったんだ。そうしたら本当に彼がやってきて、「Oh Patti」(『Provision』に収録)でプレイしてくれた。うれしかったのは、彼がたった1人でスタジオに現れたことだ。取り巻き連がぞろぞろついてくるんだろうと思っていたのに、スタジオにはDavidと僕とMilesだけ。彼はいかにもシャイな感じで、とても熱心にやってくれたよ。その後も何度か会ったし、電話ではしょっちゅう話をした。曲を書いてほしいと言われたけれど、そのころの僕は音楽業界にどうしようもない幻滅を感じていた。それで書かなかった。書きたいと思わなかったんだ。そのうちに彼は逝ってしまって。でも、彼に会えたのはすごく名誉なことだった。
LAUNCH:
ニューアルバムのプロデューサーにDavid Gamsonを選んだのは?
GARTSIDE:
Gamsonとは長いつきあいだ。といっても、僕がウェールズにこもり、彼はL.A.に行っちゃったので、何年も連絡がとだえていた。このレコードを作る気になって、デモを録音したのはいいけれど、誰にプロデュースしてもらえばいいのか、という問題が浮上した。誰の耳なら信じられるのか、全然わからなかったんだ。外部の人に頼んだ経験がないものだからね。「少なくともGamsonなら、調子っぱずれになってたら教えてくれるだろう」って思った。それで、レコードを作りたいので手伝ってくれないかと手紙を書いたら、彼はロンドンに飛んできてくれたよ。そこでデモを聴かせて、一緒にやろうってことになったんだ。正直なところ、彼との友情を取り戻すきっかけになっただけでも、このレコードを作ってよかったと思う。
LAUNCH:
以前のマテリアルではキーボードを重視していたあなたが、今回はなぜ“ノー・キーボード”の方針を取ったのですか?
GARTSIDE:
例のごとく、Davidのキーボードを録音するのにやたら時間がかかったからさ(笑)…ウソウソ。このアルバムを作る前の数年は、ヒップホップかアメリカのギター系バンドばかり聴いていた。そうするとキーボードはちっとも出てこないんだ。ヒップホップにあるのは、ストレートなビートとベースとサンプルだけ。ヒップホップには…少なくとも良質のヒップホップには、キーボードプレイヤーは存在しないし、最近の良質なロックバンドにもキーボードプレイヤーはいない、というのが僕の見解だ。それに“キーボードの虫”を締め出せば、ギターとベースとドラムスだけになる。使用楽器を限定すれば、さまざまなアイディアや影響力の一体化がたやすくなる。それぞれに異なるアイディアを持った4~5人の人間がスタジオで協力するとなると、その方が都合がいいんだ。キーボードの入り込む余地はない。敵のほうでも、お呼びじゃないのはわかってたよ。スタジオのドアに“禁煙マーク”みたいなのを貼っておいたんだ。わかる? 円の中に斜めの線を入れて、小さなキーボードの絵を描いたやつ。…というのはウソだけど、そうしてもよかったよね。
| 
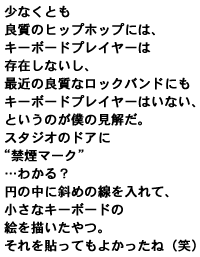 LAUNCH:
LAUNCH: