オルタナティヴが40歳を超えるとき
 |  |
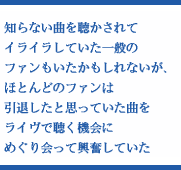 | オルタナティヴが40歳を超えるとき The Cureが12枚目のスタジオアルバム『Bloodflowers』のリリースを記念してハリウッドにあるパレスに登場した。この会場は、彼らがふだん演奏しているアリーナや大ホールの10分の1ほどの大きさである。めったにないライヴだけに、数少ないチケットを幸運にも入手できた熱心なキュアヘッズは大いに満足していた。 『Bloodflowers』は、1982年の『Pornography』と1989年の画期的な『Disintegration』に続く暗黒の終末3部作の最終作だと、the CureのリーダーRobert Smithは語っている(『Disintegration』は、ほかでもないSouth ParkのKyle Broslofskiが「史上最高のアルバム!」と言った強力作である)。 売上枚数という点で言うとthe Cureの最高到達点であることがまちがいない『Pornography』は、内容的には『Disintegration』と多くの共通点がある(後者からはトップ10ヒットとなった美しい“Love Song”が生まれたわけだが、この日『Disintegration』からは“Prayers For Rain”などのより無名な曲が取り上げられたので“Love Song”は当然演奏されなかった)。そして『Disintegration』の10年以上後に発表された最新作『Bloodflowers』とも『Pornography』は似ているのである。これは、the Cureの視点が一貫しているということなのだろうか。それとも、アイディアが枯渇したので、同じものを焼き直しているにすぎないのだろうか…(過去20年間にthe Cureがたびたび方針を変更したことはたしかである。たとえば『The Top』ではバッドトリップによるサイケデリックな世界に浸っていたのに、『Japanese Whispers』ではシンセサイザーでユーロディスコに手を出したり、と。しかし1985年の『The Head On The Door』以来、彼らはthe Cure独自のサウンドを純化する――そして、ときに組み替える――ことに専念している)。 The CureのリーダーRobert Smithをライヴで見て魅力あると思うかどうかは、もちろん、the Cureをそもそもどう思っているかによっている。Robertはステージ上でほとんど動かないし喋らない。まれに彼が観客になにかを言うときでも、もぞもぞして早口だし、それにアクセントもヘンなので、彼がなにを言っているか理解するのは不可能に近い。時々ぼそっと「サンキュー」という声が聞こえもするが、それでさえ控えめで早口なので、小さなクシャミとまちがいかねない。それにthe Cureは、ステージ上で派手に動き回らない点を、大がかりな照明効果で穴埋めしたがる傾向がある。彼らのライヴの照明は、たしかに曲のドラマ性や雰囲気を高めるのに貢献しているし、ライヴに欠かせない視覚的な要素となってもいる。しかし、しばしばバンドが暗闇やスモークから出て来ないので、口紅で斜めに線を引いたRobertの顔が歪んでいるところが、残念ながらファンにははっきり見えないのである。要するに、赤き血の流れる(というより花の血か?)ファンにとっては、なによりRobertがそこにいることが、演奏以上に意味があるのである。 The Cureが昔の曲を引っぱり出してくるたび、観客は耳をつんざくような喜びの奇声を上げた。たとえば、もはや古典と化していたミニマリズム風の“A Forest”(これは『Pornography』以前の曲のなかで、この日唯一演奏された曲だった)や、たった2曲だけ演奏されたシングルヒット、『Disintegration』の“Fascination Street”と『The Head On The Door』の“Inbetween Days”。『Kiss Me Kiss Me Kiss Me』の中東風エキゾチックなバラード“If Only Tonight We Could Sleep”が始まったときにも、客席は大いに沸いた。 とはいえ、the Cureが『Bloodflowers』の全9曲のうち7曲を演奏したときにも、観客はそれらを暖かく受け入れていた。なかでも評判がよかったのが、1stシングル“Maybe Someday”(今回のアルバムで最も美しく威光を放っていると言えるだろう)と、聴く者を圧倒する“Bloodflowers”(上で触れた“Watching Me Fall”が10分を超える頃、何人かの観客の忍耐力が試練に遭っていたことも事実だが)。 Robertはこれまで、もうすぐバンドは解散すると何回も人騒がせな発言をしてきた(現在もまた、これがthe Cureのラストアルバムだという噂が出回っている)。こんなことを言うのは陳腐かもしれないが、Robertが猫のような声で“Bloodflowers”の“These flowers will never die”というフレーズを歌ったとき、その歌詞は本来の内容を離れて、おそらくだれも意図していなかった別の意味を帯びて聞こえてきた。それは、the Cureはどういうかたちであれ、今後も生き残るだろうということだった。The Cureの歌の力が――古い曲も新しい曲も、ヒット曲も無名の曲も、ライヴの歌もCDの歌も――それを証明しているように聴こえたのだ。 by Lyndsey Parker |