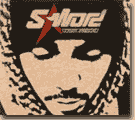↑ 
インタヴュー映像
S-WORDが語るそのままの魅力をお届けします。シングル2作のPVや本文中に語ってないことも収録! |
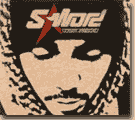
『ONE PIECE』
Def Jam Japan 2002年06月05日発売
UICJ-1004 3,059(tax in)
各曲/トラック・プロデューサー紹介
| M1: nightmare | MACKA-CHIN | | 吸い込まれるように始まるダークなサウンド。スクラッチで奏でるビートとS-WORDの声が微妙な怪しさを保って漂う。 |
| M2: カタパルトデッキ | MACKA-CHIN | | これぞ、MACKA-CHINというようなトラック。この曲でまさに、発射寸前、それとも既に発射? |
M3: Enter The ID.
□.□.□.□.□. | MACKA-CHIN | | ミドル・ビートに開放感のあるラップとそこに絶妙にぴったりはまるビートと小技の効いてるトラック。タイトルの四角には何が入るか…勘の鋭い人はお見通しだよね~?!?! |
| M4: マダマダ ―最善を尽くせ― | MACKA-CHIN | | 5月前半、モビルスーツを着たS-WORDジャケの限定アナログ盤で出されたこの曲。速いビートにがっちりはまったS-WORDらしいフロウ。フックの“マダマダいくぞ…”はリリックがユーモア。 |
| M5: EXTRA NEGOTIATION feat.XBS | D.O.I | | ふと~いビートでメインストリームらしい直球な曲。つい歌いたくなるようなサビもいい。 |
| M6: KROSS OVA'<斬> | DJ WATARAI |   デジタルのバウンシーなビートにのせたS-WORDのフロウが話題になったDef Jam Japanデビューシングル曲。 デジタルのバウンシーなビートにのせたS-WORDのフロウが話題になったDef Jam Japanデビューシングル曲。 |
| M7: IN THE ZONE | D.O.I | | トラックに対してS-WORDの倍速ラップが冴えわたるこの曲。バスケをネタですね~。 |
| M8: ULTIMATE RARE -価値上がれ- Feat.MACKA-CHIN & GORE-TEX | MURO | | こちらはニトロの2人がフィーチャリングされている曲。それぞれの個性的な声とリリックに注目デス! |
| M9: R.P.G pt2 ーBRING DA MUZiKー | DJ WATARAI | | こちらもWATARAI氏によるトラック。ウワモノがかな~り気になる感じです。 |
| M10: FOR MINUTES feat.DELI | YAKKO | | この曲は切ないメロにしっとりとした印象のトラック、子供の声のサンプリング…。息子へ向けた曲です。 |
| M11: eS-BReeSSO | MACKA-CHIN | | M12にいくためのとても濃~いインタールード。 |
| M12: THE ANSWER feat.CHRISTINA MILIAN | LOFEY |   歌姫ミリアンをフィーチャーしたメロウな曲。PVも必見です! 歌姫ミリアンをフィーチャーしたメロウな曲。PVも必見です! |
| M13: 090[Complete Ego mix] | NUMB, D.O.I.& S.W. | | 生のドラムで…と思うほどの迫力満点の打ち込み、ロック色の強い仕上がりです。 |
| M14: to the Next evo' | MACKA-CHIN | | 最後もMACKA-CHINでおわり。マダマダ深いところへ続くような…美しくもせつないトラックです。 | (文・編集部) | |
――ソロ・アルバムは、ニトロとして複数でやってる時とはまた違う感じでしたか?
S-WORD: 今までやりっ放しだった部分も、自分で最後ケツを拭かなきゃいけないというか…ボケたら突っ込んでくれる人がいる状態でラップをしてきたのに、今度はボケたら自分で突っ込まなきゃいけないという、その辺を一人何役もやらなきゃいけないのが…。 ノリとか衝動とか、自分のやりたいことの部分は今までと同じなんだけど、それを伝えるために必要な反対の自分を自分の中から出さなきゃいけない。それが思ったより楽しくもあり大変でもあり、だったな。
――それはソロ作品を作り始めてからわかったことですか?
S-WORD: どうだろうなぁ。それが好きなのかどうかはわかんないんだけど、一方向にガーっといくよりは、それに対して反論があったりぶつかったり、コミュニケーションがあったほうが幅が生まれるな、というのはニトロのアルバム通して学んでたから。ひとつの意見でまとまってるよりいろんな意見がごちゃまぜになってるのがおもしろいな、と思えるようにはなってきました。
――ニトロとソロとであえて変えようと思ったことはありましたか?
S-WORD: どちらかと言うと、あえて変えないでどこまでやれるか、ということを考えてました。今までのスタイルと今までのレコーディング方法で作ったものが、ソロとしてどれだけみんなに受け入れられるか。どれだけ自分のエゴどおりに物が作れるかというのを逆に意識したかもしれない。
――どうやらセールスをみると、それは通用してるっぼいですよね。
S-WORD: してるっぽいですよね(笑)。決してそれで勘違いはしてないんですけど。それはだぶんオレだけの力じゃないだろうし。ただ、オレは意識してメジャー寄りというか、耳に優しいものを作った気もないし、今までどおりのやり方で自分の好きなノリが伝わればいいな、くらいで作ってたんですよ。それがセールスという結果で出ちゃった。そうなると、ある程度の遊び心は許してもらえる時代になったのかな、とは思いますね。決して今オレがこのスタイルをやったから売れたってわけでもないだろうし。だったら、このままでいいのならこのままでいきたい。オレとかニトロはやりたいことしかできないから、それが受け入れられるのが一番幸せなんです。
――シングル「Kross Ova' <斬>」を最初に聴いた時は、今までのニトロのトラックと違って、デジタル感の強い、アメリカのメインストリームっぽい感じが意外でした。
S-WORD: でも、シングルの印象でアルバムを聴くと罠にハマるような気がするんですけどね。シングルはちょっと大袈裟に、派手目に作ってあるんで、モロ向こうのメインストリームを感じたりすると思うんですけど、アルバムにそれを期待してると…。
――そうなんですよね。実際、アルバムでもネタ感の強いMACKA-CHINのトラックが…。
S-WORD: 相当多かったりね。自分でもMACKA-CHINとやってるS-WORDが、一番S-WORDっぽいのかなって思う位だから。1stアルバムは彼のトラックが核になると最初から思ってたし。シングルでは「Kross Ova' <斬>」みたいなメインストリームものから「The Answer」みたいなメロウなものまで見せておいて、その両極端の間をアルバムで見せる、と。結局、アルバムを通して聴いてもらった感触がオレの伝えたいことなんですよ。で、できればアルバムをより多くの人に聴いてもらいたい。シングルはそのための罠という感じですね。逆に言えば、シングルの印象でアルバムを聴いて、受け入れられなかったら受け入れられなくてもいいし。
――トラックメイカーはどういった感じで選んでいったんですか?
S-WORD: LOFEY(USプロデューサーで「The Answer」を手掛けた)以外、今までS-WORDがラップしてお世話になってきた人、もしくはこの人達がいなかったらS-WORDはあり得なかったという人ばっかりです。プロデューサーを含めてのS-WORDなんだよっていうのをアルバムで言いたかったから。
――具体的にこういうトラックが欲しいとかの要求は?
S-WORD: ほとんど言ってない。持ってきてもらった時点で、オレっぽいというか、そのトラックの上でラップしてるオレが簡単に想像できるようなトラックばっかりだったんで。「これできるよね?」「あ、できます」みたいな。その辺りも気心が知れててよかったなって思います。
――ドラマティックなトラックが多いですよね。それはS-WORDが求めたのか、それとも自然とみんながS-WORD像というのを意識してそう作ったのか…。
S-WORD: そこはわかんないですけどね。普段から付き合っていて、あえてその曲の為にコミュニケーションをとらなくてもいい人たちなんで。だから説明しないでもオレのやりたいものが理解されてるんだなって思って、そこは愛情を感じました。
――それにしてもMACKA-CHINの仕事ぶりはヤバいですね。
S-WORD: ヤバいですね。彼も自分のアルバム(『CHIN ATTACK』)が出た直後だったし、すごく脂の乗り切ったところをもらえました。ほんと、タイミングよかったなって思いますよ。俺一人の成長じゃここまで作りあげられなかったし、逆にやっとオレが追いついたかな、というぐらいで。
――確かに、S-WORD氏自身も含めて、いま乗ってる人たちがちょうどいいタイミングで集まった感じがしますよ。
S-WORD: ほんと、運だけはいいなっていう(笑)。
――いや、運だけじゃないでしょう。
S-WORD: とは思うんですけど(笑)。でも一番光ってるところは運だなって、一応そう言っときたい。
――あと、前から思ってたんですけど、S-WORD氏の声ってトラックにすっぽり収まるような声ですよね。
S-WORD: それは自分で意識してる部分でもあるんですけど、でもラップし始めた時から、もしかしたら俺の見えないところでD.O.I.君(エンジニア)がコントロールしてたのかも知れない。この声質だとトラックの真ん中に持ってこれるよね、みたいに。高くもないし低くもない、という声なんで、ちょうど上の音と下の音の間に収まるというか。確かに自分でも、音に包まれるながらラップするのが一番やりやすい感じはする。
――この表現が適切か分からないですけど、ロックとかのヴォーカルに近いのかなって思うんですよ。NUMBとやってる曲「090」とかも相性いいし。
S-WORD: 確かに自分でアルバム作ってみて、ドラム・ループのみに乗ってるラップよりかは、いろんな音に包まれてラップしてるほうが自分でもグッとくる感じはありましたね。
――ドラマティックなトラックが多いのも、多分プロデューサーの人達がそういうことを感じていたからなんでしょうね。
S-WORD: 煽ってくる音もいっぱい入ってるしね。たぶん、ああいう音は全部、オレが酔えるために入ってる音です(笑)。自分が一番酔える状態になるにはそんだけ音が必要なんだなって思いました。いろいろ伝えたい情景がいっぱいあるというか……欲張りな奴だなぁって自分でも思います。
――歌詞やタイトルにSFやアニメっぽい感じがあったりとか、その辺も面白いですよね。
S-WORD: 個人的な好みなんですけど、メカとか新しモノ好きだったりするんで、そこらへんは要所要所に。ジャパニメーションは世界に誇れる文化だし、自分もアニメを見て育った部分があるし、それは自然に入ってきますよね。ああいう想像力ってすごいじゃないですか? フィクションなのにそこまで考えられる人間の脳みそって凄いなって。勿論リアルは追求してるんだけど、そのくらいの遊びはいいかな…というか、逆にその方が伝わりやすい部分もあると思うから。
――全体的に、サイバーでどこか冷めた部分もありますよね。
S-WORD: そういう年代なのかな。生まれたときから普通に高層ビルもあったし、メカニックな未来が想像されていた時代だし。自分では意図しないうちに、脳の中にそういう記憶が入っていったんでしょう。
――東京生まれですか?
S-WORD: 東京生まれです。
――その辺りとやっぱり関係してるんですかね?
S-WORD: 基本的に土がないところで育ってるんで……最近地方とか回ったりして、やっとそれが普通じゃないんだって気づいたんですけど。かなり狂った場所、というか、生き物としては自然じゃないところで育ったとは思いますね。逆に俺自身は土臭いものを求めてるんだけど、自分の中から出てくるものはどうしてもサイバーな感じになってしまうのかもしれない。それはどうしても出てしまうし、そういうふうに形成された人間なんで、それを否定してもしょうがないですから。
――最後にあえて訊きますが、このアルバムで一番伝えたかったことはなんだったのでしょう?
S-WORD: ヒップホップはアメリカで生まれた音楽だけど、東京で普通に生まれ育って、こういうスタイルで好き勝手に生きてる人間がいるっていうのを少しでも知ってもらえればな、と。リリックとかは瞬間の衝動で書いてるんで、間違いもあるし、5秒後に間違いって気づいても、もう言っちゃってることはしょうがない。むしろそのノリさえ伝わればいいし、聴いて身体が動けばそれでいい、というぐらいなんですよ。それよりも、あっ、こういうヤツがいるんだ、というのを知ってほしい。もしくは、プロデューサーとかゲストとか、こういう周りの人間がいた上で、S-WORDというのがいる、というのを知ってもらえればいいかなって……そんくらいです、ハイ(笑)。
さて、最後にひとつ、蛇足ながら付け加えておこう。インタヴュー中に気づいたことだが、彼はこちらの質問に答える際、「S-WORDという存在は……」とか「……という気持ちがその時にあったのかも知れない」というように、妙に客観的というか、第三者的な視点で自らを語っている瞬間が多い(原稿はこちらで手を加えているからわかりにくいかも知れないが…)。それを聞きながら僕は直感的に、これはポップ・スターにありがちな、あるキャラクターを演じていることからくる話法と少し違うのではないかと感じていた。
彼、そしてニトロというチームのキャラクターからして、彼は実際細かな計算をして作品を作るタイプではないと思う。彼自身が認めるように、「ノリや衝動を重視する」というのは本当だろう。あくまで彼は、アーティストとしてエゴイスティックなのだろうし、僕もそれでいいと思う。けれど、こうして僕のようなインタヴュアーに対して語る段になると、彼は自分や自作について饒舌に語ることができる。しかし、その時の彼とレコーディング時の彼は、ある意味本当に別人なので、故に彼の発言は第三者的になるのではないか。
これは、プロフェッショナルとして──特にインタヴューがプロモーションの中に組み込まれている現在の音楽シーンの中で──絶対にあった方が得な技能である。いや、営利的な目的だけではない。言葉で語り得ぬ衝動と、言葉でしか成立しないコミュニケーション(言葉を使わないコミュニケーションも可能だが、しかしそれは恐ろしく効率が悪い)は、本来相容れないものでありながら、しかしラップにおいてはその両立が不可欠となる。つまり、優れたラッパーに必要なのは、クレヴァーさだ。S-WORDはそれを持っているし、それこそが彼の作品のひんやりとした感触の源だと思う。取材/文●古川 耕(2002年5月) | |