濃密感と開放感を折り重ねた2時間…総てを昇華させる舞台前の最期の瞬間!
 |  | |
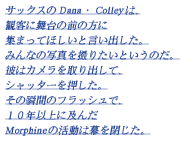 | 濃密感と開放感を折り重ねた2時間… 総てを昇華させる舞台前の最期の瞬間! MorphineのMark Sandman[シンガー/ベース]がイタリアのパレストリーナで公演中に心臓発作で亡くなったのは、去年の夏だった。その直前に完成していたグループ最後のスタジオ・アルバム『The Night』の2月リリースに合わせて、残った2人のメンバー(Dana Colley[サックス]とBilly Conway[ドラム])は先日、Orchestra Morphineという9人編成のアンサンブルを結成して東海岸で短いツアーを行うと発表した。 この「オーケストラ」のメンバーは、ColleyとConwayのほか、オリジナル・ドラマーだったJerome Deupreeや、その他のボストン周辺のミュージシャンたちだ。全員、古くからMorphineとつきあいがあり、なかには曲を共作した人物もいる。ColleyとConwayによると、このツアーはSandmanの生涯と音楽を追悼するもので、新曲をライヴで観客に届けるという彼の遺志を叶えるものだという。 たしかに2人の言うことは分かるのだが、ツアーが簡単なものでないことは目に見えていた。彼らがOrchestra MorphineでMorphineの遺産を換金しようとしているという見方は、公平でも正確でもない。ツアーを行ったからといって、アルバムが数百万枚売れるわけはないのだから。 この計画にたいして浮上した深刻な疑問は、むしろ次のようなことだった:DanaとBillyは、Morphineが終わったことを認めたくないだけではないのか。Morphineの美しさは、3人という最小限の編成に拠るところが大きく、そしてブルースの味わいがあるSandman独特の歌声から切り離せないはずなのに、大編成のバンドで複数のシンガーを起用するなんてどういうつもりなのか。そして、もしそれが音楽的にはうまくいったとしても、亡き仲間をそんなふうに追悼しようとしたら、ベトベトの感傷というあの危険な領域を回避できないのではないのか。 Orchestra Morphineの演奏が始まって3分も経たないうちに、そんな懸念は不要だったことが明らかになった。2時間近くに及んだこの日のコンサートは、気持ちのはじけ度合い、音楽の上昇感、頭を揺らせるグルーヴ感などの点で十分注目に値するものだった。 全11曲の『The Night』から10曲を取り上げたほか、Sandmanの古い作品も数曲演奏。9人のミュージシャンは、最初から最後まで涙など見せなかった。彼らは結構ガンガン演奏していたが、それは一方的というわけでなく、純粋に楽しんで曲目に取り組んでいた。もしMarkが見ていたら、この日のコンサートを誇りに思ったにちがいない。 前座のHubはすこし気になるバンドで、Chris Isaalをカッコよくしたような、雰囲気のあるバラードを歌っていた。彼らの演奏が30分あって、ColleyとConwayが2人きりで舞台に登場した。2人のまどろむようなビートで、1993年『Cure For Pain』から「Letユs Take A Trip Together」が始まった。 Colleyはまずバリトン・サックスで重厚なイントロを吹いて、歌に入ろうとマイクに近づいた。彼が口を開いた瞬間は、まるで幽霊が現れたようだった。彼は、Sandmanのヴォーカルそっくりの抑揚で歌いだしたのだ。それは、Sandman本人が別の姿で生き返ったかのようだった。 …考えてみると、それはたいして驚くことではないのかもしれない。だれかと長いあいだ音楽をやっていれば、いろいろな癖くらい覚えるだろう。しかし観客は彼の歌声にびっくりしたようで、ざわめいていた客席は一気に静まった。 そしてColleyは、残りのメンバーを舞台に上げた。その後の約90分間は、タイトでありながらルースな、あの賑やかな演奏に彩られた。この種の演奏は、一流の音楽仲間が長く付き合っていないと成立しないものだ。Conwayとデュプリーは、通常のドラム・キットと一風変わったパーカッションのセットアップのあいだを交替で行ったり来たりしていた。彼らの8本の手足はグルーヴ製造マシーンと化していた。 濃密感と開放感が交互に現れる曲目を支えたのは、Mike Rivard[ベース]とEvan Harriman[キーボード]のハーモニー感覚だった。それは、Sandmanのトレードマークだったスライド・ベースと、同一ではないが、それに匹敵するものだった。Laurie SargentとChristian McNeil[ともにシンガー]は、Colleyに迫る勢いでSandmanの領域を守っていた。Hypnosonics(数あるMarkの別活動のひとつ)には、男が女を「でかいケツ」ゆえに敬っていた時代を懐かしむ曲があるが、色っぽい声でその曲を歌っていたのがサージェントだ。彼女は、特別大きな拍手を受けていた。 なにより良かったのはホーン隊だ。Colleyのほか、Tom Halter[トランペット/トロンボーン]とRuss Gershon[サックス]。この3人がタンデムで演奏すると、内臓に響くざっくりしたラッパの音の壁が現れた。だれかがソロに入ると、それは血管のように脈打つメロディーのなかにすっと吸収された。 アラブ風の「Rope On Fire」のイントロでは、Gershonがソプラノ・サックスでヘビ使いの笛みたいなメロディーを吹き始め、他のメンバーはそれに合わせて手拍子を取っていた。「Top Floor, Bottom Buzzer」では、Halterな泣きのメロディーが鳴り響いた。Colleyは「I'm Yours, You're Mine」で巨大なベース・サックスと格闘したかと思うと、「A Good Woman Is Hard To Find」でテナー・サックスとバリトン・サックスを同時に演奏してみせた。後者のエンディングのソロは、喘息持ちの霧笛のように唸っては咳込んだ。何人かの観客がそれに歓声を上げた。 この夜のステージの喋りは、ほとんどColleyが行った。彼は人柄のいいMCだった。「All Wrong」の演奏中、彼は舞台の端に歩いて来た。最前列の客が、この日来られなかった地元の仲間のために、携帯電話を持ち上げて演奏を聴かせていたのだ。Colleyはそれを会場全体に知らせると、その客と二言、三言話をし、電話を掴んでモニターの真正面にどんと置いた。ワン・コーラス半のあいだ、電話はそこに置かれたままだった。そしてColleyは、大きく笑いながら電話を客席に放り返した。 しかし、いちばん暖かい瞬間は最後に残っていた。最後の曲は、1992年Morphineのデビュー盤『Good』から「You Look Like Rain」。その曲は、バンドと観客の大合唱となった。そして演奏が終わると、ColleyとConwayを残してバンドのメンバー7人が舞台からはけた。ちょうどコンサートの開始と同じ状態になったわけだ。 Colleyは、ツアーの最後の夜に来てくれたみんなに感謝の言葉を述べると、観客全員に舞台の前の方に集まってほしいと言い出した。みんなの写真を撮りたいというのだ。観客は喜んで彼の提案に従った。Colleyはカメラを取り出して、シャッターを押した。その瞬間のフラッシュで、10年以上に及んだMorphineの活動は幕を閉じた。 いや、ちょっと待てよ。Morphineの活動は去年の7月3日で終わったのだ、それはどうやっても回復不可能だ、という考えもあるだろう。たしかに、ある意味ではその通りだ。けれど、霧雨が降る3月の夜にバワリー・ボールルームに立って、故人への愛がはっきり伝わってくる素晴らしい演奏を聴いていると、この夜のオーケストラの精神がMorphineと連続していて、同じものを目指していることは明らかだった。 もしSandmanがいたら、このコンサートをやってくれと言ったはずだとColleyとConwayは考えたのだろう。それはよく理解できたし納得もできた。それに、もしMark Sandmanが生きていたとしても、私たちはいずれにせよこの日のバンドと似たツアー・メンバーを目にしていたのではないか、と考えることもできる。 そもそも『The Night』はMorphineのアルバムのなかでいちばんの野心作で、それ以前のどの作品と比べてもゲストが増えていて、楽器編成も複雑になっていた。このアルバムの曲をきちんと演奏するには、まあどっちみち、オーケストラが必要だったのかもしれない。もちろん、そんなことを考えていても最終的な答えなど存在しない。そのことがまた、いろいろな考えに駆り立てるのだが。 この日のコンサートのようにはっきり感傷を拒絶しながらも、私はなお、過去を回想する誘惑から逃れることができないようだ。ここで私は個人的な関心を告白しなくてはならない。ボストンで育った私は、90年代初期にMorphineの人気が出始めた頃、彼らが出ていたのと同じいくつかのクラブに出演していた有象無象のバンドのひとつに属していた。私はマークやDanaやジェローム(や、後にはBilly)と個人的に知り合いだったわけではないが、彼らの演奏はしょっちゅう見ていた。 ちょうど『Cure For Pain』が出た日の深夜、ケンモア・スクエアにあるストロベリーズ・レコード店で25人ほどの客といっしょに彼らの演奏を見たことを、私は一生忘れないだろう。マークはタクシー無線のマイクに向かって歌い、Danaはバワリーで見せたようにテナーとバリトンのサックスを同時に吹いてみんなをびっくりさせていた。当時私が知っていたボストンのミュージシャンは、どんな楽器をやっていても、どんなスタイルの音楽をやっていようと、全員Morphineには一目置いていた。 彼らがつかんだ成功は(成功といってもああいうふうだったのだが)まさに実力通りだった。彼らはいい曲をたくさん書いたし、素晴らしい演奏を行った。彼らの音は他の誰にも似ていなかったし、彼らはけっして音楽業界の公式に乗っからなかった。一言で言えば、彼らはあらゆる面で私たちの代表訴訟を行っていたのだ。 Mark Sandmanの友人たちが彼の音楽をこんなふうに一度きり舞台に甦らせたことにたいして、私はどう言って感謝すればいいのだろう。Danaが最後におやすみと言って観客が拍手していたとき、私は錯覚に陥っていた。私はふと、Markはただ舞台の袖で待っているだけで、いまにも彼が舞台に現れて、彼がたっぷりと浴びるべき拍手に包まれるのではないかと、本当にふと、そう思っていた。それが,私が彼らに言える最大の賛辞だと思う。 Mac Randall |