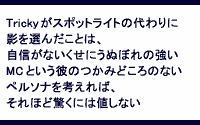| Trickyのアブストラクトなトリップホップにとって、アイデンティティを巡る政治性は、ギャングスタのストリート抗争の掟と同等のものだ。ライヴにおいてTrickyは自身の存在をほとんど無関係なものに変えることによって、この問題をもてあそんでいた。'97年1月9日にワシントンDCの9:30 Nightclubに出演した自称“雑種動物”は、3時間以上にわたるセットの大半の間、オーディエンスに背中を向け続けたのである。観客に顔を向けようと前に歩み出たときでさえ、Trickyの姿は見えにくいものだった。ステージの照明がずっと暗いままだったからだ。
Trickyがスポットライトの代わりに影を選んだことは、数カ国語に通じたスタイリストでありながら、自信がないくせにうぬぼれの強いMCでもあるという彼のつかみどころのないペルソナを考えれば、それほど驚くには値しない。実際に彼の自慢話は大きな反響を得ているにもかかわらず、すぐに女性の相棒であるMartineにマイクを渡してしまうのだ。
ライヴで見ると、いかにTrickyがヒップホッパーとDJミキサーによって設定された限界に拘束されているかが明白になる。こうした類いのアーティストたちは従来から、ステージよりもテープの上で真価を発揮するものなのだ。ギター、ドラムス、ベース、シンセというかなり伝統的な編成によるTrickyのバンドが、サウンドの問題を何とか克服してグルーヴを見いだし始めたのは、セットが始まってから30分も経ってからのことであった。その時点でもなお、目まいを起こすようなミックスをまとめ上げていたのは、Trickyのクールに脅迫するようなザラザラした声とMartineのか弱いが滑らかなヴォーカルだった。
「Christiansands」においてTrickyは“Forever, what does that mean?”という寒々とした呪文をまるでもうひとつのビートトラックのように投げかけ、そのフレーズが独自のリズムと迫力を出すようになるまで反復した。「Overcome」と「Makes Me Wanna Die」では、Martineが計算高い主人のTrickyに仕える傷ついたディーヴァを演じるところで、観客は沈黙に陥ってしまったのだ。
当夜のセットは2曲のヒップホップ賛歌で終了した。Eric B. & Rakimの「Lyric of Fury」とPublic Enemyの「Black Steel」における突き刺すような解釈の演奏には、本来ならば平静だったはずの観客に拳を突き上げさせ、Trickyが誘発するはずもない能天気な類いの笑顔をもたらす力があった。
だが、Trickyはそれでは終わらなかった。バンドはさらに1時間にわたって激しい集団即興演奏を繰り広げ、なぜTrickyがときとして“神がかり”と呼ばれるのかを例示して見せたのだ。観客の半分がすでに帰ってしまっていることも、彼は少しも気に留める様子はなかった。途中で彼は言った。
「今やってるのは全然くだらない演奏だ。だから残っていてもつまらないぜ」 By brett anderson/LAUNCH.com
|