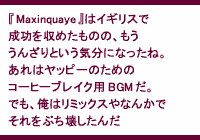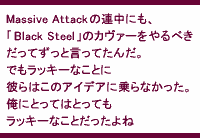| イングランドはブリストルにAdrian Thawsとして生まれたトリップホップのパイオニア、Trickyは、サイバースペース世代にとってのブリティッシュインヴェイジョンを自ら宣言しようという立場にいる。駆け出しのニューヨーカーになったTrickyは、ソーホーのナイトクラブ“Life”でDJをしたり、Bad Boy EntertainmentでNotorious B.I.G.の「Hypnotize」をリミックスしたりする間に、ロマンティックなドレッドをした新人ヴォーカリストのMartina Topley-Birdとチームを組んで、『Angels With Dirty Faces』を完成させた。『Pre-Millennium Tension』のタイトルからキャッチフレーズを作り上げた彼は、まもなく行なわれるライヴで新世代のためのギター中心のロックンロールの棺桶に最後の釘を打ち込んでしまうかもしれない。彼の影響はポップカルチャーのロールシャッハテストと言われるMadonnaの話題作『Ray Of Light』にさえ感じることができる。それではTrickyの内なるヴィジョンに耳を傾けてみよう。
――U2のアルバム『POP』をどう思いましたか? あなたの作品にかなりサウンドが似ているようですが。
TRICKY:
俺はかなり批判的なんだ、すべてがトレンド狙いのような気がしてね。タイトルを『POP』にしたのはキュートだと思う。だって本当にポップな作品だからね、そうだろ? それに「YMCA」を歌ってた連中のような格好をして出ていたビデオは、馬鹿にされないようにしながら馬鹿をやろうとしているみたいだ。まるでアルバムに対する言い訳のようなものさ。彼らがあれをマスコミの前でやって、“ほら、これはポップなアルバムだよ。自分たちの信頼性を高めようとして、若手のプロデューサーたちと仕事をしたら、ポップなアルバムに仕上がったんだ”とでも言っておくべきだったね。
でもアルバムのタイトルを『POP』に決めたとき、馬鹿をやってみようとしたんだろう。馬鹿にされるはずだったけど、実際はそうでもなかったのさ。俺はいつでも音楽で馬鹿をやっているから、その意味はわかっている。レコード会社に対してもずっと馬鹿をやってきたからね。でも彼らはそうじゃない。馬鹿をやっているふりをしながら、ビジネスをやっているだけなんだ。だから、たとえそのアルバムの中にこれまで聴いた中で最高の歌のひとつが収録されていたとしても、俺は批判的になってしまうんだ。彼らは俺に嘘をついているのだから、少しでも認めるわけにはいかないよ。それが俺の考え方なのさ。物事に対して常に真っ正直でありたいと思っているんだ。アーティストの本質と思える部分が不誠実だと感じたら、彼らの音楽を聴くのをやめてしまうのさ。ちょっとあまのじゃくかもしれないけど、そうせざるを得ないんだ。あまり良いことではないとわかっているけど、そうするしかないのさ。
――あなたの音楽的な革新性のおかげで、新たなPrinceと呼ぶ人もいます。Princeのアルバムで好きなものはありますか?
TRICKY:
そうだね、『Christopher Tracy』と『Her Parade』がいちばんよく聴いたルバムだ。でも曲としては「I Would Die 4 U」なんかだろうね。
――「When Doves Cry」のカヴァーをやったと聞いていますが?
TRICKY:
実際にはやらなかったのさ。DATには取り込んだけどね。結局は何にもできなかったよ。何故だかわからないけど、指の動きが何度も止まってしまったんだ。
――Wu-Tang ClanのRZAが地下室の浸水に遭ってビートを入れたテープを全部ダメにしてしまったそうです。もっと作るだけだと言ってますが。
TRICKY:
そんなふうに言えるなんて彼らしい自信家ぶりだよね。もし俺だったら、ガキのように泣きじゃくって、惨めな気分になるだろうな。RZAには変なオーラがあるからね。
――Tricky vs. The Gravediggazの曲「Tonite's A Special Nite」に取り組んだ感想はどうですか?
TRICKY:
深いね。俺らが最初に仕事をしたときには、それまで会ったこともなかったんだ。最初に会ったのがスタジオの中さ。そのころ彼はロンドンにいて1日中あちこち走り回ってインタヴューをこなしていたよ。だから泥のように疲れきっていて、一緒になったのは夜中の12時ごろで、4曲ほど仕上げたんだ。俺の友人のDobieがトラックを担当した。あまり口を利かない人だったけど、エネルギーがあったね。特別な存在だということは感じられたよ。
――RZAはあなたの音楽を聴いていると思いますか?
TRICKY:
もちろん、そう思うよ。でも彼は俺のことをよく知っている。彼が一緒に仕事をしたのは俺だけじゃないかな。特に俺のようなバックグラウンドを持っているミュージシャンではね。彼が心の狭いやつじゃないことはわかっている。あいつは何にでも耳を傾けている。
――私の仲間のライター達は、ときとして同業者の仕事を読んでいないように振る舞います。ミュージシャンもそんなすかした態度を取ったりしますか?
TRICKY:
確かにたまには俺に対してネガティヴな態度の連中に会うこともあるよ。誰かが俺に会いたいと言ってやって来たとするよね。それで俺のほうが最初にぞんざいな態度を取ったと考えて、俺にぞんざいな態度を示す連中もいるんだ。そんなふうに奇妙な感じのヴァイヴが漂うこともあるよ。あるアーティストが俺と仕事をしたいと言ってきたけど、俺はやりたくなかったので変な状況になってしまったことがあったね。それで彼は俺とつながりができたって周りに言い続けているんだ。だから俺はこの間“俺は一緒にやりたくないって彼に伝えてくれ”と人を介して頼んだのさ。彼を軽べつしているわけじゃないし、やってもよかったんだけど、時間がなかったんだよ。
――それはひょっとしてCourtney Loveのことですか? Holeのアルバム『Celebrity Skin』のためにセッションをしたそうですね。
TRICKY:
いや、俺が言っているのはRage Against The Machineのメンバーのことだよ。全然時間がとれなかったのさ。人間が他人に対処するのには奇妙な形もあるんだ。明らかに彼は俺と仕事をしたがっているのに、俺に対するリスペクトが全然感じられないんだよ。自分がリスペクトしていない人物とどうして一緒に仕事をしたいのか理解できなかったね。
だって見え透いているのさ。俺がロサンゼルスにいたとき、彼が俺の楽屋に現れたんだけど、俺のところを素通りしてスタッフと一緒に俺のスタッフのほうに話しかけたんだ。それで俺は楽屋を出た。だらだら過ごしても仕方ないから帰ったのさ。楽屋なんて暇つぶしの場所だから、ショウが終わったらすぐに帰ることにしてるんだよ。その時はレコード会社の連中との社交儀礼をやっていただけだったので、楽屋を離れたんだ。そしたら翌日、彼が会いたがっているっていう電話があったのさ。いったいどういうことなんだい? 俺のことを全然無視していたのに、会いたいなんてね。彼が俺に対して何のリスペクトも感じていないことは明らかだろ。どうして彼が俺と仕事をしたいのか理解できないよ。
――ではCourtney Loveの件はどうだったのですか?
TRICKY:
俺が彼女と一緒にやりたくないのは、2人がぶつかってしまうと思うからだよ。彼女は俺に自分のための音楽を作ってもらいたがるだろうから、絶対にぶつかるね。俺は最初から最後まで自分の手で仕上げたいほうなんだ。でも彼女は俺が作り上げたものをデモだと考えるかもしれないし、「これを作り直して」と言うかもしれない。そんなに寛容になれるほどぼくはまだ大物じゃないよ。そうなりたいと努力してるけどね。ミュージシャンと仕事をするときでも、彼らにハミングでベースラインを指示したりするのさ。ギターのパートにしても、誰か他の人間が俺の曲でプレイするのはまだ許容できないな。認めていいのはたぶん1人だけ、Patricia Valiantというギタリストだ。
おそらく俺が成長すれば、他の人たちと仕事ができるようになるだろうし、彼らに仕事をしてもらうことも可能になるだろう。でも今のところは無理だろうね。彼女には強力なパーソナリティがあったからこそ、現在の地位にまで到達できたんだと思う。強烈な個性が2人そろえば、競い合うようになってしまうんだ。それはやりたくなかったのさ。俺は彼女の音楽が好きだよ、例えばあの「I want my cake and eat it too」の歌だっけ? 違った、「I wanna be the girl with the most cake」だろ? あれはとっても素晴らしいソングライティングだ。とっても変な歌さ。それに俺はずっとKurt Cobainとも仕事をしたかったんだよ。
――『In Utero』と『Pre-MillenniumTension』は同じだと思いますか? 両者ともクリエイティヴなプロセスが、いわば神輿に飛び乗ってきたファンを切り捨てることにつながっていると思えるのですが。
TRICKY:
ファンだけじゃなくて、人々の俺に対する認識の仕方についてもね。あまりたくさんのことに巻き込まれたくないんだ。たとえば『Maxinquaye』について言えば、もう二度とあんなアルバムは作れないだろう。俺は15歳のころからブレイクビートに取り組んできたし、15歳からブレイクビートに乗せてラップをやってきてたのさ。それで残念なことにアルバムを作るようになるまでには、すでに次の段階に移っていたんだよ。だから『Maxinquaye』を作ったときには、ラップみたいなものからは離れていた。ヴォーカリストと組んで次のことをやり始めていたんだ。つまり音楽をどこか別の地点へ持っていこうとすることで、ある種の前進ができると考えたのさ。たとえそれがヒップホップとは違うものになったとしてもね。『Maxinquaye』はブルースだと思うな。苦悶する音楽なんだよ。
――私は『Maxinquaye』はヒップホップだと思いますよ。
TRICKY:
確かにヒップホップだと思うけど、そうは言いたくないんだ。だって誰かが「これはくだらないヒップホップなんかじゃない」って言うだろうからね。でも俺もあれはヒップホップだと考えているよ。ときどき俺は聴衆のことを観察していて、みんなのことが大好きなんだけど、あのアルバムを作るまでに俺は苦しみ抜いたから、苦しみを経験した人に俺の音楽を聴いてほしいんだ。それで俺はあんなふうにポップな部分を膨らませてみようと思ったのさ。イギリスのポップス界で成功を収めたものの、もううんざりという気分になったね。あれはヤッピーのためのコーヒーブレイク用BGMだよ。でも俺はリミックスやなんかの方法でそれをぶち壊した。つまり自分のペルソナで非常に迅速にそれを破壊して見せたのさ。俺の存在を当たり前の考えていて、もう1枚の『Maxinquaye』を早く聴きたいと思っているだけの人々に捕らわれるのは嫌だったんだ。くたばっちまえ!
――亡くなったハイチ出身のアーティストJean-Michel Basquiatのことをどう思いますか?
TRICKY:
本当のところ俺は彼の作品を見始めたばかりなんだ。彼の作品はワイルドで、特に絵画はいわば……直裁的なものなのさ。生前に評価を得られなかったのは明らかだよ。美術界はヨーロッパ側に偏っているからね。俺は彼についてはあまり多くを知らないけれど、彼の絵画やエネルギーを感じることはできる。彼は黒人社会のニューエイジだったのさ。ゲットー出身の進んだブラックキッドといったところだね。世間は彼を奇人変人扱いしたけど、実際は奇人でも変人でもなくて、進んでいただけなんだ。別のレベルに到達していたのさ。
――あなたはイングランドのブリストル育ちですが、好きなBeatlesのアルバムはありますか?
TRICKY:
Beatlesは聴いたこともなかったよ。みんな俺が聴いていたと思ってるけどね。Beatles、Stones、David Bowieなんかもちろん、そうした類いの音楽は全然聴いたことがなかったのさ。俺が聴いてたのはSpecialsとラップ、それだけなんだ。その後はPrinceにはまったけど、それはたまたまそうなっただけでね。俺は白人ゲットーの出身で、うちは唯一の黒人家族だった。とってもひどい地域だったよ。ブルックリンみたいだけど、多いのは白人の少年で、ある種ヘルズキッチンのようなところさ。学校に行ってたころからの友人は、アジア人、黒人、白人、イタリア人、アイルランド人なんかだよ。その後で黒人のコミュニティへと移っていったんだけどね。
――しばらくの間あなたはBjorkとデートしていたそうですが?
TRICKY:
もう音楽業界の人間とは誰とも付き合わないだろうな。俺とは全く違う分野から登場した人か、地球上の全然違う場所に住んでいるか、目立たない生活をしている人でないかぎりね。だってツアーに出るとBjorkのTシャツを着た連中がいるんだもの。それで俺のところにやってきては「Bjorkとデートしているのか?」って聞くんだ。会ったこともないガキがだよ。
正直に話せば俺と彼女の関係は、俺が彼女を適切に扱わなかったということに尽きるね。俺は1人の女の子を見つめ始めると、彼女に対して完全に正直でいなければ気が済まないし、「ほら2人の関係はこの通りの状況なんだから、これ以上先のことは考えないようにしようよ」なんて言ってしまうのさ。俺は旅に出ていることが多いし、ハッパもいっぱい吸うから、もし明日電話すると言ったとしても、忘れてしまうんだ。別にないがしろしてるわけじゃないんだけどね。数年前までは誰かとf**kしたとしても、先の約束なんかしなかったし、二度と電話することもなかったよ。今では多少は年齢を気にするようになって、もうそんなひどいことはできないけどね。だから今の俺は腹の底から真っ正直だけど、Bjorkと付き合ってることはそうじゃなかった。彼女と会うべきだと思われたときにも、俺は出て行かなかったしね。ある意味じゃ彼女は俺の行動から多少は影響を受けたんじゃないかな。
俺の友人のひとりがあれこれ推論して、「こんな状況になっているのは、彼女が君を嫌っているからだ」と言ってくれて、それで俺も目が覚めたよ。もう誰ともf**kしていない。誰かと仕事をしたら、それだけでお終いさ。彼らに音楽業界での友達になってほしいとも思わないよ。仲良しもほしくないし、ガールフレンドもいらない。牛肉も必要ないし、何にもいらないんだ。ただ単に自分の音楽を作りたいだけだね。俺たちはひとつの段階に突入しつつあるけど、それはもはや音楽とは何の関係もないことなのさ。Biggie Smallの死を信じられるかい? あれはくだらない映画だよ。俺たちは娯楽産業に従事しているんだ。お互いを楽しませるために働いているのさ。言葉を巡って殺されるなんて、俺にとってはへヴィなことだね。全くクレイジーだし、恐ろしいことだよ。
――ライヴで演奏した“ギャングスタラップ”についての歌は何なのですか?
TRICKY:
あれは「What You Call To Talk About」という曲で、『Angels With Dirty Faces』からのナンバーだ。ヒップホップですらなくて、かなりロックな音楽だよ。ロックミュージックの世界にも銃とかくだらないことをしゃべくるバッドボーイズがたくさんいるだろ。だからあれはバッドボーイもの風に作ったのさ。音楽とは全く関係のないことだと思うけどね。バッドボーイでいるかミュージシャンになるかの選択をしなくちゃいけないと思うんだ。だって1日の時間は限られているんだから、何をやるにしろうまくやらなくちゃね。2つのことを一遍にうまくやるのは無理だと思うよ。何も失うものがない連中と対峙しなければならないからさ。ミュージシャンとして大金を稼いでいて、大邸宅でリッチな生活をしていれば、誰かと一緒に戦争に行きたいとは思わないだろう。だから遊びでやるにはちょっと危険なゲームだと思うな。'97年の状況はくだらない映画みたいだったよ。この間テレビでSnoop Doggy Doggを見たんだけど、ヤツはたくさんのセキュリティに取り囲まれていたぜ。
――Public Enemyをカヴァーした「Black Steel In The Hour Of Chaos」(『Maxinquaye』では「Black Steel」と改題)の制作過程について教えてください。
TRICKY:
原曲の音楽はまったく残さなかったよ。曲のほうを先に仕上げて、その上からMartinaがヴォーカルパートを載せたのさ。
――アルバム『Nearly God』におけるSlick Rickの「Children Story」についてはどうですか?
TRICKY:
チューンができるのを待たなければならなかった。「Children Story」を使うことは何年も前から計画していたんだ。“よし、これに「Children Story」を乗せるぞ”と言えるようなチューンが浮かぶだろうと思っていたのさ。「Black Steel」にしても何年も前からやりたいと思っていたよ。Massive Attackの連中にも“「Black Steel」のカヴァーをやるべきだ”ってずっと言ってたんだ。でもラッキーなことに彼らはこのアイデアには乗らなかった。俺にとってはとってもラッキーなことだったよね。
――“ギャングスタラップ”を巡る激論全般についてはどう思っていますか?
TRICKY:
Geto Boysは、確かにギャングスタラップだね。俺がGeto Boysを聴くと、銃やコカインに巻き込まれたくないって思うんだ。だって恐ろしいものだからね。それはポジティヴなことだと思うな。つまり若者たちは彼らの音楽を聴いて、「このアルバムはカッコいいよ。でも銃とかの話はくだらねえ。そんなものはいらないよ」と言うようなものさ。彼らの歌詞は強烈だからね。
――'97年はSnoop Doggy DoggとLollapaloozaのツアーに出られましたね。彼の『The Doggfather』からの曲「Freestyle Conversation」のサンプルで自分のセットを始めたのはどうしてでしょうか?
TRICKY:
俺の人生と彼の人生は全く違ったものだけど、完全に感じ取ることができる。誰でもそれは感じられるだろう(「Freestyle Conversation」のライミングを始める)。誰だってレコード会社や身の回りのくだらないことに打ち負かされることがあるだろう?「Makes Me Wanna Die」みたいにね。昔はあの歌が好きだったけど、今ではそうでもない。レコード会社に台無しにされてしまったからさ。俺らはあれをシングルにしようと決めたんだ。そこまではよかったけど、これまでの曲よりも予算をかけてビデオを作ろうみたいなことになってしまった。ラジオでプレイされるチャンスも多くなるだろうからね。それで連中は曲をプッシュして、プッシュしまくったのさ。それで俺はあの曲が好きではなくなったんだよ。それじゃ「Tricky Kid」はどうだった? 「Black Steel」はどうだった? この辺のレコードは全然プッシュしてくれなかったじゃないか。
――Island Recordsは「Christiansands」をプッシュしてくれましたか?
TRICKY:
全然だったよ。これまでの2倍の予算をビデオにつぎ込むって感じだったね。ビデオにお金をかけるのは好きじゃないんだ。だって結局のところ俺の取り分から予算が出ていくだけだからさ。あれは美しい曲だったけど、連中の扱いはひどいもんだった。
――『Maxinquaye』からの「Pumpkin」も同じような感触を持つドープなレコードでしたね。
TRICKY:
いいかい、俺にしてみれば、あれはもっとレコードを売っていたはずの曲なんだ。俺のお気に入りの曲のひとつさ。あれが今リリースされていたら、莫大なヒットになっていただろう。約4年後の今ならね。
――“天才”ということをどのようにとらえていますか?
TRICKY:
そうだね、人々が誰かのことを才能があるとか天才とか言うとき、ある意味で俺はそれに同意しないんだ。人は誰それは生まれついてのアーティストだとか、自分たちにはどうにもできない才能を与えられているなんていうのさ。でもそういうものは単に通り過ぎていくんだ。俺らを素通りして、紙の上に定着してしまう。俺は君と同じように物書きでもあるんだけど、芸術は紙の上やテープに残されていくのさ。そして本当のところ俺らはそれをコントロールできないんだ。だから自分の才能を無視しないよう、無駄話をしてないで、芸術が降りてくるのに任せる必要があるんだよ。とにかくストレートに自分の中を通過させなくちゃいけない。自分の才能を無視していると、ある朝目を覚ましたときには、何もなくなっているということになるのさ。
――Spice GirlsのMel B.と付き合っていたという噂は本当ですか?
TRICKY:
彼女たちがブレイクする前に2、3度飲みに連れて行ったことがあるよ。それでお互いのことが気に入ったんだと思う。彼女が否定するかもしれないから、付き合っていたというつもりはないけど、一緒に出歩いていたのは確かさ。それから俺らはツアーに出て、彼女は大ブームを起こしたというわけだよ。一度は俺らの道のりは交差したけれど、彼女は世界中を大忙しで飛び回るようになってしまった。それで2人が衝突するチャンスはなかったということさ。Brit Awardsに出席したときには、途中で彼女と一緒にクラブへ行ったけどね。ブリストルにいたころはヒップホップを聴きに出かけるなんてことはできない時代だったよ。
――Nine Inch Nailsのことはどう思いますか? あなたの音楽の一部と同じように、彼らもロックにサンプルを使っていますが。
TRICKY:
わからないな、俺は音楽よりもイメージのほうを見てきたからね。断言できる立場じゃないんだ。彼はそれほど怖いという印象は受けないよ。彼が怖いとされている要素は、俺には効力を持たないようだね。“動物みたいにf**kしたい”なんて、それでどうしたって? 俺らはみんな動物だし、たいていはf**kもするだろ! まるでオルタナティヴミュージックを巡る議論みたいさ。ヒップホップはどれくらいオルタナティヴか? もちろんオルタナティヴな音楽だよ。レゲエミュージックとヒップホップは非常にオルタナティヴな音楽だと思うよ。
――“ジャングル”や“トリップホップ”“アンビエント”“イルビエント”といったラベル付けについて、どのように対応していますか?
TRICKY:
ジャングルだとかオルタナティヴだとか、みんなは言うけどね。あれはブラックだ、これはブルースだとかさ。音楽を指さすような行為はなくなればいいと思うな。俺は明日にでも変われるし、何かにこだわるつもりもないよ。全く新しい時代が来ているのさ。白人の若者と黒人の若者に大きな差はなくなってきているよ。我々はもはや肌の色や人種、それに性別の壁も越えてしまっている。そんなものはもはや全然関係ないんだ。俺は女性の視点からたくさんの曲を書いて、Martinaがそれを歌っている。『Maxinquaye』においてさえ、自分の内側にある母性の存在を感じているのさ。
――The Celestine Prophecy(邦題「聖なる予言」)は、お読みになりましたか?
TRICKY:
あれはドープだと思ったね。“神”とか“宗教”とか“キリスト”とかいう言葉を聞くたびにうんざりするんだ。俺は自分が神を信じているかどうかわからないからさ。俺はエネルギーを信じている。それで“神”という言葉を見たときには、自問自答してしまうんだ。いや違う、“神”という言葉は単にエネルギーを表す言葉にすぎないってね。このことはほとんど真実だと思う。それは俺が目指しているところでもあるのさ。だって俺たちはみんな神であり、いわば俺もその境地にたどり着こうと努力しているんだ。俺は非常に意識的だったよ。さっきも女の子のことについて話したけど、ただ出かけていってf**kするなんてことはできないんだ。俺はそんなに暴力的じゃない。それに俺は良き父親になろうともしている。自分の意識を向上させようとしているのさ。そんな境地に到達できたら、俺は神になれるだろう。バッドボーイにならなくても、お金持ちでなくても、誰もがリスペクトを受けることができるんだ。もう何も必要としていないというレベルに達していれば、自分自身と折り合いをつけたということが言えるだろうね。それは確かにそう思うよ。
――あなたの音楽は暗すぎるという批評家がいます。どうして今おっしゃったようなスピリチュアルな要素でご自分の音楽にアプローチなさらないんですか?
TRICKY:
俺は今起こっていることについて話しているんだ。多くの人々にとって人生とはくだらない代物なのさ。だから現時点で話せるような良いことは何もないよ。だって俺はまだ充分な意識のレベルに到達していないからね。『Angels With Dirty Faces』を聴けば、意識的な歌詞がずっと多いと思う。その意識は極めて高いものだよ。『Pre-Millennium Tension』や『Maxinquaye』、それに『Nearly God』を作ったときには、俺は意識的ではなかった。自己満足に終わっていたのさ。スーパースターを演じていたし、自分はこうだああだとあれこれ考えていたね。つまり苦悶していたわけだよ。
今の俺は意識を高めつつある。Beatlesはストロベリーフィールズについて歌ったけど、俺が育ったところには苺畑なんてものはなかったよ。レンガのパターンが続くだけの刑務所みたいな光景で、誰もお金なんて持っていなかった。今の俺は世界中を旅して回ったし、あらゆる宗教的な背景を持ついろんな人たちと話もしたんだ。それで俺も少しは意識的になって、自分のやっていることを見つめようとしているのさ。誰も傷つけたくないから、音楽という形で表現しているわけだよ。それは苦悶する音楽だ。俺たちはみんな苦悶するし、誰でも苦悶とはどんなものか知っているんだ。 By Miles Marshall Lewis/LAUNCH.com |