飛んで火に入る…

Stone Temple Pilotsの悩み多きリードシンガー、Scott Weilandは、近年最も魅力あるロックスターのひとりだ。伝説を実践する彼は、ネイルケアとアイメイクを好み、常にトラブルにつきまとわれて、時には延々と姿を消し、更正施設か刑務所のどちらかに絶えず出入りしている。良い子ちゃんが揃いも揃った“ボーイバンド”全盛の昨今、これほどジャーナリスト受けする賑やかな人物は他にいるまい。 Weilandが一番最近の“お勤め”を果たしている間、バンドのメンバーは果敢にも楽観的に構え、新譜の『No.4』を発表して、シンガーが娑婆に復帰するのを待っていた。 '99年の終わり、Weilandの釈放を待機中のRobertとDeanのDeLeo兄弟とドラマーのEric Kretzが、LAUNCHのオフィスを訪れて、Weilandのいない日々を語ってくれた。 話題は、束の間の離別(バンドは別のシンガーを迎えてTalk Showという名前でレコーディングし、一方のWeilandはソロ作を発表している)に始まり、大ヒットしたデビュー作から『No.4』で見せたエレクトリックなスタイルへとStone Temple Pilotsが遂げた進化、そして彼らが関わったオフブロードウェイのグラムロック・ミュージカル『Hedwig And The Angry Inch』にまで至った。 |
LAUNCH:レコードのリリースが決まったのにシンガーが服役中となると、バンドの機能はどうなるんですか? ROBERT: ここ何ヶ月か、俺たちもそれを繰り返し自問してきたよ。Scottが出てくるまで延期するか、それとも今出してしまうか、決めるのは俺たちだからな。で、今、出した方がいいだろうと考えたんだ。理由のひとつは、Scottの奇行癖とでも言うべきか。あいつが次に何をしでかすか、これまでもなかなか読めずにきたんでね。だから、まずはレコードを出してしまおう、と。しかも、クリスマスの時期となれば、俺たちの近況報告にはもってこいのタイミングじゃないか。前作の『Tiny Music』でも、発売から1年経ってようやくツアーに出たんで、レコードの発売からツアーまでずいぶんと間があいてしまったんだけど、みんなが相変わらず俺たちの動向に興味を持ってくれていたのには驚かされた。今回もそれくらいの猶予があれば、あいつがイイ子にしてさえすれば2月か3月には出てこられるはずなんだ。ということは、夏までには次の予定…つまりはツアーの予定が立てられるだろう。 ERIC: ハタから見るほど大変なことじゃないんだよ。リリースに合わせたライヴがないっていう、それだけの違いさ。他は全て同じ。こうして取材を受けてても、2階ではScottが別の取材をやってる気がするくらいだ。あいつがブチ込まれる前に、俺たちはラスベガスでMiller Genuine Draftの“Blind Date”に出演して、その晩だったか翌朝だったかに、LAに向かった。行く先は群の裁判所。そこであいつの服役が決まったんだ。そのショウの時点で既に…というか、判決が出る2週間も前から、俺たちには何となくわかってたんだけどね。5度目の審判でも、あいつは相変わらず憮然とした態度でいたから。そして1年の服役が決まった時にはもう、「このレコードを出す気があるかどうか」を話し合ってあったんだ。常に民主的に事を進めてきたバンドだからさ。あいつは間違いなく、リリースを押していたよ。「だって、感情的にも歌詞的にも、これが今の俺の気持ちだから」って。あいつだけじゃなくて、俺たちだって曲に対する思いはいつまでも同じじゃないんだから、待つなんてバカげたことに思えてね。 DEAN: そんなに難しい話じゃないさ。むしろ、けっこう単純だ。大きな穴がポッカリあいている感じはするけれど、でも、そう大変なことじゃない。今の俺たちにできないのはただひとつ、ライヴだけ。レコードに関しては、今回もいつもと同じように取り組んでいる。厚顔無知なマスコミの猛攻にも耐えてるし。できないのはライヴのみ。レコードだって、Scottの全面協力が得られなければ出してない。あいつがもし、今はその時期じゃないと俺たちに言ってきていたら、確かに時期じゃないんだろうから、出していなかったはずだ。あいつは全面的にこのレコードに乗り気だよ。口を出すのもはばかられるような、自然なノリがあるじゃないか。すごくイイ感じだ。 LAUNCH:Scottにどんな判決が出るか、前もってわかっていたんですか。こうなることを予想していた、と? ROBERT: もちろん! もっと前からわかってたよ。最後にScottと会ったのは、あいつが身柄を拘束された裁判所で、その前の晩には俺たちはショウをやっていたんだ。さっきの“Blind Date”がそれだったんだけど、実に現実離れした48時間だったな。ステージをこなして、次の日には飛行機でLAに戻って裁判所に出頭し、連れられて行くあいつを見送ったんだから。何ともシュールな48時間だったよ。 DEAN: 俺は1年前には予想してた。俺たち誰も、あの判決にはショックを受けていない。それが下されたのが、13日の金曜日、裁判所の13階だったってのがスゴイだろ。あぁ、誰も驚かなかったよ。Scott本人だってそうさ。 LAUNCH:一連の問題は、新譜の制作にどう影響しましたか。曲そのものや、制作のスピードに影響は? そういった体験が、新譜のどんなところに表れていると思いますか? ROBERT: 一番大きいのはScottの歌詞だろうな。あいつの生き様で歩調が決まったっていうか、それで色合いが決まったといっていいくらいだから。歌詞は抽象的に書くのがあいつの流儀だったが、このレコードでは少しだけど明快になっている気がする。音楽面でも歌詞の面でも、そしてバンドとしても、今回のレコードで俺が一番気にかけていたのは、集中して的の絞れたレコードを作ることだったんだ。バンドの本質がきちんと集約されたレコードができるのは、4作目か5作目からだというのが、かねてからの俺の説なんだけど、今度のは1作目が少々と2作目が少々、それに3作目も合わせて、このバンドの本質を見事に総括したレコードだと思う。 ERIC: 色々と問題が出てきたのは、終盤に向かう頃になってからだった。だから、あいつの服役は、レコード制作には特に影響はなかったんだ。制作自体は、実のところ最初のレコード以来のスムーズさだったよ。それは単純に、『Tiny Music』からこっち、空き時間がたっぷりあって、バンドの仲間の何が特別なのか、とか、一緒に音楽を作る時のケミストリーとか、俺たちが揃うとバカバカしいほど簡単に音楽ができてしまうんだよな、とか、そんなことを改めて振り返ることができたからだろう。このレコードは、制作に時間こそかかっているけれども…そもそもは、2枚組でも別々でも、出し方はどうあれ2枚作ろうと思っていてね。この1枚目が完成した段階で、あと4~5曲残っていたから、それはScottが出てきてから、次のアルバムで聴いてもらうことになるかもしれない。 LAUNCH:Scottがソロ作をレコーディングし、あなた方はTalk ShowとしてScott抜きでレコーディングしていた、離ればなれの時期の話をしてもらえますか。何らかの影響があったに違いないとは思いますが、さらに力をつけて戻ってきたように思えます。離れて過ごしたあの体験には、セラピー効果があったんでしょうか。それぞれのプロジェクトについて、今、どう思いますか? ROBERT: おっしゃる通りだよ。実に癒されるものがあった。このバンドの1人ひとりの価値を、誰もが悟ったんだと思う。それぞれの提供すべきものを見つめ直したことになるんじゃないかな。いきなり別のシンガーとレコードを作ることになり、Talk ShowのレコードではDeanとEricと俺が、曲だけじゃなくて歌詞まで書いた。それ自体がセラピー効果を発揮したんだ。別々にやってみて、ケミストリーの何たるかがわかったんだろう。改めて顔を揃えた時、それをお互いに確認し合ったような気がする。互いを再認識するってやつさ。 ERIC: 俺たちがTalk Showをやって、Scottがソロを作ったことで、得たものは実に多かった。というのも、当時、バンドの内部がひどく険悪になっていてね。ロクに口もきかなかったんだ。喋るとしても、お互いに吐き捨てるような感じでさ。みんな違うことをやって、違う形で自己表現してみる必要があったんだと思う。俺たちにとっては、曲の歌詞を丸々提供するのも初めてだったし、他にも色々あって視野の広がる体験だった。プロデュースも自分たちでやったしね。ミュージシャンとプロデューサーの掛け持ちがいかに大変か、よくわかったよ。ScottはScottで、前々から色んなサウンドに耳を傾けていて、やってみたいことが色々あったらしい。あいつがああいうレコードを作ったことが俺も嬉しいし、本人もすごく満足している。ただ、Talk Showでのライヴは、Scottが一緒のショウとはケミストリーの面で比べ物にもならなかった。俺たちがロサンゼルスでやった時にあいつが観に来たんだけど、「へぇ…」って、それだけだったし、あいつがソロで別のミュージシャンを連れてツアーしていた時も、向こうから電話してきて「なんか変だよ。何かが違うんだ」って言ってたっけ。去年の今頃に顔を合わせた時は、みんな諸手を上げて歓迎し合って、口々に「友達としても兄弟としてもミュージシャンとしても、おまえらがたまらなく恋しかったよ。それから、おまえらがこのバンドにもたらしているものもな」と言ったもんだ。ヨリを戻すのは、だからけっこう簡単だった。 DEAN: カタルシスってやつさ。俺たちには、これが当たり前なんだ。俺に家でセーターでも編んでろっていうのか? 他に何をすればいいんだよ。これが俺の仕事。Scottが参加できなくたって、俺はレコードを作っていくぜ。 LAUNCH:バンドの成長についてですが、新作を聴くと、これまでの3枚のアルバムが断片的に聞こえてきます。作りたい音楽に変化はありましたか? ROBERT: こいつは1枚目から3枚目をひっくるめたレコードさ。ただし、小は大を兼ねる、の境地でやってるがね。最初のレコードというのは、世間に自分たちのやっていることを、しっかり消化して把握してもらうためのものだと思う。世の中への第一歩だが、赤ん坊の歩みの方が確かな場合だってある。あれはロックなレコードだった。2枚目もロックではあったけれど、ちょっと枝葉を広げている。3枚目は、よりオープンに…ボサノヴァやジャズ、ポップにまで手を広げようという試みだった。このバンドは、豊かな才能と影響で成り立っている。俺の受けてきた影響は、Scottのそれと全然違うし、Deanのもまた全然違う。それこそ偉大なバンドの条件さ。自分の尊敬するバンドを考えても、ついこのあいだ聴いたQueenのレコードなんか、4人の間にビックリするくらいの才能が溢れている。音楽に何かしらの、それも価値のある貢献ができたら最高だよな。俺たちはまだ修行中なんだろうけど。 DEAN: 俺たちはたぶん、人間的に成長したんだよ。人間としてマシになれば、演奏だってマシになるんだと思う。この1年半ぐらいの間に、俺は自分の楽器がすごくしっくりくるようになったんだ。誰だって同じことを繰り返したくはない。『Tiny Music』と比べて、このレコードは歌詞も音楽も実によく溶け合っていると思う。Scottがシラフの状態の時に必死になって取り組んでいたのが、よくわかるだろう。『Tiny Music』の当時の俺たちは、それこそバラバラだったけど、今回はちゃんと同じ世界に生きていたしね。実際のレコーディングの過程でも、アプローチが違っていたんだ。『Tiny Music』のレコーディングは普通の家で、実にローテクだった。部屋も音響を考えた造りじゃなかったし。今回のレコードのスタンスはハイテクで、LAでも最高とされるスタジオのひとつを使ったんだ。「Pruno」と「Church On Tuesday」は、Steely DanがいつもレコーディングしているVillageで録ったんだぜ。天井を見上げながら、(Donald)Faganが「Aja」を歌ってる姿を想像してみるのも、なかなかイイもんだったよ。 LAUNCH:このアルバムで、本来の活力を取り戻せた喜びはありましたか? ERIC: 『Tiny Music』と比べると、特にね。あの時はScottが自分のことで手一杯で、いないも同然だったし、完全形のバンドが完全形のアルバムを作るっていう体制では決してなくて、けっこうメチャメチャだったんだ。そこへいくと『No.4』は、曲作りで集まった初日に「Down」と「Church On Tuesday」ができてしまった。Scottが書いていた曲に俺たちがリフをつけていって、それでもう、1曲目はほとんど完成の状態だったんだ。あいつは歌詞も適当に書きとめていたよ。それから30分後には「Church On Tuesday」ができていたというくらい、すごいスピードで息つく間もなく進んでいった。 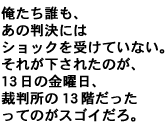 LAUNCH:評壇での扱いについてですが、自分たちと評論家との関係は、どういう状態にあると思いますか。4枚目のアルバムを出したことで、マスコミとの関係に変化は表れていますか? LAUNCH:評壇での扱いについてですが、自分たちと評論家との関係は、どういう状態にあると思いますか。4枚目のアルバムを出したことで、マスコミとの関係に変化は表れていますか?ROBERT: 確実にね。というか、当初から段々に変わってきてはいたんだよ。みんなそうだろう? もう何十年も前から続いていることさ。ちょっとした誤解や誤報は付き物だ。それもいつかは解決するものと思ってる。最近のインタヴューは、5年前とはずいぶん変わってきているよ。シーンも、ノリも違うからね。俺自身も、このバンドでの自分に前より自信が持てるようになった。それを自分で手に入れたってことだと思うよ。俺はついに手に入れたのさ。向こうは向こうで書かなきゃいけないことを書き、俺たちは俺たちで自己証明に努める。その結果、今はずっと自分に自信が持てるようになったんだ。 ERIC: 最初はどうにもくだらないのばっかりだったが、あれだけ批判されると、だんだん何も感じなくなって、どうでもよくなってくるんだよ。だからガードを張って、話したい相手とだけ話すことにすると、レコード会社は喋りたくない相手の取材も受けるようにと泣きついてくる。「変なことは言わないから大丈夫だ」って。ところが、『Tiny Music』を出して、それが前2作と比べて売れなかったってことになると、突如として評論家受けするようになって、マスコミにモテモテさ。ミュージシャン仲間からも好かれるようになる。今度はどうなるか、楽しみだよ。 DEAN: そんなもんだよ。最初の作品でとてつもない成功を収めた人は誰でも、それが何であれ、すぐ攻撃の的にされるんだ。さらし者さ。アーティストだろうが画家だろうが…まな板の鯉だ。俺が曲を書いてレコードを作るのは、私生活をさらけ出すためじゃないし、どんなジャンルを目指してるわけでもないのに、おかしな話だよな。バカバカしい。 LAUNCH:自分たちの受けてきた影響は、如実に表れていると思いますか? ROBERT: この取材の前に、ある人と話してたら、“Atlanta”でのScottのパフォーマンスに触れて、Morrison系の影響があると言われた。俺はそんなの、最初のレコードの時から気付いてたけどね。最初のレコードの裏ジャケットを見ると、ScottがMorrisonみたいなことをやってるだろ。あれはまるっきりJim Morrisonで、俺は反発したくなったけど、結局、世間が「これと似てる」とか「あれみたいだ」とか言い出すのは、その時々の時流によるんだと思う。同世代の連中と比べられて喜んでるやつは、俺たちの中にはいないはずだ。俺たちの方から与えられるものは、いくらでもあると思うけどね。これもやっぱり、音楽とは何かって話に戻っていくんじゃないのかな。音楽とは比較ではない。音楽そのものに美がある。だから美しいんだよ。 DEAN: 音楽的な影響の話だったら、ここで何時間でも喋ってられるよ。何でも聴いてるから。例えば、Bacharachの曲でも、Dusty Springfieldのとか、Carpentersのやったやつとか、アーティストによって解釈が違うのが面白い。俺はBacharach/Hal David作品の大ファンなんだ。Stan GetzとかOscar Peterson Trio、Barney Kesselも大好きで、Wes Montgomeryもたまらない。Edith Piafもよく聴くよ。半端じゃないだろ。俺の受けてきた影響だけで、何時間も話ができる。俺にとっては、人生の本当に大きな部分を占めているんだから。'68年当時、兄貴の部屋から鳴り響いてくるDoorsやThe BeatlesやHendrixを聴いて、少年だった俺の柔らかな脳味噌は、それをスポンジのように吸収していったんだ。 LAUNCH:『No.4』に収録の「MC5?」という曲は、あのデトロイトのバンドに呼びかける歌ですか? ROBERT: あの曲が、すごくMC5の曲に似てると思っただけさ。MC5は俺が尊敬してやまないバンドで、聴く度にいつも、今にも全てがバラバラになってしまいそうなところが、すごくいいんだよな。そこに美があるんだ。レコードを作る時は、積み重ねてあるレコードを引っくり返しては、インスピレーションを探すんだけど、MC5のレコードが出てきた時にも、何となくああいうMC5っぽいフィーリングを入れてみたいと思ってね。仮に付けていたタイトルをそのまま残したもので、Wayne KramerがScottのルームメイトだった関係から、直接許可が出たんだ。 LAUNCH:『Hedwig And The Angry Inch』に関わることになったいきさつは? ROBERT: 最初にあの芝居を観たのはScottで、Deanに何やら報告してたんだけど、数ヶ月前、ニューヨーク滞在中に俺たちも観て、すっかりブッ飛ばされてね。驚異的な芝居だよ。サウンドトラックはAtlantic Recordsから出てるから、レーベルメイトの関係ってわけ。なんか、知りもしない人と出会ってすぐに、ずっと前から知り合いだったような気分になることってあるだろ? Steven Traskという、あの一連の曲と歌詞を書いた人も、そういう人だった。John Cameron MitchellとMichael Cerverisもそう。『Hedwig』の脚本家だよ。参加して、本当に素晴らしい体験をさせてもらった。他人の曲を覚えるのは違和感があったけど、たぶんそれは、15歳の頃、ガレージでカヴァー曲を覚えて以来の経験だったからだろう。 ERIC: あんなに楽しいのは久し振りだったよ。人の書いた音楽で、しかも複雑な音楽だったから、やり甲斐も手応えもあった。演出には、俺たちが馴染んできたScottをフロントに据えた形とは違う、もっと色々な要素がたくさんあるからね。そんなわけで、全てはニューヨークであの芝居を観て素晴らしいと思ったところから始まったんだ。今、彼らはLAで芝居を拡張するために、いくつかのバンドのリハーサルをしている。向こうは前夜祭に出るバンドを探していて、俺たちはシンガーを探しているバンド…というわけで、話はあっという間に決まりさ。 LAUNCH:業界やレーベルから、以前より協力を得られるようになったと感じますか。今の音楽業界について思うことは? ROBERT: あぁ、それは感じるよ。もっとも、こうしてここにいること自体…そして求められているということ自体に、俺はある程度の驚きを感じてしまうんだ。今だに俺と話をして、このバンドの近況を知りたいという人がいるんだから、圧倒されちゃうよ。 DEAN: かなりえげつない業界だからな。相当えげつないし、今は特にそうだ。俺たちなんかは、最初のレコードを出した頃には業界もバンドを育てることに力を注いでいたから、まだ恵まれていたんだろう。レーベルにも、1枚のレコードからシングルを2枚、3枚と掘り下げる用意があった。でも、今ではそうはいかない。今のレーベルは、投資に対して莫大な見返りを期待して、1曲で結果を出そうとする。それでうまくいかないと壁に投げつけて、貼り付いて残らなければそれっきり。それが今の業界の現状だと思う。 LAUNCH:ステージ上での最高にクレイジーな出来事は? ROBERT: ある晩、はいていた靴の底が、部分的にはがれていたことがあって、後ろに下がった時にベースのコードがちょうどそこに挟まって、文字通り頭から1回転してしまったことがある。それでも俺は演奏を続けて、ひとつもビートを外さなかった。ベースを弾きながらバック転ができるとは知らなかったよ。前に転がってたら、ステージから落ちてたところだ。 DEAN: Gardenでのショウで、AerosmithのSteven TylerとJoe Perryがステージに上がって、2曲ぐらい一緒にやったことがあるんだけど、『Rocks』に入ってる「Lick And A Promise」のイントロの出だしで俺たちが入りそこねて、2節目の半ばで入って、危ないところで何とか追いついた。女装の2人と共演だぜ。なかなかの見物だったよ。 LAUNCH:あなた方の出身地についてプレスが混乱しているんですが、サンディエゴのバンドなんですか? それとも、LAのバンド? DEAN: 俺だけサンディエゴに住んでたからだよ。俺がインタヴューでサンディエゴに住んでるって答えたら、バンドがサンディエゴ出身っていう記事になっちまった。向こうのバンドはきっと、みんな苦虫を噛み潰してたに違いない。「あいつら、サンディエゴ出身じゃねぇぞ。LAの変人のくせして」って、変に気合が入っちまったってやつだろう。サンディエゴでも、クラブのオーナーたちからはすごく良くしてもらったんだぜ。俺たちを、どんどん出演させてくれてさ。当時、LAではなかなかクラブに出られない時期だったんだ。例の出演料を払って演奏するシステムで、時代錯誤な連中が横行してた頃だから、俺たちは毛色が違ってた。ちょうど、ピチピチのパンツにカウボーイブーツ、そして髪の毛はツンツン…って時代の終わり頃でね。どっちにしろ、俺たちはハマらないわけ。そんな中、Coconut TeaszerのAudrey Marpoolとか、Club Lingerieでも俺の幼馴染みが勤めてる関係で度々やらせてもらったりして、俺たちの周りには本当に親切な人たちも何人かいたんだ。うん、サンディエゴの人たちは、実にナイスだったよ。 LAUNCH:振り返って、このバンドの頂点だと思うのは? ROBERT: 皮肉を言うつもりは毛頭ないんだけど、このバンドはかなりの実績を残してきたと思う一方で、本当の実力を見てもらえたら…って気持ちもあるんだよね。何言ってんだと思われるだろうが、やっぱり自分には自分が一番厳しい批評家なんで、このバンドの本当の実力、つまり全員そろって100%発揮したらどれだけのことができるバンドなのか、それはまだ見てもらってないと思うんだ。今まで色々な人たちと共演したり、曲を書いたりする機会があって、そのたびに俺は圧倒されてきた。それで謙虚に構えるようになってね。 LAUNCH:Stone Temple Pilotsは、なぜ特別なんでしょうか? DEAN: Stone Temple Pilotsを差別化するのは、時代を問わない曲をいくつかちゃんと持っているという点だと思う。「Interstate Love Song」あたりの曲は、これからも長くラジオで流れていくだろう。育った環境が大きいんだろうな。Robertと俺は東海岸、EricとScottは西海岸と、育った場所はアメリカの両岸に分かれているのに、RobertとEricと俺の音楽の趣向といったら、ほとんどそっくりなんだから驚くよ。そして、そこにScottという存在が放り込まれたところに美しさがある。あいつが軍国主義のBlack Flagで過ごした、ハンティントンビーチでの日々が培ったものをね。 LAUNCH:ロックスターでなかったら、何をしていたと思いますか? ROBERT: 「ご一緒に、ポテトはいかがですか?」 DEAN: 俺には、これしかできないよ。やりたいことも、これしかない。レコードを作りたいとか、俳優としてキャリアを積んでいきたいっていう人間の場合、それこそが肝心なんだ。これっきり息ができなくなったって構わない、ってくらいでなきゃいけないのさ。 by dave_dimartino |