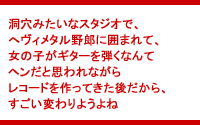| 「ここ数年、ギターにぞっこんなのよ」。バッファローにある自宅からの電話口で、Ani DiFrancoはそう言った。頑ななまでに独立独歩の道をゆくフォークシンガーであり、オルタナティヴミュージック界のスーパースターでもある彼女が、そのキャリアをスタートさせたのは11年前。バッファローのバーを会場に、Beatlesのカヴァーを大声で歌い上げ、攻撃的なリズムギターの奏法や人目を引くステージでの存在感で注目を集めていった。すでに13枚のアルバムと、何百本、何千本というショウを経てきた彼女のキャリアだが、その主役は叩きつけるような弾き方が印象的なアコースティックギターだった。
ところが4年ほど前から、DiFrancoはツアー要員として他のミュージシャンを雇い入れ、楽曲に膨らみを持たせ始める。今ではサイドマンを4人――それにサイドウーマン1人――を伴なって、ファンク、ヒップホップ、ストラットにロック、果ては少々のジャズやサーフギターまでステージに取り込んでいる。それはつまり、コンサートでもスタジオでもDiFranco本人の演奏が控え目になることを意味しているのだ。
「バンドが一緒だと、曲に空間が必要になるのよ」とはDiFrancoの解説だ。「最近、私が書いている音楽は前よりファンキーになっていて、だからアレンジも簡潔であまり密なものではない。ということは私のギターの居場所も少なくなるのよ。とはいってもギターは大好き。『Reckoning』のほうにアコースティックがあんなにふんだんに入ったのは、そのせいだと思うの」
DiFrancoの最新作『Revelling/Reckoning』は2枚組で、彼女のキャリアにおいて最強の作品のひとつと言える。“What How When Where(Why Who)”“Ain't That The Way”(共に『Revelling』収録)といったバンド総動員のファンキーでラジオ受けしそうな曲から、『Reckoning』収録の内省的なアコースティック曲まで、趣を変えていくアルバムだ。後者のうち“Grey”などは、DiFrancoが我々に提供してきた楽曲の中で最も繊細かつ瞑想的なものに数えられる。また、曲作りのわざ師たるJohnny Mercer、Sammy Cahnなどのスタンダードに通じる感触の、底知れずメロディアスなアコースティック曲も数多い。
「Jon Hassell(ジャズトランペッターで『R/R』にゲスト参加している)が最近、私の歌を褒めてくれて、スタンダードをいくつか録音してみるべきだって言われたんだけど、考えたら私はソングライターなんだから、スタンダードを歌うなら自分で書いてしまおうと思って」
「そう思ってすぐに書けてしまったわけじゃないのよ。そういう時代のことを私はよく知らないしね。ただ、美しい曲のためなら私は貪欲でしょ。それに私も、15年やってくる中で、初めの頃のような普通の曲の構成からはみ出したメロディ感覚を培ってしまっている。成長するにつれて、曲の組み立て方にしてもメロディのつながり方にしても、変ったものを模索するようになったから」
「もっとも、書いている時は直感に従ってるだけ」とAniは続ける。「音楽を勉強したわけじゃないから――楽譜も読めないし学理もちんぷんかんぷん――自分の直感を信じる以外、他にやりようがないのよ」
DiFrancoが1年がかりでまとめた『Revelling/Reckoning』は、自身のレコーディング施設であるDustbowlで作った初めてのレコードでもある。「要するに私の自宅なんだけどね。それでも、バンドのメンバーを個室に隔離するくらいの広さはあるのよ。ミキシングには24トラックのデジタルの卓があって――でも、昔の真空管アンプのほうが暖かみのある音になる気がするから、他にアナログの機材もたくさん置いてあるの」
「洞穴みたいな設計のスタジオで、へヴィメタ野郎に囲まれて、女の子がギターを弾くなんてヘンだと思われながらレコードを作ってきた後だから、すごい変わりようよね。真夜中に閃いて録音するのも勝手だし、私の好きな“バンド全員でライヴ”って録音も可能なの。それも、適当に原始的な環境でね。私も今までより自分を出せたわ。他人の時計に合わせてやってるわけじゃないから、実験するのも自由だし」
DiFrancoの話では、『Revelling/Reckoning』のベーシックトラックは、昨年、根を詰めた5日間のセッションを2度行なって録ったそうだ。一度はDustbowlで、そしてもう一度はオースティンのCongress Houseという彼女お気に入りの小さなスタジオで。「そしてテープを自宅に持ち帰って、あとは私がひとりでオーヴァーダブをしたり、新たにアコースティックのやつを録音したり」
彼女のアルバムがすべてそうであるように、『Revelling/Reckoning』もDiFrancoのRighteous Babeレーベルから発表される。徐々に中規模へと成長してきたこのインディペンデントレーベルには、Arto Lindsayの型破りブラジル音楽や、Tuba & Bassというニューオリンズのトリップホップデュオをはじめ、今や数多くのアーティストが名を連ねている。ただし、同レーベルの売上げ――現在300万強――の主だったところはDiFrancoのアルバムが稼いでいるのだ。大手レーベルも彼女への求愛をついに止めてしまった今――(「彼らにできるのは、うちの計算機に数字のゼロを増やすことだけ。なのにそれは、私には思いもよらないような、そして払うつもりもないような代償を伴なうことになるのよ」)――ラジオで流れることも滅多になければ、ビデオは計算式から消えたに等しい(制作費の問題と誰も放送してくれないという事実の両面から)という状況の中で、Aniはメインストリームにありながら自らの魂を損なう心配をあまりしなくていい立場を楽しみ、自分の現状に満足している。
では、世界制覇に向けたDiFrancoの次なる計画は? 「私はたいてい、新作がリリースになる前にもう次のレコードに取りかかっているの。だから、すでに次の作品に向けて曲を書き始めているんだけれど、もしかしたらまたライヴ盤になるかもしれない。バンドで作り変えたり形が変わったりした曲がたくさんあるから。私は今もライヴが身上。毎晩違うでしょ。たくさんあるレコードの中から曲を網羅しながら、新しいものと、作り変えられた古いものを混在させていくのが楽しいのよね。古い曲がつい昨日書いた曲みたいに響いてくるというゾクゾクするような瞬間もあって、それがたまらないの」
DiFrancoは数多いサイドプロジェクトでも忙しい。『Freedom Hightway』という、Woody Guthrieから今日に至るまでのプロテスト音楽を散りばめた映画のサウンドトラックに1曲提供しているほか、ベーシストのRob WassermanとWoodyの娘、Noraがプロデュースを手掛ける企画用に、Woody Guthrieの詩の一部に曲を付ける作業も進行中だ。また、かつてPrinceの名で知られていたアーティストとしてかつて知られていたアーティスト、ともお近づきになった。DiFrancoのレーベル、Righteous Babeを、新たなインディーズ事業の雛型として例に挙げていた紫の殿下は、自身の『Rare Un 2 The Joy Fantasitc』にDiFrancoを招いて歌とギターで参加させ、そのお礼にDiFrancoの『To The Teeth』にゲストとして顔を出している。さらには昨年、ソールドアウトになったミネアポリスでのショウの後で、紫の君はDiFrancoをPaisley Parkでのオールナイトジャムセッションにも招いた。そこで思いついた最後の質問:どちらのほうが背が高いんだろう? Aniか、それともPrinceか?
DiFrancoは大笑いしたが、出てきたのは模範回答だった。「その話はしないほうがいいんじゃないかな」。くすくす笑いながら彼女は言う。「私はもうずいぶん長いこと厚底ブーツをはいてるんで、実際よりも背の高い自分に慣れてしまっているのよ。ただ、これだけは言っておこうかしら……。私の厚底ブーツのほうが、彼の厚底ブーツより大きいのは確かよ」 |