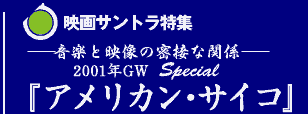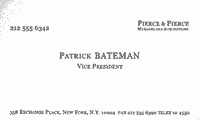『アメリカン・サイコ』

「アメリカン・サイコ」サウンド・トラック
VICP-61333 2,400(tax in)
2001年4月4日発売
1ユー・スピン・ミー・ラウンド(ライク・ア・レコード)(ドープ)
2モノローグ1(ジョン・ケイル)
3サムシング・イン・ジ・エアー(アメリカン・サイコ・リミックス)(デヴィッド・ボウイ)
4ウォッチング・ミー・フォール(ザ・キュアー)
5トゥルー・フェイス(ニュー・オーダー)
6モノローグ2(ジョン・ケイル)
7トラブル(ダニエル・アッシュ)
8ペイド・イン・フル(コールドカット・リミックス)(エリック・B.&ラキム)
9フー・フィーリン・イット(フィリップス・サイコ・ミックス)(トム・トム・クラブ)
10モノローグ3(ジョン・ケイル)
11ホワッツ・オン・ユア・マインド(ピュア・エネジー・ミックス)(インフォメイション・ソサエティ)
12パンプ・アップ・ザ・ヴォリューム(マース)
13ペイド・イン・フル(リミックス)(ザ・ラケット)
|

気になる「アメリカン・サイコ」の予告編はこちら!


2001年年頭に来日したクリスチャン・ベールの記者会見の模様はこちら!
『アメリカン・サイコ』
(2000年アメリカ)
2001年5月3日より、恵比寿ガーデンシネマにて公開!
●監督/メアリー・ハロン
●脚本/グィネヴィア・ターナー
●音楽/ジョン・ケイル
●音楽監修/バリー・コール、クリストファー・コバート
●出演/クリスチャン・ベール、ウィレム・デフォー、クロエ・セヴィニー、ほか
●配給/アミューズピクチャーズ
上映時間/102分
Special Thanx to www.americanpsycho-j.com |
| ブレット・イーストン・エリスが原作を発表した10年前当時、フェミニスト団体が抗議運動を起こすなど物議を醸し、映画化が決まるや、ディカプリオが主演を買って出たとか、製作前からやたら問題作らしい匂いを放っていた作品。
少なくとも、殺人シーンの血の量は『ハンニバル』以上である。

▲ ハンサムで完璧主義者で超エリートの証券マン、クリスチャン・ベール(パトリック・ベイトマン)。高級ブランドのスーツを着こなし、ナルシスティックに身体を鍛えている。 |
物質主義の'80年代。ウォール街を我が物顔で歩く証券会社の若きエリート、パトリック・ベイトマンはバブリーという言葉そのままの生活を送っている。生活臭のないインテリアで統一された高級マンションに住み、むやみやたらと身体を鍛え、デザイナーズ・スーツを身に纏って、全身、薄っぺらな見栄に塗り固められている。同類のヤンエグ仲間と名刺の洗練度を競い、人気レストランのテーブルの予約を争い、寄るとさわると他愛ない話題で盛り上がる。
そんな彼は、ただ憂さを晴らすかのように、密かに殺人に興じていた。
ほぼ出ずっぱりの主役を演じるのは、最近では『シャフト』でもイヤなヤツに扮していたクリスチャン・ベール。本作を“風刺作品”と呼ぶ彼は、「脚本を読んで、ベイトマンという人物に笑ってしまった。原作は、ほとんどの書評で暴力ばかりが語られていたのに対し、監督・脚本のメアリー・ハロンは、多くの人が軽視する、この作品の持つ風刺や知性という部分を描くのが狙いだと言い、そこが面白いと思った。周りの人間みんなに『この役をやったら、キャリアを自ら棒に振ることになる』と言われ、かえってやる気になったよ」と言う。

▲娼婦2人を部屋に呼び入れるシーン。ちゃんとタキシードでお出迎え。
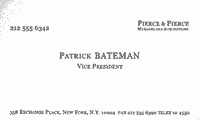
▲ これが、超エリートのクリスチャン・ベールの名刺。文字の色やフォント、紙質までこだわって作ったのだが…。 |
確かに、本作が提供してくれるのは、恐怖より、笑いのほうが勝っていたりする。他人にはどうでもいいものに偏執的にこだわる主人公の滑稽さ。ギャグ漫画で、唐突にシリアスな顔に一変したキャラが額に汗し、拳を握ってしまう、あの感じに似ている。
そして、主人公がなぜ殺人を犯すのか、その心理を探ること自体にはあまり意味がない。良心との葛藤もここには存在しない。ベールによれば、「ベイトマンがシリアル・キラーだというのは、僕にはどうでもいいこと。彼は、“欲こそすべて” “我こそは宇宙の覇者”と信じる'80年代の人間の極端な象徴なんだ。これは、そんな時代を映し取り、それに対する洞察を描いた作品」だそうだ。
さて、本作では、音楽が小道具以上の働きをしている。
まず、スコアをJohn Caleが担当しているところは要チェック。ハロン監督とのコンビは『I SHOT ANDY WARHOL』に続いて2作目。そして、主人公、ベイトマンの殺戮の前戯を盛り上げるのは、Huey Lewis And The Newsの「Hip To Be Square」、Whitney Houstonの「Greatest Love Of All」…と、'85~'86年のいかにも人畜無害な選曲。Phil Collinsの「Sussudio」の使われ方なんて、もう…。
それに、いちいちベイトマンの勿体ぶった講釈が付くのだが、スタイリッシュであることに心血を注ぐ彼の'80年代の音楽に対する変な執着は、あまりにこっぱずかしくて、笑いを禁じ得ない。
また、殺人シーンではないが、Katrina And The Wavesの「Walking On Sunshine」も、『ハイ・フィデリティ』に続いて、お気楽さの象徴のように使われている。ただし、この映画を最も想起させ易いこれらの曲は、サントラには入っていない。
みごとナイス・ガイ脱皮を遂げた前述のクリスチャン・ベールのほか、秘書役のクロエ・セヴィニー、ベイトマンのライバルのエリートを演じるジャレッド・レト、ベイトマンの婚約者には、顔の造作はファニー・フェイスの部類なのに、なぜか美人風の役が多いリース・ウィザースプーンと、若手個性派が集結。現実味ある不条理の世界を作り上げている。 |
|