カムバック後も変わらぬベテランの底力
 |
|
カムバック後も変わらぬベテランの底力 |
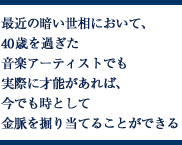 | Carlos Santanaは1年と少し前まではカムバックを模索する年老いたロックの伝説であった。 確かに彼のポピュラー音楽界への貢献や優れたミュージシャンシップは否定できないものである。だが、彼の音楽市場全体での存在感は(忠実なファンとジャムバンド信奉者、懐古趣味の中年リスナーを除いて)、かなり前から薄れてしまっていた。 9部門でGrammyを獲得し、2100万枚を売り上げた今ではMetatronが正しかったと言ってもかまわないだろう。実際にSantanaの商業面での復活は、おそらく近年のポップス界で最も心暖まるストーリーであった。つまり最近の暗い世相において、40歳を過ぎた音楽アーティストでも実際に才能があれば、今でも時として金脈を掘り当てることができる事実を思いださせてくれたのは歓迎すべきことなのである。 Carlosと9人編成のバンドが登場したステージは、ロングアイランドの美しい砂洲にある海辺の劇場で、『Supernatural』リリース後では初めてのニューヨーク地区でのライヴであった。 このアルバムの大成功がSantanaのショウにどのような影響を与えているのかが唯一の大きな不安材料であったが、彼らのパフォーマンスが楽しめるもので、インスピレーションに溢れたものになることは充分に予想できた。 Santanaが過去20年間に発表した数多くのアルバムの大半はムラのある作品だったが、彼らはずっと超強力なライヴアクトの地位を維持してきたのである。しかし、今回のツアーは基本的にゲストスターのおかげで火がついたアルバム(大胆に言わせてもらえばチョイ役での友情出演をズラリと並べただけなのだが)の成功を後追いするものであった。 ゲストの面々にも自分のキャリアを追求する必要があるので、Santanaの大掛かりな全米ツアーのステージにLauryn Hill、Dave Matthews、Eagle-Eye Cherry、Everlast、Eric Claptonその他のアーティストが入れ替わり立ち替わり毎晩のように登場することなどありえないのだ。もしそれが現実ならば、ニューアルバムの曲はどれくらい演奏されるのか、そしてサウンドはどのようになるのだろうか? 最初の疑問にはすぐに答が出た。オープニングは『Supernatural』の最初の3曲を順番どおりに演奏、終演近くまでにはアルバムの曲の大半が披露されたのである。そのサウンドに関しては、答は常に前向きなものとはならなかった。 豪華なゲストがいないところは、Santana専属のヴォーカリストであるTony LindsayとAndy Vargasのリレーチームが歌を担当した。二人は威厳をもってステージを動き回り第一級のノドを聞かせたが、「Love Of My Life」(アルバムではMatthewsが歌っていた)や「Put YourLights On」(同じくEverlast)といった曲では、やや個性に乏しいヴォーカルに聞こえるのは否めなかった。そうした個性の乏しさは演奏全体にもあてはまり、パンチ力を産み出すはずのグルーヴが薄められていた。Carlosのギターソロでさえ計算ずくのギミックに思えたくらいである。フレットボード上で左手を最も低いポジションから最高音までスピーディーに走らせるお馴染みのテクニック(ちょうどDick Daleとは逆方向のように)も、何度か繰り返されることになった。最初に聞いたときにはテンションを作り出すクールな技に思えても、3度目には創造性の欠如を感じさせてしまうのである。 だが、こうした残念な状態は長くは続かなかった。数曲進んだところで、実際には何人かの特別ゲストの出演があることが明らかになったのである。(といってもさほどの衝撃ではない。結局ここはニューヨークなのだ)。 最初にステージに登場したのは、R&Bヴォーカルのデュオとして知られるProduct G&Bで、『Supernatural』からの「Maria Maria」での役割をエネルギッシュに再現し、オーディエンスを初めて総立ち状態にしたのだった。
そして本当のお楽しみの時間がやってきた。「Black Magic Woman」と「Oye Como Va」はいつものように官能的で、聴衆はうっとりと聴き入っていた。さらに言えば、これらの曲を演奏するときのSantanaの喜びは明らかであった。(私だけでなく、彼もまた新曲よりも昔の名曲の方がずっと心地良いのであろうか?)。 焼け付くようなサステイン音、ブルージーなチョーキング、炎のような速弾き、Carlosはあらゆる技巧を知り尽したうえで、正しく真の名人らしい優雅さで曲に合わせて繰り出してくるのだ。彼の昔のアルバムのタイトルにもなっていた“love, devotion, surrender(愛、献身、降伏)”の3つの魔法の言葉の意味を音楽に乗せて伝えるという点では、彼に匹敵するギタリストはほとんどいないだろう。 最後にはとっておきの出し物が用意されていた。Santanaは最も魅力的な共演者であるMatchbox TwentyのRob Thomasを呼び出し、『Supernatural』がトップへと昇りつめるきっかけとなった曲「Smooth」を披露したのである。Thomas自身や彼の“情熱的なラテン系女性”を描いたありきたりな歌詞のセンスをどう評価するにしても、「Smooth」が極めてキャッチーな曲であることは誰もが認めざるを得ないだろう。それに昔の名曲の中でも最高の部類に入るいくつかのナンバーに続いて演奏されても、驚くほどフィットしていることも確かであった。延長されたコーダ部分でバンドは強烈なメレンゲの歓喜へと突入、観衆は前へ踊り出て大いに盛り上がったのである。 ほとんどのアーティストならば、こうした瞬間を迎えればショウは終わってしまうものだが、Santanaにはあてはまらない。Thomasはステージの後方に移動してパーカッション軍団に参加(そこにはロックスターのエゴなどない。少なくとも当夜に関しては)、Marvin Gayeの「Right On」をゴージャスに演奏したのだ。 Carlosはライヴでこの曲を好んで取り上げているが、その沸き立つようなグルーヴと社会問題を意識した歌詞が彼にピッタリなことを考えれば全く不思議ではない。この曲で彼はトランペッターのBill Ortizのところに歩み寄ってスポットライトを譲り、Miles Davisでも誇らしく思うようなクールで洗練されたソロを披露させたのである。 最後はやはり名曲の「Jingo」でSantanaが舞い上がるような演奏を聴かせた。終演後CarlosはいつものようにBob MarleyとJohn Coltraneの霊に祈りを捧げながらオーディエンスに祝福を与えたのである。Metatronも微笑んでいたことだろう。 オープニングのMacy Grayに関しては、不可抗力のために大半を聴き逃してしまったが、聴くことのできた数曲から判断する限り、彼女は自分のステージのやり方を心得ているようだった。 GrayはパフォーマーとしてJames Brown/Princeスタイルのレヴュー形式に凝っており、急テンポで場面を次々とダイナミックに転換し、曲と曲とを極めてタイトに連結し、アクションにも途切れを見せなかった。このように偉大な伝統を取り入れつつも、自分に合うように応用していた。派手な羽付きのパンツスーツをカジュアルに着こなした彼女は、Santanaよりも大規模なバンド(10人編成)とシンガー(3人、全員が人目を引くネオンブルーのウィッグを着けていた)にサポートされていた。Grayは魅惑的な「I Try」 by Mac Randall |
この記事の関連情報
カルロス・サンタナ、さらに6公演を延期
カルロス・サンタナ、ステージ上で倒れる「脱水症状を起こしてしまった」
カルロス・サンタナ、胸部に不快感を覚えラスベガス長期公演を中止
サンタナ<50周年記念第2弾>、最高傑作と評される『天の守護神ーSA-CDマルチ・ハイブリッド・エディションー』発売決定
サンタナ、傑作1st AL『サンタナ』発売50周年を記念し超希少“ 4chサラウンド・ミックス”が収録されたSA-CDマルチ・ハイブリッド盤発売
サンタナ、ザ・ラカンターズ、マイリーも<Woodstock 50>への出演中止
サンタナ、R・ルービン・プロデュースでアフリカン音楽にインスパイアされた新作発表
ウッドストック50周年記念フェスティバル、ラインナップ発表
リンゴ・スター、サンタナ、ウッドストック記念イベントに出演

