少年から青年へ

旧名をImmatureというこのグループは成熟し、その成長ぶりは誰の目にも明らかだ。最新作に収録されている一連の曲には、シンガーとして、またエンターテインメントのプロとしての、バンドメンバーの並外れた能力がはっきりと示されている。 現在はIMXという名前になったこのグループは、若者らしい楽観主義の繊細な面を今でも示す一方、ヒップホップ・ソウルのなかに、世間ずれした表現を包みこんでいる。 「Keep It On The Low」「Beautiful」「Stay The Night」などの曲では、ファンは期待どおりのハーモニーを堪能できる。そればかりかIMXは、昨今の様々なサウンドやテクニックを大胆に実験している。これは、おおぜいのソングライターやプロデューサーとの共同作業の賜物だ。 IMXは今までとは別のグループであり、どれだけ変わったかは一目瞭然だ。グループのメンバーBatmanの説明を聞くと、この変化はImmatureからIMXに進むと決定した時から始まったという。 Batmanは言う。 「名前を変えたのは、そういう時機だと思ったからだ。それまでにもそのことはずっと話し合っていた。“I-Mature”に変えるとか“I”を取って“Mature”にするとかね。絶好のタイミングだと思ったんだ。長い活動休止状態から復帰したところだったし、こんなに長く世間と離れていたことはなかったからね。今ではずいぶん成長したし、時間が経って、僕らの音楽も僕ら自身も成熟したと感じている。今回の名前変更で混乱する人もいるかもしれないけど、やっぱり僕らだということをみんなわかってきている。みんな“I-m”に慣れているよ。アルバム『We Got It』を発表した頃から名前変更のことは口にしていたしね」 新作には陽気なパーティーソングがたくさん入っている。もっとも以前は、このグループはバラードで有名だった。彼らのバラードは熱情的なところがあり、それを聴いた若い女の子たちは顔も知らないこの3人の若者に向かって、抑制できないほどに叫び、永遠の愛を誓っていた。Immatureはソウルフルなバラードを見事に歌い上げて、ステージを下りるときには常に新たなファンと崇拝者を獲得していた。 子供たちのグループがディズニーランドに行って羽目を外すように、IMXのメンバーは新作にたいへん満足しているようだ。現在のレコーディングでは量のために質を落とすようなことはないが、ヒットシングルの量産を義務づけられた者にとって、これは楽なことではない。 この才能に恵まれたシンガーたちは今や、演奏家のなかでは小細工に頼らずに才能を伸ばすことができるエリートグループに属しており、そこには何のトリックもない。まさに、ギャングスタ・クルーナーたちが支配する業界における本物のシンガーたちだ。 「あらゆる階層のファンを獲得しようとしてるんだ。あらゆる年代層のね。大人、母親と父親、小さな子ども。みんなをファンにしたいんだ」 このグループが実際に“みんな”を獲得したのは、これが初めてかもしれない。またメンバーが自分たちの曲を共作したのもこれが初めてで、そのことがヒット曲を作りを一層神経を悩ますものにしている。 Batmanは言う。 「まだ克服していない。僕らは今でも少しばかり神経質なんだ。以前はあらゆることに神経質だった。ビデオ撮影にすら神経質だった。でもハードワークとはそういうものだ。少しくらい疲れても、もっと仕事をし、もう少しハードに進めていかなくちゃならないんだ」 このグループは、マネージャーのChris Stokesが主としてプロデュースしており、ファンの層をますます拡大させている。IMXはグループとしても個人としても、十代のロマンスを若者の恋愛関係にまで高めている。現在、グループの歌詞はこれまで以上に感情に訴える高いレベルに達しており、メンバーがこの数年間に経験した変化が反映されている。 Immatureはしばらく人目につかなかったが、活動を停止していたわけではない。全米でコンサートを行ない、プロモーションにもできる限り姿を現した。そうしたタイプの注目は、グループによっては悩みの種となる。気取った振る舞いが始まり、ジェラシーが生まれ、“New Edition”の例を引くまでもなく、成功を収めていたグループが解散に追い込まれる。しかしBatmanによれば、そうしたグループとは異なり、IMXにとってジェラシーは問題にはならなかった。 Batmanは語る。 「僕らはみんな親友なんだ。僕らにとってジェラシーは問題にはならなかった。僕らはそんなグループじゃない。僕らはみんな兄弟なんだ。わかる?8才の頃からお互いずっと一緒で、今では僕も18歳だ。だけど僕らはすごく自信がある。いい音楽でありさえすれば、みんなシングルもアルバムも気に入ってくれるって思うんだ。すごく前向きに考えてる。本当にすべてが楽しいんだ」 by Vic Everett |
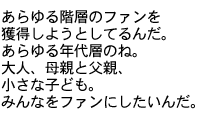 Batmanは説明する。
Batmanは説明する。