ルーファス・ウェインライト、最新インタビューを公開
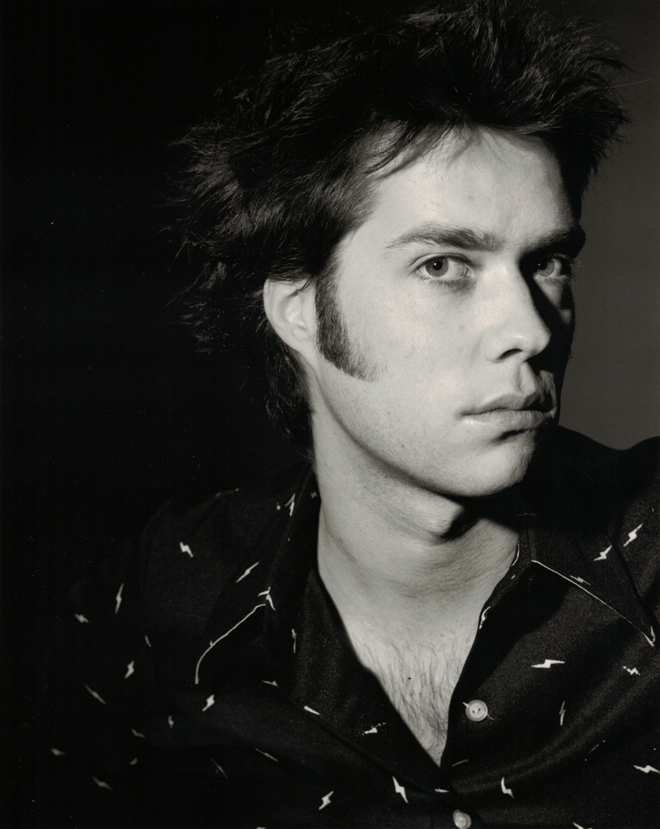
3月28日(水)、29日(木)の2日間に渡ってデビュー20周年記念公演を行うルーファス・ウェインライト。11年ぶりのバンド編成で、1stアルバムの『ルーファス・ウェインライト』と2ndアルバム『ポーゼス』からの楽曲をパフォーマンスする必見の内容だ。全米ツアー中の本人へのインタビューを公開する。来日公演の見どころや日本のファンに向けたメッセージ、先日リリースしたプロテスト・ソングに込めた思い、LGBTQアーティストを巡る環境の変化についてなど存分に語ってくれた。
――まずは今回のツアーを思い立ったきっかけ、殊に、最初の2枚のアルバムをセットにして聴かせようと思い立った経緯を教えて下さい。
ルーファス・ウェインライト(以下、ルーファス):2枚を一緒に披露しようと思ったのは、僕にはこれらのアルバムが、対を成しているように感じられるからなんだ。ほら、デビューして最初の2枚のアルバムというのは、そのアーティストの運命を決定付けるような作品だよね。より具体的に言うと、まずファースト・アルバムには、何年もかけて自分の表現を磨いた挙句に綴った、渾身の曲が収められている。つまり、自分以外の人は一切関知していない、全く未知の音楽をいきなり世界に送り出すわけだから、ある意味でアーティストが主導権を握っていて、有利な立場にあるよね。僕の場合、まさにそうだったんだ。しかも非常に恵まれた環境で、大手レーベルのドリームワークスと契約し、オーケストラと、素晴らしいプロデューサーと、素晴らしいミュージシャンたちの手を借りて、素晴らしいスタジオでレコーディングを行なった。でもセカンド・アルバムは違う。ここで本当の試練が待ち受けている。セカンド・アルバムが1枚の作品として十分な重みを備えているか否か、ファースト・アルバムを聴いた人に発展的な音楽体験を与えられるか否か――というテストにパスしなければならない。僕は『ポーゼズ』でそれを実現できたと感じているし、これら2枚が僕のキャリアの核になってくれたと思うんだ。……いや、“核”と言うよりも、キャリアを軌道に乗せた“エンジン”だね。2枚を聴けば、僕がほかの人たちとは違う風変わりな試みを目論んでいることが、分かったはずだから。
――確かに当時のあなたは非常に風変わりな存在でしたが、その点は自分でも強く意識していたんですか?
ルーファス:そうだね。自分はユニークだと認識していたし、デビュー当時を振り返ると自分でも驚愕することがあって、それは、当時の僕が備えていた途方もない自信なんだ。自分がユニークだと分かっていて、それでいて、世界は自分を必要としていて、僕が伝えようとしていることには重要な意味があると100%確信していた。ただ自分の運命を全うしているだけで、全世界が僕の歌を聴くべきだと。尋常じゃない野心があったんだ。当時そういう野心を持ち合わせていて良かったと思うし、今は逆に、そこまで野心に振り回されていないことに、ありがたみを感じているよ(笑)。僕の野心は理解されなくて、傲慢な人間だとか、自信過剰でエゴが強い人間だとか批判されたこともあった。でも、音楽的に非常にユニークであるだけでなく、当時の音楽界でゲイであることを公言する数少ないアーティストのひとりだったわけで、あれくらい強気で自信があったからこそ、生き延びられたと思うんだよね。しかも僕は自分の人生を無防備に曲にさらけ出していたし、現実に、エイズに死ぬんじゃないかと恐れてもいた。色んな意味でサバイバルの知恵だったんだ。自信が功を奏したのさ。それにしても、あそこまでの激しさが自分にあったことに驚かされるよ。
――しばらくソロでのツアーが続いたあとで、久しぶりにバンドを率いてのパフォーマンスをするのはいかがですか?
ルーファス:いい感じだよ。何しろ今回の僕には、ジェリー・レナードという素晴らしいミュージカル・ディレクターがいるからね。彼とは過去にも何度か組んでいるけど、デヴィッド・ボウイやスザンヌ・ヴェガとのコラボが有名で、音楽界では一目置かれている存在だし、バンドのメンバーも彼が中心になって集めてくれたんだ。だからほんと、最高だよ。これまで様々なメンバー構成のバンドとプレイしてきて、ここにきてようやく満足の行くコンビネーションに辿り着いた気がする。今のラインナップで作っている音楽には、すごく興奮させられるよ。それに、これらの曲は過去に繰り返しプレイしていて、僕も知り尽くしているだけに、非常に成熟してきたような感触があるんだよね。深みが増してきたと言うか。かつ、今の僕はこれらの曲を通じて何かを証明する必要もないわけで、純粋に音楽を楽しめるという点においてもエキサイティングだよ。
――セットは2部構成で、セカンド『ポーゼズ』のセクションはオリジナル盤をほぼそのまま再現していますが、ファーストのセクションでは順番を変えたり、曲を入れ替えたりしています。セットを構成する上での考えを教えて下さい。
ルーファス:2枚のアルバムを1本のライヴ・パフォーマンスで再現するにあたって、単純に2枚ともそのまま演奏するのは、つまらないような気がしたんだ。それに長過ぎるようにも感じて、少し手を加えることに決めたのさ。だから、第1部は基本的に『ルーファス・ウェインライト』をプレイするんだけど、比較的新しい曲も含めて、アルバムに入っていない曲を幾つか交えている。実はライヴ会場でしか購入できないニュー・アルバムがあってね。『Northern Stars』というタイトルで、ジョニ・ミッチェルやニール・ヤングやレナード・コーエンといったカナダ人アーティストの曲をカヴァーしているんだ。その中からジョニの曲『青春の光と影(Both Sides, Now)』をライヴでは披露していて、最近リリースした『Sword of Damocles』も第1部で歌っているよ。両方とも宣伝しないといけないから(笑)。その後、第2部が『ポーゼズ』なんだけど、こちらは一転して、よりフォーマルで、MCもほとんど挿まない。アルバムを1枚の絵画作品として提示しているような感じだね。あれはまさにそういう作品だから。そんなわけで、1本のライヴ・パフォーマンスの中で多様なアプローチを試みていて、そこは自分でも気に入っているよ。
――アンコールのラストソングは毎晩ザ・ビートルズの『アクロス・ザ・ユニバース』のカヴァーです。映画『アイ・アム・サム』のサントラで歌った曲ですが、なぜこの曲をラストに?
ルーファス:理由のひとつは、ちょうど『ポーゼズ』と同じ時期にレコーディングした曲だからなんだけど、『アクロス・ザ・ユニバース』のすぐ前に歌うのは、『ゴーイング・トゥ・ア・タウン』なんだ。過去数年間のソロのライヴではたいてい、『ゴーイング・トゥ・ア・タウン』のあとは『ハレルヤ』という流れにしていて、どうもあの曲のあとには、より超自然的と言うか、幽玄なところがある曲が相応しいように感じるんだよね。『ゴーイング・トゥ・ア・タウン』は生臭いアメリカの政治に関する曲だから、宇宙全体に目を向けたスケール感のある曲を並べて、バランスをとっているのさ。
――セクションごとに着替えている衣装は、誰が手掛けたんですか?
ルーファス:僕の友人であるカナダ人のファッション・キュレーター、ティエリー・マキシム・ロリオが監修してくれたんだ。このツアーのアーティスティック・ディレクターなんだよ。数年前に世界各地を巡回して話題になった、ジャン=ポール・ゴルチエの展覧会『The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk』でキュレーターを務めた人でね。色んなデザイナーと組んで衣装を構成してくれたんだけど、主にヴィクター&ロルフの服で、一部ヴィヴィアン・ウェストウッドの息子(注:ジョゼフ・コー)に提供してもらったものも含まれているよ。
――ルーファス・ワールドの構成要素を網羅した成長の記録『ルーファス・ウェインライト』、ニューヨークで過ごした20代のダイアリーのような『ポーゼズ』、これら2枚のアルバムと改めて向き合って、どんな感慨を抱きましたか?
ルーファス:実は想定していた以上に心理的なインパクトが大きくて、こんなはずじゃなかったのに……と、戸惑ってしまったよ(笑)。まずリハーサルを行なって、その時はただ楽しかったんだ。時代を遡って、曲によっては久しぶりに細かく聴き直したものもあったから、再考する作業には興奮させられたしね。ところがLAでツアーの初日を迎えた時、僕はものすごく感情的になってしまって、「初日だし、バンドと一緒にライヴをやるのも久しぶりだし、今LAで暮らしている僕にとって地元での公演だから、こんなに緊張して熱くなっているに違いない」と自分に言い聞かせたものさ。そうすることで気分が幾らか落ち着いて、それからアメリカ各地でプレイしているうちにだんだん慣れていって……。なのにニューヨーク公演の日を迎えると、またもや精神的にすっかり打ちのめされちゃったんだよ(笑)。というか、ライヴ自体は素晴らしかったんだ。でも僕はステージでずっと、何かを必死に探し求めている孤独な青年だったニューヨーク時代の自分の姿を、哀れなルーファス坊やが、色々あってセントラル・パークの中をとぼとぼ歩いている姿を頭に思い浮かべていて、それはもう強烈な一晩だったな。だからこうして過去のアルバムを辿るのは、間違いなく、非常にパワフルなプロセスだと言えるよ。
――あなたが触れたように、20年前、セクシュアリティを最初からオープンにしている男性アーティストは非常に稀でしたが、ここにきて当たり前のことになりましたよね。LGBTQアーティストを巡る環境の変化についてはどう感じていますか?
ルーファス:う~ん、どれだけ変わったのか見極めるのは、すごく難しいと思うんだ。確かに一方では、ゲイであることを公言するのはいたってノーマルなことで、昔のようにそれで逆風が吹いたり、成功の妨げになったりはしなくなった。でもトランプ大統領が出現し、保守・右翼勢力や狂信的なクリスチャン勢力がこれまでになく大きな影響力を誇っている今、僕たちが勝ち取ったポジションは実は非常にあやふやなのかもしれない。だからこそ、油断しないで今後も可能な限り正直であり続けること、リアルであり続けることが重要だと思う。自分を隠さずに。昔の状況に逆戻りするのはいとも簡単なことだと思うし、残念ながら進化は止まってしまったような気がしないでもないよ。
――先程も名前が挙がった、11月のアメリカでの中間選挙に合わせて発表した新曲『Sword of Damocles』と、ブッシュ政権下の2007年に発表した『ゴーイング・トゥ・ア・タウン』、2曲のポリティカルな内容の曲も今回のセットに含まれています。あなたは『Sword of Damocles』を昨今の政情への“アーティスティックな返答”と評していますが、プロテスト・ソングの型にはまらないこういう曲に仕立てた狙いは?
ルーファス:まずこの曲は、我々全員の頭上に“ダモクレスの剣”がぶら下がっているのだと説いているんだ。要するに、歴史の中で今我々は、政治的な意味でも、文化的な意味でも、環境問題においても岐路に立っているということだね。途方もなく大きな変革が必要とされていて、それは辛いプロセスに、恐らくバイオレントなプロセスになるだろうし、衝撃も大きいだろう。でも剣は落とされなければならないんだよ。従って、必ずしも直接トランプ大統領に宛てて書いた曲ではなくて、変化をもたらそうと呼びかけている曲なのさ。ほら、僕は前回の大統領選挙ではヒラリー・クリントン候補を支持して、彼女は結局負けてしまったわけだけど、「トランプのおかげで、これまでは表面的に取り繕っていて隠されていた人種差別や憎悪や性差別といった問題がさらけ出される結果になったんだから、それは良かったんじゃないかな」とは言いたくない。クリントン候補のほうが大統領に相応しかったことに変わりはないからね。とは言え、こういう現実を突き付けられている今、それに対処するよりほかに選択肢はないんだよ。
(注:ダモクレスは、ギリシャ神話に登場するシラクサ市の王ディオニシウス1世の廷臣。彼がしきりにディオニシウスの栄華を褒めそやしたところ、王は自分の代わりにダモクレスを王座に座らせた。彼は王になった気分で悦に入っていたが、頭上を見上げると1本の髪の毛で吊るされた剣の切っ先が光っていて、栄華繁栄の中でも常に危険と隣り合わせなのだと諭したとされている)
――トランプ政権になってからアメリカとカナダの比較論も盛んになりましたが、あなたの場合は両方の国のアイデンティティを併せ持っているわけですよね。
ルーファス:ああ。すごくおかしいんだけど、実はカナダにもかつて、スティーヴン・ハーパーというとんでもない首相がいたんだ。僕はよりによって、アメリカはオバマ政権でカナダはハーパー政権だという時期に、カナダで暮らす羽目になった。だから、オバマ時代のアメリカではあまり長く過ごすことができなかったんだよ。そしてようやくアメリカに戻って来たと思ったら、トランプが大統領になった! だから、どちらの国でもいい時代を逃してしまった気がする。そんなわけで、僕がもしも日本に移住することになったら、気を付けたほうがいいと思うよ(笑)。
――ちなみに『ゴーイング・トゥ・ア・タウン』はイラク戦争を受けて誕生した曲でしたよね。その後ジョージ・マイケルがカヴァーし、2年前にはリリー・アレンがウィメンズ・マーチ(注:トランプ大統領の就任式翌日に世界中で行なわれた抗議デモ)に際して歌いました。そして、2019年の世界においても有効なのですが、このようにして曲が辿ってきた旅路についてどう思われますか?
ルーファス:そりゃあ、僕の曲を素晴らしいアーティストたちが歌ってくれたことには大いにインスパイアされるし、感激もしたし、感謝の気持ちを抱いているよ。特にジョージはシンガーとして、僕の長年のヒーローのひとりだったから、本当に感動したな。そして今の世の中においても有効だという事実は、残念なことでもあるけど、僕はどうも物事のダークな側面に目を向けがちなんだよ。つい、心を困惑させる事柄について歌ってしまうのさ。
――10月には2作目のオペラ『Hadrian』も初演されました。あなた自身の手応えは?
ルーファス:この作品については本当に大きな誇りを抱いているよ。トロントでの初演は大成功だったし、あちこちのオペラハウスが興味を示していて、まさに今、次にどこでどう見せるのか交渉を進めているところなんだ。何しろ大作だからね。全4幕で、主要な登場人物が13人もいる。物語も非常に重厚で深みがあると思うし、オーディエンスに挑みかけるようなところがある。ぜひとも正式にスタジオでレコーディングを行なって、アルバムにしたい。もちろん完璧な形になるまでには、恐らくこれから2年くらいを費やして、少しずつ手を加える必要がある。偉大なオペラ作品はどれもそういうものだし、とにかく今のところ、心から仕上がりには満足しているよ。
――今作は内容警告付きで18歳以上限定という、演出面でも型破りな作品のようですね。オペラの世界の常識を破りたいというような意図もあったのでしょうか?
ルーファス:(笑)これは少々大げさな話で、カナダ人らしいリアクションだと思うよ。カナダ人はあれこれ細かいことを心配し過ぎるんだ。確かに、かなりセクシュアルなシーンがひとつあるけど、品位をもって表現されているし、実際は非常に美しくて、音楽的にもロマンティックなシーンなんだ。過激なことをして挑発しようという意図は全くないよ。ショッキングでも何でもないし、単にふたりの男性が愛し合っているというだけ。世の中では、そういうことも時たま起きるのさ(笑)。
――ポップ・アルバムは2012年発表の『アウト・オブ・ザ・ゲーム』以来途切れていますよね。ミッチェル・フルームと新作をレコーディングしていると報じられましたが、進行具合は?
ルーファス:今まさに絶賛制作中だよ。ミッチェルは素晴らしいプロデューサーで、コラボレーションを心から楽しんでいる。僕とミッチェルの組み合わせは、まさに夢の取り合わせだよ。カリフォルニアという天国が引き合わせた運命のふたり、だね。いや、「地獄が引き合わせた」と言うべきかな。天国であり、同時に地獄でもあるのがカリフォルニアだから(笑)。
――もしかしてポリティカルな趣のアルバムになるのでしょうか?
ルーファス:いいや、そうはならないと思うよ。むしろ、非常にパーソナルなアルバムになると思う。もちろん、怒りを多分に含むことになるだろうけどね。傷を負った種族として(笑)、僕たちみんなが共感できるような題材に触れてはいるけど、今の僕はそれよりも、人々の魂を癒すような曲を歌いたいんだ。
――思えば、デビューした年に二度来日しています。特に記憶に残っていることはありますか?
ルーファス:覚えていることはたくさんあるけど、日本の社会そのものに驚嘆させられたと言うべきなんじゃないかな。視覚的な面もさることながら、食事から生活習慣に至るまで、何もかも含めて。あれ以来何度も訪れているけど、時間に余裕がある時は必ず歌舞伎を観に行っているんだ。能もぜひ一度観てみたいと思っていて、とにかく舞台芸術を鑑賞するのが好きなんだよ。
――3月の来日公演を楽しみにしているファンに、メッセージをお願いします。
ルーファス:前回の来日から少し時間が空いてしまったから、まずは「ごめんなさい」と言っておきたい。みんなと再会できるのを楽しみにしているよ!
訳:新谷洋子
ライブ・イベント情報
【東京】
3月28日(木)・29日(金) 東京国際フォーラムホールC 19:00開演
■一般発売
11月24日(土)