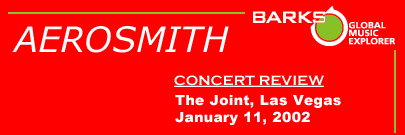『Just Push Play + Live & Rare』
Sony Music International SICP-87~88(2枚組)
2002年1月30日発売 3,150(tax in)
【DISC 1】
1 Beyond Beautful
2 Just Push Play
3 Jaded
4 Fly Away From Here(radio edit)
5 Trip Hoppin'
6 Sunshine
7 Under My Skin
8 Luv Lies
9 Outta Your Head
10 Drop Dead Gorgeous
11 Light Inside
12 Avant Garden
13 Won't Let You Down
14 I Don't Want To Miss A Thing
【DISC 2】
※レア・ライヴ・トラック他を収録したボーナスCD
1 Draw The Line
2 Chip Away The Stone
3 Same Old Song And Dance
4 Big Ten Inch Record
5 I Wanna Know Why
6 Lord Of The Thighs
7 One Way Street
8 Walk This Way
9 Dream On
10 Just Push Play(New Remix)
11 I Don't Want To Miss A Thing(Live Version)
 | | | どこから話を始めようか。とりあえず、最初にこれを言わせていただくとしよう。正直なところ、ハリウッドぼけした我が人生で、これほど素晴らしいロックンロール・ショウを観たのは初めてだ。StonesもKissも、CooperもGuns N' Rosesも、それぞれの最盛期に観たことがある。Iggyだって……。何でも観てきた私だ。他でもないAerosmithだって過去に3度、観たことがある! しかし何をもってしても、まさに何をもってしても、ラスヴェガスのHard Rock Hotel & CasinoにあるThe Jointに押しかけたAerosmithが、会場を包み込んだあの衝撃とは比べ物にならない。Cheap Trickという一貫して優れたライヴを見せるバンドがこの日は前座をつとめたのだが、ボストン出身の不良たちが手を変え品を変え、自らの魂とギターから繰り出すエネルギーと、歌と、カリスマ性と、才能の津波には、彼らですら歯止めをかけられなかった。自分がこんなことを言う羽目になろうとは思いもしなかったが、つわものCheap Trickも、この夜は成す術もなく洪水に押し流されてしまったというわけだ。Aerosmithは私に、そして会場のひとりひとり――バーテンダーやドアマンから、斜に構えたレコード会社のお偉いさんたちに至るまで――に対して、比類なき地上最高のライヴ・ロックンロール・バンドであることを証明して見せたのだ。それにしても、すごい肩書きではある。
'70年代当時、Aerosmithは見事なレコードを作りながらも、ステージには当たり外れがあって、'70年代初めの若くてハングリーなライヴ・ショウも、同年代の終わり頃には締まりのないヘロイン禍による小競り合いに取って代わられる。しらふに戻り、『Permanent Vacation』『Pump』といった画期的なアルバムでキャリアを立て直してからは、状況が逆転。Aerosmithは、ライヴでは威力を発揮しても、その勢いの大半がレコードでは鳴りを潜めるようになった。確かに、昨年の『Just Push Play』にはハッとさせられる瞬間がいくつかあったが、『Toys In The Attic』や『Rocks』といった過去の名作には遠く及ばない。とはいえ友よ、彼らが巨大ドームとは違う親密感のある会場で気ままにやろうという気になったら(ショウに先だってHard Rock前に並んだファンたちが「彼らがこんな小さなところでやるなんて、信じらんないよ!」とつぶやいていた)、そんな夜のAerosmithはどこをとっても黄金期のまま――あるいは、それを遥かに凌いでいるかもしれない。Tylerの歌は上手くなっている。Joe Perryのプレイも上手くなっている。要はそういうことなのだ。
'70年代のロッカーには珍しく、年齢とともに力強さを増している2002年のAerosmithは、バンドとしてさらなる高みに到達するかもしれない。Aerosmithは感傷的なパワー・バラードをこれでもかというほど熱く歌い、説得力をもって売ってしまう。例えば“I Don't Wanna Miss A Thing”。レコードで聴くそれはまったくの時間の無駄で、'80年代終盤のElton Johnのアルバムや、'80年代半ばのSteelheartの作品あたりに入っていてもおかしくないような、Diane Warrenのペンになる捨て曲なのだが、ライヴとなるとこれが新たな意味を持つようになるのである。Tylerがあの高音で歌い上げ、Joe Perryが味のあるブルースのリックを奏でれば、あの曲はもう『Armageddon/アルマゲドン』とも惑星の衝突とも関係なくなって、若くはないハードロッカーたちの心のアンセムへと姿を変えてしまう。この夜も、そんな瞬間が何度かあった。“Pink”や“Jaded”のようにアルバムではいささか地味だった曲が、コンサートでは驚くほど生命感を帯びていたのだ。PAの一時的な故障でさえ、バンドを少しもたじろがせはしなかった。PAの音が消えたのは“No More No More”のエンディング近くで、その間、彼らはモニター・ミックスだけが頼りとなったが、本人たちはただ笑って、何事もなかったように演奏を続けた。そしてあろうことか、PAなしでパワーが半減してもなお、Aerosmithは世界中の他のどんなバンドよりもすごかったのである。
言うまでもないが、AerosmithのショウがTylerとPerryに尽きるなどと誤解してはいけない。ギタリストのBrad Whitford、ベーシストのTom Hamilton、そしてドラマーのJoey Kramerは、いずれも最上級のミュージシャンであり、明らかにグルーヴの基盤である。しかし、歌を売っているのはTylerとPerryだ。彼らは自分たちの歌を体現している。50代半ばにして、この男たちには未だ滲み出る個性と魅力があり、服装もクールなら、元ジャンキーにしては恐ろしいくらい溌剌としている。Tylerは常にエネルギッシュな首謀者で、そのパーティ少年的パーソナリティとJames Brownばりのアクションでショウを引っ張り、ダイナミックな声で全体のサウンドを締める。ひとつひとつの音に緩急をつけて彼は歌う。
そして当然ながら、Joe F-kin' Perry以上にクールな奴などいない。退廃的で華麗に荒んだギター弾きの原型を生み出したのはKeith Richardsかもしれないし、そのイメージを極限まで推し進めたのはJohnny Thundersだったかもしれないが、それを一番クールに呈示しているのはPerryだ。整った顔立ち、無造作な黒髪、低く構えたギターと、どこから見てもクールそのもの。あでやかなソロを炸裂させながら右へ左へと動き回れば、その都度ヒーロー然としたロック・スターのポーズを決め、Keith譲りのバックコーラスを歌う。この夜のJoeはとりわけのっていて、2曲――『Just Push Play』の“Drop Dead Gorgeous”(どちらかというとJoe Perry Projectの没ネタみたいに聞こえるが……いや良い意味で!)と12小節のブルースをひとしきり――でバンドを率いたほか、長めのソロも何度か披露した。“Draw The Line”では、Perryがステージの縁にひざまずいてスライドのソロに突入。そしてそのクライマックスでは、'70年代初めの“Midnight Rambler”におけるMick Jaggerよろしく自分のシャツを引き裂いて、それでギターを叩き始めた。“すげぇな、Joe Perryが床の上で、シャツでギターを引っぱたいてるぜ!”と、これはその場にいなければわからない類のショウなのであった。
もうひとつ、この日のギグを特別なものにしたのがセットリストである。クラブでのパフォーマンスということで、バンドは通常の演目から大胆に方向転換し、いわば危ない橋を渡ることにしたのだ。昔ながらのファンのお気に入りである“No More No More”“Adam's Apple”“Toys In The Attic”“Seasons Of Wither”といったところを一気に駆け抜けると、James Brownの“Mother Popcorn”、Fleetwood Macの“Rattlesnake Shake”とカヴァー曲を送り出して夢見心地の観客を大喜びさせた。滅多に演奏しない“Sick As A Dog”では、'76年にスタジオで録音した時と同じようにTom Hamiltonがギター、Perryがベースを弾いて演奏するとTylerが宣言。同曲の半ばではしかし、PerryがベースをTylerに渡してエンディングのソロに向けてギターに持ち替え、Tylerは満面の笑顔でベースをポロポロと爪弾き、曲を終らせた。実際に観客の前でやるのは、もしかしたら初めてだったのかもしれない。Tylerによれば、この日の演奏はすべてライヴ・アルバム用に録音されていたそうだから、是非、その場面も収録してもらいたいものだ。それこそ貴重なのだから。
あぁ、もちろんヒット曲だってやった。当たり前なところでは“Dream On”“Walk This Way”“Same Old Song And Dance”(同夜のベストナンバーのひとつだったことを付け加えておこう)、そして“Love In An Elevator”。残念ながら“Last Child”や“Back In The Saddle”はやらなかったが、“What It Takes”の痛烈なヴァージョンと、なんとなんと『Just Push Play』から“Light Inside”の度肝を抜くライヴを聴かせてくれた! “Mama Kin”はやらずとも、“Big Ten Inch”で我々を楽しませ、そして“Train Kept A Rollin'”で会場を湧かせたのだから、細かい好みは人それぞれあるにしろ、全員が納得したのではないかと私は思う。このバンドはヴェガスという華やかな町の小さな会場で、彼らを愛してやまない熱狂的ファンの一群を前に親密感のあるショウをやることで、2002年のロック界を牛耳っているのが誰なのか、下品でヴォルテージの高い、下半身に訴える念書を顔面に突きつけた、というわけだ。断っておくが、それはLimp Bizkitではない。
では最後に、我がSteven Tylerの言葉を借りて。「みんな、帰って一発やろうぜ!」 By Frank Meyer/LAUNCH.com | |