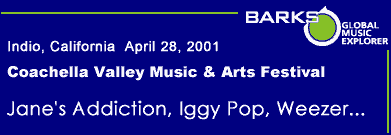| パームスプリングス郊外の砂ぼこり舞う夜深き南カリフォルニア砂漠で、第2回コーチェラヴァレー・ミュージック&アーツ・フェスティバルが開催された。このフェスティヴァルは、レディングやグラストンベリーといったイギリスの比較的のんびりした音楽祭をお手本にしているようで、その狙いは多くの面で成功していた。駐車場は無料。ミネラルウォーターの価格はまずまず。洗濯できる水道、本物の水洗トイレ、大量のトイレットペイパーが屋内の洗面所で利用可能。そしてなにより良かったのは、客席でのレイプや強盗、放火など、ウッドストック'99で起こった各種の非常識な暴力行為が、ここではまったく報告されなかった点である。
しかし、コーチェラとイギリスでは、大きな違いがひとつある。'01年4月28日、イギリスのレディングの気温は未だ肌寒い12℃。同じ日、コーチェラは37℃。我々はボーイバンドのコンサートに来ているのではない! 約3万人のコーチェラの観客は、容赦なき砂漠の直射日光で脱水症状と日射病を起こし、カリカリのベーコンみたいにピンクに焼けて意識朦朧になっていた。ひとつ疑問がある。こういった開催地は、なぜいつも汗だくの砂漠でなければならないのか。どこか海の近くに、野外フェスティヴァルが開催できて、ここよりせめて10℃ほど涼しい場所がないのだろうか。
しかし、有害な日光で赤く日焼けする危険を別にすれば、コーチェラは暑い午後を過ごすのにふさわしい場所だった。およそ50組のラインナップ(野外ステージ2カ所、テント会場3カ所)は壮観であり、アメリカだけでなくヨーロッパで開催されているさまざまな音楽祭を意識して、出演者は大胆かつ繊細に選ばれていた。その長大なリストの一部を転記すると、ロック分野では、物憂げさがカッコいいDandy Warhols、再々結成したばかりのJane's Addiction、向かうところ敵なしのパンク戦士Iggy Pop、パソコンマニアの神様Weezer。テクノ関連ではChemical Brothers、Kruder & Dorfmeister、Paul Oakenfold、The Orb、Photek、Ian Pooley、Roni Size、Fatboy Slim、Squarepusher、そしてTricky。ラッパーは、Aceyalone、Del Tha Funkee Homosapien、Gangstarr、Mos Def、the Roots、そしてSouls Of Mischief。
さらに、ただただ素晴らしい分類不可能なアーティストとして、怒りで緊迫した魂Nikka Costa、ティファナのエレクトロニカDJ(「ティファニカ」?)Nortec Collective、ラテンファンクのソウルブラザーズOzomatli、アイスランドのアヴァンギャルドSigur Ros、そしてフランスからアンビエントなアシッドジャズのSt. Germain。それでもまだ見るものがないと汗まみれの大群が不満を抱いた場合に備えて、目の保養になる美しい彫刻の庭、冷房の効いたありがたいフィルムテント(Radioheadの『Meeting People Is Easy』、Mos Defのドキュメンタリー『Freestyle』、Dandy Warholsの短編『The End Of The World As We Know It』などを上映)、最新のPS2ソフトで遊べるPlay Stationセンター、雑誌『Urb』主催のDJテント、そしてビアガーデンが2カ所。要するに、コーチェラ・フェスティバルのメニューは、観客それぞれがなにかを楽しめるというような分量ではなかった。1日限りのこの音楽祭が、観客が疲れ果てるまで13時間続くという点を考慮しても、そのメニューは、1日で食べきれる限度を超えていたのである。
まだ明るく早い(少なくともロックンロールの基準では早い)午後2時30分、Dandy Warholsのライヴが始まった。ビーチボールやハッキーサックやかき氷が恋しくなる晴れた昼間に、ドラッグを連想させる彼らのどんよりした曲が似合うはずはない。だが、遠目でも分かるくらい血色の悪い彼らはこの試練を受けて立ち、“Minnesoter”や“Godless”など夢見心地の曲を演奏した。しかし現実には、The DandysはIggy Popの前座にすぎなかったのである。
“The Igster”の姿は美しかった。金髪で山羊ヒゲをたくわえた彼は、シャツを着ずに有名な恐怖の肉体を誇示していた(彼の体重は、骨と傷とスジを全部合わせて43kg)。彼のエネルギー、混じりけのない剥き出しの力は、他のどんな出演者をも上回っていた(ほとんどの出演者は、彼の半分ほどの年齢だ)。コーチェラの太陽のもと、54歳の彼は凶暴な勢いで“Search And Destroy”や“The Passenger”“Lust For Life”や“Raw Power”などの名曲を歌い、同じく凶暴に人生を説いたりしていた(「俺は朝起きると、こう言うことがある。『今日はいい日になりそうだ。今日は本当の正義が実現しそうだ。今日はラジオで本当にすごい曲が流れそうだ!』」)。
歌のあいだの喋りでよかったのは、誰かビールは要らないかと彼が尋ねたときだった。彼はそう言うと、バドワイザーがいっぱい入った蓋のないプラスティックカップを客席に放って、最前列付近の観客をびしょ濡れにした。この乱暴な行為に彼は悪びれず、「俺は実生活では困った人間なんだ」と言い訳をして(真実を述べたのかもしれない)、“Real Wild Child”を歌いだした。そのビートは、まったく乱れていなかった。ライヴが終わりに近づいたころ、彼は悪戯っぽく観客に笑って「おまえたちに会えて嬉しいぜ!」と満足げに言い放った。そのときの大声援から判断すると、観客もそう思っていたようだった。
午後3時45分からのIggyのライヴは、会場の二極化が最も著しい時間帯だった。黒っぽい服を着て首筋まで髪を伸ばしたロックファンは大群を成してPop閣下の会場に詰めかけていた(まだ真昼間なのに)。同じころレイヴァーたちは、コーチェラのどこかでSmith & MightyやIan Pooleyのグルーヴに浸っていた。しかし、The Roots(Iggyの直後に登場し、オーガニックでカッコいいヒップホップ/ジャズを1時間演奏)とOzomatli(メキシコの対仏戦勝記念日、5月5日の「シンコデマヨ」を1週間早く祝って、同じくメキシコの「死者の日」の風習にならって行列を作り、離れたところにあるステージでパレードをしていた)が、それぞれジャンルを融合した独特の素晴らしい曲を披露したおかげで、観客はひとつにまとまった。
帰って来たWeezerが6時30分にメインステージに現れたときには、あらゆる種類のロック人間が会場にうごめいていた。グロースティックを振るテクノ少年から、バイクでやって来た初老のヒッピーまで。そしてだぶだぶのWeezerのロゴ入りTシャツを着てバランスをとっている11歳の男の子と、日焼けした肩からその子が落ちないように四苦八苦している父親などなど。
L.A.のオルタナティヴロックFM局KROQのシャレたDJ、Tami Heideが「みんな、大麻パイプを持って来たか?」と言ってWeezerを呼び込んだ――Weezerの最新ラジオヒットが“Hash Pipe”だからだ(で、それは無理だったよ、Tami。観客はリュックサックはもちろん毛布まで、正面玄関でゲシュタポに取り上げられたんだ!)。しかし、大麻の助けがあってもなくても、コーチェラの観客たちは彼らを暖かく迎え入れていた。Weezerは近日リリース予定の『Green Album』(このアルバムは5月病にかかった『Pinkerton』より、通称“blue album”ことデビューアルバム『Weezer』に感じが似ている)から何曲かを演奏した。その未発表の新曲“Island In The Sun”(Kenny RogersとDolly Partonのデュエット“Islands In The Stream”と間違えないように)や“Don't Let Go”は、前述の“Hash Pipe”とともに観客の反応がよかった。しかし、なんと言ってもWeezerの魅力はヴィンテージ物である。“In The Garage”や“You Gave Your Love To Me Softly”“Buddy Holly”“Undone (The Sweater Song)”“Sex Wax America”で客席は大合唱、さらに一部では狂乱のダンスが始まった(ステージ進行を妨害する悪質なものではなかった)。そしてライヴが終わりに近づき、壮大な“Only In Dreams”で日が暮れかけたとき、Weezerの巨大な「W」の文字が100万ワットの輝きを放った(この「W」は、かつてのVan Halenの「V」のパロディだ)。それは、みんなが野外コンサートに望んでいるひとつの素晴らしい瞬間だった。
しかし残念ながら、コーチェラの会場がどこも明るかったわけではない。空の色が濃くなって、あたりがすっかり暗くなると、数百本のグロースティックでは灯りが足りないことがはっきりした。ホラー映画『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』並みに、会場の端から端へ歩くのが怖くなってきたのである。まもなくフェスティバル会場は、果てしなき障害コースとなった。ステージからステージへ、テントからテントへ移動する観客を、酔っ払いや潰れたペットボトル、砕けたブリトーが待ち受ける。この障害物に足を取られると、食べ残しの野菜バーガーに顔から突っ込んでしまうのだ(コーチェラ・フェスティバルは整然と行き届いていた面もあったが、ゴミ箱がほとんどなかったのはどういうわけだ)。しかし、日が暮れていい点もあった。我慢できる程度には、気温が下がったのだから。
しかし、その気温を再び上げようとしたのが、フランスから来た6人組St. Germainだ。リーダーは、名人バーテンダーの手際よさで各種音楽を調合するLudovic Navarre。彼らがUS3を思わせる鮮烈なブレイクビートジャズを演奏しだすと、会場のいたる所でDeadheadのような激しいダンスやスピンが始まった。しかし、ボンゴやサックスのソロでは、観客はミュージシャンに敬意を払って、息を殺して静かに聴いていた。その点は記しておかねばならない。一方、モハヴィテントの近くでは「あ、Bad Companyのサウンドだ!」という声が聞こえた。そうかい? じゃあ、Paul Rodgersはいったいどこにいる。それに、なぜこのバンドは、観客が繰り返し“Feel Like Makin' Love”をリクエストしているのに気づかないんだ。分かった、これは別のBad Company(悪い仲間)なんだ。けど、このグループが「Bad Company U.K.」と改名しようとしても無理というものだ。イギリスにはつねにBad Companyがいる。オリジナルのthe Bad Companyが!
さて、オリジナルと言えば、誤解を招くBad Company(悪い仲間)に続いて登場したのは、Sigur Rosだった。前評判の高いアイスランドの地の精たちがアメリカのステージに初めて立つというので、モハヴィテントには過剰な期待が立ちこめていた。1曲目は、Pavarottiによく似た高齢のゲストヴォーカリストがタキシード姿で陰鬱な葬送行進曲を歌った。これにびっくりしたレイヴキッズや困惑した観客が数十人ほど隣のテント(Fatboy Slimが出演中)に移動したが、それを我慢して、あるいは好奇心を抱いてテントに残った者たちは我慢してよかったと思ったはずだ。Sigur Rosのライヴは、全部を見ると驚き以外の何物でもなかった。ボーイソプラノのような信じられない高音を持つリードシンガーJon Thor Birgissonは、ファルセットで悲嘆を歌い上げ、ギターを弓で弾いていた。後ろでは4人の弦楽器奏者が遠吠えのような声を上げるのだが、奇妙なことにこれが、不安を覚えるほど美しかったのだ。あえてたとえるなら、Cocteau Twinsと『OK Computer』のころのRadiohead、そして『Disintegration』時代のCureとLowが、共作でAlfred Hitchcockの映画のサウンドトラックを作ったところを想像していただきたい。すべては雄大でありながらミニマリズム的で、ささやき声のように静かでありながら轟音のように響く。呆然としたひとりの観客が、この霊的で異様な音楽を表す適切な単語を探り当てようとして「コレハ、ナントイウ種類ノ音楽デスカ?」と片言の英語で尋ねた。だれも答えられなかった。唖然とした別の観客は「びっくりだよ」と答えるのがやっとだった。
夜もこの時間になると、残念なことに大物出演者の出番が重なっていて難しい選択を迫られることになる。自分のクローンを作らないかぎり、Jane's AddictionとFatboy Slim、Chemical BrothersとTrickyをすべて見ることは不可能なのだ。そこで、Jane's Addictionの4年ぶりのコンサートを選んだ人が多かったのは不思議ではない。彼らが10年前に始めた「ロラパルーザ」は、多数のアーティストが出演するこの種の音楽祭の先駆けと言えるもので、その後の音楽祭の手本となって一連の流れを生み出した。
Jane's Addictionの演出は、まちがいなくコーチェラで最も派手だった。まずは、不気味なプラスティックの木々に蛍光色の紙の花が咲く手の込んだステージセット。ステージのあちこちで大道芸人集団、Circque Du Soleilの頭のヘンな道化たちが、細い竹馬に乗ってよろよろ歩いている。関節が逆に曲がるセクシーな美女たちは、木の妖精の葉っぱやチアリーダーのスカート、あるいはストリッパーのスパンコールとバタフライを着けて、そこらじゅうで跳ね回ったり同性愛に身悶えていた(注:Jane's Addictionが裸同然の女性ダンサーを起用しても、Motley Crueのレヴューとちがってアートに見えてしまうのはなぜだろう)。
フロントマンのPerry Farrellは、以前と変わらず無類のショーマンだった。彼は命知らずのバイク野郎、Evel Knievelのようないくつもジッパーのあるパンツスーツと、羽根飾り付きのいかがわしい帽子(“Been Caught Stealing”を歌うとき、この衣装一式を盗んで捕まったと彼は言った)という出で立ち。そんな彼がステージに立っていると、バックアップのダンサーたちがかすんでしまうほどだ。彼はまた、David Lee Roth的な冗談を連発し、西海岸は「1番いいものが1番ある1番の海岸」で、コーチェラには「セクシーな女がいっぱい来てる」と言ってニヤッと笑った。
オリジナルのベーシスト、Eric Averyの代役にPorno for PyrosのMartyn Le Nobleを迎えたJane's Addictionはヒット曲をノンストップで演奏した(“Mountain Song”“Nothing's Shocking”“Stop”“Classic Girl”“Ain't No Right”“Ocean Size”、そして観客待望の“Jane Says”はカリプソにアレンジされていた)。彼らは、これらの曲の半分のあいだメインステージにいて、残り半分では観客席のなかに設置されたサテライトステージに移動した(後ろの方から、遠いステージのアリみたいな出演者を見つめて目が疲れていた観客はこれで楽になっただろう)。サテライトステージでの最後の曲“Been Caught Stealing”の演奏中、Red Hot Chili PeppersのFlea('97年のJane's Addiction再結成ツアーにベーシストとして参加)がメインステージに登場すると、観客が大歓声で彼を迎えた。Fleaが長いベースソロを弾いているあいだ、Jane's Addictionのメンバーは一列に並んでコンガを踊りながらメインステージへ。最後に全員で7分間の“Ted, Just Admit It”を演奏しているときも、Perry FarrellのせいでFleaがかすんでいた。いや、この曲ではFarrellが派手な銀ラメの舞台装置に変身して、彼自身も姿を消したように見えた。それは、会場全体の照明不足を補って余るほどまぶしかった。
最後にふさわしいそんな光景を見たあとは、近くにあるベストウェスタンホテルの24時間営業の熱い風呂に頭から飛び込む以外、すべきことは残っていなかった。 By Lyndsey Parker/LAUNCH.com |