【今さら聞けない楽器のア・ソ・コ】お題「パンデイロ」
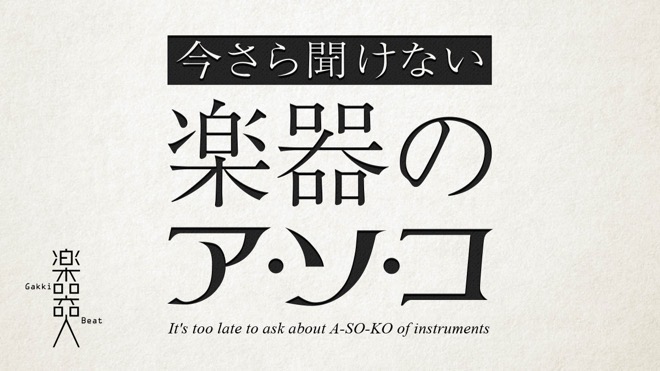
“楽器”と一口に言っても、多種多様さまざまな部品から構成されているのはご存知の通り。え、そうなの?的なものから、世界の民族楽器まで、今さら人には聞けない“楽器のア・ソ・コ”、ご紹介します。記念すべき第100回のお題は「パンデイロ」です。
◆ ◆ ◆

パンデイロはブラジルのフレームドラム。プラチネイラといわれる金属円盤(鈴、ジングルとも)の響きが通常のタンバリンよりも少なく、細かなリズムを明瞭に出せることが特徴のひとつ。またタンバリンのジングルは皿を背中合わせにして重ねられており大きな音がするが、パンデイロは逆に皿を伏せた向きで重ね合わせてある。さらに皮の張力を変化させて、音の高さを変えることができるため、高音、中音、低音を利用し、さまざまなリズムの表現が可能。その一方でレガートの表現が難しいため4ビートを表現しづらい点も。
演奏するジャンルやスタイルによって大きさやヘッドの材質も異なり、ショーロでは10インチ程度で軽い木枠、ヘッドは山羊の革のものを、サンバなどでは10~12インチで合板枠で、ヘッドはナイロン/プラヘッドのものがよく利用される。
カーニバル・パレードでは、パンデイロはスルドが発明されるまで、最も低い音としてサンバの基礎的な楽器だったことでも知られる。その後さまざまな楽器が発明・使用され、打楽器隊の人数が増加すると、周りの楽器の大音量で、パンデイロ本来の演奏が活かされなくなった。そのためマラバリスタ(ジャグリング、曲芸師)のようにパフォーマンス用として使われることが大きくなった。
文・編集部
◆【今さら聞けない楽器のア・ソ・コ】まとめページ