【インタビュー】Koochewsen、バンド名の表記を変え最新のものを見せ続ける決意に満ちた最新音源「your TV/English man」

Koochewsenの最新音源「your TV/English man」が、6月15日にリリースされる。独自のダンス感覚を活かして“マニアックなのに、驚くほどキャッチー”という楽曲に仕上げた「your TV」、センシティヴな世界を巧みにを創り上げている「English man」ともに完成度が高く、彼らのファンならずとも必聴といえる。前作「ヴィーナスの恋人/深海魚のマーチ」から4ヶ月強という短いスパンのリリース(両作共に配信限定シングル)でいながら、新たな顔を見せていることも見逃せない。バンドの状態が良好なことを感じさせるKoochewsenのメンバー4人に集まってもらって、現在のKoochewsenについて大いに語ってもらった。
また、前シングル「ヴィーナスの恋人/深海魚のマーチ」が、5月28日からストリーミング配信開始。さらにすでに公開されている「your TV」のMVに続き、「English man」のMVも新たに公開されている。
◆Koochewsen~画像&映像~
■「your TV」はメッセージ性みたいなものは考えていなくて
■浮かび上がってくる世界や情景を楽しんでもらえれば
――新しいシングル「your TV/English man」を作るにあたって、テーマなどはありましたか?
小林リヨ:なかったです。いつもそうですけど、僕達は音源を作る時にテーマやコンセプトを決めることはなくて。日々曲を作って、いろんな曲ができあがっている中で、今のタイミングで出したいなと思ったのが「your TV」と「English man」の2曲でした。
網走ぱうろ:僕らが出してきているアルバムは、コンセプトがあるように感じると思うんですよ。でも、作る前にコンセプトとかがあったわけではなくて。その時に出したいものをチョイスして作品にしたら、コンセプトがあるような感じになっていたんです。実は、深く考えているわけではないという(笑)。
――自然体でリリースされているんですね。では、「your TV」の話からいきましょう。「your TV」はテクノに通じる無機質かつ幻想的な歌中とサイケデリックなサビ・パートのコントラストが印象的なナンバーです。
小林リヨ:この曲の構想は、2016年くらいからあった気がする。なぜかわからないけど、“your TV my TV”と連呼したいという気持ちがあって、それを形にしたという感じです。元々は、すごく不穏というか観ている人を置き去りにするような映画を撮るデヴィッド・リンチという映画監督がいて、こういうことを音楽で表現したいなと思って。形をいろいろ変えていって、今の形に収まりました。形を変えたのは、作っている時にMVにするということを意識しだしたっていうのがあります。アニメーションのMVにしたいなと思ったんですよ。それを念頭に置いたアレンジにしたし、サイズが短いのもアニメーションで長いMVを作るのはお金が掛かるし、アニメーターさんが大変そうだからというのが理由です(笑)。
――サイズが短いことは、凝縮感に繋がっています。「your TV」は、テレビという虚構の世界と現実の狭間を漂っているような感覚の歌詞も注目です。
小林リヨ:歌詞は、言いたいことがあるようで何もないんですよ(笑)。テレビ批判だと捉える人がいるかもしれないけど、そうではなくて。強いて言うならば、“俺のテレビがあって、お前のテレビもあるよな”というだけです。メッセージ性みたいなものは考えていなくて、歌詞も含めて面白い曲になったら良いなと思っていて。それで、自分の手癖を並べていったら、こうなったという感じです。なので、それぞれが歌詞を読むことで浮かび上がってくる世界や情景を楽しんでもらえればと思います。
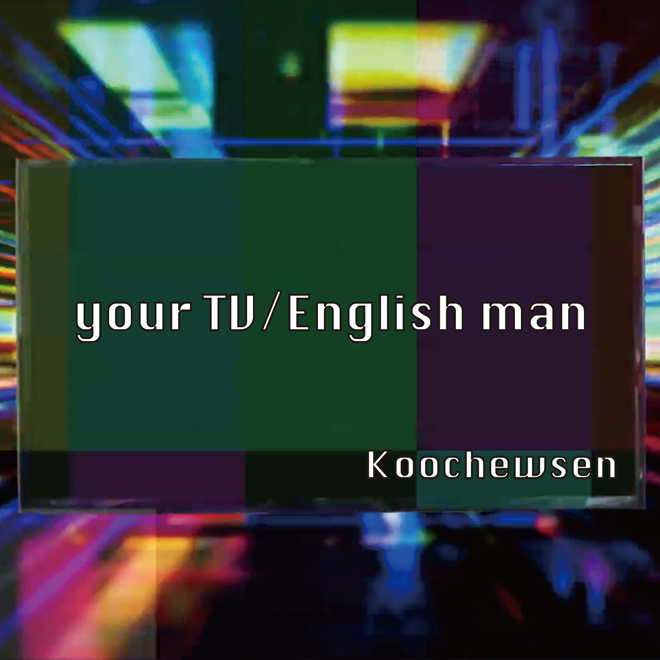
――聴く時のリスナーの状態によっても印象は変わって、いろいろなイマジネーションを楽しめると思います。では、「your TV」のレコーディングは、いかがでしたか?
ベントラーカオル:この曲はKoochewsenには珍しく、レコーディングの直前まで“これっ!”という形にならなかったんです。レコーディングのギリギリまで、みんなで面白がりながら、とにかくメチャクチャにするという作業をしていましたね。今までバンドとして使わなかった機材的なアプローチもしましたし、実はこの曲はギターの音が一切入っていないんですよ。
――サビ・パートでギターのコードが鳴っていませんか?
ベントラーカオル:いえ、あれもギターではなくてシンセです。
小林リヨ:ギターを一切入れないということは考えていましたね。この曲はライブの時にハンドマイクで歌いたいなと思っていたんです。
ベントラーカオル:そう。それを実現させるために三人がサンプラーを使うという(笑)。あとは、バンドとして初めてカットアップ(録った音を切り貼りすること)も使いました。最後のサビに入る前の直前のキメは、ベースは生では絶対にできないようにしたよね?
西平匠杜:そう(笑)。
ベントラーカオル:キメの最後の“ダカダカッ!”というスネアだけが生で、そこからまたバンドの演奏に戻っていくという。そういう新しい勢いのつけ方をしたりとか。そんな風にして録っていって完成させて、実際にライブで演奏することになった時に、初めて誰がどの音を出すかという役割分担を真剣に検討しました。

▲小林リヨ
――キーボード単体で見てもシンセ系の音色とトラディショナルなオルガンの音を同時に鳴らすというセンスの良さが光っています。
ベントラーカオル:ビンテージ感のあるエレピやオルガンの音と、もうちょっとクラブ・ミュージック寄りな音の組合せというのは、今のトレンドじゃないかなというのがあって。それで、そういう手法も採り入れてみました。
網走ぱうろ:僕はこの曲を最初に聴いた時に、'80Sニューウェイブ的なところを2018年に持ってきた感じだなという印象を受けたんです。XTCとか、邦楽でいうと平沢進(P-MODEL)さんとかの匂いがあるし、あの当時のSF感とかもあるなと思って。そういうところで、ドラムはマシン的なところとサビの肉感のコントラストを、どう出すかというのがあって。サビは、マーチングっぽいパターンを叩いていますが、そこはレコーディングの時に、リヨさんから結構言われました。「もっと来て。もっと来れない?」みたいな感じで(笑)。それで、“なにくそ!”と思ってがんばりました(笑)。
小林リヨ:あのフレーズは、リハでもだいぶ詰めたよな?
網走ぱうろ:詰めたね。
小林リヨ:打ち込みを多用しているので、生々しいパートとの対比を過激に出したいというのがあったんです。“人力キターッ!”みたいな感じを出したかったんですよね。
網走ぱうろ:この曲は、まったく異なる要素を同居させて一つの曲に昇華するということが大きなテーマとしてあって。一番“人らしさ”が出るのがサビなので、入念にアプローチしたんです。他のパートはある意味、無機質なダンスビートで、いかに躍らせるかというのがあって、パットを使った打ち込みとかもしたんですよ。そのぶん、サビは“人感”を凝縮しました。

▲西平匠社(タクト)
――人らしさを出すと同時に、曲中の情景創りをドラムも担う形になっています。
網走ぱうろ:それは、意識していました。だから、そう感じてもらえたなら良かったです。
西平匠杜:僕は、この曲を初めて聴いた時に、めちゃくちゃテンションが上がりました。打ち込みを多用しているから、もし自分が生のベースを弾くことで世界観が変わってしまうなら弾かなくても良いかな…くらいに思った。それくらい衝撃を受けましたね。この曲のベースはドラムと同じで、肉感的なサビと、それ以外のカッチリしたパートのコントラストをどう出すかということがポイントとしてあった。そこから生まれる歪(いびつ)な感じを出すのが面白かったし、ベースにディレイを掛けて“ドゥーン!”とスライド・ダウンするフレーズを効果音的に入れたりしたんです。
ベントラーカオル:ヒップホップなどで、シンベを使って多用する手法ですよね。そういう要素を入れたくて、やってもらいました。
網走ぱうろ:あのベースは、すごくカッコいいよね。今までそういうベースのアプローチはなかったから、すごく新鮮でした。
西平匠杜:それに、ベースを弾くだけじゃなくてサンプラーも使って、この曲のレコーディングはすごく楽しかったです。
小林リヨ:歌は、オート・チューンを使ったのは多分初めてですね。あとは、歌中のラップに驚いたとよく言われるけど、曲を作っていく中で音を聴いてラップをやりたいなと思ったんです。だから、僕の中では自然な流れでしたね。2017年に出した『愛のクウチュウ戦』(2017.6.14 release)でもちょっとラップをしたけど、もっと音階があってメロディアスなラップだったのに対して、今回はよりラップっぽくなっています。ラップは実際にやってみて気づいたけど、自由度が高いんですよね。メロディーに合わせて言葉を乗せるよりも言葉を詰め込めるし、メロディーを歌うよりもいろんなことができる。それは、デカかったですね。それに、聴いてくれた人が歌詞カードを見なくても何を言っているのかがちゃんとわかるラップということも意識しました。
――サビの突き刺さるような歌との対比も効いています。
小林リヨ:サビは、もう気持ち良く歌ったという感じですね。それだけです。
◆インタビュー(2)へ
この記事の関連情報
【インタビュー】「DAM CHANNEL」20代目MCに森 香澄、サポートMCにチャンカワイが就任「プライベートな部分も引き出せたら」
2024年3月のDAM HOT!アーティストはアーバンギャルド、フジタカコら4組
【イベントレポート】<ビッグエコー35周年記念カラオケグランプリ>決勝大会が大盛況。応募4,061件の頂点決定
2024年2月のDAM HOT!アーティストはOHTORA、我生ら4組
2024年1月のDAM HOT!アーティストRKID'z、EINSHTEINら3組
2023年12月のDAM HOT!アーティストは学芸大青春、the paddlesら4組
2023年11月のDAM HOT!アーティストはACE COLLECTION、3markets[ ]ら4組
T-BOLANのメンバーと一緒のステージで歌えるチャンス、大好評実施中
2023年10月のDAM HOT!アーティストはNORTH、グラビティら4組