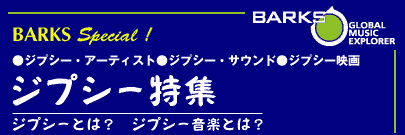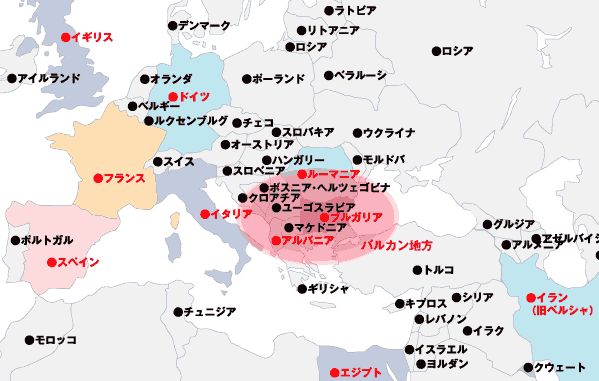『Essences』(エッセンシズ)
Tonino Baliardo(トニーノ・バリアルド)
エピック・インターナショナル ESCA-8323
2001年5月30日発売 2,520(tax in)
|
| 今年の日本の夏は、ちょっとしたジプシー・ブーム。
5月末から公開されていたトニー・ガトリフのフラメンコ映画「ベンゴ」に続いて、同じくガトリフのジプシー音楽ロード・ムーヴィ「ラッチョ・ドローム」や、あのホアキン・コルテスが主演したマヌエル・パラシオス監督の「ジターノ」が上映される。
また音楽の方も、7月にはジプシー・キングスの全国公演に続いて、8月後半から9月初旬にかけては<ジプシー・サマー>と銘打たれたコンサート・シリーズが開催される。昨年の初来日公演が大反響を巻き起こしたルーマニアの“義賊楽団”タラフ・ドゥ・ハイドゥークスをメインに、マケドニアのブラスバンド/コチャニ・オーケスター、そして同じくマケドニアの国民的人気歌手/エスマといった実力派のジプシー・ミュージシャンたちが大挙来日、東欧系ジプシー音楽の精髄を見せてくれるはずだ。
こうしたジプシー・ブームは、日本に限ったことではなく、近年欧米各地で巻き起こっているわけだが、その先導役を務めたのは、ユーゴスラヴィアのエミール・クストリッツァ監督による「ジプシーのとき」「アンダーグラウンド」「黒猫・白猫」、あるいはトニー・ガトリフ監督の「ラッチョ・ドローム」「ガッジョ・ディーロ」「ベンゴ」といった一連のジプシー関連映画だった。
そしてその気運の中でタラフ~などの東欧系バンドも急速に注目を集めるようになり、様々なCDが相次いでリリースされるようになったわけだが、特に一番人気のタラフ~は、山本耀司のパリ・コレにモデル兼ミュージシャンとして出演したり、また映画「ザ・マン・フー・クライド」(日本では今秋公開予定)でジョニー・デップと共演したりと、ちょっとしたアイドル扱いにもなっている。
一番驚いているのは、これまで長年にわたり、差別され蔑まれてきた彼ら自身だろう。
元々ジプシーという名称は、英語のエジプト人(エジプシャン)がなまったものである。16世紀、この肌が浅黒くエキゾチックな身なりをした放浪民の一団が初めてイギリスに姿を現した時、彼ら自ら「小エジプト(現在のバルカン半島南部地域)から来た」と説明したのが、こういう名称の元になったらしい。
ヨーロッパやペルシャの古い文献、あるいは言語学的推察によれば、現在ジプシーと呼ばれる人々の源は、インド北西部にあると考えられている。紀元10世紀頃に、そこからある群集が西進し、中近東を経て、バルカン~東欧に入り、15世紀ぐらいにはイギリスからフランス、スペインなどに到達、そこから更に北アフリカ諸国や南北アメリカ大陸にまで移動、放浪が続いたというのが、最も有力な説だ。
フランスでは“ジタン”、スペインでは“ヒターノ”、イタリアでは“ツィガーヌ”、ドイツでは“ツィゴイネル”と呼ばれているが、それらには差別的ニュアンスが少なくない(実際彼らの歴史は虐殺や迫害などの連続だった)ことから、近年では、政治的・人権的配慮の下、彼ら自身の呼称である「ロム(ロマ)=人間」が統一名称として用いられることが多い。
彼らは約一千年の間、熊使いや馬喰、冶金、占い、そして楽士などを代々の生業にしつつ、行く先々の土地で様々な文化的要素を取り入れ、独自の表現様式をフレキシブルに創造・継承してきた。
特に、音楽的才能には秀でている。
たとえばスペインのフラメンコは、遥かインドから継承してきた歌や踊りをベースに、アンダルシア地方のイスラム文化やスペイン古来の文化などがミックスされて出来あがったものだ。ジプシーは、現地の文化への同化を拒む侵入者、部外者でありながら一方では、今や消滅したその土地固有の伝統文化を継承していたりもする逆説的存在でもあったわけで、結局、この侵入者、触媒、保存・継承者としての多層的・多面的な在り方そのものが、ジプシー文化の醍醐味、神髄と言っていいのだろう。
先日来日したトニー・ガトリフの発言はとても印象深い。
「ジプシー文化の魅力をひとことで言えば、自由ということだ。ジプシーは生き方も自由だし音楽も自由だ。楽譜もリハーサルもないから、好きなように演奏できる。間違った音も出したいように出せるし即興もできる。ジプシー音楽は、リズムも音階も多くのものを抱合しており、そこに豊かさがある。ジプシー文化とは、つまり世界文化なんだ」 |
|