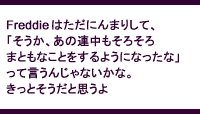| ようやくにしてQueenに然るべき敬意が表されつつある。Aerosmith、Steely Dan、Paul Simon、Michael Jacksonらと並んで、ロックンロールの殿堂にその名を連ねようとしているのだ。授賞式でベーシストのJohn Deacon、ドラマーのRoger Taylor、そしてギタリストのBrian Mayが、'91年に亡くなったFreddie Mercuryの不在を惜しむだろうことは間違いない。
Queenはバンド名を冠したデビュー作を'73年に発表して以来、複数の名ライヴ盤を含めて17を超えるアルバムを世に送り出してきた。LAUNCHは先頃、ロックの殿堂入りやFreddie Mercuryについて、そしてイギリスのポップアイドル、Robbie Williams(!)とのツアーあるいはプロジェクトの可能性について、さらにはファンに対するQueenの忠誠やQueenに対するファンの忠誠について、Brian Mayから話を聞いた。
――ノミネートについては、どう伝えられたんですか?
BRIAN :
マネージャーと電話で話していた時に、「あぁ、そう言えば君たちは殿堂入りするんだよ」と言われたんだ。はっきり言って、イギリスにいるとあまりよくわからなくてね。こちらでは大きく報道されていないから、それがどういうものなのか世間もよくは知らないし。だから、今まで僕らがかなり失望していたものと思われていたようだけど、実はそうでもなかったんだよ。とはいえ、聞いた時は本当に嬉しかった。他の受賞者のリストを見れば気分は上々さ。Michael JacksonにAerosmithとくれば、みんな僕の昔からの仲間じゃないか。彼らと同じ扱いというのは、まったくもって嬉しいことだ。
――クリーヴランドにあるロックの殿堂を訪れたことはありますか?
BRIAN :
いや、ないんだ。一度、僕らから寄贈をしたことはあるけれど、実際に行く機会はなかった。ぜひ、行ってみたいね。
――ロックの殿堂委員会の面々が、Queenの何をもってノミネートを決めたのだと思いますか? あなた方のように評壇の受けが芳しくないバンドに対して、彼らはおよび腰になりがちなんですが。
BRIAN :
面白い質問だが、それは僕にはわからないよ。僕らが……、RogerとJohnとFreddieと僕が相手にしてきたのは、僕らのとっての現実、つまりショウに来てくれたり、レコードを買ってくれたりする人たちだけだったからね。僕らが評論家の類と友達だったとは思えないし、彼らに好かれていたとも、彼らを好いていたとも思えない。今回投票した委員会にも、評論家やジャーナリスト的な要素はあるんだろうが、代がわりしているから僕にはあまり馴染みのない顔ぶれだろう。そういう人たちが僕らの何を認めたのかと問われれば、こんなに遠く離れたところから想像するに、僕らの純粋な努力、純粋なインスピレーションということだろうか。
Queenについて他にどんな意見があろうとも、とにかく僕らは20年間、オーディエンスに対して徹底的に尽くしてきたんだから。今だって多少かたちは違うものの、尽くし続けているけど、あの年月に関してはそれこそツアーをしてアルバムを作ることが僕らの人生だった。もっとも、それをとことん楽しんでもいたんだけど。
――ロックの殿堂の授賞式では、ステージでの演奏が慣習になっていますが、Freddie Mercuryのヴォーカルに恥じない人材は思い当たりますか?
BRIAN :
いろいろな考えがあるとは思う。Aerosmithと共演できたらいいだろうな。これは僕が前から考えていながら、なかなか実現しなかったことでもあるんだ。他にもあれこれ話はしているよ。噂もたくさん出回っているが、いずれを認めることも僕はしない(笑)。あいつら、いい加減だからね。イギリスでは何でも活字にしてしまう。アメリカではどうか知らないが、イギリスのマスコミは真実よりも偽りを記事にすることのほうが多いんだよ、まったく。
――Queenの残りのメンバーがRobbie Williamsと組むという大きな噂がありますが、真実の程は?
BRIAN :
本当のことを言おう。Robbieとは話をしているし、共演もしている。いいやつでね。お互い、いろいろなアイデアを出し合ってはいるよ。ただし、まだ何も確定していない。彼は素晴らしいエンターテナーで、近年イギリスから登場した中では“本格派”と呼んでいい数少ないうちのひとりだと僕は思う。ああした……ちゃんと歌えるやつはなかなかいないからね。最近じゃ、ただ歌えるということすら珍しくなってしまった。格好ばっかりの連中が多い中、彼は歌えて、そして観客を楽しませることができる。非常に勇敢な男で、世間の臆測を裏切るところが多いというのもいい。その点、Freddieに通じるものがあるんだ。勇気さ。自分を信じる勇気。とはいえ、さっきも言ったように今の段階では何をする予定もないよ。
編集部註: 実際には授賞式では、Brian MayとRoger Taylorのヴォーカルによる“We Will Rock You”、さらにFoo FightersのDave Grohlを招いて彼のヴォーカルによる“Tie Your Mother Down”が演奏された(3月21日付ニュース参照)。
――Freddieになり代わって何を言うわけにもいかないとは思いますが、Queenがロックの殿堂入りを果たすと聞いたら、彼は何と言うでしょうね。
BRIAN :
Freddieはただにんまりして、「そうか、あの連中もそろそろまともなことをするようになったな」って言うんじゃないかな(笑)。彼ならきっとそうだと思うよ。暖炉の上にトロフィや盾をずらりと並べられる僕らは本当に幸運だけど、真に意味があるのは、実際に演奏したり、実際に反応を得たり、実際にレコードを作ったりしている瞬間だったんだ。僕らにとって大事なのは――別に賞をもらうのが嬉しくないということではないけど――やはり自分たちが何より好きなことを実際に“やる”ことだった。たぶんFreddieも、「行ったほうがいいかな? うん、行こうか」って言うはずだよ(笑)。
――さて、あなたの近況は?
BRIAN :
どんどん忙しくなっていくようで、今はしっかり手綱を締めているんだ。Queenの最盛期には不可能だった、バランスの取れた生活というのを最近は心掛けているんでね。あの頃はひたすら消耗するばかりで、私生活にいささか差し障りがあったというのが正直なところだから。あれからいくらか自分の時間を取り戻しつつ、基本的にはずっと忙しくしているよ。『Furier』という、ヨーロッパでは公開済みでイギリスでも最近公開された映画のサウンドトラックを手掛けたんだが、これがアートっぽい映画でね。フランス語だからアメリカで一般公開されるかどうかは疑わしいけど、僕としては自信作なんだ。映画では『Highlander/ハイランダー』や『Flash Gordon/フラッシュ・ゴードン』などなど、断片的にはずいぶん曲を書いてきたけど、ここではサウンドトラックを全て手掛けている。
他にもいろいろとやっていて、中でも最近は不思議とブルースの仕事が多かった。自分でもブルースに立ち返ってみたいという思いがあって、それでいろんな人と共演していたんだけれど、それがソロアルバムではなくて、いくつかのプロジェクトというかたちで日の目を見ることになりそうだよ。今のところ大きなものとしては――音楽とは直接関係がないから変に思うだろうけど――実はプロデューサーとして動いていて、僕が長年情熱を傾けてきた題材を扱う映画を友達と一緒に製作中なんだ。どういうものかはここでは教えられないが、一種の歴史映画で、できる限り正確かつ正直に歴史の記録を正そうというもの。長期にわたるプロジェクトで、取りかかって1年くらいになる。複数のスタジオと話もしているし、目下のところ僕にとって一番の情熱の矛先はこれなんだ。
――音楽の世界での経験と比べて、映画のプロデューサーというのはどう違いますか?
BRIAN :
非常に大きな世界だし、自分が今まで歩いてきたのとは違う道だという点で、謙虚な気持ちにさせられるというのはあるね。僕は映画界からもある程度の敬意を表してもらっていて、それはありがたいことだけど、必ずしも全ての扉があらかじめ開かれているとは限らないだろう? 努力が必要だ。僕の友人というのはBBCの放送作家だから、2人ともいわば一番下のレベルからスタートして、果たして自分たちのアイデアで世間を楽しませることができるかどうか、やってみようというわけさ。
――長期にわたるプロジェクトということですが、どれくらいかかるんでしょうか?
BRIAN :
まぁ、1年半のうちにはシューティングに入れるかもしれないな。そうなってもらいたいよ。シューティングって映画の撮影のことで、人を撃つんじゃないからね。それは、よっぽどのことがない限りあり得ない(笑)。
――最近、どんな新しいバンドに心を動かされましたか?
BRIAN :
やはりFoo Fightersは挙げておかないと……。改めて訊かれると、いつも困るんだ。曲を聴いた時は良いと思っても名前を覚えてなくて……あ、Spacehogとかね。
――Queenの音楽やベスト盤が続々とリリースされることについて、あなたの考えは?
BRIAN :
レコード会社との関係は良好だから、そのコントロールは僕らの手中にあるに等しいんだ。僕らにはレコード会社が2つあって、ロサンゼルスのHollywood Recordsが全米を網羅し、その他の国についてはEMIと組んでいる。契約書には、僕らがおおよそ成り行きを指図できるものと書かれてあって、対立することもあまりない。所属レコード会社を憎んでいる人が多い中、僕らはずっと、極めて恵まれてきたんだよ。もちろん話し合いはするが、やり過ぎず、趣味のいいものであれば、いくつか企画物を出すのもいいんじゃないかと僕は思っている。それに、昔のものを新しいオーディエンスに提供するチャンスがあれば……、うん、僕は賛成だ。何も支障はない。度を越したものや、趣味の悪いものになると困るけれど。
――現時点であなたは、自分の人生でやるべきことは全てやったと思いますか?
BRIAN :
やり尽くしていないことは必ずあるものだよ。あのバンド……かつて僕がいたバンド、つまりQueenの実績は心から誇りに思っているし、その後に自分がやったこともそれなりに誇らしいけれど、やりたいことは何しろたくさんあるんでね。完璧な曲を書きたいという思いは常にあるし、これは何も僕が最初に言い出したことでもないだろうが、とにかく人はさらに遠くへ足を伸ばし、新たな地平を拓きたいと思うものらしい。そういう情熱にかけては以前と変わらないね。
それに、新しい顔ぶれと仕事をするのもまた楽しいものだ。Foo Fightersとの仕事はとてもやり甲斐があって興奮もしたし、興味深く新たな体験だった。それに何といっても楽しかった。思わぬ収穫のひとつだね。ネガティヴな部分も当然あって、僕らを嫌いだという人たちは何をやっても嫌いなんだろう。それはそれで受け入れるしかない。しかし、優れた人たち、ヒーローとされる人たちと繋がりがあるなんて、ひどくスリリングなことじゃないか。僕がその気持ちを忘れることはなさそうだ。きっと、ずっと少年のままなんだよ。いつだって僕は、コンサートやレコーディングスタジオにわくわくしながら出かけて行く少年のような気持ちでいるんだ。 |