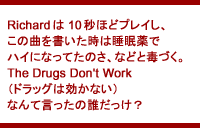| スーパースター・グループから人気のリードシンガーが抜けてソロになると、過去の音楽的関係をすべて断ち切ろうとすることが多い。つらい別れをしたガールフレンドの写真や思い出のものを全部燃やしてしまうのと同じ。だが、そうした極端な過去の精算はややもすると裏目に出るものだ。シンガーがライヴで昔の曲を歌うのを頑として拒否したり、インタヴューで前のバンドのことはしゃべらないと言っても、やはり、長年のファンはデビューからヒットするまでの経緯を忘れないからである。それどころか、かつてのバンドを蔑んだりすれば、かえってファンを逃してしまうことにもなりかねない。さらに、昔のグループほど成功できないかもしれないという不安から、過去を拒絶するしかないと考えているような印象を与えてしまう。
一方、この逆の例として、過去の栄光から踏み出すのが怖いあまり、ソロになっても昔のヒット曲ばかりライヴで歌う元リードシンガーもいる。その結果、自身のソロ作品は過小評価され、早々にVH1の『Where Are They Now?(あの人は今どこに?)』にでも招かれそうな、過去の人と思われてしまうのである。過去と現在を結ぶ危ない綱をうまく渡り、バンド当時の曲にソロワークと同じく新しい雰囲気を与え、ソロワークも過去の名曲と同じく優れた曲にしていくタイプは滅多にいないものなのだ。
その滅多にいないひとりがRichard Ashcroftである。元Verveというイギリスのサイケポップ・バンドのフロントマンでありシャーマンだった彼なら、バンドメンバーがバックについていようといまいと、今後も成功するだろう。ただ、2月3日のハリウッド、Knitting Factory Westでのパフォーマンスは、Verveを伴ったL.A.でのコンサートの出来ほどではなかった。その主な理由は、アコースティックギターを抱えた彼が、ステージ中央のマイクスタンドからまったく動かなかったことにある。このため、お馴染みのオルタモントのヒッピーよろしく狂気に取りつかれたような行動を見せられなかったのだ(残念なことに、精神分裂気味のナンセンスな言葉もなければ、あの長くしなやかなサルのような腕を振り回すことも、Robert Smithのような指芸もなかった)。とはいえ、その一風変わったスターらしいパワーで充分楽しませてくれたし、ソロの曲も、彼が真のスターであるばかりか、真のアーティストであることを証明してくれたのである。
以前の曲も新曲も、同じように丁寧に時間をかけて歌ったのが良かった。“Sonnet”“Lucky Man”“Velvet Morning”といったVerve時代の素晴らしく感動的なバラードから、現状にぴったりなタイトルのソロアルバム『Alone With Everybody』 に収録された“On A Beach”“I Get My Beat”“You On My Mind In My Sleep”のような美しいナンバーまで上手くこなしていく。人気バンドを抜けてソロになったシンガーが出すアルバムは、たいてい影が薄いものなのだ(Ian BrownやDavid Lee Roth、Joe Strummer、Stingでさえそうだ)。それに比べ、Richardの新曲は、Verveの傑作“The Drugs Don't Work”や“On Your Own”と肩を並べるほどの出来である。
確かにノリに欠ける部分もあった。なにしろ曲は全部けだるいテンポばかりで、Richardも気ままに始めたりやめたりし、曲の途中でギターを変えることさえあった。それにステージでは、あの狂った魔術師あるいは変人学者のような行動がまったく見られなかった。時折、Jerry Springer(素人暴露トークショウの司会者)のように怒鳴るのが緊張感をかもしだし、もしかして、この静かなセミアコースティック・ショウが冷血なカオスへ変わるのではないかと期待を抱かせる。
例えば、“Lucky Man”の途中で急にギターを弾く手を止め、理由もなく「このクソッタレ!」などと喚いたり、観客をわざとからかって「B面の終わりでも弾いてやろうか」と言ったかと思うと、“Never Wanna See You Cry”を10秒ほどやり、この曲を書いた時は睡眠薬でハイになってたのさ、などと毒づく(The Drugs Don't Work=ドラッグは効かない、なんて言ってたのは誰だっけ?)。あるいは曲の合間に、ざわついている下品な客に癇癪をおこして怒鳴り散らす(これは当然だ)。「雑音の中でもなんとか耳を凝らしてる観客のためにやってんだぞ。テメエら、さっさと出てって払戻しでもしてもらいな。くだらねえフットボールの話ばかりしてるテメエらのために歌う身にもなってみろ!」(これには喝采の声があがったが、依然として雑談を続ける図々しい連中もいたのには呆れる。また、それをものともせず歌いまくったRichardに敬意を表す)。
ただ、Richardの怒りを買った無礼な連中は少数で、満席の観客の大半は1曲1曲にうっとりと聴き惚れているか、感極まって叫んでいるかだった。Verveの“Space And Time”と“The Drugs Don't Work”は特に、観客との掛け合いが楽しい。Cheap Trickの『Budokan』に入っている“I Want You To Want Me”のようで、ファンの熱狂がRichardの散漫なパフォーマンスを活気(=verve)づけているといえる。昼寝から目覚めたばかりのジャンキーのような、だるい態度も見られたパフォーマンスでは、ファンの熱狂は確かにありがたい。
90分のコンサートは最後に気合の入ったパフォーマンスで終わった。それはソロになっての曲“New York”だ。エンディングで『Kill City』スタイルの延々と続くサキソフォン・ジャムに突入したが、辛うじて退屈になるのを免れた。Richardは義務的にアンコールに現れ、うっとりするようなシングル“A Song For The Lovers”をプレイ。彼独特の甘く柔らかなヴォーカルを最高に引き立てる曲だ。続いてソロのB面“Leave Me High”と、Verveの預言的なデビューアルバム『A Storm In Heaven』収録の初めての自作曲“See You In The Next One (Have A Good Time)”。この曲の歌詞は、ショウのオープニング曲“Brave New World”のリフレイン「I hope I see you on the other side」に似ており、ここで終われば最初と最後がちょうど一対となるところだったが、あと1曲、誰もが待っている曲がある……。
そう“Bitter Sweet Symphony”だ。Richard は、Verveの大ブレイクとなったこの曲を、Andrew Loog Oldham に捧げると苦々しく紹介。言わずと知れたRolling Stonesとレコーディングしたオーケストラ指揮者である。MickとKeithによる“The Last Time”を彼がオーケストラヴァージョンにしたものが、ループサンプルとして“Bitter Sweet Symphony”に使われたのだ。このサンプリングは著作権をめぐる泥仕合となり、不可解なことにVerveはこのスマッシュヒットからまったく印税をもらえないという判決になった。「オレにはあの金の権利がねえってさ!」と文句を言い、一度Oldhamの野郎にごあいさつしてやんなきゃな、とか何とか半分マジでつぶやいてから、Richardはガハハと笑う。「まったくLenny Bruce(辛らつなことで有名なコメディアン)みたいな言いぐさになっちまって、やだね」。
そして、その曲をやっと、Oldhamのサンプルなしでプレイした。あのヴァイオリンなしでは確かにある種の壮麗さに欠けるものの、最小限のバックでRichardの甘いヴォーカルが歌う印象的なメロディは、何と言おうと“Bitter Sweet Symphony”の成功がStonesからの1フレーズだけに拠るものではあり得ないことを証明している。そろそろ保留となっている印税が払われてしかるべきだろう……。
だが、Richardはそれほど気にする必要はない。Verveとしても充分成功しただろうが、ソロとなった彼が今のような上昇気流に乗っていれば、印税は将来もっと大量に入ってくるに違いないからだ。 |