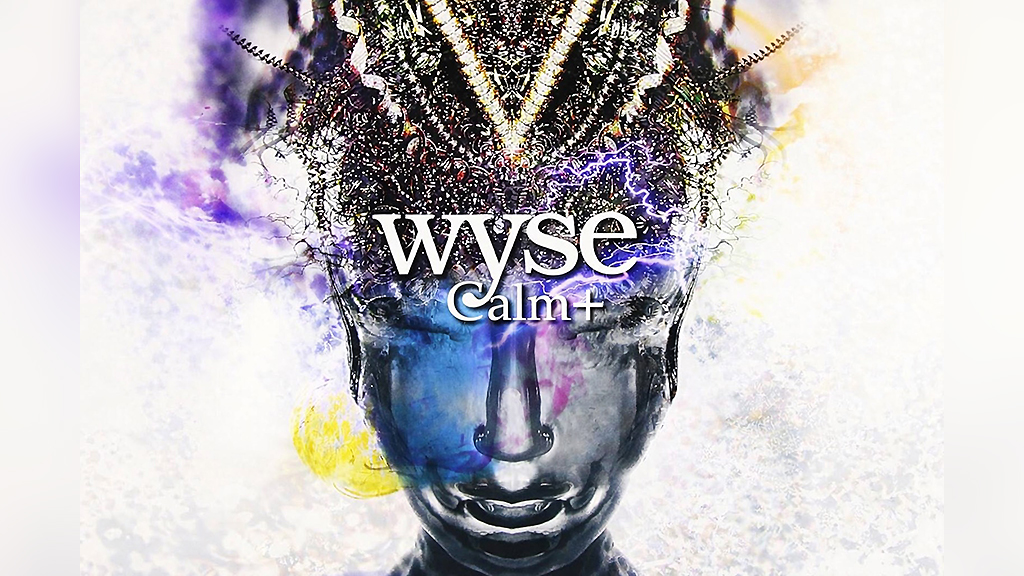【インタビュー】wyse、過去を洗練する2026年ツアー<Calm+>の意図を語る「もっと火を強くしていく」

本日2月14日、バンド結成27周年を迎えたwyseが、これを記念して東京・新宿ReNYにて昼夜二公演のライブ<結成記念日公演『27の奇跡』>を開催した。積み重ねてきた27年という年月のなかで、現在のwyseこそ過去最高の状態にあるという言葉が今回のインタビューでも語られているが、それを証明するような飛び切りのサウンドとパフォーマンスと熱量が会場に充満した祝祭感溢れる1日となった。
wyseは2025年、自身の出発点に立ち返るべくインディーズ期の楽曲再生ツアー<1999-2001>を開催したほか、1990年〜2000年代のV系バンド集結による一大イベント<CROSS ROAD Fest>に出演するなど、原点に向き合い、刺激的な日々を経てきた。そこで揺さぶられ、想像もしていなかった気づきや発見が得られたという。結成27周年記念公演で発売されたライブ音源『Live Tour 2025『1999-2001』Live CD』には、その高揚感や多幸感までも詰め込まれている。
そして2026年のwyseは、5月30日から全国8ヵ所を廻るツアー<wyse Live Tour 2026『Calm+』>を開催することが本日発表となった。同ツアーはwyseがメジャーフィールドで活躍するキッカケとなったアルバム『Calm』(2002年)にフォーカスした内容になるとのこと。過去を検証し、未来のwyseへと繋げていく新たな旅の始まりだ。BARKSは、月森 (Vo)、TAKUMA (2nd Vo, B)、HIRO (G)、MORI (G)の4人のメンバーに、瑞々しさを伴って生まれた強く熱い想いを余すことなく語ってもらった。
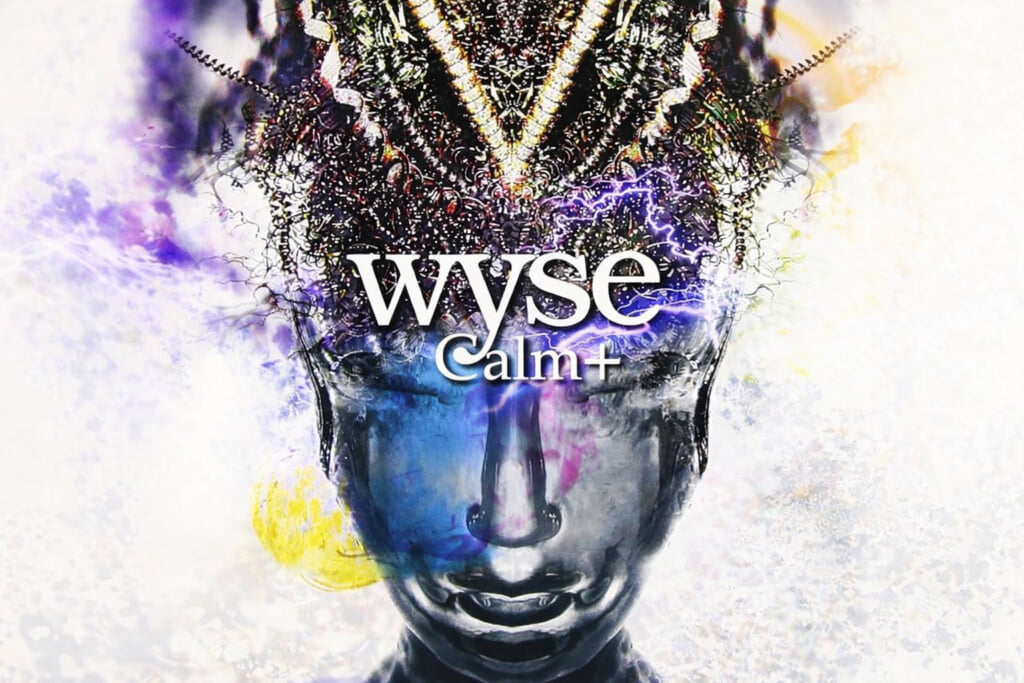
◆ ◆ ◆
■2025年の活動があったからこそ
■信じる気持ちがさらに強くなった
──2026年の話をする前に、まずwyseの2025年を振り返ってお聞きしたいのですが、11月に幕張メッセ イベントホールで開催された<CROSS ROAD Fest>に参加したことはバンドにどんな影響を及ぼしましたか?
MORI:最初にお話をいただいた時は、参加するバンドが同世代だったり、先輩にあたる方ばかりで、共演が楽しみだなと。それとwyseには広い会場が似合うという想いがずっとあったので、みんなに知ってもらえる良い機会だなと思っていました。ライブ後には「wyseのことは知っていましたがライブは初めて見ました」とか「結成当初以来、久しぶりに見ました」っていうメッセージもたくさんいただいて。規模の大きいイベントだからこそ得られたことだったので、いいキッカケになりました。
──HIROさんは会場の景色を見てどんなことを感じましたか?
HIRO:MORIも言ったように、wyseは大きい会場でも魅力を発揮できるバンドだと思っていたんですが、いざステージに立ったら、幕張メッセは想像以上に大きくて度肝を抜かれました。でも、ライブが始まってみると緊張することもなく、何より皆さんが温かく迎えてくれていることが伝わってきたので、“これは楽しむしかないな”と。初めて生のwyseを見た方や、久しぶりにwyseを見たという方もたくさんいらっしゃったので、見たことがある方にはパワーアップしたwyseを届けられたと思いますし、初めて見た方にも今の自分たちを知ってもらえて良かったなと思っています。あんな機会がいただけたことに感謝です。

──今後のモチベーションにもなった大きな意味を持つライブでした?
HIRO:そうですね。いつか、ワンマンであのステージに立ちたいという夢も抱けたので、意義は大きかったですね。
TAKUMA:あれだけの数のお客さんがいて、“楽しみたい”という気持ちもたくさん集まる空間だと思っていたので、wyseのステージはもちろん、イベントとしてもいかに楽しんで帰っていただけるかが重要だなと思っていました。そういう意味でも2日目トップバッターとしての役割を考えて臨みました。先輩方や同世代のバンドと共演できるのも刺激的ではありましたが、だからこそ、一番手を務める身としては、“いい日になってほしい” “いい日だったなって思いながら帰ってほしい”という気持ちをベースに、その上でステージ作りを考えました。結果、いろんな角度から僕らも楽しめたし、得るものもすごく大きかったですね。自分たちの可能性、作ってきた楽曲、長くやってきたからこそ持てる自信、そういうものを手放しちゃいけないと改めて強く確認できましたね。wyseというバンドの芯にグサッとくる刺激をもらった1日でした。
月森 : 久々の大きな会場で、たくさんのお客さんの前に立つイベントでしたが、個人的には会場がどの規模でも、映える映えないはあれど、歌や演奏に優劣がついてはいけないと思っているので、今のwyseができることをしっかりやりとげて、そのうえで自分も楽しむ。そういう日だろうと思っていたし、その通りに自分たちの出番は終えられたんじゃないかと思っています。その後、久しぶりに他のアーティストの方々のパフォーマンスをフロアに降りて全て見させていただいて、そこで感じたことを全部持ち帰って、ひとりで飲みながら自問自答のループを繰り返したりしていましたね。そうしたら、TAKUMAから電話があって、お互いにイベントから持ち帰ったものを伝え合ったり、どう思ったか、どうしていきたいのかとか、それこそ久しぶりにできたその長電話が、もしかしたら一番良い時間だったかもしれません。

──<CROSS ROAD Fest>を挟んで開催したwyseインディーズ時代の楽曲再生ツアー<Live Tour 2025『1999–2001』>もバンドにとって大きな収穫があったと思います。そのファイナルを収録したライブ音源が本日2月14日にリリースされたわけですが、そもそもこのようなツアーをやろうと思った経緯を教えてください。
TAKUMA:wyseは2024年に25周年を迎えたんですが、一連の活動が終わりに差し掛かる頃には“次はどうなっていくんだろう。何をしよう”と思うぐらい、自分たちにとって比重が大きい年だったんですね。周年が終わった時、一回空っぽになったというか、リセットされた感覚があったんです。
──ええ。
TAKUMA:そんな中、新しい楽曲を作って未来のwyseを提示する方法もあるけど、そうじゃないなって。周年の活動で感謝だったり、いろいろな気持ちを受け取ったからこそ、自分たちの歴史をもう一回振り返ってみたいと思ったんです。これまで歩んできた道には大切なものがちゃんとあるので、そこにもう一度触れてみることで、気づけるものもあるかもしれない。過去に戻るという意味ではなく、向き合うことで掴めるものがあると思ったのが、インディーズ時代をテーマとしたツアーをやろうと思ったキッカケです。
──当時のアレンジのまま演奏したスペシャルなツアーでしたが、これはどなたからの提案だったんですか?
TAKUMA:メンバー全員がそういうモードでした。後にリテイクバージョンとしてリリースした曲たちもありますが、そもそもwyseってライブのたびに少しずつ曲のアレンジが自然と変わってきたバンドなんです。その公演や演出によっても、曲の構成とかポイントポイントにアレンジを加えたり。たとえば始まり方とか終わり方とかね。常に“今”に照準を合わせて活動してきた。でも、25周年を終えて次に向かうテーマが見えた時に「当時のアレンジじゃないと意味なくない?」って。
HIRO:<1999–2001>という大きなコンセプトがありましたからね。その時期のwyseの楽曲を演奏するっていう。ファンの方々がライブの内容を想像しやすいタイトルを掲げているので、当時のアレンジで演奏することは、話さずとも暗黙の了解だったと思います。未来に向かって前のめりに進んでいくのも、過去に向き合ってみるのも、進むことには変わりはないし、そのほうが今後、自分たちの足跡を辿って大事にしながら歩んでいけるんじゃないかって。

──ツアー中に蘇ってきた想いや新たな発見、受け取ったものもあったのではないでしょうか?
MORI:コンセプトを打ち立ててからは、自宅で過去の曲を聴き直している時や、リハーサルでみんなで合わせている時も含め、瞬間瞬間で気づきや学びがありました。ツアー中に感じる熱も声援も想像を超えるもので、<CROSS ROAD Fest>も、ツアー完結編となった12月のファイナル(東京・Veats Shibuya公演)も、全て揺さぶられましたね。2025年の活動があったからこそ、みんなを信じる気持ちがさらに強くなったし、wyseを他のバンドのファンの方々や共演するバンドのメンバーの方たちにも見てほしいと思う気持ちがより強くなりました。
──そういう気持ちになったのは久しぶりのことですか?
MORI:個人的にはそうかもしれないですね。気づかないうちに思考が凝り固まっていたというか。自分たちが引っ張って前に進んでいくことにとらわれていたことも、頭が硬くなっていた要因のひとつだったのかなって。もっと気持ちをみんなに委ねたり、一緒に乗せていってもいいんじゃないかっていう気づきがあった1年でもありました。
HIRO:さっき「過去に向き合ってみるのも」という話をしたんですが、僕はそこで“何か見つけないとダメだな”って思っていたんです。もちろん“今ならこう弾くよ”っていう思いもありますけど、今後自分がどういうアーティストになっていきたいのか考えた時に、昔の自分にヒントがあるんじゃないかと。あらためて聴くと一番衝撃的なのはテンポでしたね。全曲速いんですよ(笑)。
──BPM(曲の速さ)ですか。
HIRO:そうなんですよ。“何をそんなに生き急いでいたんだろう?”って。でも、それがあの頃の鼓動で、そういうビート感で生きていたんだろうなと思いました。なので、当時の切迫したテンポそのままは再現しないまでも、熱量や感情は落とし込めるはずだと思って臨んでいましたね。

──実際、ライブを見て、その熱量とエネルギーに圧倒されました。月森さんはどんなことをツアーで感じましたか?
月森:アレンジや演奏、歌い方も進化している現在形があるんです。それがインディーズ時代の曲に絞って、それを昔のアレンジで構築すること自体が、僕にとっては挑戦でした。歌に関していうと、発声の仕方も違うし、年月を重ねて声も変わっている。昔の歌い方や声を知っている人がツアーに来てくれた時に、“ああ、こうだった!”と思ってもらえるぐらい、昔の自分に近づけることが大変でしたね。インディーズ時代は発声の仕方も全然わかっていなかったので、1本ライブをすると声が出ないぐらいにかすれてたんですよ。それがまたカッコいい部分もあったのかもしれないけれど。
──若さゆえに突っ走るみたいな?
月森:発声法を確立した今は、あの頃と同じことはできないんですけど。それでも観に来てくれた人が“こんな歌い方を再現してくれるんだ!”って感じられるぐらい、どこまで過去の自分に向き合えるかが課題でした。どこまで再現できたかはわからないですが、ファンの方々も僕らが表現したいことを理解して、一緒にライヴを作り上げてくれたので、ツアーが進むにつれて会場の熱量が増していったし、自分が挑戦したかったことを受け取ってもらえたのかなと。