【コラム】BARKS烏丸哲也の音楽業界裏話045「202×年、LuckyFesにAIが登場した瞬間を妄想する」
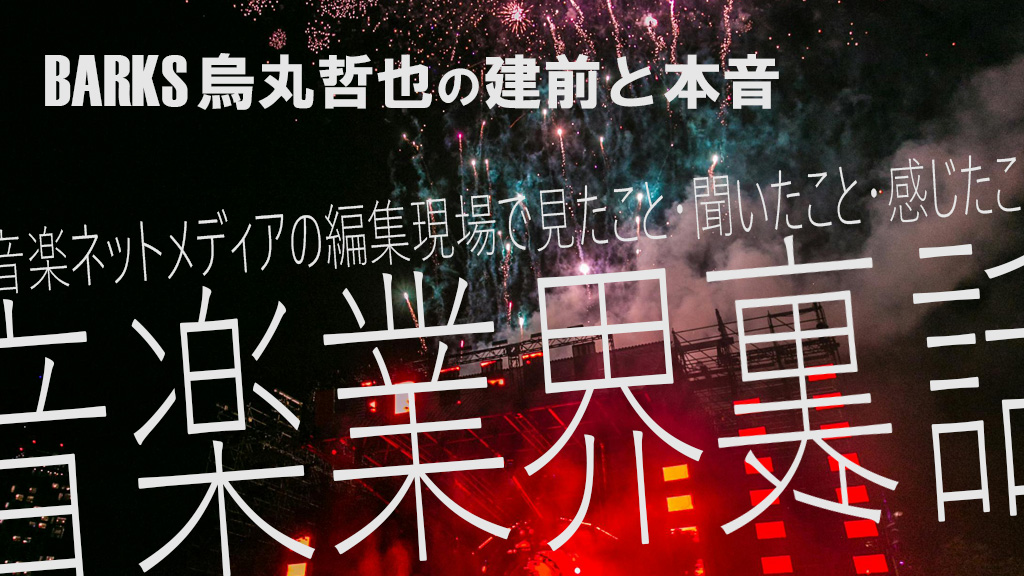
ステージからはギターが轟音に鳴り、ドラムが腹に響き、オーディエンスが拳を振り上げる。音が鳴っているだけなのに、どうして私たちは泣きそうになるのか。生演奏に身を浸すとドーパミンとセロトニンが一気に噴き上がるからだ。フェス会場で隣人と腕を振り上げればオキシトシンが放出され、見知らぬ者同士で肩を組んで笑ってしまう。そういった化学連鎖は、最新の神経科学によって裏付けられている生理現象のひとつでもある。
脳内ホルモンだけではない。共同体験の同期は、呼吸や心拍、そしてステップさえも揃えてしまう。結果、「また来年ここで会おう」という合言葉がその場をかけがえのない宝島へと変貌させる。それがフェスってやつだ。
音楽体験は記憶と結びつき、時に人生を更新する。「波形」を「快楽」「喜び」に変換する脳という知覚装置をベタ踏みできれば、音楽は人生最大級のエンタメ・エンジンになる。そしてそのベタ踏み装置こそ「ライブ」「フェス」だと私は思っている。
ネット上の映像やサブスクでいくらでも音楽は楽しめるのに、なぜわざわざチケットを買って混雑の中を出かけていくのか? それは「他人と一緒に体験する」ことが想像以上に「脳に効く」からなのだろう。人間の脳は「音」と「人」にめっぽう弱いとみえる。多様性が叫ばれる個の時代に「誰かと同じリズムで揺れる」ことがどれだけ貴重で尊いことなのかは、コロナ禍を通して再確認したことでもある。いわばフェスは、推しの音楽を聴く場であると同時に「ひとりじゃない」を確認しに行く場所だ。もちろんファミリーの絆にも欠かせない。
さて、ここからは近未来の妄想話。
202×年夏、某ひたちなかで開催された実験的なフェスの一幕。AI DJが、リアルタイムに観客の動き・歓声・SNSの反応を解析し、BPMや選曲を変化させながらプレイを行った。BPMに合わせて手を上げ、光るリストバンドが同期し、ビジョンに映し出されたリアルタイム・レンダリング映像が酩酊感を加速させ、カメラが笑顔の熱狂を判定する。視覚と聴覚と運動性の快感が噛み合い、かつてない刺激的な体験が会場を包みこんだ。観客がノるのではなく、AIにノらされる時代の到来だ。

とは言え、観客のノリを読み取り「ノリを生み出すプレイ」を逆算しフィードバックするというこの演出は、これまで行われてきた「演者と音/照明を操るエンジニアとの連携プレイ」を、巨大なスケールでAIが真似てみたものにすぎない。
同じ空間を共有し同じグルーブに身体を寄せる。皆が共鳴し思いが共振することが「フェスの快楽」だけれども、それを最大化させるのはアルゴリズムだという事実は、なかなかシュールな状況だ。「エモーショナルな展開」を統計的に予測し「過去の感動」に似た構造を設計する。「この曲順なら泣く」「このタイミングで転調すれば感動する」というパターンは、既に読み取られている。
…でも、その楽しさの主体は誰なんだろう。
AIが奏でたクライマックスで我々が涙したとしたら、それは「仕組まれた感動」なのか? それとも「感動した自分こそが真実」なのか? ライブは、ステージ上のミュージシャンがどんなふうに曲を届けるかを体感するところだ。ノイズもミスも演者の身体から発されるからこそ、僕らは共感し拳を挙げる。涙腺がゆるむ。Tシャツが汗で重くなる。
演者が人ではなくAIだとしても、脳の心地よさを最大化するアルゴリズムで攻められれば、僕らはきっと涙を流してしまうんだろう。人間はそのようにできている。おそらく人は、警戒しながらも徐々にAIにノるようになる。まるで自動車やスマホに慣れていったように、便利さと快適さの中で自然に溶け込んできたように。
突発的なシンガロング、予定外のアンコール。あるいは歌詞を間違えて爆笑が起きる瞬間、機材トラブルによる不完全な音響状態…そういう不確定性の連鎖はフェスという場のダイナミズムを生んできた。その場の空気ごと未来に持ち帰れるような記憶の爆心地として震わせた感動は、予定調和のスケジュールや演出では作れない。
「間違える自由」は、まだ僕らの手の中にある。感情を司るホルモンという微量要素のコントロールをアルゴリズムに任せてしまうのは、人間の尊厳を失うことなのだろうか。30万年の人類進化の歴史を振り返っても体験したことのない、対応しきれないほどの激震が目の前に迫っている。
さあ、アーティストたちよ。AIを単なるツールとして使い倒し、そのクリエイティビティをAIの力で具現化させてくれないか。僕らを救うのは、AIじゃなくてアーティストなんだから。

文◎BARKS 烏丸哲也







