“心の化身”…普遍的真実の探求

Liveのカリスマ的シンガー・ソングライター、Edward Kowalczykは、“新時代のポップ・グル”というレッテルを貼られることを嫌う。 にもかかわらず、彼の詞の世界にしみ込んでいる精神世界への忠誠心は、実際にそれを体に彫り込んでしまうほど彼の存在と深く結びついている。 …というのは、私がニューヨーク市のIrving Plazaで初めてEdに会ったとき、彼の首の後ろあたりに、一節の言葉を彫り込んだタトゥーを発見したからだ。その言葉がどういう意味なのか彼に尋ねると 「実際は僕が教えを受けている導師のマントラでね」 だがそのことに触れた以外には、この28歳の「自称スピリチュアリスト」はそうした彼の個人的習練について詳しく語ることを丁重に断るのだった。 「すべての道はさまざまな形で真実につながっている、と僕は心から信じているんだ。何年ものあいだ僕は、普遍性が歌詞の前面に出るようにいつも心を注いできた。いま歴史のこの瞬間に、とても重要なことだと思えるのは、人々が互いの違いではなく互いの類似性を見るようになり始めていることなんだ」 普遍的な愛のメッセージ、そして彼個人の信条を加えずにまっさらの真実を探求すること。それは、Liveの4作目のフルアルバム『The Distance To Here』の曲を書くにあたってKowalczykの「大きな目標」だった。 ロスにあるKowalczykの自宅で行なわれたこのインタビューの中で、彼は『The Distance To Here』でLiveが到達した新境地について語った。 |
LAUNCH: どういったいきさつから、精神世界に関心を持ち始めたのですか。またその精神性をLiveの音楽にどう取り入れていったのか教えてください。 ED: たしか18歳ぐらいの頃に興味を覚えるようになって、あらゆる東洋思想や精神的な教えにのめり込み始めたんだ。僕は、実に長きにわたってこの道を歩んできたよ。特に今回のアルバムでは、世界中の人々が僕らの曲を聴いて自分自身のための何かを見出すことができるように、(歌詞を)普遍的にしようと本当に努力した。これは、実は前のアルバムから学んだ教訓だった。 作詞家として僕が一番興味を持ってるのは、根源的な感情や人間性を伝えることなんだ。『The Distance To Here』でも、僕のメッセージのありのままが歌詞から伝わるように、本当に心を砕いたよ。 僕のメッセージは、究極的には普遍性があって精神を高揚させるものだと思うんだけど、スリランカの人、オーストラリアの人、シカゴの人、あるいはドイツの人、どこの誰もがみんな、僕の歌詞から何かを得られるようにしたかったんだ。 LAUNCH: Liveは『Throwing Copper』では驚異的な成功を収めましたが、それに比べると『Secret Samadhi』は今ひとつでした。この作品がLiveにしては成功しなかったことについて、どう考えていますか。また、あのアルバムを作ったことでバンドが得たものは。 ED: “サマディ”(瞑想の状態)という言葉を使ったのは、個人的にはとても大事なことだったんだ。でもある意味では、その言葉の意味を知らない大部分の人々と僕らを隔てることにもなった。だけどあのアルバムは、コンセプトにしても他のどんな面でも、多くの人々が求めてた『Throwing Copper』のパート2にするつもりなどまったくなかった。あれは、あの時点でバンドとして作らなければならない作品だったと僕は思っている。あのとき僕らは、ミュージシャンとしてあるいはソングライターとして進歩したいと感じていたんだよ。僕個人のことを言えば、作詞家として、『Mental Jewelry』や『Throwing Copper』での“メッセージのある男”というイメージからしばらく逃れようとしていたところがあったね。あれは成長のためのレコードだった。バンドの中で、納得できるレベルを探し求めていたんだ。 LAUNCH: では、前作と比べて『The Distance To Here』はどうですか。 ED: 『The Distance To Here』を作って、Liveはバンドとして達成感を強く感じた。Liveでいることに満足できる場所を自分たちの中に見出すことができたっていうかね。今のLiveは、途方もないエネルギーに溢れていて、同時に、大きな安定感と強さがある。初期の頃の切迫感を取り戻して、しかも曲は以前より良くなってる。曲が良くなったのは、『Secret Samadhi』で実験と進歩を自らに課して、「Lakini's Juice」みたいな曲を作ったことで前進した成果だと思うよ。『The Distance To Here』の中の「Where Fishes Go」「Voodoo Lady」「The Distance」といった曲は、Liveにとってはまったく新しいもので、これまでとは全然違うスタイルやアレンジを取り入れてみたんだ。
by Gail Worley |
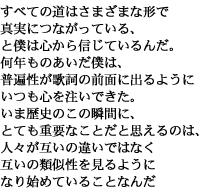 LAUNCH:
LAUNCH: