【インタビュー】バンドマンであり楽曲提供者でもあるエンドウ.からみた、著作権のあれこれ
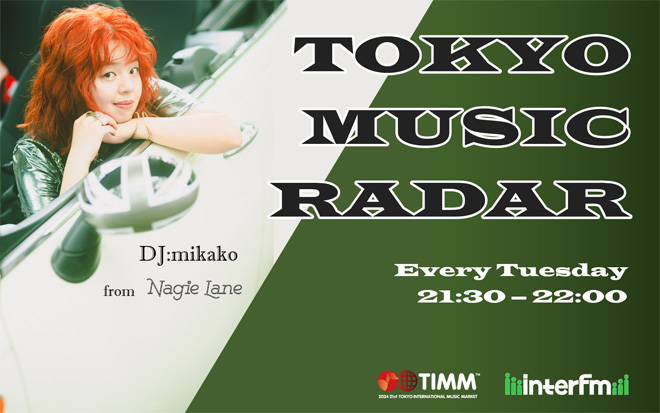
毎週火曜日よる9:30~10:00に放送されているInterFMのミュージックプログラム「TOKYO MUSIC RADAR」では、日本の音楽シーンを担う様々なゲスト/アーティストが登場し、貴重なトークが繰り広げられているが、今回登場するのはGEEKSのG&Voを務めるエンドウ.氏だ。
GEEKSの活動のみならず月蝕會議のバンマスでもあるミュージシャンの彼だが、作詞・作曲・編曲を始め音楽プロデューサーとして活動するのみならず、一般社団法人 日本音楽作家団体協議会の常任理事を務め、さらに2022年からは一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)の理事をも担う人物でもある。
現役のバンドマンであり様々なシーンで楽曲を提供するミュージシャンでありながら、同時にあらゆる人々へ著作権への理解を深める活動を行う立場にもある、そんな貴重な存在となるエンドウ.氏から、知っているようで知らない著作権の真実をわかりやすく紐解いてもらった。

左から、mikako、エンドウ.
──(mikako)アーティストでありながらJASRACの理事を務めたりと多岐にわたる活動をされていらっしゃいますが、そもそも理事になられたきっかけは何だったんですか?
エンドウ.:著作権に興味があったんです。そもそもアーティストとして音楽活動をしているんですけど、「もっとお金が欲しいな」「印税とかもっともらいたいんだけどな」と思って、昔JASRACに電話したんですよ。
──(mikako)JASRACに電話?
エンドウ.:そう。「もっと欲しいんですけど、どうしたらいいんですか」みたいなことを言ったら、色々教えてくれて、自分の権利がどうなって音楽出版社がどうで、あなたの楽曲はJASRACに登録されてて…と教えてもらって、「なるほど、そういう風になってるんですね」というところから興味を持ち始めまして。要は「遊ぶ金欲しさ」がきっかけです、残念なことに(笑)。
──(mikako)私自身もアーティスト活動をしていますけど、よくわかっていないことも多いんです。まず根本的なところなんですが、そもそも著作権ってなんなんでしょう。
エンドウ.:なるほど、いい質問ですね。著作権っていうのは、世界的に「人権のひとつ」だと言われてまして、世界人権宣言とか国際人権規約とかで定められてて、法務省や外務省といったホームページにも載っているんです。もうちょっと平たく言うと、クリエイターにとっては生活の糧としてお金を稼ぐ手段…知的財産というものですね。
──(mikako)知的財産、ですね。
エンドウ.:著作権って「いろんなことを禁止する権利」なんですよ。勝手に使っちゃいけない、勝手に変えちゃいけない、勝手に展示しちゃいけない、勝手に譲渡しちゃいけないとか、作り手=権利者が様々なことを制限できる権利ですね。要は創作物を守るための権利なんです。
──(mikako)なるほど、大事なところですね。
エンドウ.:アーティストの稼ぎを守るという点でも大事ですし、そもそも自分の作品を我が子のように愛している方ばかりですから、それを保護するためには非常に大事なものなんです。
──(mikako)今では一般の方も様々な発信ができる時代ですから、権利関係にもいろんな影響が出てきますよね?
エンドウ.:いろんな曲を扱えるようになっちゃったので、著作権的には法律違反が山ほど起こりまくっていると感じます。皆さんは悪気なく悪意なくやっているので、そこはちょっと気を付けなきゃいけないところですね。
──(mikako)著作権について気になった時は、JASRACのホームページとかを調べればすぐにわかりますか?
エンドウ.:いや、結構わかんないです(笑)。JASRACってクリエイターから預かった曲の権利を預かり、曲を使いたい人に対して使わせて対価を徴収し、そのお金をクリエイターに還元するという「お金を徴収して分配する組織」なので、「著作権とはなんぞや」とか「専門的なことを教えてくれる組織」ではないんですよね。だから文化庁とかに電話した方がいいかもしれないですね。みんな文化庁著作権課に電話しちゃってください(笑)。
──(mikako)人の声を使って歌わせるような生成AIもあるんですが、音楽制作の現場でもAIは結構使われているんでしょうか。
エンドウ.:使ってますよ。僕自身も使ってますね。最近は「AIを使っている」というと炎上するじゃないですか。みんなデリケートで強いアレルギーがある時期なのかなと思いますけれど、音楽制作現場ではずいぶん前からAIは使われてます。生成AIではなく補助的なAIで、音質をコントロールするイコライジングで「高域をシャリシャリさせる」とか「低域をずんずんさせる」とかでは適切なAIが使われてることがいっぱいあります。あと、僕が楽曲提供をするときは仮歌を入れるんですけれども、これも今はAIの合成音声を使っています。それは歌い手の許諾のもとで販売されているものですね。
──今に始まったことじゃないんですね。
エンドウ.:「すみっコぐらし」を描いているよこみぞゆりさんの「なんでもいきもの」というコンテンツがありまして、このテーマソング「なんものいいじゃん」は作詞・作曲・編曲が全部僕なんですが、イコライジングやコンプなどの音質調整作業でAIは使われていますよ。AIが騒がれる随分前から制作補助ツールとして世に出ているもので、多くの現場でみんな使っていたのでだいぶ浸透していると思いますね。
──(mikako)なるほどそういう時代なんですね。さて著作権に関してですが、一問一答で理解を深めていきたいと思うのですが、お題をいただけますか?
エンドウ.:いいですね、じゃ最初の問題に行きましょう。「結婚式で新郎新婦の入場曲を、有名なアーティストの曲にする」、これはお金が発生するでしょうか。
──(mikako)いや、世の結婚式で全部お金を徴収していることもないと思いますし…これは発生しないんじゃないですか?
エンドウ.:「×」です。発生するんですね。じゃあ、誰が支払うのかって話ですけど、これは式場が支払うお金で、新郎新婦じゃないんです。ただ、そのコスト分を新郎新婦からいただくような式場プランもあるとは思いますけどね。
──(mikako)結婚式で「この曲をかけたい」って時に、それを式場に伝えて式場側がJASRACにOKかどうかを確認するという段取りを踏むんですか?
エンドウ.:確認しなくてもOKなんですよ。JASRACとかNexTone(著作権管理団体)で管理されている曲だったら使っていいんです。後日、式場側が「○○○の曲を使いました」と報告して使用料を支払うかたちです。そしてそのお金はそのアーティストに分配されるんです。
──(mikako)なるほど、わかりました。一問目から「×」をもらっちゃいましたが、次行きましょう。
エンドウ.:問題です。「では、その結婚式で、あるアーティストの曲を新郎新婦もしくは友達が演奏する」、これはお金がかかりますでしょうか。
──(mikako)…んー、さっきの話の流れからすると「かかる」んですかね。
エンドウ.:「○」正解です。かかるんです。場内で音楽を流すのも演奏するのも、楽曲利用という点では全く同じことなんです。では次。「フットサル大会の会場で、観客が盛り上がるようにアーティストの曲を使う」、これはお金がかかるでしょうか。
──(mikako)かかってほしい。
エンドウ.:「○」はい、かかります。イベントとして行われている大会ということで営利ですから、楽曲の利用は先程の式場と同じですね。
──(mikako)だんだんだんわかってきました。
エンドウ.:じゃあ次ですよ。「ラジオで曲をオンエアする」、それにお金はかかるでしょうか。
──(mikako)かかる。
エンドウ.:「○」そうなんです。でもね、mikakoさんが曲を流してもmikakoさんが払う必要はないんですよ。ラジオ局が年間で支払っているんです。どんな曲を流したかは、JASRAC/NexToneのような著作権管理団体に申告して、そこからアーティストに分配される仕組みです。
──(mikako)ラジオ番組によっては、曲をいっぱいかける番組もあったりしますけど、その番組はお金がかかるよねみたいな話になるんですか?
エンドウ.:そうはならないんです。支払う金額は「年間売り上げの何%」と定められて、その額をラジオ局は支払うので。ただ分配は、長くいっぱい使われたらその作家にいっぱい分配されるので、アーティストにとっては、たくさん長く放送してもらったほうが嬉しいですよね。
──(mikako)いいことを聞きました。自分のラジオ番組では自分の曲をいっぱいかけよう(笑)。
エンドウ.:それがいいですよ(笑)。では次行きますね。「YouTubeで、歌ってみた動画を公開した」、これにお金はかかるでしょうか。
──(mikako)YouTubeって広告収入を設定すると収益を得ますけど、その設定をしていなければお金はかからない…かな。
エンドウ.:「×」ですけど、惜しいですね。広告が付く/付かないに関係なくお金を支払う必要があります。ただ、アップロードした皆さんは支払う必要がないんです。なんでかっていうと、YouTube自身がJASRAC/NexToneにお金を払っているから。それで皆さんは無料で音楽を扱えるようになっているんですね。ラジオ局やYouTubeのようにJASRAC/NexToneのような著作権管理団体と包括契約をしてるサービスでは、楽曲は利用し放題です。
──(mikako)だから気にせずカバー動画を上げることができるわけですね。
エンドウ.:カバー動画ならいいんですけど、音源となると著作権とは別の「隣接権」という権利があるので、レコード会社から申し立てがつくことはあります。アーティストの楽曲音源そのものじゃなくて、自分でアコギで弾き語りするとか、自分でカバー音源を作るのであれば安心ですね。
──(mikako)そのあたりは人力でチェックしているんですか?
エンドウ.:YouTubeは全部コンピューターで自動でやってます。
──(mikako)自分で作った曲なのに、申し立てを受けたという話を聞いたことがあるんですが…。
エンドウ.:それはメロディマッチングという技術がありまして、メロディーが同じだとこの曲を利用したと判定されることもあるんです。日本と海外の曲だとルールが違ったりもするので、そこはなかなか難しいところなんですね。
──(mikako)ヒップホップの世界ではサンプリングという文化がありますが、これはどういう考え方になるんですか?
エンドウ.:色々あるんです。ケースバイケースで、共作という形にして元ネタの人が作者として登録されていたり、自分の曲の中でサンプリング元の人の曲が流れたというメドレーという扱いもありますし、音楽出版社の方で登録は全部こちら側にして、サンプリングしているよというクレジットを表記の上、お金の分配をサンプリング元に支払うという方法…つまり権利登録はしていないけど、契約で支払い条件を整えるというやり方もあります。それはもう交渉次第なんですね。
──(mikako)サンプリング元の方との交渉によるものなんですね。
エンドウ.:要は、サンプリングの許諾が取れていればいいわけです。「お金さえくれればなんでもいいよ」っていうスタンスの人も割と多いので、そこをまとめればいい。僕もね、以前、外国のすごく有名な曲のイントロを使わせてもらったことがあります。僕は使いたくなかったんですけど、そういう企画で曲を作ってくれというものだったので。レコード会社がちゃんと許諾を取ったんですけど、印税の75%を持っていかれました。イントロだけなのに…(笑)。
──(mikako)それはなかなかシビアですね。では引き続き一問一答をお願いできますか?

エンドウ.:はい、いきます。「市区町村の主催するチャリティーイベントの会場で楽曲を流したら、お金が発生するでしょうか?」
──(mikako)かかるかな。市区町村っていう時点でちゃんと組織が運営しているものなので、お金が発生します。
エンドウ.:「×」です。というか、ちょっとこのイベントの情報が少なすぎるので補足が必要ですけど、まず「市区町村の主催するするチャリティーイベント」ってことは、おそらく「非営利」なのだろうと判断しました。さらに「入場料も取ってない」んじゃないかなと。チャリティーってことは、原則として「出演者にもギャラが払われてない」「無償でボランティア」で出てたりするんじゃないかなと。
──(mikako)要するに、金銭の発生がない。
エンドウ.:そう、それですと著作権使用料は発生しないんです。
──(mikako)営利か非営利かでだいぶ違ってくるということですか?
エンドウ.:ポイントが3点ありまして、まず「営利か非営利か」、その次に「入場料があるかないか」。最後のハードルとして「演奏者にギャラが払われてるかどうか」。
──(mikako)もし出演料が支払われると?
エンドウ.:著作権料がかかります。要は全部無料だったら著作権使用料は発生しません。これはJASRACのルールではなく著作権法の決まりなんです。権利制限と言いまして「著作権が及ばないよ」っていう考え方です。さて、次の問題ですが「友達の友達を自宅に招待して、その自宅で限定盤のCDをかけて一緒に音楽鑑賞をした」。こちらはいかがでしょう。
──(mikako)金銭発生してないもんね。友達と一緒に楽しく聴いただけだから、かからない。
エンドウ.:「○」、これはかからないですね。当然です。ただね、あんまり音楽著作権法に詳しくない方のイメージだと「鼻歌を歌ったら、JASRACがお金を取り来るぞ」みたいな都市伝説をよく聞きましたけど、当然お金なんか発生しないよ、っていう(笑)。
──(mikako)そこは皆さん安心して。
エンドウ.:お風呂で思いっきり歌って、窓が開いていて外にそれを聴いていた聴衆がいたとしても、お金なんかかかりませんから。
──(mikako)そのお風呂の近くで、YouTube撮影しちゃってた場合は…
エンドウ.:それはYouTubeが払います。じゃあ、この場合はどうでしょうか。「音楽を聴きながら朝の身支度する様子を、SNSで生配信する」。
──(mikako)これは「かかる」んじゃないでしょうか。
エンドウ.:「○」正解です。これはSNS側にお金が発生しますね。YouTubeやInstagram/FacebookであればOK。YouTubeは包括契約をして払っていますから、我々はやりたい放題。…と言っても、原盤(アーティスト音源)には注意しなきゃいけないですよ。レコード会社や原盤の持ち主が「うちの音源はそういうのはダメだよ」って言ったら申し立てがついたりします。著作権的にはOKでも、これは著作隣接権なので権利が違うんですね。
──(mikako)隣接権というのは?
エンドウ.:隣接権は、レコード制作者とか実演家(演奏や歌唱)に与えられる権利なんです。演奏した人の権利、もしくはその録音物を作った人の権利ですよね。著作権はメロディーや詩の権利なんです。これがまた別物でして複雑なんですよ。ただ1点、X(旧Twitter)に関してはJASRACと契約していないので、Xで楽曲を使いたい場合は、個人でJASRACと直接契約する必要があります。とはいえ、ほとんどの方が申請しないままで勝手にやっちゃっている実情がありますので、XとJASRACの協議がずっと続いている状況ですね。
──(mikako)YouTubeではOKでも、それをXに上げるのは…
エンドウ.:原則的にはダメなんです。
──(mikako)アーティストを目指していたり、自分の歌声を広めたい人たちがカバー動画を出すなら、YouTubeやInstagram/Facebookなら大丈夫、ということですね。
エンドウ.:あとは、JASRAC/NexToneの管理楽曲じゃない自分のオリジナル楽曲であれば、もちろんそれは自分次第なので、どんなプラットホームでも自由です。
──(mikako)そうですね。では最後の質問をお願いできますか?
エンドウ.:はい、最終問題です。「店舗を間借りして、1日限定のカレー屋さんを行う時、店内BGMを好きなアーティストの楽曲にした」、これは?
──(mikako)なんか引っ掛けがあります?1日だけ?でも、これはダメでしょう。
エンドウ.:「○」正解です。これは今までの流れと一緒で営利目的ですよね。お客さんがお金を払って食べに来ているという商売なので、そこでBGMを流すときは、ちゃんとお金を払ってくださいということです。
──(mikako)BGMとして、ラジオを流していたらどうなんですか?曲がかかりますよね?
エンドウ.:これがですね、放送に関しては、著作権法の中で特別に分けられていまして、これはOKなんです。中華料理屋さんでテレビが流れているとかありますよね?これもOKなんです。あと、有線放送も別で許諾されているのでOK。
──(mikako)じゃあ、お店で流すならラジオがいいですね。
エンドウ.:ラジオは安心(笑)。

──(mikako)たまにお店で曲が流れてるなと思ったら、ピコン♪って音が入ったりとかして、あれってスマホで流している気がするんですけど、あれは?
エンドウ.:アウトです。もちろんお店がJASRACやNexToneと契約していればいいんですけど、ただ問題はSpotifyやApple Musicを流している場合で、あれはSpotifyやApple Musicとの規約違反になります。「商売目的で流しちゃダメだよ」となっているんですよ。個人で音楽鑑賞するためにその分のお金をもらって提供しているものなので、それを別の商売でBGMとして使うんだったら、それは話が違うよっていうのが基本原則なんです。やっぱりラジオが最強ですね。
──(mikako)ラジオが世界を救いますね(笑)。でも色々気をつけないと知らないうちに法を犯してしまいそうですね。
エンドウ.:そうなんです。譜面もそうですよ。音楽教室だけじゃなくて、学校の部活でも譜面のコピーってダメなんですよ。
──(mikako)え?
エンドウ.:音楽の授業で使う分には大丈夫なんですけど、部活はダメなんです。授業は教育目的なので大丈夫なんですけど、部活って、それはまた別の話になってきちゃって。部活で誰かが持っている楽譜をコピーするのもダメなんです。自分で書き起こした譜面というのも、楽曲を譜面に起こす行為は複製に当たるので、それを自分のためにやるならいいんですけど、家族とかを超えて、他者に配ったりしたら複製権の侵害っていうことになっちゃうんですよね。
──(mikako)ダンス部で、自分で買った曲をダンスに合わせてアレンジして、トラップビートを長めに伸ばしたりして、それを文化祭で披露するみたいな場合はどうなるんですか?
エンドウ.:アレンジ…変えちゃってるんですよね? 著作権の種類にはいろんなものがあるんですけど「同一性保持権」というのがありまして、要は「勝手に変えないで」っていう権利があるんです。「この間奏をこんなに長くされたら、もとの作品と変わってきちゃうから嫌だよ」っていうようことをちゃんと禁止できる権利です。なので、その創作者・著作者にバレて怒られなければ平気かもしれないですけど、「変えないでくれよ」って言われちゃうかもしれない。
──(mikako)じゃあ、単純にその楽曲で踊りたいとなれば?
エンドウ.:ちゃんとJASRAC/NexToneに申請すればOKです。実際に、学園祭や文化祭の季節になるとその利用申請がすごく増えるんですよ。皆さん、ちゃんとやってくれてますね。
──(mikako)先の「同一性保持権」ですが、著作権的にはOKのYouTubeで「歌ってみた動画」をあげた場合、著作権利者がNOと言ったら、ダメになる可能性もあるということですか?
エンドウ.:そうなんですよ。カバーがもうめちゃくちゃバカにしたカバーとか、名誉を毀損するようなふざけたものだったりすると、いくらJASRACが許諾を出していてもレコード会社がOKでも、著作者が嫌だって言ったら、それは止められるんです。そういう権利です。替え歌もそうですね。許す人もいるし1文字も変えないでくれっていう人もいますから、これはもう人それぞれですね。あとね、原盤(アーティスト音源)…例えば有名な楽曲音源とかマイナスワンのカラオケ音源をそのまま使って自分が歌った時にも申し立てがついちゃうことがありますが、実は申し立てがついても、そのまま公開できたりすることがあります。それはYouTubeのルールとして「ブロック」か「マネタイズ」か「トラッキング」が選べるんですね。要は、動画を取り下げさせるか、お金をもらうか、何もしないで見張るかを権利者(レコード会社)が選択できる。マネタイズを選ぶことで、レコード会社に収益がいきますが、その代わり動画はそのまま公開していていいよっていうパターンが1番多いです。もちろんブロックで「もう使わせません」っていう場合もありますが、言われた通りに動画が非公開になっておしまいっていう感じで、何も訴えられたりするものじゃないです。
──(mikako)いろいろありますね。今後の著作権に関して、生成AIの存在によって今後どのような規制やルールが設けられるのでしょうか。
エンドウ.:なかなか予測しづらいんですけれど、AIの技術は止まりません。もう絶対生成AIで音楽が作られるようになりますし、歌うようにもなりますから、求められている制度とか規制は対価還元ですね。つまり、学習したのなら、その学習の元ネタの皆さんにちゃんとお金を払うとか、ですね。
──(mikako)声の主とか?
エンドウ.:声の主もそうですし、例えば僕の曲が学習されていたとしたら、僕にお金が入るべきですし。創作者(著作者)や実演家(歌手/プレイヤー)にも対価が還元される仕組みがないことには、感情的にもなかなか認められないんじゃないかなとは思いますね。
──(mikako)声だけじゃなく、歌い方とかその特徴にもアーティスト性ってありますよね。
エンドウ.:生成AIに学習してほしい人と学習してほしくない人がいるはずですから、ちゃんと自分の意思で選択できるようになるべきかもしれないですね。例えば僕がイヤだったら「学ばれない自由」があると思うんです。もっともっと学ばして僕のセンスを学習してほしいと思えば、「学んでほしい自由」もあると思うんで、これはやっぱり選択できるべきかな。そういう制度がはっきりしてくるといいのかな。
──(mikako)アーティストは表現をしているわけですから、そこを学ばれても対価が支払われないのはやっぱり悔しいですしね。難しいですね。
エンドウ.:サブスクサービスがなかった時代に、いろんな楽曲が無料で聞き放題みたいなサービスが出てきて裁判になったことがあるんですが、でもね、やっていることは今と同じなんです。だけど、今ちゃんと認められているのは、お金がちゃんと還元されているからなんですね。レコード会社や作詞・作曲者、アーティストにちゃんと還元されている。もちろんお金の規模が小さいっていう人もいっぱいいますけど、ちゃんと還元されているので認められてきた。だからAIも、そうやって対価還元の制度とか仕組みができたら、みんな認められていくのかなとも思います。
──(mikako)現段階で、すでに何か改善点のようなポイントはありますか?
エンドウ.:小さなことですけど、絵でも曲でもそうですけど、生成AIで作られたものはそうだと分かるような印…電子透かしがちゃんと入るようにしましょうっていうのは進んでいます。AIであることを偽って人間が作ったかのような発表の仕方をすると、どんどん混乱してお金の流れもおかしくなっていく危険性がありますからね。
──(mikako)まだまだ学ぶべきこともたくさんありそうですね。
エンドウ.:いろんな団体や行政がセミナーなどは開催していて、定期的に繰り返されているんですけど、多くの人には届いていないという現実もあって、これは発信する我々とか行政がちゃんとやらなきゃいけませんし、気になる人も自分から情報を探しに行ってほしいなと思います。それが合わさってようやく広まっていくのかな。
──(mikako)昨今では高校の授業で「情報I」というものもありますから、時代に即した知識や理解を得る授業カリキュラムも増えるといいですね。
エンドウ.:JASRACは「ラーニングスクエア」という出張講座を文化事業としてやっているんです。講師として大学教授とか僕みたいな理事が出向いて著作権の授業をするんです。それ全部無料なんですよ。それで僕も高校によく著作権の授業をしに行っています。申請なども手続きが必要ですけれど、無料で授業を受けられますから、みなさんぜひ利用してください。
──(mikako)それはいいですね。
エンドウ.:学校だけじゃなくて、団体、会社、企業、市区町村とか任意団体とかでもOKですので、ぜひ活用してください。よろしくお願いいたします。
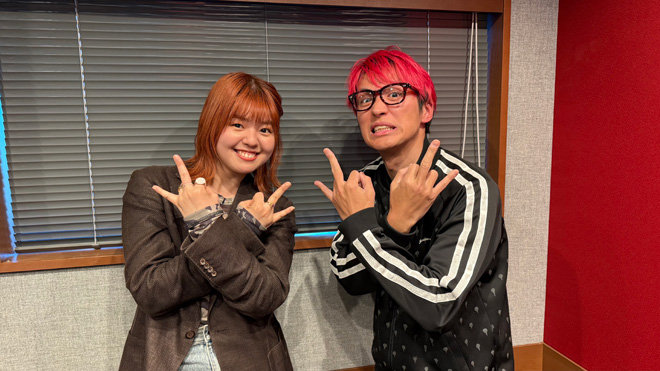
取材◎mikako(Nagie Lane)
文・編集◎烏丸哲也(BARKS)
◆エンドウ.オフィシャルサイト
この記事の関連情報
【インタビュー】Nagie Lane、最小にして強靭に生まれ変わった3声のハーモニー
【インタビュー】Awesome City Club「皆さんと楽しめるお祭りのような1年にしたい」
【インタビュー】CiON遂にデビュー、唯一無二のブラス×アイドル・スタイルで魅了
【インタビュー】カメレオン・ライム・ウーピーパイ「もうヤバいというところまでだらだらして追い込みます」
【インタビュー】MindaRyn「日本大好き、アニソンシンガーになる夢を叶えるために日本に来ました」
【インタビュー】音楽分野における、AIが抱える問題と危険性・可能性[後編]
【インタビュー】音楽分野における、AIの最新事情とその可能性[前編]
【インタビュー】Billboard JAPANチャートから読み解く、日本アーティスト人気の裏側
【インタビュー】2024年の日本の音楽シーン、何が起こったか