【コラム】BARKS烏丸哲也の音楽業界裏話044「音楽に忍び込む錯覚という快感…AIが拓く錯聴の近未来」
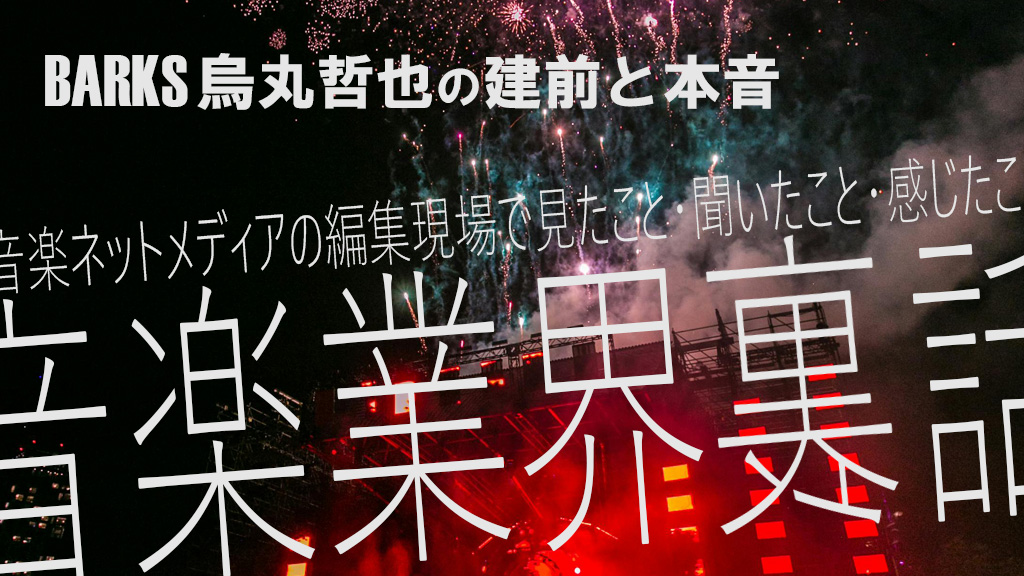
目を閉じて音楽に耳を澄ます。大元は空気振動という物理現象だけれど、僕らはそれを音楽として知覚する。音楽は、耳に届く振動を素材として脳が頭の中で構築する「知覚のドラマ」だ。
実のところ、そこには少なからず錯視ならぬ錯聴(音響錯覚)が存在している。楽器経験者であれば、その楽器の音だけを拾うような聴き方も得意になる。いわゆるカクテルパーティー効果の一例だけれど、流れ込んでくる膨大な音の情報量から、自分にとって重要な情報のみを選択し効率的に情報を処理することもできる。
要は、音源として詰め込まれた膨大な情報から、恣意的にあるいは無意識のうちに何を享受しているのかは、人によってまちまちだ。自分だってその時の気分やコンディションによって変わってしまう。
つまりは、私が聴くこの曲とあなたが聴くその曲は、同じではないかもしれない。というか受ける印象や感じるものは全く違うものになる。そりゃそうよね、音楽なんて好みなんだもん。
ただ脳の性質上、この世界には、聞く者の意識によって変容する「音の蜃気楼」がいくつもある。たとえば、音が永遠に上がり続けているように聞こえる「シェパード・トーン」。レディオヘッド「Like Spinning Plates」で聴けるあれだ。
あるいは「バ」と言っている映像を観ながら「ガ」と聞くと「ダ」と聞こえてしまう「マガーク効果」。視覚から入った情報と聴覚から入った情報にズレがあると脳は必死に正解を見出そうとするけれど、その不整合が新しい体験を生むこともある。宇多田ヒカル「花束を君に」ではリップと歌詞のズレを演出に採り入れることで、「知覚的不安定性」が記憶に残る体験へとつなげ、歌詞の意味に含みを持たせる効果を持たせることに成功した例なのではないか。
音の二重聴取というファントムワードもある。聞く人の意識により「green needle」にも「brainstorm」にも聞こえるような現象は、人間の脳が「意味」を必死に構築しようとする結果生じてしまう、いわば知覚のバグだ。
こうした現象は、かつては心理学や音響学の研究対象にとどまっていた。が、時代は変わった。いまやAIがそれらを分析し、模倣し、さらには創作の武器として解き放つ時代がやってきている。
音楽の現場でも、その萌芽は確かにある。たとえば、シェパード・トーンは映画『ダンケルク』のサウンドトラックやMuseのライブ演出でも使用されてきた。永遠に上昇していくような音は、観客の心拍を上げ、終わりの見えない緊張感を作り出す。これはもはやメロディではなく生理現象を刺激する音の幻覚だ。
ファントムワードのような「どちらとも取れる」音のデザインは、もっと身近なエンタメだ。TikTokで話題になった「Yanny / Laurel」現象のように、音の聞こえ方が人によって分かれることは、SNS時代の拡散性とも相性がいい。「なんて聞こえる?」という問いそのものが音楽の一部になる。AIはこの特性を理解し、意図的に多義的な音声フレーズを生成することが可能だ。
これからの音楽では、こうした錯聴効果がライブ演出やVR空間、パーソナライズされた音楽体験の中でますます活用されていくのだろう。観客の位置や視線、感情状態に応じて音の「聞こえ」が変わる…そんな音の錯覚空間の設計は、もはやフィクションでも絵空事でもなくなった。AIは、脳がだまされる法則を学び、自在にその錯覚を設計することができる。
音楽は振動ではなく錯覚だ。その錯覚こそが人を震わせる。AIが作る未来の音楽は、「何Hzの音を鳴らすか」ではなく「誰の脳がどう錯覚するか」を中心に設計されていくのだろう。そこには「聴こえる」ではなく「感じる」という、これまで以上に刺激的な音楽体験が待っているかもしれない。
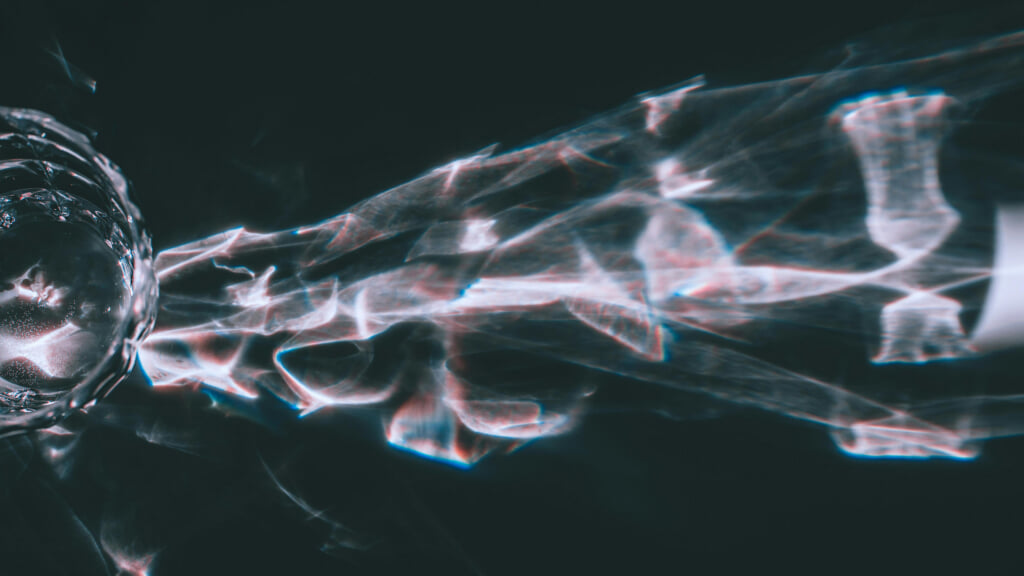
文◎BARKS 烏丸哲也