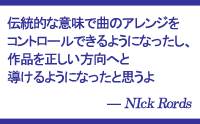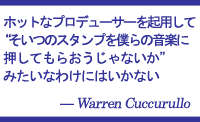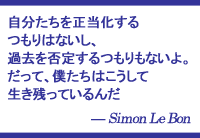| 【前編からの続き】
――アルバムのシークレット・トラックとして「Someone Else Not Me」をスペイン語で録音しようと決めたのはどうしてでしょうか?
SIMON:そうだね、昔から何か外国語で歌いたいと思ってたんだ。それでスペイン語なら世界中で使われているからぴったりだと思ってね。僕が広東語とかの中国の方言で歌えるはずもないし、オプションは限られていたのさ。それにスペイン語はとってもロマンティックで、エモーショナルな響きのある言語だからね。僕らはスペイン語のコーチを頼んで歌い方を教えてもらったのはもちろん、一緒に歌詞をスペイン語に訳したり書き直したりしたんだ。とてもうまくいったよ。だからフランス語もやってみることにした。僕は学校でフランス語を話しながら育ったから、とてもやりやすい言語なのさ。歌詞の翻訳を頼んだだけで、すぐに録音できたよ。
――そのヴァージョンを聞くことはできますか?
SIMON:フランス語ヴァージョンのこと? カナダからの輸入盤を買えば、フランス語のやつも聞けると思うよ。
――『Pop Trash』の最後の曲が「The Last Day On Earth」で、ファーストアルバムの最初の曲は「Planet Earth」でした。これには何か関連があるのですか?
SIMON:「The Last Day On Earth」と「Planet Earth」間に具体的なつながりはないよ。でもおかしいよね。この間ファンから電子メールをもらったんだけど、Duran Duranの曲には天体や宇宙に関するものが多いんだって。例えば「The Last Day On Earth」に「Planet Earth」、それに「New Moon On Monday」とか「Sun Doesn't Shine forever」「Mars Meets Venus」といった具合さ。だから僕たちはちょっと宇宙的というか天体志向のバンドなんだろうね。それと「The Last Day On Earth」が面白いのは、みんな黙示録的な作品だと思っているようだけど、ほんとは違うんだ。あれは今を生きることについて歌っていて、“今日が君の地上での最後の日だとしたら、どうする? 明日からは生きていられないとしたら、自分の人生をどうするんだ。だって実際にそれは今やってなくちゃいけないことなんだよ”という意味なのさ。
NICK:僕たちはきっと意識下で天体に関するテーマを抱えているんだろうな。天体はいろんなことの比喩にも使われているしね。「The Last Day On Earth」は何よりもまず、人生を無駄に過ごすなというメッセージに関わる歌なんだ。
――それでは、どうしてあんなにアグレッシヴな曲になったのですか。
NICK:それはWarrenの男性ホルモンのレベルが上昇して、僕たちの音楽をぶちこわそうとしているからだよ。
――そうですか……。それでは'80年代にスタートしたバンドとして、長寿の秘訣はなんでしょうか? 自分自身を作り直すことでしょうか? 新たなファンを取り込むことなのでしょうか?
SIMON:それは常々自問自答していることでもあるんだ。考えてみれば'80年代から生き残っているバンドは僕たちとU2、それにDepeche Modeくらいのものだね。再結成はあるけど、昔やっていたことをまねしているケースが多くて、いやになるよ。僕たちは常に前進して発展を続けてきた。その過程で多くのファンを失ったのも確かだ。だって「Rio」みたいなのをやり続けたり、「Reflex」路線を続けてきたわけじゃなくて、ずっと変化し続けてきたからね。僕たちのやり方についてこれない人たちもいたのさ。
でも一方では、僕たちの音楽的な実験や前進する姿勢を理解してサポートしてくれるファンも開拓できたんだ。それにはとても満足しているし、僕たちが続けてこれたのもそのおかげだよ。だって音楽を変化させることで、自分たちにとっても違った意味が出てくるし、生き生きした状態を保てる。エキサイティングであり続けることができるのさ。そのことが何よりも今の僕をエキサイトさせてくれている。僕らが最初にスタートしたころは、ビデオを作ったりスタジオに入ったりすることだけで興奮していたけど、それと比べてもずっとエキサイティングなんだ。最初にレコーディングスタジオに入るというのはビックリするくらいの大事件なのさ。でも段々それに慣れてくるとあまり興奮しなくなるよね。今でも僕たちを、とりわけ僕を興奮させてくれるのは、自分たちが作る音楽であり、これは健康的な精神状態だと思うよ。
NICK:僕たちはずっと曲作りとライヴ演奏に集中してこれたし、あまり売れなかったアルバムの時期にもコアなファンを維持することができたと思う。僕たちが何をやっているかを知るだけでも関心があるという人たちがいてくれたからね。部屋に集まって演奏を始めるたびに、何かが起きたり何かが閃いたりして、僕たちに曲を仕上げたりアルバムを完成させるまでやり続けようという気にさせてくれるんだ。それがさらに次の作品へとつながっていくのさ。今でもすでに次のアルバムに使えそうな素材はいっぱいできてるよ。これがいつまで続くことになるかは誰にもわからないけどね。
僕たちはソングライティングに関してはいいユニットだし、お互いを理解しているから、どのようにやればいいかもわかっている。僕たちにできるのは、続けるつもりがあればの話だけど、曲作りの技術を磨くことだけなんだよ。昔よりはずっと進歩したと確信している。初期の作品に自信がないというわけじゃなくて、一部には素晴らしいエネルギーを持つ曲もあるし、ナイーヴさがアピールにつながっていた曲もある。でも、もっと伝統的な意味で僕たちは曲のアレンジをコントロールできるようになったし、作品を正しい方向へと導けるようになったと思うよ。自分たちのアルバムを聞き返して、“あの曲は入れるんじゃなかった”みたいなことはないのさ。
――Duran Duranのことを昔のバンドとしてしか認識していないような新しいファン層をどのように拡大されているのでしょうか?
WARREN:残念なことに新しい層、幅広いオーディエンスにアプローチする唯一の方法はラジオでプレイされることなんだ。でも最近じゃアメリカだけでなく、いたるところでフォーマット別のコンパートメント化が進んでいる。イギリスで有力なロンドンのいくつかの局は、古いバンドはまったくかけない、完全にストップなんだ。Cherだけは例外でプレイされるんだけど、Cherのレコードはまるで新しいディスコバンドみたいなものさ。
Duran Duranの場合は“とってもホットなミキサーやプロデューサーを起用して、やつと1枚全曲作って、そいつのスタンプを僕らの音楽に押してもらおうじゃないか”みたいなわけにはいかない。僕たちはそんなことは絶対やらないし、自分たちにとってナチュラルな音楽だけを演奏し、信念を守っていきたいんだ。僕たちは常に実験はしているけど、他の誰かの言うままに演奏することはありえない。最近じゃそういうのも多いけどね。だから僕が考えるところでは、インディーズ系の素晴らしい小品の映画が主要都市の3、4館だけで封切られるのと同じ方法でやるしかないだろう。それで映画を見た人が友人に“これはいい映画だから、見たほうがいいよ”って薦めて、次第に広がっていくんだ。こうした口コミと音楽のクォリティだけで広まって、より多くの人が僕たちのことを発見してくれるといいんだけどね。
――あなたがたの初期における成功はラジオでのエアプレイと同様に、MTVでのオンエアに負うところが大きかったと思うのですが、ミュージックビデオがバンドのブレイクにとってこんなにも重要になると予測できましたか? MTVがあなたがたのキャリアにとってこれほど重要なものになると予想してましたか?
NICK:MTVがどんなことになるのかなんて誰にも予想できなかったと思うよ。実際に僕たちがMTVを訪ねたのは「Hungry Like The Wolf」が出たころだった。確か覚えているかぎりそれが最初だったと思うんだけど、MTVはマンハッタンにあったのに、マンハッタンでは放送されてなかったのさ。アメリカではまだ3つの州でしか放送されていなかった。1つはテキサスで、それとニュージャージーとどこかもう1つ、たぶんフロリダのどこかだったかな、それだけだったよ。MTVはレンガの壁にかこまれた一室で、全員がファーストネームで呼び合うようなところだったね。まったく新しいビジネスって感じでさ。とはいうものの、素晴らしいアイデアだと思ったよ。今では簡単に見られるけど、そのころは音楽を放送するテレビなんてなかったから、音楽専門のケーブルチャンネルというのは斬新だった。本当に優れたフォーマットだと感じていた。インタヴューがたくさんあって、ライヴ映像やバンドの昔の映像など、次から次へとビデオが登場した。本当の音楽チャンネルで、ゲームショーなんかやっていなかった。
SIMON:24時間ノンストップのビデオチャンネルというMTV全体の性格を考えてみたとき、“これは大きなことになるぞ、だってラジオができることはみんなやってるし、それ以上のことができる”と僕は考えたよ。実際にそうなったけど、今じゃ変わってしまった。ところで僕は朝にMTVを見ている、おかしいだろ。朝にはランニングマシンで走るんだけど、前にテレビを置いてずっと見てるのさ。その時間帯にはずっとビデオを流しているので、他の番組はまったく見ないですむんだ。ドキュメンタリーとかくだらないゲームショーとか、MTVが視聴者に押しつけるガラクタはやってなくて、正しいミュージックビデオの 番組が見られるからね。
――Duran Duranのビデオは極めて高いクォリティでした。このMTVと呼ばれるニューメディアを活用しようというのは誰の決断だったのですか?
SIMON:僕たちはビデオ時代が始まったころに登場したので、それが非常に可能性の高いメディアになると気付いた賢明なスタッフがいたのさ。2、3本のビデオを作ってみたらすぐにそのパワーを知らされたよ。テレビ画面のあるところなら世界中どこにでも存在できるし、ネットワークというもののパワフルさを考えれば、その存在感が大変なものだと認識したんだ。それで“オーケー、これでいこうぜ、みんなルックスもいいし。いかした監督とシナリオライターを雇って、何か面白いのをつくろうじゃないか”ってことになったのさ。だから何か他のことでも良かったのかもしれない。'70年代に活動していたらステレオということだったのかもしれないね。幸運だっただけじゃなくて、ものごとにとびつく直感みたいなものが必要なんだ。こうした列車のようなものが、いつでも前を通りすぎているのさ。どんなキャリアを積んでいようと関係ないチャンスがね。列車が近づく音を聞いて、いつ飛び乗ってしがみつくかを決めるんだ。そしていつ飛び降りて離れるかも決めなくちゃいけない。これが重要なのさ。だってこうした列車は地下深く潜り込んでしまうことがときどきあるからね。
NICK:ビデオに関しても広い視野で見ることが重要だと思うんだ。確かに一度にたくさんの場所に存在できる素晴らしい機会だと考えた。アルバムがリリースされた週にオーストラリアに行くことはできない。たぶんアメリカかヨーロッパに行くだろう。でも少なくとも新曲が何なのか、中身がどうなのか程度のことは伝わる。それに曲に合わせてちょっとした映画を作るというアイデアは、僕たちがみんな映画の大ファンだから、素晴らしいチャンスだと思えたのさ。
でも実際のところDuran Duranは決してビデオからブレイクしたんじゃなくて、ビデオに助けてもらっただけだよ。僕らの曲はずっとラジオからブレイクしてきたし、今でもそうだと考えている。MTVがラジオの後を追っているという面が大きいのさ。それにMTVはそんなに多くの場所で放送されてなかったから、視聴者はそんなにたくさんはいなかったんだ。もちろん今では巨大だけど。でも聴衆のところにつながって、何度も曲を聞いてもらう必要があった。その意味で初期のMTVが良かったのは、曲を何度もローテーションでプレイしていたことだね。最近ではビッグなローテーションに乗せてもらえるアーティストは限られていて、若くて面白いバンドがブレイクするチャンスはなくなった。とはいうものの、ビデオにだって長い歴史があるんだ。今でこそオンエアしてくれる場所は他にもいっぱいあるけど、僕たちが初期のビデオを作り始めたころは、イギリスではTop Of The Popsという番組で1回放送され、オーストラリアではCountdownで1回、MTVではたぶん放送されていたいくつかの州で数回、あとは運が良ければ全米放送の別の番組で1回、そんな程度と考えていたのさ。世界中に散らばった数ポイント、それで終わりだったよ。まさか20年後に世界中に25チャンネルでビデオが放送されるようになるとは誰も想像できなかったと思うよ。僕たちだってそんなふうに考えたことはなかったね。
――さきほど'80年代組の再結成の話が出ましたが、オリジナルDuran Duranの5人による再結成がいつか実現する可能性はありますか?
SIMON:“再結成”というのは僕らにはおかしな言葉だね。まるで誰かがいつもドアの影で立っているみたいな感じさ。確かに検討したことはあるけど、今年は現実的でないという結論になったんだ。実現の可能性はあるかもしれないし、ないかもしれないということだよ。それが起こるとしたら、それはやるべき正しいことでなくちゃいけないし、とにかく今はないということだ。絶対ありえないと言えば、嘘になってしまうと思う。もちろん可能性はあるよ、僕らが生きている間ならね。
NICK:この“オリジナルの5人に戻る予定は?”という質問は、半年ごとに繰り返し持ち上がってきたけど、これで15年も続いていることになるね。僕としては後ろ向きのことはやりたくないから、可能性は低いと思うよ。他の連中がどう思っているかは、わからないけど。それでも、絶対ないとは言えないね、わからないんだから。適切なタイミングで充分に興味のもてるプロジェクトが持ち上がって、しかも昔とは何か違うことをやれる道が見つかるのだったら、もっと友好的な観点から検討してもいいと思うな。
――Warren、あなたはDuran Duranの非オリジナルメンバーとして、いわばRon Woodのような存在ですね。つまりとても長い間Duran Duranにいるのに、今でも“新メンバー”だと思われている。そのことにどう対処していますか?
WARREN:そうだね、確かGuitar Magazineのインタヴューで誰かそんなことを言ってたよ、僕はまるでDuran DuranにおけるRon Woodみたいだって。でも僕としてはむしろDuran DuranのKeith Richardsだと思っている。僕は音楽を持ち込んでいるからね。実際にもっといい例を挙げるとすれば、Fleetwood MacにおけるLindsey Buckinghamの役割が近いだろうな。もっとも彼はシンガーで僕は歌わないけどね。僕は音楽とメロディーの人間だから、曲を持ち込むのが役割なのさ。
――多くの人たちがあなたのことを、おそらくサイドマンだと考えているのには、むかつきませんか?
WARREN:アルバムのクレジットを読めば、曲はメンバー3人で作られたと書いてある。でも例えば“作曲:Warren Cuccurullo、作詞:Nick Rhodes & Simon LeBon”みたいに誰が何を作ったのかを書き出せばややこしくなってしまう。だけど音楽に詳しい人が曲を聞けば、みんなギターで作られたことがわかるだろう。とってもギタリスト的な曲作りだからね。
――Warren、あなたとNickは「Bored With Prozac And The Internet」という別プロジェクトを進めていると聞きましたが、それについて教えてください。
WARREN:うん、Nickと僕はTV Maniaというチームなんだ。これは制作チームで、Duran Duranのアルバムをプロデュースしているほか、僕らが推したい他のアーティストのための曲も作っている。それで僕たちは'96年に『Bored With Prozac And The Internet』というアルバムを制作して、すでに完成させている。でも未だに適切なタイミングと販売ルートを探っているところで、今の感じではたぶんインターネットでリリースされることになるだろう。できれば2001年には発売したいと考えているんだ。このアルバムのヴォーカルはすべてテレビから取り込んだもので、とっても面白い内容になっている。サンプルの権利をクリアにするのは悪夢だったけどね。
NICK:TV Maniaのプロジェクトはとっても奇妙なストーリーだよ、本当は4年も前に完成させているのにね。録音、ミックス、マスタリングと全てが終了しているのに、倉庫で眠っているんだ。何とか世に出したいけど、メジャーのレコードレーベルから出すつもりはない。この種のプロジェクトを大企業が扱ってうまくいくかどうか自信が持てないからね。一般のリスナーが聞き馴染んでいるほとんどの音楽よりも、ちょっと抽象的な作品なんだ。ジャンルも不明だし、ラジオがどう扱うかもわからない。エレクトロニクスやサンプリングのグルーヴがいっぱい使われている。どのジャンルにも属さないし、多くの人々、とりわけラジオの連中をいらだたせる音楽だと思うよ。だからリリースを控えてたんだけど、正直なところインターネットでリリースしたいと考えている。まさにそこが安住の地だよ。
僕には理由が説明できないけど、インターネットは成熟してきたと思う。数年ぶりにサウンドを聞いてみたけど、昔よりずっと音質が良くなっている。これまでリリースを待ってきただけの意味はあったし、インターネットでの発売を本当に楽しみにしているよ。一部の人々にはショッキングな音楽だろうけど、これまでにないサウンドの音楽なのさ。
――何か他にTV Maniaのプロジェクトは進んでいるのでしょうか?
NICK:およそ50曲が公開へ向けての様々な段階にある。だから次から次へと出てくるだろうけど、内容は多種多様なものだよ。何組かのアーティストをプロデュースしたいと考えている。インターネット・レーベルのLo-Fiを立ち上げようと頑張ってきたけど、それもまもなく実現するだろう。でも、こうした事業にはとっても長い時間がかかるんだ。自分で望んでいたのよりもずっと長い時間がね。それでもし実現した暁には、そのレーベルで僕らは何組かのアーティストをプロデュースすることになるはずさ。
――Duran Duranが今でも存続して、しかも音楽的な成長と実験を続けているという事実は、このグループの商品寿命は短いだろうと予測した人々に対する甘美なリヴェンジだと思われますか?
NICK:うーん、確かに僕たちと音楽評論家との関係はずっと奇妙なものだったからね。でも僕は評論家のために音楽を作っているわけじゃない。どこかにいいレヴューが載るのは、誰かが読むと思えばいつでも気分がいい。だけど結局のところ僕が興味を持っているのは実際のリスナーであり、音楽を愛してくれる大衆にアクセスすることが重要なんだ。その点に関して僕たちはかなりうまくやれたと思っている。そうした人々にアプローチすることができずに、悪いレヴューばかり書かれていたら、今ごろきっとブチ切れちゃってるよね。
――マスコミでのレヴューはバンドが存続するにつれて好意的になってきていると思いますか?
NICK:わからないよ、全然そんなの読んでいないからね。読み始めたら気が変になってしまうよ。ときどきだけど“誰かがいいことを言ってくれてたよ”とか“この雑誌で誰かがひどいことを言ってたぜ”とか教えてくれる人もいるけどね。でも、そんなのいちいち気にしちゃいないのさ。
――最後の質問です。Duran Duranは過小評価されてきたバンドだと思いますか? 最近VH-1で放送された「The List」では、“歴史上で最も過小評価されたバンド”のリストでDuran Duranが第1位にランクされていましたが。
NICK:Duran Duranが僕たちのオーディエンスや僕たちとつながりのある人たちから過小評価されたことは一度もないと思うよ。おそらく多くの人々は僕たちが作った音楽をじっくりと聞く時間がなくて、曲の内容とかクォリティについて論理的かつ公正な判断ができていないんだろう。だけど一度でも膨大なファンをつかんでしまうと、シリアスなロック評論家の多くをいらだたせることになるようだね。彼らは男性向けのバンドみたいなものしか好まない傾向があるからね。連中が好きなのは男性ホルモン全開のBruce Springsteenとか、その類のバンドなのさ。僕たちみたいなのは全然お気に召さないようだね。
SIMON:過小評価されていると感じるのは、実際には僕とは関係のない話だよ。だって“かわいそうな僕たち、過小評価されちゃって”なんてのはちょっといじけてるだろ。それは第三者がいうようなことだと思う。僕たちが過小評価されてようとされてなかろうと、知ったことではないね。“過小評価”が何を意味するのかはとっても主観的なことだろう?
言えるのはDuran Duranが他のバンドよりもマスコミからひどい扱いを受けてきたということ、それは事実かもしれないね。確かに僕たちはティーン向けのバンドだと見なされるという苦い経験をしてきた。特にスタートしたころ、とりわけアメリカではそうだった。そのために離れていった人も多かった。僕たちの音楽を気に入ってくれたかもしれない多くの人たちが、全体的なイメージに惑わされて引いてしまったんだ。バンドがイメージを振り払うのはとっても難しいことなのさ。自分たちを正当化するつもりはないし、過去を否定するつもりもないよ。だって、僕たちはこうして生き残っているんだし、昔のようなことはもうやっていないからね。罪悪感を感じることも謝罪するようなこともまったくないと思うよ。僕はDuran Duranの歴史をとても誇りに思っている。僕が今こうしていられるのもそのおかげだからさ。 |