
| 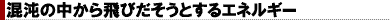
――前作『イキルサイノウ』とは確実に違う内容のアルバムに仕上がりましたね。
山田将司(Vo/以下、山田):そのときに生まれたものをやったということなんですけど、かなりいいと思ってます。ただ、内にこもってばかりではどうしようもないなぁという気持ちはあって、心構えとしては、個人的にはちょっと肩の力を抜いたところはあったかもしれないですね。『イキルサイノウ』のような世界で場を共有することもコミュニケーションとしては全然ありなんですけど、もっと素に近づいた、日常に近づいた、心を開いた状態ではあるなと思うんですよ。力の注ぎ方として、一点を増幅させる感じというかね。
――今までにない突き抜けた爽快感がありますね。
菅波栄純(G/以下、菅波):うん、俺らが扱うテーマとして、人間の根深いところをえぐり出そうとはしてますけど、そんな流れはありつつ、わかりやすい痛快な面も描きたかったんですね。それこそヤンキー漫画を読んで“いやぁ熱くなった”みたいな単純さっつーか。重いことを重く言うんじゃなくて、絶望しているように見えて、どこか楽観的な気持ちもあったり、泣いたらすっきりしちゃったり。そんな生々しさを求めたいから、ちょっと複雑な感情をすごくストレートな音楽でやりたいなと。混沌の中から飛びだそうとする、わけのわからないエネルギーが出ているような気がします。
松田晋二(Dr/以下、松田):『イキルサイノウ』の重さや根底でふわっとしている感じが、音楽としてポップに響くアルバムができたと思うんですよ。だからこそ達成感があったし。メンバーが素手で闘っているような作品がいいなと思ってたんですね。今回の新しい部分は、その肉体的な感じがわかるところなんじゃないかな。
菅波:今までが渦巻いているエネルギーだとしたら、今回は躍動しているって感じかな。
――そういった意味では、歌にも演奏にも自然と変化が出てきて然るべきですよね。
岡峰光舟(B/以下、岡峰):どのパートも同じだと思うけど、クライマックス感みたいなものを一緒に演出したい気持ちがある。今回はベースも曲全体の流れを見て、つけられたと思うんですよ。それも考えてというよりも直感的なところのほうが大きかった気がしますね。
菅波:どっちかというと光舟のほうがギタリストっぽいフレーズで、俺がベーシストっぽい資質なんですよ。ある種、逆転してる感じが俺らのオリジナリティではあると思うんですね。曲によってはスタンダードな形にも戻ったり。その幅は武器だなと思いますね。
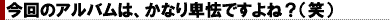
――決して難解ではないにせよ、セオリー通りの聴かせ方をしない面はありますよね。
岡峰:普通に考えたらロスになりそうなところを、逆にそれを強引にエネルギーにしているところはあったりする気がしますね。
山田:歌にしても、結局はリアリティを持たせたいわけで。昔はエネルギーのほうに寄りすぎていたかもしれないけど、ポロッとこぼれ落ちるようなものもある。それはバランスなんだけど、俺らが伸び伸びできたほうが、曲的にも活きてくると今回思ってましたね。
松田:今回のアルバムは、かなり卑怯ですよね?(笑) 昔、親に言われたじゃないですか。遊ぶときは遊んで勉強するときは勉強しろみたいな(笑)。それこそ「墓石フィーバー」のような面白味だけでアルバムを作ったとしても、どこか満足いかない部分が出てくる。今回もそれを探し求めていた結果、「キズナソング」「ヘッドフォンチルドレン」「奇跡」のような曲が生まれてきた。ホントに一つ一つのバランスが絶妙に成り立って、キャラが生まれたと思いますね。
――最終的に“ヘッドフォンチルドレン”をタイトルに持ってきた意味合いは?
菅波:この曲ができたときに、最も日常の体温だなと思ったんですよ。たとえば、ヘッドフォンをしたまま電車に乗っていたら、“この電車には爆弾が仕掛けられています”とアナウンスが流れても気付かないわけじゃないですか。町には出ているけど、実は現実からは離れている。自分の部屋のまま外に存在しているような状態というかね。わりと自分がそうだから言うんですけど、コミュニケーションが億劫になってきたり、怖くなってきたりして、周りに優しい人とかよくしてくれる人がいるのに、俺は一人ぼっちだみたいな気持ちになっていたりする。でも、やっぱりそこから抜け出したい、世界と関わりたい。
松田:言葉的にも“ヘッドフォンチルドレン”が全体をパッケージングする一つのテーマになったんですね。どの曲の世界観も分散しないまま、すべてのストーリーが結びついてアルバムが完成したと思います。
取材・文●土屋京輔 |
|


