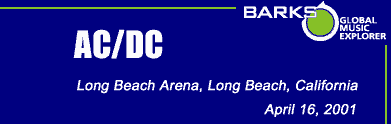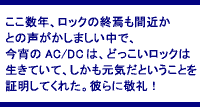| このたび新装と相成ったLong Beach Arenaのこけら落としであるこのショウは、シワ取り手術もなんのその、結局は何も大して変わっちゃいないことを証明してくれた。巨大な会場を取り囲む人の列は、シンシナティがWhoを迎えた時のような長さだし、正面入口の前では相も変らぬ説教師たちが、メガホン片手に“ハイウェイを燃やす”云々について熱弁を振るっている(その大半は大昔、KissやW.A.S.P.をここで迎えた終末論者と同じ顔ぶれに違いない)。私自身のここに至るまでの道のりは、奇跡的に事件のひとつもなく、ロング・ビーチへと続くハイウェイはガラガラに空いてさえいた。もっとも、3つ連続で出口を間違え、しまいには無理矢理Uターンまでしてアリーナにたどり着いたのが8時ちょうどだったのだが。おかげで前座のWilde Mouth Masonはすでに終わってしまっていた。カナダ出身ということ以外に私が入手し得た、彼らに関するささやかながら貴重な情報といえば、1時間待ちのビールの列に並んでいた女性から聞いた「良かったわよ」というコメントのみ。よっしゃ、Wide Mouth Mason。今回は悪かった。貸しが出来ちまったようだな。
予定通りの8時45分、エサを待ち侘びた子犬のようにAC/DCがステージに転げ出てきた。彼らの外観はというと(頭上に4つしつらえられた巨大スクリーンに映し出されればことさら)、オーストラリア産ロックバンドも中年にさしかかり、しかもひとりとして優雅に年を重ねてはいないことがばれてしまう。とはいえ、その汲めども尽きぬエネルギー(そしてギタリスト、Angus Youngが流すオイル缶ひとつ分もの汗)を思えば、この男たちが今なお、その3分の1ほどの年端もいかぬバンドをあっさりやっつける力を持っていることは間違いない。後退しつつある額が数学教師を思わせるAngusも、服装は今もって小学生のそれである。ドラマーのPhil Ruddは今やシンバルを正確に叩くのに眼鏡が必要だが、やはりショウが始まって1時間は煙草を絶やさなかった。
オープニングは最大のヒット曲のひとつである“You Shook Me All Night Long”。彼らが繰り出すあまりにもタイトなグルーヴの前には、マシーン製ロックのNine Inch Nailsあたりは、そこらの飲み屋のバンドさながらに思えてしまう。これだから、AC/DCを批判するのはおよそ不可能なのだ。確かに彼らは、夜な夜などころか月ごと、年ごと、あるいはアルバムごとの変化すら見せない。他に思いつくどんなバンドよりも、AC/DCは独自のスタイルを体系化し決して見失うことがないのだ。それを着飾るでも、いじくり回すでもなく、あくまで直球、かつシンプル。AngusとMalcolmの兄弟がユニゾンでオープンコードを奏でれば、ベーシストのCliff Williamsはどこまでも単音を鳴らし、Ruddは装飾音がほぼ皆無の4ビートを刻み、ヴォーカリストのBrian Johsonが思い出したように雄たけびを上げる。その方程式が有効なんだから仕方がない。バンド自身、深く考えてみたことはないんじゃないだろうか。要するに、不滅ということなのだ。
と、ここまでダラダラと述べてきたのも、AC/DCがAC/DCにしか出せない音をそのまんま出していたということを言いたいがためである。これほど正確なビートを、容赦なく力強いグルーヴと共に繰り出せるバンドは、この星に2つとない。完璧なタイミングとスウィング感を誇るリズムの帝王Rolling Stonesをもってしても、である(Kieth Richardsから一言あるであろうことは間違いないが)。とことん的を絞った混じりけのない表現はもちろん、このバンドは、どんなに拡大解釈してもバラードと呼べるものは一切発表したことがないし、キーボードを導入したことも、外部から楽器を取り入れたこともなく(“Long Way To The Top”のバグパイプが唯一の例外)、競合者たちが得てして陥りがちな小手先の技に甘んじたこともない。AC/DCとは、あらゆる目的に照らして、この世で有数の頼り甲斐のある存在なのだ。
それだけに、意外な展開があるとすればステージの演出面ということになる。この夜、巨大な金色のAngus像がギターを抱えてステージ中央に陣取り、かすかに動くそれには電飾付きの赤い角と悪魔のような目が施されていた(“我が前に偶像は作らず”――とか言わなかったっけ?)。となればやはり、一番人気のグッズのひとつは電池式の電飾の付いた“Angusの角”だ(訳注:Angusはスコットランド原産の牛の固有種名でもある)。いつもなら大歓声と共にライターの炎の海が広がるところ、会場の端から端まで光る角の先っぽが浮き沈みするのが見える。なんてロックンロールなんだろう。他にも、巨大な棒状の風船も売っていて、以前なら“Honky Tonk Woman”の演奏中に振り回されていたのではないかと思しきこれが、今回は“Whole Lotta Rosie”でお役を果たしていた。また、皆のアンセム“Highway To Hell”の最中にステージから吹き上げられた火柱にも度肝を抜かれ、Beavis & Butt-headが彼らを愛してやまないのも無理はないと納得!
大掛かりな演出がなくたって度肝を抜くことはできる。“The Jack”が始まると客席をカメラが巡り、その先にはこの曲で無料奉仕をしようと待ち構えていたと思われる地元ストリッパーが勢揃い。張りぼてと本物のオッパイが中央のスクリーンに踊るも、私の隣にいた10歳くらいの男の子は、手に入れた光る角のほうに興味があるようだった。まだ数年早かったか。花道に歩み出たJohnsonが自らの立派な胸を見せびらかしていたが、やがて「そっちにはかなわないよ!」と降参。Angusも当然、名乗りを上げて、彼のテーマソングとも言うべき“Bad Boy Boogie”では、期待通りのストリップショウを展開した。
4人はハードにロックし続け、いわずもがなのクライマックスへと持っていったところで、Bon Scott時代の大曲でショウを締めくくる。“Whole Lotta Rosie”、そして“Let There Be Rock”という、これ以上ないワンツーパンチだ。大注目のアンコールは、キャノン砲が炸裂する“For Those About To Rock(We Salute You)”。
ここ数年、ロックの終焉も間近かとの声がかしましい中で、今宵のAC/DCは、どっこいロックは生きていて、しかも元気だということを証明してくれた。Stonesをはじめ、スタジアムを満杯にするショウの多くとは対照的に、この日のファンはバンドの最近の曲にも同様の熱意を示し、“Stiff Upper Lip”や“Hard As A Rock”“Safe In New Yok City”も、“Hell Ain't A Bad Place To Be”のような名曲と同じように受け入れられていたのだ。これこそ、このバンドが未だ生命力に満ちているという何よりの証拠だろう――ファンが新しい作品を支持しているということが。したがって、ロックンロールがどうなろうと、AC/DCの連中は彼らが望む限りアリーナでライヴし続けていけそうだ。彼らに敬礼! By SL Duff/LAUNCH.com |