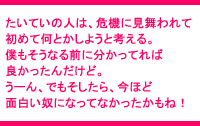| 活気に満ちていた'80年代の数年間、Boy Georgeはポップワールドを制していた。爽やかでアップビートな彼のバンド、Culture Clubは世界各地で巨大な成功を収め、George O'Dowdはその性別不明のキャラクターを目にも鮮やかな形でメインストリームへと導いた。(すべての優れたロックスターがそうであるように)あらゆる常識をくつがえすGeorgeの愛やドラッグ、そして法律に対する苦悩は、タブロイド紙の一面を飾る格好のネタとなり、彼が少しでも間違ったことをしようものなら、たちまちそれが報道され、分析された。'86年の逮捕を経て、実際にジャンキーであったことをマスコミに告白したのち、Boyという名で知られるこの男は、世間が見守る中、薬物を断ち切ることに成功する。だが、すでにCulture Clubの時代は終焉を迎えていたのだった。
しかし、そんなことに屈しないGeorgeは、ソロ名義でいくつものスマッシュヒットを放った。'94年、シングル“The Crying Game”でグラミー賞にノミネートされ、さらに'98年のグラミーではついにBest Dance Recording賞を獲得する。そして同じ年にはCulture Clubを再結成。2曲の新曲をレコーディングし、ツアーも行なった。このリユニオンは大した話題にはならなかったものの、そんなことはどこ吹く風で、ここ数年のBoy Georgeはギャラの高い売れっ子DJとして復活すべく、イギリスやヨーロッパのクラブを満員にしながら忙しく動き回っている。そして、最近ではダンス/トランスミュージックの新作『Essential Mix』をリリースした。
ラスヴェガスでBoyのDJショウ――まるで催眠術をかけられたようにうっとりしてしまった――を観た後、ハリウッド・ヒルズにある、彼の友人でシンガーソングライターのAmanda Ghostのスペイン風邸宅で彼と話をすることができた。彼は“ダサモード”のファッション――“Beer:Proud Sponsors of casual sex since 1858(ビール:1858年以来カジュアルセックスの名誉スポンサー)”と書いてあるTシャツ姿――だったが、髪はスパイキーなプラチナで、その顔にはもちろん完璧なメイクが施されていた……。
――ヴェガスでのショウはとてもワイルドでしたね。
BOY:
あんまり良かったんで、こっちがビックリしたよ。DJブースは、アーティストとしての仕事を、僕が完全にコントロールできる数少ない場所のひとつさ。ラジオやダンスチャートで今、何が流行ってるかってことを気にしなくていいんだからね。あそこには完全な自由がある。だから好きなんだ。
――アメリカツアーは楽しいですか?
BOY:
イギリスのダンスシーンはもう出来上がってて繁栄してるけど、アメリカはまだ何がどうなるか分からないからね。僕はイギリスじゃ、かれこれ7年くらいDJやってるわけだけど、アメリカはものすごくデカい国だからさ。都市の1つひとつが新しい国みたいなんだ。まるで自分がパイオニアになったような気分だよ!
――それはたぶん、あなたが本当にパイオニアだからじゃないでしょうか。
BOY:
ありがとう。君だってかなり伝説的な人じゃないか。
――うわぁ! あなたにそう言われるなんて……。私の場合は有名っていうより悪名高いんですけどね。
BOY:
それだって別に悪いことじゃないよ(爆笑)。Culture Club時代に僕ら、ここ(アメリカ)で大成功したけど、自分自身“一体どうしてそんなことが出来たんだ?”って思うんだ。アメリカを征服するにはものすごくスタミナが必要だからね。
――今やあなたはDJとして成功したわけですが、自分ではあと何回くらい変身できると思いますか?
BOY:
僕は双子座生まれだから、ひとつのことが上手くいかなかったら、他のことで自分を忙しくするタチなんだ。といっても、意識してやってるわけじゃない。自分の達成したいことをリストに書き出したりはしないよ。むしろ“ぶっつけ本番”タイプの人間なんだ。“ヘタなウンコも数打ちゃくっつく”ってことわざ知ってるだろ?
――そのことわざ、正確にはちょっと違うと思うんですが、でも、言わんとするところは分かります。ということは、構想や戦略を練ったりはしないんですか?
BOY:
僕はMadonnaじゃないからね。君はきっと間違った……
――イメージを持ってると? どうもMadonnaより私のほうがあなたに近いみたいですね。何でも気の向いたことをやるっていう……。
BOY:
驚いたなあ。それってまさに僕が言おうとしてたことだよ。フィーリングこそが僕にとっては大事なんだ。自分がしたくないことをやらなくてもいいっていう点では、たぶん僕は贅沢な身分なんだろうけどね。
――そうですね、恵まれてますね。あなたがそれに気付いてて良かったです。
BOY:
でも知ってる? それを築いたのは自分自身なんだ。他の誰にもらったものでもないんだよ。
――もちろん、あなたが自分で築いたものですよね。
BOY:
誰だってそうなんだよ。
――結局、最終的には誰でも、自分が求めた通りのものを手に入れるんですよね。そう思いません?
BOY:
そう? じゃあ今度はトム・クルーズをゲットしようかな
――そうですね、彼は今フリーだし。さて、こうして何度も再起を遂げていることについて、ご自分では驚きを感じてますか?
BOY:
僕はただ、自分のやってることを精一杯やるだけさ。もっと若い頃は自分自身のキャラクターのことでいろいろ思い悩んだけど、それはセラピーを受けて克服したし、人生を楽しんだり、自分がやっていることをエンジョイすることのほうがよほど大事だって気付いたしね。
――世間の注目を浴びながら、セラピーを受けたり依存症を克服したりするのは大変だったんじゃないですか?
BOY:
いや、別に。セラピーを受けてるところは誰にも見られないわけだし。でも、僕はそれが恥ずかしいことだとは全然思わないよ。弱い奴がすることだって人は思うかもしれないけど、カウンセラーのところに行って“僕はメチャクチャになっちまった、助けてくれ”って言うのだって、すごく勇気のいることなんだから。
――あなたのその言葉で、他の人も助けを求めやすくなりますよね。
BOY:
たいていの人は、深刻な危機に見舞われて初めて、自分の問題を何とかしようと考えるものなんだ。僕も実際にそうなる前にちゃんと分かってれば良かったんだけど。うーん、でもそしたら、今ほど面白い奴になってなかったかもね!
――それに曲に書けるようなことも、こんなにたくさんなかったかもしれませんね。
BOY:
歌えることもね。
――昔から歌は得意だったんですか?
BOY:
幼い頃から歌ってたよ。すごく小さい頃はBusby Berkelyとか、古いハリウッド映画とか、Carmen MirandaとかLiz Taylorが大好きだった。ゴールデン・グローヴ賞の時の彼女見た? 何だか大量に薬でも飲んだみたいだったよね。ああいう表情、見覚えあるんだ。前に1度だけパリのマキシムで彼女に会ったことがあるから分かるけど、たぶんあの時は舞台の隅々まですべて照明を当ててたと思うよ。凄い光を発してたからね、彼女。
――彼女のためだけに舞台中にライトを?
BOY:
そのはずだよ。彼女の身体の周囲だけ物凄い光の層が出来てたもの。まあ、僕が何かに酔ってたのかもしれないけど……。
――大量の薬とか? ところで、あなたは本当に素晴らしいソングライターですが、今でも曲作りはしてるんですか?
BOY:
ああ、もちろん。今年はソロの新作を作る予定なんだ。前よりももっとリズムをベースにしたものになるんじゃないかな。けど、ダンスミュージックだろうとポップソングだろうと、僕の書くものには常にストーリーがある。これまでのキャリアの中で様々なスタイルの音楽を作ってきたせいで、市場における僕の位置付けは難しくなったとは思うよ。今の音楽はすべてカテゴリー分けされてるし、マーケットリサーチと人口統計学から成り立ってるからね。
――ちょっと魂の抜けたビッグビジネスになってしまってますよね。
BOY:
それも今後は変わると思う。ただ問題なのは、若い人たちの反抗心がどんどん薄れてきているってことだ。アメリカでは、最もエキサイティングな音楽は黒人アーティストたちから発信されている。Missy ElliottとかBusta Rhymesとかね。もちろん、彼らはメインストリームの一端を担っているわけだけど、それでもアメリカ在住の黒人ってことでまだまだ危機感があるし、実際、僕もこの国にはいまだにひどい差別があると思うしね。
――Eminemは危険だと思いますか?
BOY:
いや、彼を脅迫的だとは全然思わない。ちょっと小生意気なガキだくらいは思うけど。ミュージシャンってのは、慣習やしきたりに逆らっていくべきなんだ。媚びたりしないでね。僕はBowieにすごく影響を受けたんだ。彼は伝統反対派だったし、常に自分は異邦人だという考えを持っていたからね。Eminemがひどいセックスパラノイアにかかってるのは見てれば分かるし、彼のファンにしても同じさ。ちょっとあけすけ過ぎるって感じかな。
――アメリカ人は、まだまだセックス問題を怖がっているんですよね。
BOY:
それを言ったらイギリスだって同じだよ。
――あなたは自分を楽観主義者だと思いますか? それとも悲観主義者?
BOY:
“皮肉屋は失望した楽観主義者に過ぎない”って僕の気に入ってる言葉があるんだ。これこそまさに僕のことだよ。シニカルでいるってことは、長い目で見れば、楽観的になれるってことだ。物事に対して現実的な態度をとるようになるわけだからね。オープンな心を持った観察眼の鋭い人間なら、人は一見どんなに攻撃的に見えても本当は傷つきやすくて脆いんだってことが分かるはずだよ。
――あなたの宗教的バックグラウンドについて教えてください。話を聞いていると、とてもスピリチュアルな方のようですが?
BOY:
僕は自分が成長するにつれ、人生が特別で、人間が特別であるとを考えさせてくれる儀式的なことに興味を持つようになった。果たして、自分自身がスピリチュアルかどうかは分からないけどね。だって、いわゆるスピリチュアルな人たちって、時々やたら傲慢に見えることがあるだろ?
――でも、私たちは皆同じですよ。ウィ・アー・ザ・ワールド、ウィ・アー・ザ・チルドレンです。
BOY:
確かにね。でも、ほとんどの人はそれに気が付いてないみたいなんだよね。
――神の存在を深く信じていますか? つまり天の力ってことなんですが?
BOY:
天の力は誰でも持ってるものだと思うんだよね、マジで。こう言うと尊大に聞こえるかもしれないけど、でも僕は神に関してオーソドックスな考え方はしない。ただ、神は何にでもいるって思うだけさ。それが僕の考え方。神はどんな人にも、どんな物にもいる。あらゆる無生物にもね。そう考えれば、誰にでもブッダになれる可能性があるってことに気付くはずだ。
――そう気付いたら素晴らしいことですよね! あなたは今、恋をしていますか?
BOY:
いつだって恋はしてるよ。みんなには恋なんかしてないって言ってるけど、説得されやすいたちだから! まあ、確かに恋愛はここ7年ほどしてないね。セックスはしたけど、恋愛はしてない。僕が出会う人って、母親とか父親代わりを求めてる人が多いんだ。誰かに世話をしてもらいたい人がね。美しいものにはつい引き寄せられちゃうんだけど、一緒にいて楽しくて、知性もあわせ持っている人と出会いたいよ。
僕の曲の中に“君を見る時、僕の目には宝石しか映らない/その輝きは、しばしば愚か者の目を眩ませてしまう”って歌詞があるんだけど、本当に人の弱さに惹きつけられやすいんだ。誰かを支配したいとか、威張りちらしたいとか、そういうことじゃなくてね。たぶん、それは自分が失ってしまった何かなんだと思う。自分が子供の時に失ってしまった、子供らしさってものを求めてるんじゃないかな。
――仏教徒はそれをマーヤー、つまりすべては幻想だと信じているみたいですね。結局、人生を楽しいものにするのも辛いものにするのもその人自身だと。
BOY:
僕の曲にも“In Maya”ってのがあるよ。うん、確かに僕はマーヤーの中にいる。で、その状態をけっこう気に入ってるのさ。 |