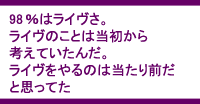| ロサンゼルスにあるマヤン・シアターのバックステージで、Groove Armadaの2人のキャプテンは極めて対照的な風情を見せている。ソファにゆったりとくつろぐTom Findlayは、長身でくだけた格好をしたブロンド。Indianapolis PacersのRik Smitsだと言っても通りそうだ。一方、椅子に浅く前かがみに腰かけたAndy Catoは、背が低く細身、肌は浅黒く気性の激しそうなタイプ。2人のスタイルはかけ離れているように見えるが、口を開くとまったく一心同体となり、お互いの考えをうまく補い合う。彼らが熱っぽく語ってくれた最新のプロジェクトは、大好評を得た米国でのデビューアルバム『Vertigo』をひっさげてのツアーである。
といっても大したことではないと思う向きもあるだろう。なにしろエレクトロニックなアーティストといえば、すでにOrbやChemical Brothers、Underworldのようなグループが皆ツアーをしているのだから。だが、TomとAndyはひと味違ったアプローチを見せてくれる。アルバムの再現にコンピュータを使ったり、(今年初めにやったように)単にDJ役を務めるのではなく、アルバムの曲を9人編成のライヴバンド用に完全にアレンジし直しているのである。
コンピュータから生身のミュージシャンによるプレイへの移行プロセスを、Tomは当然ながら「オーガニック」という言葉で表現。それを受けてAndyが補足する。「曲を聴きながら、『これはワウワウ・ギターを使うと最高だろうな』とか思うんだよね」ある程度の編集は必要だったとTomも認める。「1曲の中に3、4種類のビートが入ってる場合は、どれがライヴに一番ぴったりなのかを決めなくちゃならない」その結果、アルバムとはかなり違ったサウンドになり、ダブ・レゲエやSteely Danの“ライヴ・サンプル”さえも所々で聴こえてくる。
こうしたプロセスの途中で、うまくいかなかった曲ももちろんある。「“At the River”はものすごく難しかった。何度やってもダメだったんだ」とAndyは振り返る。Patti Pageのサンプルを再現するのは不可能だったので、サンプルはそののまま残すことに。それでも「98%はライヴさ」とTomは強調する。
「みんなちょっとテクノロジーに頼りすぎてるよ」テクノ・ミュージシャンの言葉としては少々皮肉にも聞こえるが、Andyはそう不満を漏らす。だが、それが彼の正直な気持ちなのだ。「ライヴのことは当初から考えていたんだ。ライヴをやるのは当たり前だと思ってた」
確かに当たり前かもしれないが、そう簡単な展開ではなかった。Groove Armadaのツアー3日目にして、早くも曲に修正が加えられたのだ。「クラブで実際に観客を前にし、巨大なPAを使うと、リハーサルでうまくいったことが必ずしもうまくいかないこともある。だからやり直しが必要なのさ」とTomが肩をすくめる。
このツアーが終わると、Groove ArmadaはもっとDJ中心の方向性に戻ることになっている。すでに英国で出ていたリミックス・アルバムを、米国でもこの夏遅くにリリース。また、他のDJと同じく、TomとAndyも自らミックスを手がけたアルバムのリリースを予定している。「これは『Back at Our Place』というシリーズの1部なんだ」とTomが言う。このアルバムシリーズは、DJ自身が夜、自宅に帰ってから聴きたい曲を集めたものだ。ではGroove Armadaは家に帰ると、一体どういうもの聴きたいのだろうか? 「気分を静めてくれる音楽さ」とAndyは言い、Al GreenやBarry Whiteなどのソウルのスタンダードに加え、もう少し新しい曲をいくつか口にした。どれも意外なものばかりだが、意外さで知られるGroove Armadaならではとも言える。 |