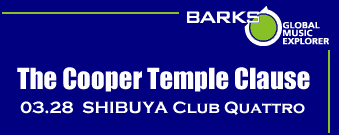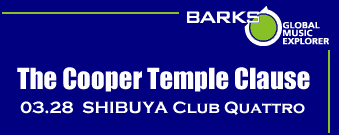| この日のライヴはアルバムのオープニングと同じ「Did you miss me?」でスタート。一瞬、拍子抜けするくらいの穏やかなイントロから徐々にテンションを上げ、最後はとんでもなくラウドになるという、スタートダッシュにはもってこいのナンバーだ。聴き手はやがて押し寄せる爆音をジリジリしながら待ち、一瞬のブレイクののち、Voのベンがしゃがれた声を張り上げると一気に爆発する。古典的ではあるが、こんな大仰な芸当をやって、なおかつカッコよく聴かせるバンドはここ数年いなかった。やはり彼らは、現在のイギリスに現れてしかるべきバンドなのだと確信させる幕開けだ。
クアトロのステージに並ぶメンバーは、それぞれが気ままに動いているように見えて、ひとつの音の塊を叩き出す。6人というのはバンドの人数としては少なくないほうだが、そのうち3人はマルチプレーヤーで、互いの楽器をとり替えてプレイすることもしばしばだ。Voでフロントマンのベンは幼い頃に日本に住んでいた経験があるらしく、日本語のMCも丁寧かつで堂に入ったもの。しかし、どこかオーディエンスと距離を置いているようにも見える。噂の凶暴なタンバリンさばきはそれほどでもなかったが、リアム・ギャラガーにカート・コバーンが乗り移ったような歌声は一級品だ。そのベンを上回る勢いでタンバリンをぶっ叩いていたのが、ベースのディズ。プレイしている最中もまったく落ち着きがなく、飲みかけのビール缶を弦にこすりつけて中身を飛び散らせるなど、最も天然かつエキセントリックな行動が目立つ。担当楽器に“madness”とあるのは伊達ではないようだ。
この日のセットリストは、「555-4823」(と日本盤ボーナストラック)を除くアルバム全曲とファーストEPからの2曲。パンキッシュなギターが炸裂する「Film-maker」や、すでに代表曲といってもいい「Panzer attack」「Let's kill music」などは当然のように盛り上がるが、個人的には「Who needs enemies?」を聴けたのがよかった。アルバム中のミディアムナンバーの中でもとくにブルージーなこの曲は、ホーンや女性コーラスがアレンジされていて、ちょっと異質な仕上り。聞けば、EPでデビューを飾る前からの曲らしいが、彼らがカタルシスを追求するだけのバンドではないということを示す佳曲だと思う。
 | 少し意外だったのが「Panzer attack」ではキーボードのキランに加え、ギタリスト2人がエフェクト類やシンセをプレイしていたこと。このへヴィなキラー・トラックは、ベンが弾く1本のギターとキーボードの層で演奏されていた。2人のギタリストのうち、トムはエフェクトとアナログ・シンセ、ベースも担当する最もマルチ度の高いメンバーだが、実際のステージ上でもギターとその他の割合が半々くらい。さらに「Digital Observation」ではバイオリンの弓でギターを弾くという、古くはジミー・ペイジ、最近ではシガー・ロスの十八番まで披露した。気が付くとステージに座り込んだりしているので、見えないこともあったが、音に対する好奇心はいちばんのよう。バンドの持つ実験的な姿勢には彼の存在の影響が大とみた。
ベンによる短い曲紹介をはさみながら、およそ1時間にわたるライヴはアンコールなしで終了。ラスト「Murder Song」のイントロで、ダンのギターのシールドが抜けるというハプニングもあったが、このときメンバーの顔からこぼれた笑顔で、それまで張り詰めていた空気が図らずもほぐれた。何もなければ、この高いテンションを保ったまま、ステージを終えていたことだろう。それは、自らの音楽への揺るぎない自信に裏打ちされた、とんでもないテンションだった。しかしその笑顔は、彼らがまだ二十歳そこそこだということも同時に思い出させた。たった2枚のEPで英国ロック期待の星に祭り上げられたクーパー・テンプル・クロースだが、そのプレイには自由な発想とそれを形にする恐るべき柔軟性がある。この先、彼らはまだまだ変わっていくのではないか。
「Panzer attack」のPanzerとは第二次大戦中のドイツの装甲戦車の名だ。しかし、その戦車は柔らかくしなやかな鋼鉄でできていて、好きなように形を変えることができる。彼らのステージを見終わった後、そんイメージが頭に浮かんだ。 文●佐伯幸雄 |