| 非ポップス・ファンにとってRavi Shankarは、Philip GlassやヴァイオリニストのSir Yehudi Menuhinといった権威あるクラシック、ジャズのアーティストとコラボレートしたインド古典音楽界の大物である。ロックファンにとってはGeorge Harrisonにインドの音楽と哲学について教えた人物であり、モントレー・ポップ・フェスティバルやバングラディッシュ救済コンサート、ウッドストックで演奏した幻惑的な音楽家でもある。さらに芸術映画の愛好家にとっては、有名なインドの映画監督Satyajit Rayによる『Apu』三部作のスコアを書いた作曲家だ。
Ravi Shankarがインドから登場した最も著名な音楽家であることに間違いはなく、そこに10億人が暮らしていることを考えればこれはたいした偉業であると言えるだろう。
Shankarは13歳の時に兄Udayの舞踊団でダンサー兼サポート演奏家として初舞台を踏んで以来、これまで71年間にわたって世界中で公演活動を行なってきた。'38年、18歳のShankarはダンスを断念して、導師Ustad Allauddin Khanのもとでシタールの修業をすることになった。6年後にインド古典音楽の正式教育を完了した彼は、インド中で定期的に演奏し始める。'54年には初めてソビエト連邦で演奏し、'56年には西欧と米国で初のソロコンサートを行なった。それ以来、Shankarは世界中のリスナーに自身の音楽を届けてきたのである。
新アルバムの『Full Circle/Carnegie Hall 2000』はタイトル通り、例の一流音楽ホールにおける19回目の公演を収録したライヴドキュメントだ。
「私たちの演奏は全面的なインプロヴィゼーションだから、ライヴ録音にはたいてい納得できないものなんだ」と尊敬を集めるシタールの巨匠は告白する。
「この楽器はとてもデリケートなので、少しチューニングが狂ってしまうことが時々ある。演奏しながらチューニングする方法もあるにはあるんだがね。録音されているとを知っていると、あまりいい気分では演奏できない。だが今回はどういうわけか、うまくいったよ。編集もほとんどしないで済んだ。非常にわずかな箇所だけだ。出来にはとても満足しておるよ」
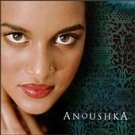
『Anoushka 』 | このアルバムのもうひとつの重要な側面は、娘のAnoushkaの貢献である。彼女は9歳半のときに父親からシタールを習い始め、まもなく20歳の誕生日を迎えるところだ。Anoushkaは13歳からShankarと一緒に演奏しており、父の75歳の誕生日にライヴデビューを飾っている。彼女自身も『Full Circle』をはじめとするShankarの録音をリリースしてきたレーベル、Angel Recordsから2枚のアルバム(『Anoushka 』と『Anourag』)を発表している。では、Shankarは娘がシタールを演奏するように奨めたのだろうか、それとも彼女自身の決断だったのだろうか?

『Anourag』 | 「多少は期待しておったな」と父親は認める。「だが娘に自分で選んでほしかった。あの子はシタール以外にもピアノとか歌とかいろいろと興味があって、決めかねていたんだよ。シタールを選ぶべきだとこだわったのは母親のほうだったよ」
それ以来、ShankarがAnoushkaにとって唯一のシタールの師となった。父親はシタールの指導のために必要な伝統的な師弟の絆から親子関係を切り離そうと努めたが、そのふたつが渾然一体となってしまったことを嬉しそうに認めている。これまでのところ、音楽的な成果が損なわれるようなことはないという。
Shankarは、自分の娘がインド古典音楽の伝統を継承してくれていることに満足しているようだ。この数年来というもの、彼はその様式に新たな関心を見出してきたという。
「私が演奏を始めたころは、古典の形式を実践する人間は極めて少なかったな」と話すShankarは、インド古典音楽を活性化するためにコンサート、教育活動、作曲、ラジオ/テレビでのトークといった非常にハードな作業をこなしてきた。現在ではベテランミュージシャンのみならず、熱心なオーディエンスを擁する若い演奏家たちが古典の復興に努めている。自身が20世紀の半ばに演奏を開始したころよりも、最近のほうが古典音楽を理解し、評価してくれる人々が増えているというのが彼の見方だ。
このシタールのヴィルチュオーソは自分の使命をさらに全うするために、先ごろインドのニューデリーにRavi Shankar Foundationを設立した。この施設にはインド古典音楽の研究センター、Shankarや他のインド音楽のマエストロたちの作品を集めた資料室、レコーディングスタジオが備えられている。教育機関そのものではないが、選抜された生徒たちが古式ゆかしい学習法、Gurukul Systemで音楽を学ぶことができるという。インド古典音楽復興における自身の貢献度に話が及ぶと、Shankarの答えは控えめなものであった。
「自分で言うことではないだろう。'56年からやっているから、人はいろいろと言ってくれるがね」
今でも自身をインドの文化大使のように感じているかと訊かれても、彼は謙虚な姿勢を崩すことはなく、自分はインドの音楽と文化をできるだけ多くの国に届けようとベストを尽してきただけだと表明するにとどめた。
Shankarにとって、音楽の演奏とは演奏家としての立場よりも音楽そのものが重要なのだという。これは多分に“にわとりと卵”的な議論だろう。
「音楽自身がすべてを語るのだ」とShankarは断言する。「それが私の信念なんだ。どんなに懸命に音楽を説明したり語ったりしようとしても、結局のところ心に届くのは音楽そのものなんだよ」。彼は笑いながら付け加える。「時にはそうもいかないんだがね」
あまりに大きな音量や不協和音の音楽は好きでないことを認めながらも、どんなジャンルにも良い音楽は存在すると彼は信じているという。
「魂の込められた、心を和ませる良い音楽ならば、どんなものでも感動するよ。どんなジャンルにも良いミュージシャンはいるが、優れたミュージシャンシップとは演奏技術だけでなく、マインドやハートに触れることができるかどうかに現れるものなんだ」
これまで制作したアルバムで何かお気に入りの作品はあるかという質問に、彼は笑いながら答えた。 「残念ながらひとつもないよ。たいていのアルバムでもっとうまくできたはずだと思うからね」。ここでも彼の態度は謙虚なものだ。「いや、本当にないんだ」
この芸術家にとって音楽を録音するということは、パズルの断片をひとつに集めるようなもので、とりわけ彼が会得しているあらゆる複雑なラーガ(旋法)を取り扱う場合に顕著だという。
「ミュージシャンが歌ったり演奏したりする間に起こった、何かファンタスティックなものをキャッチできるというのは本当に素晴らしいことだよ。素晴らしい音楽におけるそのような限られた瞬間を捉えることができれば、録音技術は人類に与えられた素晴らしい贈り物となりえるのだ」
『Full Circle』のライナーノーツでは“ラーガとは芸術家の内なる魂を反映する美学である”というShankarの言葉が引用されている。背景で繰り返されるそのフレーズを聞いた後で、彼はインド音楽と自身のキャリアの中心に横たわるメロディの形態を説明するための、よりシンプルで魅力的な言葉で結論を述べた。
「ラーガとは心を彩るものだよ」 By Bryan Reesman/LAUNCH.com | 


