【逆輸入インタビュー】宇宙から来た翻訳家たち

宇宙から来た翻訳家たち |
東京のテクノ・サーフ・パンク集団Spoozysの基本メンバー4人が、今回のインタビューのために、マンハッタン都心の24階にあるロンチの広い会議室にやって来た。 彼らが席に着いてまもなく、通訳を付けましょうと彼らが言ってきたのはもっともだと判明した。Spoozysは、基本的な英語はきちんと把握しているが、すこし込み入った質問になると、母国の日本語に戻ってしまうのだ。 明らかに彼らはそのほうが楽なようだった。通訳付きのインタヴューは、記憶するかぎり私は初めてだ。そして、身振り手振りをこんなに交えて会話をしたのは、まちがいなく初めてだった。その点では1等賞である。 ある意味で、それはSpoozysにふさわしい。彼らの音楽自体が、一種の翻訳なのだから。 40年ほど前の人々ならポップミュージックだと思うであろう音楽が西暦2000年にどう聴こえるかと、彼らは現代的解釈を行なっているのだ。 彼らの全米デビューアルバム『Astral Astronauts』を彩るのは、たとえばアナログシンセのプーとかピーという音であり、あるいはロボットの声であり、騒がしいドラムマシーンやギザギザした感じのエレキギターである。 そしてなぜかは分からないが、それらは時折、変貌してある懐かしい曲を思い出させる。その曲は「Wipe Out」、往年のTVのスパイコメディー『それ行けスマート』のテーマ曲だ。 彼らの歌詞はほとんど英語ということになっているが、本当かどうかは分からない。しかし、そんなことは結局のところどうでもいい。リードヴォーカル兼マルチ楽器のJun Matsueが、「How Do We Communicate?」の下行コード進行に合わせて嘲笑を浮かべたり、「Highway-Hypnosis」の歌詞のいたるところで狂った悲鳴を上げたりしているのを聞いていると、通訳なしでも興奮は伝わってくるからである。 「確かに日本ではふだん英語を話しませんけど」とJunは言う。 「ぼくらは、ロックを聞いたり映画を見たりして、単語やフレーズを拾ってるんですよ。だから、ある種のロックンロール英語を知ってるんです」 バンドリーダーにふさわしく、このインタビューで話をしたのはほとんどJunだった。ドラムのWataru Daiko、キーボードのNaomi、そして謎のNoiseman(バンド内での彼の役割は「ノイズを立てる」ことである。論理的だ)は、すました表情でほとんどのあいだ椅子にもたれていた。 音楽的には、ここでDevoやB-52'sを引き合いに出せばいいことは明らかだった。しかし私は面白半分で、地味な話題を振ってみた。 Bill Nelsonが'70年代後半に組んでいたRed Noiseというバンドが『Sound-On-Sound』というアルバムを出してますが…。 驚いたことに、Junはこの話題を拾ってくれた。 「ええ、よく知ってます」とJunは言う。 「そのレコードは小学生のときしょっちゅう聴いてました」 なるほど、辻褄が合う。とげとげしいヴォーカル、ギターの派手な装飾音、そして逆上したテンポ。SpoozysとRed Noiseには、そんな共通点がある。 もうひとつ、Spoozysがいま名前を挙げた3つのバンドと共通しているのは、SF的なイメージに愛着を持っている点だ。曲のタイトルを並べてみると、「Astral Astronauts」や「Russian UFO」「Tiny Head Creatures」や「AI (Artificial Intelligence)」。これで足りないなら、彼らがライヴで宇宙服を着ているという事実を付け加えれば十分だろう。 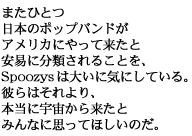 「ぼくはずっと、子供のころ興味があったもの全部を混ぜ合わせようとしてるんです」とJunは言う。 「ぼくはずっと、子供のころ興味があったもの全部を混ぜ合わせようとしてるんです」とJunは言う。「それは音楽だけじゃなくて、SF映画やTVゲームも含まれるんです。ぼくは、インヴェーダーゲームのようなゲームの音が好きでした。そのあともずっと、シンセサイザー音楽のそういう音に刺激を受けてきました。いまぼくが担当している楽器は主にギターですけど、Spoozysの音楽の中心にある楽器は、本当はシンセサイザーなんです。シンセサイザーのおかげで、こういう音が出せるんですから。それに、ステージで宇宙服を着てヘルメットをかぶるとすごいんですよ。ぼくらの曲を知らない人たちでも、すぐに反応が返ってきますから」 米では今回のアルバムが初のリリースとなるが、Spoozysは1996年の結成以来、日本で他に2枚のアルバムをリリースしている。さらに、Junはソロアーティストとして日本の大手レコード会社と契約している。 彼によると、ソロの曲はSpoozysの曲とはまったく違うらしい。 「ソロはもっとギター指向です」と彼は言う。 「それにSFのイメージもあまりありません」 インタヴューが始まって45分が過ぎると、私には質問がなくなってしまった。しかし、バンドのメンバーは話を続けている。とうとう通訳がこう尋ねてきた。 「すいませんけど、今度はメンバーの方からあなたに質問してもいいでしょうか?」 「ええ、どうぞ」私は言った。 unは『Astral Astronauts』のジャケットをどう思うかと言った。それはJunの写真をコンピューター加工した画像で、Junの姿は人造人間あるいはアクション人形のように変わっていた。 「これ、カッコいいですね」と私は言った。「曲にも合ってる」 「なにか思い出しませんか?」彼は尋ねた。 「TVの『サンダーバード』みたいだなあ」と私は言った。 『サンダーバード』とは'60年代のSFシリーズで、俳優はひとりも出演しない。登場するのはすべて、小さくてぎこちない操り人形である。 「じゃあ、あなたにはこの顔はあまり日本人ぽく見えないんですね」彼は言った。 「そうですね。とくに日本人ぽいとは思わないですね」 Junは大きく息を吐いた。「よかった」と彼は言った。 またひとつ日本のポップバンドがアメリカにやって来たと安易に分類されることを、Spoozysは大いに気にしている。明らかに、彼らはそれより、本当に宇宙からやって来たとみんなに思ってほしいのだ。たしかに、彼らにとってはそれがいい。 Noisemanはそれまでほとんどノイズを立てていなかったが、このときついに話に加わってきた。 「Shampoo再結成の件でなにか知りませんか?」と彼は言った。 「いえ、なにも。申しわけない」 「じゃあ、なにか分かったら教えてもらえませんか。Shampoo情報はつねにチェックしておきたいんです」 彼は冗談を言ったのだ。と、私は思っている。 Mac Randall |