【インタビュー】Dragon Ash「俺達しかできないこと言えないこと説得力があること無いことを研ぎ澄まして考えて作ったアルバム」

Dragon Ashが3年振りにリリースする、10枚目となるオリジナル・フルアルバム『THE FACES』。多様な音楽性を表すタイトルを冠したこの作品について、Kjはライヴのステージ上から“人生で一番身を削ったアルバム”とファンにメッセージした。新たなDragon Ashの第一歩を印すマスターピースを完成させたメンバー全員に話を聞いた。
■潜り抜けてきた修羅場の数は半端じゃないですから
■アルバムを作るとなったら俺たちが何をするべきかを考える
――まず、2013年という年はどんな想いで過ごした1年だったかをお聞かせください。
ATSUSHI(Dance):2012年の方が突っ走った感は強かったんですけど、2013年はその手応えを感じました。だいぶ客観的に物事を見られるようになったかなと思います。まだ全然走ってる感じはあるんですが、それが一歩引いて見れるようになりましたね。
HIROKI(Gt):制作とライヴと集中した年でしたね。あとは筋トレを続けられました、1年間。
Kj(Vo.Gt):あとあれもやってるじゃないですか、極悪集団。あ、ジェイソンズ(HIROKI率いるミクスチャーバンド)。
HIROKI:いや、あれはいいから。
Kj:あれはいいからって(笑)。
――Kjさんはいかがですか?
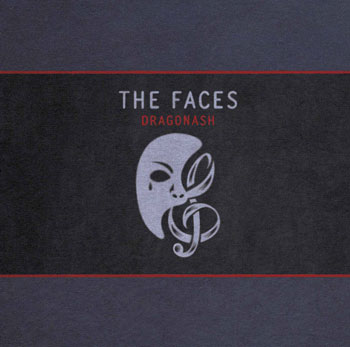 Kj:そうですね。音楽人生で一番がむしゃらに、語弊があるかもしれないけど“働いた”年でしたね。もう、寝る間も惜しんで色んな事をやらせてもらいました。
Kj:そうですね。音楽人生で一番がむしゃらに、語弊があるかもしれないけど“働いた”年でしたね。もう、寝る間も惜しんで色んな事をやらせてもらいました。――今年はNHK大河ドラマ『八重の桜』への出演(斉藤一役)という話題もありました。俳優業から音楽活動にフィードバックされたことは実感として何かありましたか?
Kj:ありましたね。全く違う職業といえばそうだし、同じ職業とも言えるし、勉強になりました。
桜井誠(Dr.以下・桜井):自分はアルバムを制作できたというのが一番です、動きとしては。向上意欲というか、新たなものに対する明確な目的というのはレコーディングが一番なんで。課題じゃないですか、一曲一曲が。で、やみくもに練習をしたりするのって、実は凄く難しいというか目標値を決めるということ自体曖昧だと思うし、上を見ればきりがないので。自分は何のためにドラムをやってるのか? ということに立ち返ると、やっぱりDragon Ashで良い作品を作るためにやってる。新しい楽曲が来て、それに対して情熱を燃やすというのが、やっぱり一番好きだな、ということを改めて思った年でしたね。
DRI-V(Dance):個人的には、怪我が多かった年でした。そういう動きたくても動けない時に、どういう考えでいたら良いのか、客観的な面で見れた一年でした。今までの感じじゃ駄目だ、と思いましたね。
BOTS(DJ):Dragon Ashは活動する上で莫大なエネルギーは持っているんですが、Dragon Ashは凄い大きなものになっているから、グルっと最初に回す力は非常に必要で。それが一旦回り始めて、どんどんみんながそれぞれのエネルギーを利用して、さらに遠心力を加えてどんどんスピードを増して回って行くために、自分もちゃんとそこに上手く加担できたかな、と。最終的に凄いスピードで回って、空を飛ぶくらいになってたような一年だったかな。
――その遠心力がDragon Ashのファンだけじゃなく、音楽ファンも巻き込んでいったという実感がありましたか?
BOTS:先日のワンマン・ライヴ(2013年12月3日EX THEATER ROPPONGI)でちょっと新曲をやった限りでは、夏フェスとかは俺らのファンだけじゃないから、新曲やっても「ポカーン」みたいな感じだけど、やっぱりDragon Ashのファンが集って、新曲やって、しかもkenkenが歌うとか、想像もしないようなシーンでも盛り上がってくれたりとか、グルリと回る輪がファンも含めて大きなものに、なおかつつスピードを増しているという実感はあります。
――先日のライヴではアンコールで、Kjさんがこのアルバムのことに触れて「人生で一番身を削ったアルバム」と言っていましたが、どんな部分にそれを一番感じたんでしょうか?
Kj:う~ん…。17年も(バンドを)やってたらさ、冗談じゃないわけじゃないですか? もう人生ですからね。そうなってくると、もちろんまだまだ経験豊富なバンドもいるし、背中に追いつけない先輩も沢山いるけど、でも俺らだって潜り抜けてきた修羅場の数は半端じゃないですから。インナーマッスル半端じゃないんですよ。音楽は人生なんで止められないんだけど、いざアルバムを作るとなったら、外的にかかるプレッシャーというか、この死線を潜り抜けてきた俺、メンバーたちが何をするべきか?というのは考えるよね。まあ、もう取材で過去を振り返らないというのは決めてるから、そういうことはもう言わないんだけど、俺達しかできないこと言えないこと、説得力があること無いこと、というのを研ぎ澄まして考えて作ったということかな。歌詞を書くのなんて誰でも大変だし、練習なんて誰でもしてることなんだけど、もう少し精神的なことかな。
 ――今回はファンの方も新生・Dragon Ashの作品として待ち望んでいるアルバムだと思うんですが、アルバムとしての全体像が見えるキーになった曲はありましたか?
――今回はファンの方も新生・Dragon Ashの作品として待ち望んでいるアルバムだと思うんですが、アルバムとしての全体像が見えるキーになった曲はありましたか?桜井:やっぱり、イントロから「Show Must Go On」の流れですね。それを(2013年の)6月くらいにレコーディングしたんですが、この2曲が出てきた時点で、グッとアルバムのイメージが湧くようになった。いつもそうなんですが、イントロと1曲目は「これでいきます」って建志が持ってくるんで、それを前提として同じBPMでイントロと1曲目は作られていて、整合性のあるものになっている。混沌としたイントロから1曲目の出だしの爆発力は痺れましたね。
――最後の「Curtain Call」で完結する、ひとつのショーのようなアルバムになっていますが、イントロと「Show Must Go On」が出てきた段階でそこまで考えていたんですか?
桜井:いや、「Curtain Call」は最後の最後に録った曲で、元々は歌も乗せずにトラックだけで締めくくろうかという建志のアイデアで。でも録ってるうちに「やっぱりこれは曲にしたいな」っていう発想になって。そこで急遽歌詞を乗っけて完成しました。
◆インタビュー(2)へ
この記事の関連情報
Dragon Ash、最新曲「Straight Up feat. JESSE」が「ABEMA サッカー」テーマソングに
【速レポ】<REDLINE>Dragon Ash、「でも俺はまだバンドやってるよ」
Dragon Ash x The BONEZ、スプリットツアーの追加公演の開催が決定
<REDLINE>、SiMのMAHを中心とした一大プロジェクト“REDLINE DREAM BAND”始動
The BONEZ×Dragon Ash、最強のマッチアップによる初の対バン全国ツアー開幕
Dragon Ash x The BONEZ、未発表コラボ曲を含む限定CDシングル「Straight Up e. p.」の発売が決定
Dragon Ash、新曲「Straight Up feat. JESSE」が映画『十一人の賊軍』のキャンペーンソングに決定
Dragon Ash、JESSEと最強タッグのコラボシングル「Straight Up feat. JESSE」を配信リリース
SHANK主催フェス<BLAZE UP NAGASAKI 2024>、出演全9組を一挙発表