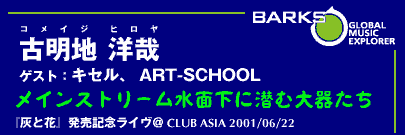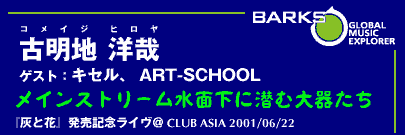『灰と花』
ミディ MDCL-1410
2001年6月21日発売 3000(tax out)
1 the lost garden(studio recording version)
2 acrobat(makes me green)
3 夢のかげ
4 sweet rain
5 星の埋葬
6 花が咲いたら
7 ライラックの庭(album version)
8 ghost
9 メランコリー(part2)
|
| ほんのちょっと前まで、“第2次バンドブーム”とでも言うべき盛り上がりを見せていた日本のインディ・ロックシーンであったが、ここに来てそれも収束に向かいつつある。
それはなぜか。
その理由は、今の日本のインディ文化が極端な二分化へと向かいつつあるからだ。これまでの既存のJ-POP流の音楽性に迎合したかのような音楽性をとる“売れ線志向”のバンドと、そうした商業的システムに背を向け難解な方向へと音楽性をシフトさせていくバンドと。
要するに、“わかりやすいもの”と“わかりにくい”ものとがハッキリと二分してしまったがために、かつてのニルヴァーナのような“既存の《ポップ》の概念を大幅に変える新しいタイプのポップさ”を持ち合わせた、インディからメジャーへと向けて一石を投じるようなバンドがほとんどなくなってしまったのだ。
それじゃあ、既存のメインストリームなんてまるで変わりやしない! ここ数年、もてはやされてきた下北沢や渋谷で盛り上がっていたインディのシーンの火は消えてしまうのか?
その問いに「そんなことはないぜ!」と返してくれたのが、この日のライヴ。
主役は3組、ART-SCHOOL、キセル、そして古明地洋哉。
この日のライヴは基本的には古明地のメジャー・デビュー・アルバム『灰と花』の発売記念によるものだが、傑出したこの孤高のシンガーソングライターに花を添えたのは、やはり期待度の高い新星たちだった。
まず登場したのは、現在のインディ・ギターバンド・シーンで頭抜けた実力を発揮する4人組バンド、ART-SCHOOL。
このバンドは何といっても小柄で可愛らしい美青年ヴォーカリスト・木下理樹の魅力に尽きる。小柄でキュートなルックスはなかなかに母性本能をくすぐるものがあるが、最大の魅力はその今にも壊れそうなガラスのような繊細さと、そうした性格に実によく呼応した甘くて切ないメロディのセンスだ。そうした要素からは、ニルヴァーナやウィーザーのような内向的なバンドをこよなく愛し、無神経なマッチョさや汚い大人社会といったものに対する嫌悪感という、いとおしいまでに純粋な彼の気持ちが伝わってくる。
この日のライヴも、演奏や歌唱力の点でまだ及ばない点は見受けられたものの、そのメロディの独特な憂いと、か細い高音ヴォイスで一生懸命泣きそうになりながら歌う木下の姿は、非凡なものを大いに感じさせた。
続いて登場したのは、京都出身の兄弟デュオ、キセル。
ひとくちに“デュオ”といっても彼らの場合、最近流行りのストリートのフォークの連中とは違い、MTRに録音したアンビエントな打ち込みリズムをバックに、“究極の癒し系”とでも言うべき囁くような声で、浮遊感溢れる切ない歌を聴かせるといった、今の日本にはまず存在しない珍しい逸材だ。
ライヴもこの辻村兄弟だけがギターとベースを持ち、後はテープに収録したリズム素材のみといった実にユニークなライヴであった。この日は楽器とテープの音量調節自体がうまくいかず必ずしも良いコンディションでのライヴとは言いがたかったが、それでもその特異な個性をアピールするには充分の内容であった。
彼らも古明地同様、6月にメジャー・デビューしたばかりなのでこれから要注目だ。
 撮影●熊野智晃 撮影●熊野智晃 |
そしてこの日の最後に登場したのが古明地洋哉。
彼の特色はなんといっても、自分の心の内面にふきだまる渾沌とした想いを1枚の抽象絵画のように表わした比喩の多い言語表現と、その言葉のイメージを立体的に組み立てた卓越した楽曲アレンジにある。
アコースティック・ギターで内なる心の呟きを表現し、ディストーション・ギターや突如のテンポや拍子の変化にどうにも止められない感情の高まりを表現し、一見ダークと思わせつつもよく聴くと実は清清しさに溢れたメロディは絶望の中に差し込む一縷の光を思い起こさせる。
そんな風に、楽曲の1曲1曲が隙がなく完璧に構築された音楽性であるがゆえに、これまでそれらがライヴで実現されることが少なかったのだが、この日のライヴは古明地の持つそうした圧倒的な世界観が見事に表現された素晴らしいライヴとなった。
ステージ中央の椅子に終始腰かけてアコースティック・ギターを黙々と弾きながら淡々と歌う古明地。
彼の歌声は決して“叫ぶ”でも“歌い上げる”でもなく、観客一人一人に“語りかける”ものであり、観客はやがてそれに引き込まれる。そして、ひび割れた轟音ギターとエレクトリック・ヴァイオリンの痛々しい音色が今度は逆に聴いている者の胸をしめつける。
この“静”と“動”の対照的なコントラストに満ちた大きなスケール感と手に汗握るような緊迫感は、英米の一流の洋楽アーティストのソレと比較しても全く遜色はない。そして、これほどまでに深く自分自身の精神と向かい合った生々しい感情に満ちた歌も、今の主流J-Popには全く見受けられないものだ。
「こうしたアーティストがメインストリームで受け入れられれば、日本の音楽シーンも大いに刺激になるはず」
そこまで思わせる程の説得力がこの日の古明地にはあった。
現在、冒頭にも書いたように、日本のインディ・シーンは大きな曲り角に立ちつつあるが、この日の3アーティストのような存在が健闘して行けば、この先は間違いなく明るいものとなるはずだ。 |
|