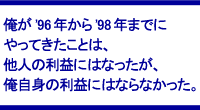| 「彼は悪魔、彼は悪魔、悪魔、悪魔」――ダミアンのようなシュプレヒコールに重なる“2000B.C.”の騒々しく薄気味の悪い空襲警報を聴いた途端、あなたは何かの巻き添えになってしまったことに気付くだろう。しかし、何が起こっているのか、はっきりとはわからない。すると、しゃがれた、耳馴染みのある声が聞こえてくる。復讐の念に揺り動かされた声。過ぎし時の記憶を呼び起こすドープなMC。ここ最近はあまり聴いたことのないような手法。それはラッパーがレコードを作るためにはテクニックが不可欠だった時代を思い出させる。
この言葉遊びは、比喩の天才、極上のマイク使いのものだ。そう、少年少女たちよ、あのリリカルテロリスト、オリジナルバトルキャット、Canibusが帰ってきたのだ。労働者階級最後のMCとして。
「俺はネット上でお前と戦う/俺は直接お前と戦う/俺は電話を通じてお前と戦う/コレクトコールで電話してこいよ!」。Canibusの2ndアルバム『2000B.C.』は、この説得力ある一節から始まり、昔気質のMCが好むTV番組『S.W.A.T.』のテーマ曲に重なっていく。
少し前のCanibusは、アンダーグラウンドでは恐れを知らぬ態度でマイクに挑むことで有名だった。しかし、'98年のデビュー作『Can-I Bus?』で、彼はアンダーグラウンドMCからラジオ向きのラッパーに仕立て上げられようとしていた。彼のコアなファンはそれが気に入らず、Canibusは自分自身でいることが大切だと悟ったのだった。そして彼はアンダーグラウンドに帰ってきた――『2000B.C.』を耳にしたファンはこう言うだろう、「Wellcome back」と。
「おまえらは前のアルバムに怒りを覚えたんだろ/謝るよ/なあ、俺にはどうしようもないんだ/クソったれのWyclefが全部ダメにしちまった」。ニューアルバムのタイトル曲にあるこの一節は、『Can-I Bus?』に対する評論家たちの激しい非難に答えたものだ。前作を心待ちにしていた彼らは、いざそれを耳にした途端、全編にわたる過度のプロダクションに対して失望を露にした。“2000B.C.”は弱虫野郎どもに向けた曲ではない。だが、ファンはCanibusの発するすべての単語を聞き取るために、ステレオの巻き戻しボタンを壊れるほど何度も押すはめになるだろう。
「俺のデビューアルバムは、みんなが期待したような作品じゃなかったんだ。俺にしてみりゃ、ゴールドディスクが家の壁にかかってるのは悪いことじゃないがね。朝起きて、壁のゴールドディスクを見るのは気分がいいもんだ」とCanibusは語る。しかし、信頼できる相談相手だったはずのエグゼクティヴ・プロデューサー、FugeesのWyclef Jeanのせいで投げつけられたアルバムの悪評に関して、彼は未だに苦い思いをしているのだ。
「Clefは俺とは合わないってことさ」と彼は言う。「あいつのやり方は変なんだ。向こうも俺のことをそう思ってるだろうけど。あのアルバムの制作はあっという間だった。彼のネットワークは全く違ってたんだよ。奴は俺をDavid LettermanやConan O'Brien(ともに人気ヴァラエティ・ショウのホスト)の番組に出演させることはできたが、『Video Music Box』は無理だった。あれにはびっくりしたね。俺にはそのネットワークの違いがどれだけ大きいのかわかってなかったけど、いったん外へ出て、また全く別の入り口から入り直さないといけないくらいのことだったんだろうな」
Canibus自身や彼のバックグラウンドについてよく知らない人は、『2000B.C.』に満ちあふれる怒りに対して疑問を持つに違いない。しかし、彼には敵対心を持つだけの理由があるのだ。これまでに彼がやってきたことはすべて、他のアーティストのキャリアの助けにはなったが、彼自身のためではなかった。ラップテロリストとして他のラッパーのアルバムにゲスト参加したことにより、彼らのアルバムが売れ、彼らの利益を上げるのに貢献してきたのだ。「その時にはわからなかったんだ」と彼は悲しげに言う。「でも、俺が'96年から'98年までにやってきたことは、他人の利益にはなったが、俺自身の利益にはならなかった」
今ようやくヒップホップ界のCharles Oakley――ゴミ箱から這い出し、毎晩自らルーズボールに飛び込んでは怪我を負う、労働者階級のMC――が自らの取り分を手にする時がやってきた。『2000B.C.』はある意味でCanibusの本当のデビュー作と言えるのかも知れない。今度こそ世の中に彼自身を証明するのだ。今回、彼はようやくBeatnutsのJujuやDJ Clue、Irv Gottiなど、自分が望むプロデューサーを選ぶ機会を手にし、RakimやKurupt、Ras Kass、Killah Priestなど、自分が望むMCたちを自分の曲にゲスト参加させることができたのだった。
マイクが手渡されるたび、これが最後かと思わせるようなパフォーマンスを見せるCanibus。彼はレコード制作の契約を結ぶことは名誉であって、権利ではないと考えている。自分が楽しみながら仕事できることを幸せに思っているし、たとえそれで稼げなくても同じことをしているだろう。しかしビジネス面から見れば、今度こそ、自分の取り分はきっちり確保しておきたい。 |