【インタビュー】SNARE COVER、メジャーデビューという大きな扉を開けた記念すべき1曲

SNARE COVER(スネアカバー)というアーティストをご存知だろうか。札幌在住、バンド歴20年、現在はソロ形態で活動している、ソングライターの斎藤洸(たけし)による音楽プロジェクト。国内のシーンでは知る人ぞ知る存在かもしれないが、2017年の<エマージェンザ・ミュージック・フェスティバル>日本大会優勝、アニメ作品『メイドインアビス』の音楽や挿入歌も手掛けるなど、その実力は高く評価されている。音楽のほかにも保護猫活動家として精力的に活動し、「ありがとう!わさびちゃん」など著書も多く発表している、知られざる才能のカタマリのようなアーティストだ。
7月26日にビクター/カラフルレコーズからリリースされた最新シングル「Hourglass」は、メジャーデビューという、彼にとって大きな扉を開けた記念すべき1曲だ。SNARE COVERとは一体どんなアーティストで、ここから何を目指すのか。札幌市内の自宅にリモートを繋ぎ、現在の心境を聞いてみた。
■これを出し切ったら死ぬんじゃないかぐらいの
■刹那のピークの声の出し方に憧れていました(笑)
――SNARE COVERについて、YouTubeで見られる限りの映像を見せてもらったんですが。カバーシリーズを録っているのって、もしかしてその部屋ですか。窓の外に山が見える。
斎藤洸(以下、斎藤):そうです。ヒグマが生息する田舎です(笑)。
――良いところですね。声も出せるし音も出せる。
斎藤:いちおう、今のところ苦情は一度もないです。
――生活している環境と、音楽を作る環境とは、やはり切り離せない関係にあると思いますか。
斎藤:そうですね。本当にそれが、自分の音楽にとって必ずプラスになっているだろうという意識と、今一緒にやってくださっている方々も、そこをすごく重要なポイントとして置いてくれているので。東京に住んでやるのとは、おそらく出来上がる音楽が違うだろうと。
――うまく言葉にならないですけど、北海道出身アーティストの音楽には、独特の広がりとスケールの大きさがあるように感じています。風土的なものか、精神的なものか。
斎藤:確かに。僕の場合は歌声も、自然と調和するというか、そういう意識も持って歌っているので、そう感じてもらえるのかもしれない。
――かつて、東京に住んだことは?
斎藤:まだ一度もないです。
――映像を見ると、3人組だったバンド初期のラウドでノイジーな演奏だったり、ダンスミュージックを取り込んだり、ソロプロジェクトになって以降はアコースティックギターとエレクトロニクスの組み合わせだったり。20年間で大きく変遷しているように見えるんですけど。
斎藤:もがいて、あがいて、やっていましたね。
――20年をひとことで振り返るのは難しいでしょうけど。どういう日々でしたか。
斎藤:いろいろな模索というか、今自分にとって何がベストなのか?を常に追求して、その時聴いている音楽に影響されながら、その時のトレンドにも悩まされながら。でも自分に出来ることはこれだよねって、いろいろ考えながらの日々でした。自分の出来ることと、理想の形みたいなものを意識しながら作っていた20年間でしたね。
――最初にバンドを始めた時は、どういうことがやりたかったんでしょう。
斎藤:始めた頃は10代後半で、その時に聴いていた音楽が80年代後半や90年代前半あたりの、ニルヴァーナとかのグランジや、オルタナあたりのアメリカのロックとか、イギリスのレディオヘッドとか、そのへんの音楽が自分の中で一番来てる感じがあって。時代的にはちょっとズレているんですけど、どっぷりハマったのがそのへんの音楽だったんですね。そこからの影響が大きかったです。
――そういう、洋楽マニアックのサウンドと、4オクターブ出るという斎藤さんの技巧的なハイトーンボイスとの組み合わせが、SNARE COVERの大きな魅力だと思います。最初からそういうスタイルでした?
斎藤:いや、最初はこんなに裏声とか、ヘッドボイスという高い声を、こんな形で出してた記憶はなくて。刹那のピークの、これを出し切ったら死ぬんじゃないかぐらいの(笑)、そういう声の出し方に憧れていました。それこそカート・コバーン、日本だとイースタンユースの吉野さんみたいな、爆音の中でピークを極めるみたいな、そういう境地に音楽で行きたいなと思いながら曲を作っていて、どっちかというとギターロックの方向性だったんです。それで声帯をかなり痛めて(笑)。今思えば、あまり自分に向いている表現じゃなかったなと思ったりもします。
――2016年にソロプロジェクトに進化したあたりからは、アコースティック+エレクトロニクスというスタイルの楽曲が中心になっていきますよね。それも、当時聴いていた音楽の影響がありますか。
斎藤:少なからず影響はあると思います。ジェイムス・ブレイクとか、音楽の歴史のどこから取って来てるんだろう?みたいな、完全にオリジナルで、この人にしか出来ないみたいな、そういう音像に影響をすごく受けて、「自分だったらどうやるか」を考えてました。ジェイムス・ブレイクの影響はたぶんあると思います。あとはビョークだったり、ビリー・アイリッシュの初期の頃だったり、サウンドやメロディの作り方がすごく挑戦的だなと感じていました。
――わりとトレンドに影響されるタイプでもあるんですかね。悪い意味ではなく。
斎藤:確かにトレンドとかは、意識してはいると思います。それでも結局自分が作れば自分のものになるという意識でやってはいますね。
――その都度、音楽的にいろいろなものを入れていくと。
斎藤:ちょこっとつまんで(笑)。一人のアーティストを深く聴いて知っている、という感じではないです。良いものだけを取り入れている感覚ではあると思います。
――そして今回、活動20年にしてメジャーデビューという、大きな節目がやって来ました。率直に聞きますが、どういう経緯だったんですか。
斎藤:これは、今所属している事務所のバックアップもあって、出来ることになりました。ずっと札幌で、インディーズでやってきたものが、SNARE COVERの音楽をもっと世の中にしっかりと広めていくために協力してくださる方がいて、今の形があるんです。
――もともと、そういう希望はずっとあった?
斎藤:そうですね。メジャーデビューといってもいろんな表現の仕方があると思っていて、今の時代のメジャーデビューのありかたというものは、自分が音楽を始めた頃とどういうふうに変化しているかはわからないですけど、ただメジャーデビューという形は、20年やって来たからこそ重みや深みがあると思っていて。そこに対してより決意が固まるというか、自分の音楽を広めていくことに責任を感じるというふうに思っています。
――それ、最近のnoteにも書かれていましたよね。好きなことをやることは今までさんざやってきたから、これからはこの歌声を広める責任がある、と。
斎藤:本当にそう思っています。
――面白いなと思うのは、「この歌声を広める責任」という言い方で、そこにあまり私欲を感じないというか、客観的な視点を感じていて。
斎藤:それはあると思います。ここまでやってきて、自分の中で満足してるか?といったら全然してないのと、やりたいことは何だろう?と思った時に、自分が出来るのは音楽しかないと思っていて。自分が人間として生きて、この世の中に何か残したいと思っていて、それが出来るのは音楽しかない。そのために、まだまだ本来知ってもらうべき人がいるとして、そこに届けることを今までやれていなかったので、今のスタートラインはあるべき自分の姿だと思っているので、ものすごい感謝の気持ちもあるし責任もある。というふうに思っています。
――ほかに、そのnoteの文章の中でも、「愛とは何か」「生命とは何か」というテーマをしっかり歌っていきたいと、力強く語っているのが印象的でした。それって、20年間を貫くテーマだったりしますか。
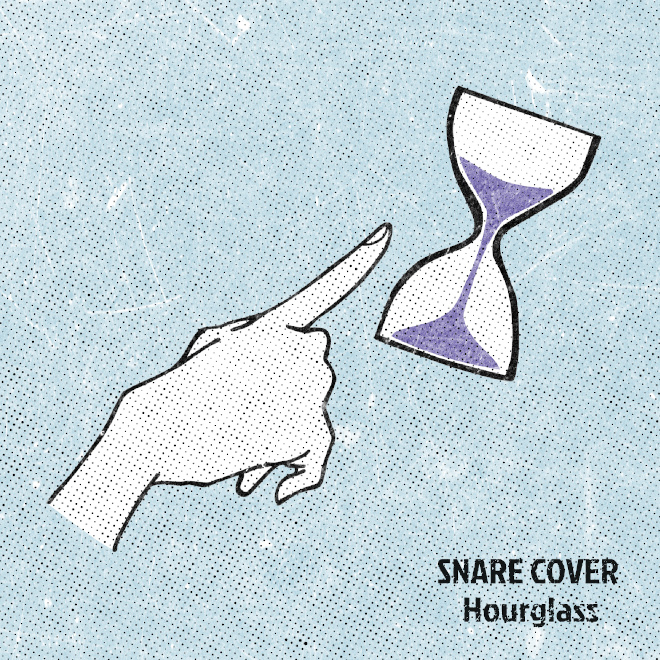
▲「Hourglass」
斎藤:そうですね。命とか、生きる意味とか、今それを発信しても、そう簡単に伝わるものじゃないと思っているんです。みなさん漠然とどこかで感じていたとしても、日常的に使っている言葉ではないというか、すぐそばにあるものではなくて、奥深くにあるものなので。でも自分はシンプルにそこをずっと歌ってきたつもりで、そこに対して執着があるというか、そこは音楽を始めた頃から変わりはないです。ただ最初の頃はそれを迷いなく表現していたというか、やればやるほどその境地に自分がどんどん昇っていって、悟りの境地まで行ってるみたいな感覚でいたんですけど、20年経って今になると、むしろ逆に生きることに対する執着心が強かったり、死ぬのが怖かったり、もっと広がって大きくなっていくイメージが、逆に小さくなっていって、解像度が上がっていく感覚があるんですね。「生きること」と「死ぬこと」に対して。それを今なら、よりストレートに伝えられるだろうと。生命を歌うということを、より人間的に伝えられるのは今だろうとは思います。
――確かに、スリーピース時代の楽曲は、たとえば「プラネタリズム」とか、宇宙的というか、壮大なイメージが広がるものが多かったかなという印象があります。
斎藤:当時はそう歌うしか方法がなかったんです。たとえば、たくさんの人たちが歌っているような恋愛のことを歌うのは、当時の若い自分にとっては「ラブソングを書くのは苦手」みたいな感覚があったんですね。でもラブソングがなぜそんなに世の中で歌われて、みんながそこに感動するのかには理由があって、自分が本当に核の部分で感じていたこと、「なぜ自分は生きているのか」「自分という意識はいつ生まれたのか」「なぜこんなに悲しくなるのか」とか、心の中で起こる大きな爆発みたいなものを、ラブソングを作る人たちはたぶん考えている。世の中に恋愛の歌が多いのは、そこに響く人が多いということだと思うので。当時は気づかなかったんですけど、自分が感じている核みたいなものをぶつけるポイントとして、恋愛の歌というのは、今の自分なら苦手という感覚を持たずに歌える、深いところで表現出来るんじゃないか?と思ってはいるんですよね。
◆インタビュー(2)へ