【インタビュー】織田哲郎、ソロ・デビュー30周年記念インタビューPART2:「音楽に選ばれた男」がいかにして音楽シーンの頂点に立ったか?

祝・ソロデビュー30周年。「織田哲郎30周年インタビューPART2」は、稀代のヒットメイカー・織田哲郎の30年間に及ぶ激動のヒストリーを時系列に沿ってたどり直す試み、その前編だ。創作の原動力、ヒットを生む秘訣、プロデューサーとしての栄光と苦悩の日々、そして新しい時代の音楽家としての生き方など、日本のポップス史に偉大な足跡を残すシンガーソングライターが語る言葉は、率直で飾りなく、それゆえ非常にポジティヴで力強く響いてくる。この「PART2」では83年から93年までの歩みを振り返ることで、「音楽に選ばれた男」がいかにして音楽シーンの頂点に立ったか?を追ってみることにしよう。
■アルバムを請け負って作るほうが実質的には全然忙しいわけ
■そこで一旦自分を解散したんですよ。織田哲郎解散(笑)
──83年にソロ・デビューを果たしてからの80年代の織田さんの活動は、数年前に出た3枚組ベスト『GROWING UP』を聴けば振り返ることができます。あらためて、あの頃の曲を聴くとどんな思いがありますか。
織田哲郎(以下、織田):そうだなぁ…音が古いとか古くないとかそういうことよりも、あの頃は人として辛いことがいっぱいある時期だったから。音楽の中にそういう辛さがいっぱいこもってるんだよ。だからあんまり聴き直さないようにしてたんだけど、あの『GROWING UP』を作るためには当然がっつり聴かないとしょうがないわけで。いろんなダークな思いが蘇っちゃって、キツかったですよ。でも今となっては、それが逆に良かったという気がするな。
──1987年が、織田哲郎史上最も忙しかった1年だったということを、以前におっしゃってましたよね。
織田:そう。オレが29の年なんだけど、ふと“あと365日で30になっちゃうんだ”と思って、“30でまだこんなもんなのか?”というのが嫌だったんだよね。いろんな意味で“オレの描いてた30はこんなもんじゃない”というのがあって、とにかくそこから1年は、24時間の目盛りを入れたスケジュール帳を作って、入るものはそこに全部入れていった。まぁ、はた迷惑だったけどね(笑)。事務所の人間とかエンジニアもそれにつきあってたわけだから。ほんとにあの年は、ほとんど寝てなかったな。平均睡眠2~3時間で1年通してる。しかもその時、テレビのレギュラーとラジオのレギュラーも2本持ってたからね。いつもぼけーっとしてるから、何しゃべってんのかわかりゃしない(笑)。ひどかったなあれは。
──今思うと、どういう心境だったんですかね。修行とか?
織田:修行でしょうね、完全に。自分の限界を知るという意味で、あれはやって良かったと思う。本当にその時、限界を知ったもん。それまではレコーディング・スタジオにいることが楽しくてしょうがなくて、帰りたくないと思うぐらいスタジオにいることが好きだったはずなのに、その年に初めて“もうここにいたくない”と思った(笑)。限界というものがあることを知りました。
──その頃は作曲家、プロデューサー、そしてソロ作品と同時進行ですよね。
織田:もう全部です。1987年は自分のアルバムを1枚とミニアルバム1枚出していて、人のものも3~4枚責任を持って作って、それでテレビとラジオのレギュラーを持って、よくやってたなってほんとに思うんだけども。
──その年に限らず、80年代の織田さんの仕事量はものすごいですよ。83年のデビューから89年まで、まったく休みなく走っている。
 織田:よくやってましたね。それでね、その頃で懲りたからそのあとはあまりやらなくなったんだけど、結局忙しいのは人の曲を書くことじゃなくて、アルバムのプロデュースを請け負うことなんですよ。曲を作る時間というのは、短い時も長い時もあるけど、そんなにたいした時間じゃない。でもアルバム全体をプロデュースとして請け負うと、アレンジ、レコーディング、歌入れにトラックダウンと、必ずこれぐらいの時間を取られるというものがあるわけで。
織田:よくやってましたね。それでね、その頃で懲りたからそのあとはあまりやらなくなったんだけど、結局忙しいのは人の曲を書くことじゃなくて、アルバムのプロデュースを請け負うことなんですよ。曲を作る時間というのは、短い時も長い時もあるけど、そんなにたいした時間じゃない。でもアルバム全体をプロデュースとして請け負うと、アレンジ、レコーディング、歌入れにトラックダウンと、必ずこれぐらいの時間を取られるというものがあるわけで。──確かに。
織田:だから90年代に入ってから、オレがいろいろ目立つ曲を書くようになった時が“一番忙しかったでしょう?”ってよく言われるんだけど、全然そうじゃない。87年のほうが、TUBEのアルバムも半分以上オレが作ったし、清水宏次朗、亜蘭知子のアルバムもそうだし、アルバムを請け負って作るほうが実質的には全然忙しいわけ。だからそれに懲りて、90年以降はそういう請け負い方をめったにしなくなったんですよ。曲もなるべく“シングルしか書きたくない”ということで、ボツならボツでいいから“シングルにするかボツにするかどっちかにして”って。そうしないとね、あのままやってられないの。とてもじゃないけど。
──バンドだったらたぶん解散してますね。一人だから解散できないですけど(笑)。
織田:でもさすがに、そこで一旦自分を解散したんですよ。織田哲郎解散(笑)。
──それが89年頃でしたっけ? 一度音楽活動を休止した時期がありましたよね。
織田:それにはいろんな理由があるんだけど、仕事に関しても自分の限界が見えたり、私生活においてもいろんなことが激変していた時だったから。それまで一緒にやっていたミュージシャンをみんな呼んで、“WHY”(79年に結成したユニット)からずっと歴史順に、その時関わってくれたミュージシャンと一緒に演奏するというライヴをやった(*89年8月、MZA有明での4時間ライヴ)。それをやった時は“これがオレの人生最後のライヴかもしれない”と思っていて、そこから先のビジョンはすべて白紙にしちゃったから。
──そこが最初の大きなターニングポイント。
織田:そう。この前ある人に“なんでそんなに無防備なんですか?”って言われたんだけど、言われてみれば、人生において“メシを喰うためにこうしなきゃいけない”ということを考えたことがないの。音楽を作るということが“自分の中で90点以上楽しくないんだったらもうやめよう”という感じで生きてたんだよね。“80点でいいから音楽でメシを喰って行こう”という概念がなかったから、その時はもう音楽をやめたほうがいいと思ったわけ。これから何をするということも全然頭になくて、とりあえず白紙!と。実は24の時にも一回白紙にしてるんですよ。ソロデビューする前に。
──それは織田哲郎&9th Image(*80~81年)をやってた頃ですか。
織田:9th Imageが終わったあとですね。今だったら、一人でも音楽をPCで作れるじゃないですか? あの頃は弾き語り以外の音楽を構築するためには、まず人を集めなきゃいけないから。だからバンドを組むとか、事務所と話すとか、そういう人と関わることに完全に疲れちゃって、人と関わらないで済む仕事をしようと思ったんですよ。陶芸とかね(笑)。
──そういえば、織田さんはもともと美術に惹かれてたんですよね。
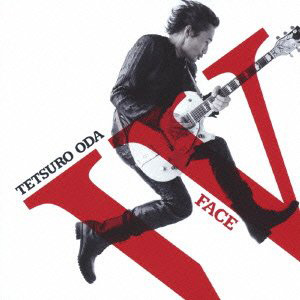
▲織田哲郎『W FACE』KICS-1977~8 ¥3,150(tax in)発売中
織田:中学の頃は絵描きになりたいと思ってたから。もう一回真剣に絵描きを目指そうかなとか、陶芸家になろうかなとか。そんなことばっかり考えてて、頭の中に音楽がない状態だった。その時のことを言うと、たまたまた見てもらった占い師のおかげなんですよ。
──占い師ですか。
織田:代々木でたまたま入った喫茶店にいた手相見の人。その時のオレなんていうのは…今でも職務質問をよくされるんだけど(笑)、その時はもっとひどい格好で、グルグル眼鏡で髭ぼうぼう。向こうもよもや音楽をやってるとは思わなかったと思うんだけど、手相を見ながら“あんた、音楽とかやるといいんだけどね”っていう話をされて、“ほお? それは面白い”ということになった。しかもその占い師がヒマで、そこから5~6時間話し込んじゃった(笑)。そしたらその人がオレと同じうお座のA型で、昔ミュージシャンだったっていうからさ。
──何なんでしょうね。同じ匂いを感じたのか。
織田:昔ジャズをやってたっていうんだけど、面白くてずーっと話し込んじゃった。そうこうしてるうちに何かがすっきりして、“そうか、やっぱり音楽かな”という気になってきて、“もう一回ちゃんとやってみるか”と。そこでデモテープを作り始めたんだけど、でもほら、そこまでにいろんなことに疲れちゃってるから、“まずはオレのやりたいようにやろう”ってそこで決めたの。今度はやりたいことだけやって、それを一緒にやりたいというミュージシャン、レコード会社、スタッフがいたらやろうと。で、オレが21の時に(長戸)大幸さんがオレ込みでビーイングを作って、その時はオレも一応まだビーイングにいたから、最初のソロアルバム『VOICES』(83年)はビーイングから出たんだけど、どうせだったら自分の事務所も作っちゃえって、何の稼ぎもないのに事務所を作っちゃった。
◆インタビュー続きへ
この記事の関連情報
『CDTVライブ!ライブ!』にKAT-TUN、A.B.C-Z、JO1、fromis_9ら出演。90年代J-POP企画も
【photo gallery】<中津川ソーラー>、うじきつよし × 織田哲郎 × 佐藤タイジ
松本隆、吉田拓郎、山下達郎、織田哲郎らの証言も、NHKでKinKi Kids特集放送
相川七瀬、25周年アニバーサリーイヤーを完走。織田哲郎、布袋寅泰らも祝福
「DI:GA ONLINE」にて、オリジナル・ラブ、水曜日のカンパネラ、LiSA、織田哲郎らのプレゼント企画実施中
【インタビュー】ROLL-B DINOSAUR「織田哲郎はバンドがやりたいということがこの2ndアルバムではっきりしたよね」
織田哲郎、新曲「CAFE BROKEN HEART」がNHKラジオ『深夜便のうた』に決定
吉田拓郎トリビュートALにポルノ、民生、THE ALFEE、ミセスら参加
デビュー20周年の相川七瀬、“七瀬の日”ライブに織田哲郎。どぶろっくもサプライズ