Dirty Old Men、タワレコ限定4曲入りシングル「Dirty Old Men e.p.」リリース大特集
Dirty Old Men タワーレコード限定発売の最新シングル 「Dirty Old Men e.p.」2010.3.3リリース
怖くて殻に隠れていた自分自身をさらけ出して音楽に昇華できたのは 人との出会い、そして音楽の大切さを実感できたからこそ
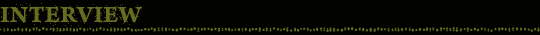

「高校2年生のときにバンドを組んだんですよ。ベースの山田(真光)くんは高校1年から3年間一緒。でも1年生の時はひとことも話したことがなかったんです。このバンドを組む前はドラムの野瀧(真一)くんと、Going SteadyとかHi-STANDARDとか、その時流行っていたバンドコピーバンドを組んでました。そのバンドが解散したあとにオリジナルのバンドを組みたいなって思ったんです。オリジナルをやりたい気持ちは1年の時からあったんで、“このままじゃダメだ”と思ったんですよね。で、解散後、山田くんがベース弾けるらしいというので、掃除の時間のトイレで誘いました。そのときに初めて喋ったんですよ」
「歌詞は日本語で書いたものを英語の先生に歌詞をつけてもらったりしたんですけど、“表現出来ないよ”っていう言葉が多かったみたいで。だったら日本語の方がいいのかなって。日本語詞の良さを痛感したのは、当時バイトをしていたライヴハウスで日本語詞のカッコいいバンドに出会ったのがきっかけなんです。無名でも格好良いバンドってたくさんいると思うんですけど、ベビーカーっていう茨城のバンドがすごくかっこ良かった。もう解散しちゃったんですけどね。そのバンドに感動して、“俺も日本語で歌詞を書こう!”ってなったんです」


「歌詞を見ていると、自分ってヒネくれているなって思いますよね(笑)。伝えたいものを遠回し遠回しに伝えることのほうが多いなって。でも、歌の中で“ありがとう”って言葉を伝えるにしても、どのアーティストにも負けたくないって気持ちなんです。そのための言葉の流れを感じたり、ここで“ありがとう”を歌詞に入れたらグッとくるだろうなっていうのはすごく考えます。前までは、今ほど歌詞について考えていなかったんですね。人と違うようにしなきゃって思っていたり、自分を隠したり、なるべく見られないようにしたり。でも今作は自分の気持ちが思いっきり出ている。歌も強く歌ったり、ちゃんと表現できるようになったと思うんですよ。なんの仕事でもそうだと思うんですけど、明日のことなんてわからないじゃないですか。僕も確かなものを探しながら描いていて。人生、不安材料って多いじゃないですか。今回の歌詞を書いているときは、その不安材料が心の中にいっぱい湧いていたんですよ。でも光が見えてほしい、希望というものが最終的にあった方がいいなと思って、すごく悩んで書いた「解いた手」とかも最後は光が見えるような感じになっている」

「長過ぎるから歌詞を切ったんですね。歌詞を削るとなると、伝えるためにはもっと言葉を意識しないと伝わらなくなってしまうから、それで悩みましたね。歌詞の良さって、短い文でも伝わるというのが一番いいと思うんです。でも僕はまだまだできてないなって思う。この曲は、夏の終わりと自分が終わる音を重ねている歌詞なんですけど、そもそも映画みたいな曲にしたかったんです。別れて、最後はまた2人は再会するんですけど、このあと、ハッピーエンドなのかどうなのか、難しいところなんです…。僕もよくわかんないんですけどね(笑)。聴いた人にお任せします」
「僕、ずっと自分を隠していたんですよ。作家的なところがあって、格好良く見られたいと思って書いていたから、伝わらなかったこともいっぱいあったんだけど、今回は本当に追いつめられていたので、自分を出す部分が出たと思います」

「全国ツアーに来てくれたお客さんが、泣きそうな顔で“ありがとう”って言ってくれるんですよ。こっちこそありがとうなのに。僕らが音楽をここまで続けられているのって奇蹟だと思うんですよ。みんなに支えられて、僕らがやれているから。それでこの曲を書こうと思って。一番衝撃を受けたのが、癌を患ったファンの方と出会ったことなんです。カップルで観に来てくれたんですけど、つきあい始めてから彼女が癌だということがわかって、入院するときに彼氏さんが、僕らの「moon wet with honey」って曲をiPodに入れて渡したそうなんです。彼女はその曲を聴いて、“彼と半分こずつして頑張れました”って。まだ彼女は闘病中なんですけど、一日だけ病院から外出許可をもらって観に来てくれて。それでライヴ後に“信さん(高津戸)は僕らのヒーローなんです”っていきなり言われて、闘病の話をされて。2人で手をつないで、“私たち、結婚するんです。ありがとう”って言われて、ズシンと来て。こんな“ありがとう”があるんだって。ずっと不安で、俺なんて才能あるのかなって思いながら毎回曲を書いてて、そんな風な人がいるんだって肌で感じました。俺が誰かの光になれているって感動した。この2人がきっかけだけど、みんなに伝えたい曲です。この曲を書いたときに、お客さんに媚びているって思われたらイヤだって思ったんです。でもそういうもんじゃない。この気持ちはもっと重いんだって、悩みながら書きましたね。大切にしなきゃいけない曲だから」
「この作品を作って、自分の中でも改めて音楽に対しての気持ちを知りましたしね。僕なんて音楽がなければただのチャランポランなヤツなんで、いつも音楽に助けられてるんですよ。そのありがたみを感じています。これからももっともっと伝わる曲を書いていきたいと思います」
取材・文●大橋美貴子

この記事の関連情報
DIRTY OLD MEN、アニメ『弱虫ペダル』OP&ED曲含むアルバム『Blazing』本日リリース
Dirty Old Men、未来へとつながるものを求め辿り着いた入魂の最新作『doors』大特集
秀吉主催イベントにDirty Old Men、竹内電気の出演決定
Dirty Old Men、大切に育て上げた1曲1曲が詰まった最新アルバム『GUIDANCE』特集
Dirty Old Men、汗だく大興奮でJ-WAVEスタジオ生ライヴ
Dirty Old Men、ラジオ番組で30分を超える生ライブを敢行
Dirty Old Men、初フルアルバム・リリース&ワンマンツアーを発表
Dirty Old Men、力強く前に進む『somewhere』リリースインタビュー<後編>
Dirty Old Men、力強く前に進む『somewhere』リリースインタビュー<前編>