【月刊BARKS 佐久間正英 前進し続ける音楽家の軌跡~プロデューサー編 Vol.2】80年代のプロデュース~BOΦWYからブルーハーツへ


【月刊BARKS 佐久間正英 前進し続ける音楽家の軌跡~プロデューサー編 Vol.2】80年代のプロデュース~BOΦWYからブルーハーツへ
「日本のロック」が、未だ商業的な成功を果たせなかった80年代初頭。押し寄せるパンクやニューウェーヴなど新たなムーヴメントと、劇的に発展するテクノロジーの中で、やがて日本のロックのスタイルそのものを変えるバンドが登場することになる。その名はBOΦWY。その出世作『BOΦWY』(85年)のプロデュースを手がけた佐久間正英は、あとに続くバンドたちの良き理解者であり、進むべき道を示すガイドとして、80年代を通じて最も影響力のあるロック・プロデューサーとしての地位を確立してゆく──。
構成・文●宮本英夫
●最初から遠くのお客さんを狙うのではなく一番近いところにいる人がどう感じるかが基本かなとは思いますね●
──80年代初頭には、アイドルや歌謡曲の仕事もやりつつ、ロック・バンドのプロデュースも増えていきますね。
佐久間正英(以下、佐久間):それ以降の、自分のプロデューサーとしての仕事の足がかりになったのが、SKIN(80年)をやったことです。パンクっぽいバンドをやったのはSKINが初めてで、そこでどういい音を作るか、どうカッコよくしていくか、いろいろやったのが、そのあとBOΦWYとかをやる流れの一番大もとになった感じがします。今聴いても、SKINはすごく好きですね。
──85年には、そのBOΦWYとの劇的な出会いがあります。
佐久間:これは何回も話してるけど、プロデュースの話が来て、初めて打ち合わせに行った時に、「怖いなあ、イヤだなあ」と思ったんですよ(笑)。見た目とか、態度とかね。でも、ドラムの高橋まことだけは古い知り合いだったから、「あ、まこっちゃんがいるんだ」って気づいて、そこで救われた気持ちになった(笑)。覚えてるのは、打ち合わせした時に「どういう音にしたいのか?」という話をしたら、たぶん布袋くんだったと思うけど、「ロックにしたい」って言ったんですよ。ロックバンドに「ロックにしたい」と言われたのは初めてで、「それはどういう意味だろう?」って考えたんですね。そこでいろいろ考えて、当時の録音環境やエンジニアを含めて、日本じゃ無理だなと思って、ベルリンに行くことにしたんです。実はもう一つ理由があって、これは笑い話になってるんだけど、怖いから断りたいという気持ちもあって、「ベルリンに行くならやります」という言い方をしたら、その時のディレクターがすぐに「行きましょう!」という返事をくれて、やることになったという(笑)。それでベルリンで、前の年に根津甚八さんのレコーディングで行った時に知り合った、マイケル・ツィマリングと一緒にやることになった。
──そもそもBOΦWYから佐久間さんのプロデュース依頼があったのは、メンバーの意見だったんですか?
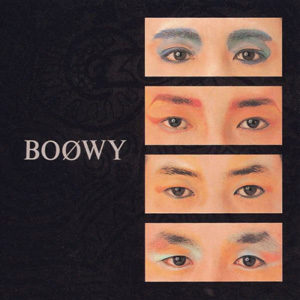
▲BOΦWY『BOΦWY』

▲BOΦWY『JUST AHERO』
──佐久間さんが関わった『BOΦWY』『JUST AHERO』の2作は、それまでのBOΦWYとはガラリと変わりましたよね、音もイメージも。あれはどういう作品だと思ってますか?
佐久間:あれは今聴いてもいいですね。素晴らしいと思う。最初にレコーディングに入った頃は、まだリズム隊がヘタッピで、苦戦したんですけど、2枚作る間にめきめきと腕を上げましたよね。マッチャン(松井恒松)にはピッキングから教えて、いわゆる佐久間式ピッキングを教えた最初の相手じゃないかな。そしたら本当に必死になって練習して、ブースにこもってずっとやってました。
──BOΦWYは佐久間さんとの共同作業を経験したあと、大ブレイクを果たして…。
佐久間 すごいバンドになっちゃいましたよね。
──ここで聞いてしまいますけど、その後佐久間さんが手がけた作品は、そのアーティストにとって大きな転機になるものが多いと思うんですよ。
佐久間:まあ、成功したバンドの場合は、そういうケースが多いですね。
──端的に言うと、売れるきっかけを作るというか。そのへんは意識されてますか? ヒット請負人というか、商業的な成功を念頭に置くということは。
佐久間:そういうふうに意識はしてないですね。ただ、そのバンドごとにいいものというのは違うわけですけど、「いい」と言われる状態に持っていく、という意味では意識しています。商業的ではないかもしれないけど。経験上「まず周りの人間がどう感じるか」が大切で、たとえばマネージャーやディレクター、そういう人たちが興奮してくると、うまくいくんですよ。最初から遠くのお客さんを狙うのではなく、一番近いところにいる人がどう感じるか。そういう人たちが、「今度の作品はすごいんだよ」という気持ちが強くなって、それが周りにも波及していって、それが全体の流れになっていくという、そういうことが基本かなとは思いますね。
──そのあとは、THE STREET SLIDERSをプロデュースされます。彼らもある意味、怖いバンドだったんじゃないかと思うんですが…(笑)。

▲THE STREET SLIDERS『天使たち』
──なんか…すごいですね。
佐久間:スタジオのマイクを生かしっぱなしにしておいたんだけど、本当に誰もしゃべんない。
──気を入れたんでしょうか。
佐久間:何でしょうね?(笑) あれはすごかった。ああいうタイプの、ピリピリした雰囲気を持ったバンドは、そのあといなくなっちゃいましたね。ハリーは、レコーディングの場とかライヴとかでは本当にいい奴で、ちゃんとしてるんですけど、何か違うことで障害があったりとか、気にくわないことがあれば、遥か彼方の人になっちゃう(笑)。
──80年代で言うと、ほかにはUP-BEATとか。
佐久間:UP-BEATはけっこう長くやってましたね。
──ブルーハーツも1枚、やられてますよね。『YOUNG AND PRETTY』(87年)を。

▲ブルーハーツ『YOUNG AND PRETTY』
──もしもそうなったら、日本のロックの歴史が変わったかもしれないです。
佐久間:だいぶ経ってから、ブルーハーツのリミックス盤みたいなものを作る企画があって(*名義は「盗賊団」)、かなり面白いものになったんだけど、その時に「リンダリンダ」のマルチテープを初めて聴いたんですね。スタジオで一人で作業してたんだけど、ヒロトが何かちょっとしゃべってて、「じゃあ行きます」って言って、「どぶねずみみたいに…」ってパッと歌いだす。それがすごかった! 一人でひたすら感動してました。ヒロトは本当にすごいと思うし、ヒロトとマーシーのコンビもすごい。後年、マーシーのソロも僕はやってるけど、2人ともすごいですね。
──普通ロックバンドのプロデュースというのは、メンバーの「こういう音にしたい」という意見がまずあって、そこから始まることが多いですか。
佐久間:決まってないものもあります。もちろんバンドなんで、やりたいことは大体決まってますけど、ちゃんとビジョンが見えてないケースは多いですね。雑な言い方をしちゃえば、レコード会社や事務所がバンドを見つけてきて、「この子たちをどうにかしてください」みたいなこともあるので(笑)。BOΦWYが成功したあと、「BOΦWYみたいにしたいんです」というのが、けっこうありましたね。そう言われても…(笑)。
──80年代のプロデュース・ワークを今振り返ると、全体的に、どんな思いがありますか。

▲氷室京介『NEO FASCIO』
──退院してすぐですか? それは相当ハードですね。
佐久間:もうスケジュールが決まっていたので。入院してる時にも、病室に「氷室京介より」っていうお花なんか届くもんだから、もう大変で(笑)。しかも本人が見舞いに来てくれて、目立つ目立つ(笑)。いい奴なんですよ、本当に。病み上がり直後だったから、『NEO FASCIO』のレコーディングは大変でしたね。体力的にもそうだし、2か月ぐらい楽器に触ってないから、弦が押さえられない。リハビリしながらレコーディングという感じで、そういうことも含めて印象深いですね。『NEO FASCIO』は、音楽的にも転機になった作品だと思います。演奏はそうる透(Dr)と2人だけで、オケは僕が全部作って。一人で全部やっちゃうやり方でフルアルバム1枚作ったのは、たぶんあれが最初ですね。自分のソロアルバムを除けば。そういうやり方としても転機になったし、音楽シーンに対しても、転機になった作品かなと思います。
次回は、「90年代のプロデュースその1~JUDY AND MARY、GLAYをめぐって」をお送りする。「バブル崩壊」の不吉な予兆から始まった90年代も、日本の音楽シーンは逆に大きな発展を見せ、ミリオン・セールスが続出する百花繚乱の時代へと突入する。その中で大ブレイクを果たしたJUDY AND MARY、GLAY、黒夢などのプロデュースを手がけた佐久間正英は、欠点をプラスに変え、新たな刺激をバンドに持ち込むことで、バンドの持つポテンシャルを無限に広げていくことになった──。
佐久間正英は現在、脳腫瘍の手術後のリハビリに励んでいる。9月9日(月)、渋谷CLUB QUATTROで行われたTAKUYAのバースデイライヴに出演し、元気な姿を見せてファンを安心させた。氏の回復を祈り、この連載を掲載させていただきます。
◆佐久間正英 オフィシャルサイト
この記事の関連情報
【俺の楽器・私の愛機】1296「佐久間正英が作られたシンライン。その時、俺は号泣した。」
佐久間正英が遺したプロジェクト「blue et bleu」が最初で最後のリリース
佐久間正英、遺作「Last Days」のミュージックビデオ完成。最後のレコーディングの模様
佐久間正英が最後にプロデューサーOKを出した遺作「Last Days」が先行配信
【nexusニュース】NOTTV「LOVE&ROCK」で佐久間正英追悼番組が放送決定
スペースシャワーTVで佐久間正英追悼番組を放送
佐久間正英、永眠
佐久間正英、ヒット曲からレア音源、新曲も収録のコンピ盤『SAKUMA DROPS』
【月刊BARKS 佐久間正英 前進し続ける音楽家の軌跡~プロデューサー編 Vol.5】2000年代のプロデュース~未来の音楽家へのメッセージ